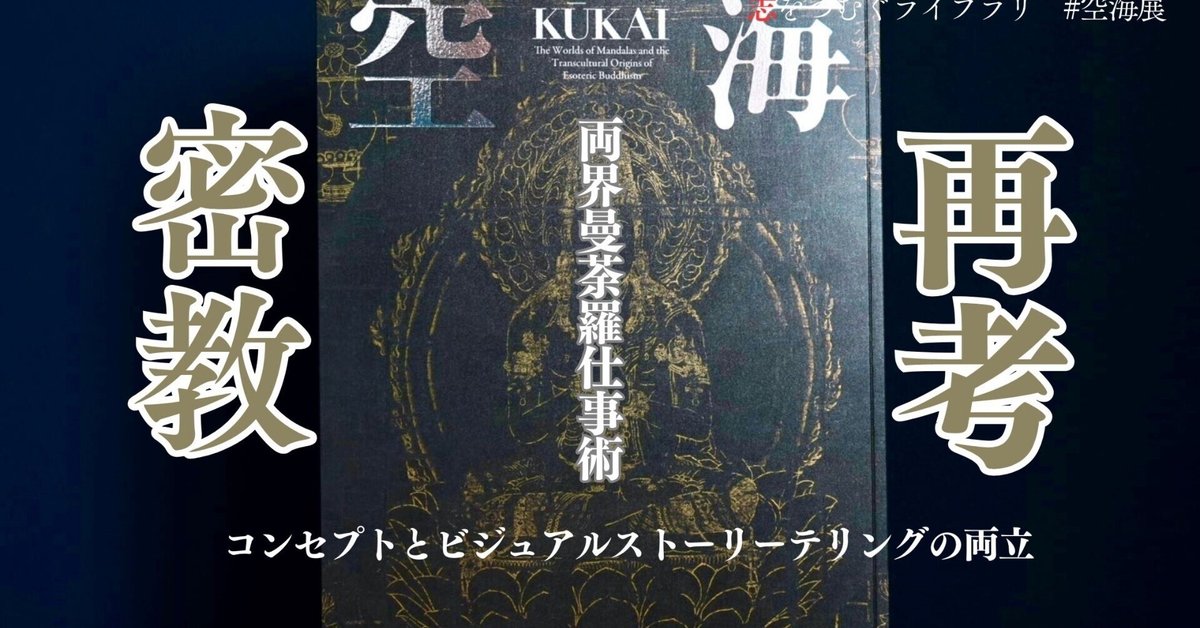
空海展”空海 KŪKAI ―密教のルーツとマンダラ世界”で弘法大師の仕事術を再考する〜
本年は2024年4月13日(土)~6月9日(日)の期間、奈良国立博物館弘法大師・空海の生誕1250年の記念特別展として奈良国立博物館で”空海展〜空海 KŪKAI ―密教のルーツとマンダラ世界〜”が催されています。私どもも早速行って参りました。
本展の世界観
弘法大師・空海といえば、日本真言密教の祖として知られています。
平安時代、遣唐使船に乗ってたどり着いた唐より青龍寺において恵果大阿闍梨より伝法された密教の極意を日本に持ち帰りその教えを世に弘められ、日本仏教史だけではなく日本文化に大きな影響を与えています。
今回の空海展は、奈良国立博物館の井上洋一館長をして”かつてない”と言わしめるほどで、実際に、230年ぶり修理後初公開となる空海が直接制作に関わったといわれ現存最古の曼荼羅である神護寺の国宝・高雄曼荼羅や空海の自筆であるこれも国宝・聾瞽指帰ろうこしいきなど、各々を観るだけでもめったとできないものがなんと奈良国立博物館で一堂に会するわけでこれほど貴重な機会もありません。
また、これまでは絵画と仏像などはジャンルが異なるため別々に展示されてきたことはあったものの、本展では立体曼荼羅としてその世界観を体験できるように展示物が配置されて、より空海が伝えようとした宇宙観をより五感で感じられるような空間づくりがなされているとのことですがこのあたりは会場まで足を運んで体験してよかったところ。
空海の息づかいを感じるほどの直接の仕事をここまでひとまとめに観れるのは生きているうちに幾度あるのか?と考えるとまさにかつてない圧巻の企画だと思います。
さて、
「密蔵深玄にして翰墨に載せ難し。
更に図画を仮りて悟らざるに開示す。」
公式図録より引用)
コンセプトとビジュアルストーリーテリングの両立
目白押しの展示品があるなか、最初に目に飛び込んできたのは吊るしののぼりに書かれていたこの言葉です。弘法大師空海が持ち帰ったものはさまざまですが、その中でも有名なのは密教の世界観を図絵を用いて表した両界曼荼羅図でしょう。
上記の空海の言葉を思いっきり超訳しますと、
「小難しいことは素人には分からん。マンガにせぇ。」
というように少なくとも私には聞こえます。
そして一民間事業者としてこの言葉に触れて改めて思ったのが、コンセプトとビジュアルストーリーテリングを両立させることの重要性です。
事業者というのはお店を営業する、商品をつくり、販売するということと同時に情報を伝えていくことも付加価値に変えていくためには軽視できません。
複数の同業他社がある中で顧客がなぜあなたの会社の商品を選ぶ必要があるのか?あるいは社会にとってその企業が欠かせない理由というものをメッセージとして伝えることができるかどうかで経営の勝敗が決まるといっても過言ではありません。
さて、これは私どものひとつの解釈に過ぎませんが、ある見方をすれば空海の持ち帰った両界曼荼羅の世界観はひとことでいえばビジュアルストーリーテリングだと思っています。
空海はそれまでの日本の仏教が経典重視で煩瑣で小難しくなりがちだったところに、慈悲の世界観を放射状に展開する胎蔵界曼荼羅と、智慧の世界観を表すビジュアルストーリーテリング形式で展開する金剛界曼荼羅によって「目で見て一目で分かる」ようにした、と考えるとしっくりくるのです。
宇宙のはたらきがマインドマップのように展開、帰納する胎蔵界はコンセプト(理念)の設計の際に必要な思考ツールの役割も果たせるし、絵物語のように悟りの階梯を表す金剛界はそのコンセプトを人それぞれの器量に応じて、あるいは世のトレンドに応じてどう伝えるかのストーリーテリング考える思考ツールとも見えるからです。
あるいは、空海の両界曼荼羅を思考の型として理念を設計したりその理念を物語形式で図絵を用いて映像化することで情報の伝わる精度、速度が飛躍的に高まるということを示唆しているようにも見えるのです。
メジャーリーガーの大谷翔平氏が学生時代に目標設定シートに使用したのはこの曼荼羅をモチーフに応用したマンダラチャートと言われていますが、情報が図絵で整理できる思考ツールとして活用しやすかったからでしょう。
やはり、情報の把握、伝達の効果性を考えるならば子どもに絵本物語を読み聞かせするように図絵を用いることは欠かせません。
今なら曼荼羅はどのように扱われるか?
また現在、映画「オッペンハイマー」が話題となっておりますが、いつも難解な科学テーマにチャレンジするクリストファーノーラン監督の作品も映画だからなんとなく云わんとすることが見えてくる、と言うようなことがあると思います。
空海が唐から密教の教えを持ち帰るまでは、もちろん、個々に心象を映像化するということの重要性は気づいていた人はいても、ここまで体系的にそしてビジュアルとしてまとまった「哲学」として世に弘めた人もいなかったわけで、それまで民衆にとっては何もないところにいきなり当時世界最先端の唐の文化の結晶とも言える両界曼荼羅の図絵がやってきたことは衝撃だったことが目に浮かびます。
ですので、「もし、空海が今生きていたらどんな仕事をするのか?」という視点で物事を考えてみるのも面白いかもしれません。
まだ普及したとはいえないことも加味してVRゲームの世界において、NintendoSwitchのゼルダの伝説ブレスオブザワイルドやティアーズオブザキングダムのオープンワールドで自由度の高い冒険の旅を新しい拡張世界で体験する。ゲームの元型であるゼルダ姫を救うというミッションの中で失った記憶を取り戻したり、人類普遍の人生で大切なことを五感を通じてゲーム体験できる世界観。Nintendoならすでに開発に着手しているかもしれませんね。

空海の書を原文そのまま読んで解釈して今に活かすのは難しいとは思いますが、それでも私どもが弘法大師・空海の仕事として最も取りいれたいエッセンスがあるとしたら、企業(事業体)が社会に果たすべき使命としての理念を確立すること、そしてそれを物語として提示して活かせるのではないかということであり、それは前述の空海の曼荼羅へのアプローチに尽きるのではないか、と思うのです。
生誕1250年記念 特別展「空海 KŪKAI ― 密教のルーツとマンダラ世界”公式図録
さて、空海展の話に戻りますが、やはり遠方の方はなかなか足を運ぶのが難しいという場合もあることでしょう。この場合は”生誕1250年記念 特別展「空海 KŪKAI ― 密教のルーツとマンダラ世界”公式図録も販売されていますのでご参考いただけたらと思います。
実際、私どもがいったのはGWでしたので会場は混雑しており、空海の直筆なども観れて直接の仕事の熱気みたいなものは肌で感じることはできましたが、それでもなかなかひとつひとつの資料をゆっくり観ることができませんでした。後でしっかり振り返りたいなと思っていましたが、この図録は展示されていたものを詳しく紹介されていますので本展のテーマである密教のルーツを始め空海の仕事を研究するにこの上ないものだと思いますので永久保存版として書棚に大切に保管したいと思っています。

空海名言辞典(付・現代語訳)/高野山出版社
あともうひとつ、この本をご紹介しておきます。弊社業務の高野山合宿研修の後に山内の書店で購入したものですが、一般の書店にはまず流通していない本です。
多分、真言宗の僧侶とか空海のコアなファンしか買わないだろうと思われるくらい「売れる」を狙った本ではないことはいわずもがな、内容はというと空海の著作から名言を分類、必要に応じて語句を検索できるようになっている辞典です。
空海の残した著作を全部調べたい方は空海全集という全8冊の分厚い本がありますが、揃えるに重たく、読み解くのに難くちょっとハードルが高いです。しかしながら、本辞典は現代の仕事にも通じる重要なエッセンスだけを抽出したような側面もありますので、入門者でも上級者でも幅広く使用できる携帯サイズのこちらの方が実用的かと思いご紹介させていただきました。
なお、本書は空海の原文はもちろん、現代語訳までついています。この、辞典を見るに文芸の章では作詩に作文、書道に筆法と宗教哲学だけではなく空海の仕事に対する具体的な考え方にまで触れられることができます。
ひとつだけこちらでもご紹介しておきましょう。
詩は物色の意を兼ねて下るを好しと為す
若し物色有りて意興無ければ巧と雖もまた処として之を用うる無し
(文鏡秘府論南/文筆眼心抄)
この記事が参加している募集
この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?
