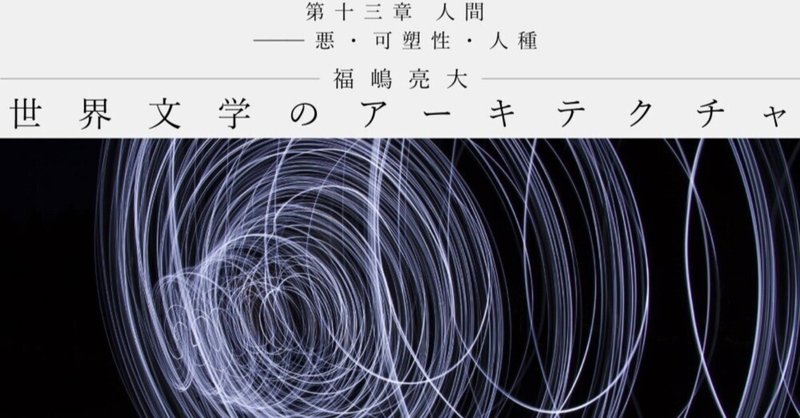
第十三章 人間――悪・可塑性・人種|福嶋亮大(前編)
福嶋亮大 世界文学のアーキテクチャ
1、悪の発明――ラス・カサス的問題
文学にとって世界とは何か。私は歴史的な見地から、その問いを初期グローバリゼーションと紐づけた。世界とはたんに空間的な広さを指す概念ではなく、異質なものとの接近遭遇がたえず起こる場である。異なる歴史、異なる習俗、異なる人間との関係の集合体としての〈世界〉――その成立に欠かせなかったのが、アメリカ大陸へのヨーロッパ人の進出であり、「万物の商品化」を加速させる資本主義のプログラムであった。「世界文学とは新世界文学である」(第七章)という私のテーゼは、異質なものとの関係の無尽蔵の発生を、その根拠としている。
その一方、グローバリゼーションの発端にはおぞましい暴力がある。一六世紀スペインの神学者ラス・カサスの『インディオの破壊についての簡潔な報告』は、まさにその暴力を告発した文書である。先住民――ヨーロッパ人の誤認のせいで「インディオ」と呼ばれた――の虐殺のカタログと呼ぶべきその記録は、ヨーロッパの発明した「世界」が、他者との対話や競合ではなく、搾取と破壊から始まったことを証言している。
ラス・カサスによれば、コロンブスがアメリカ大陸に到着した一五世紀末に「まったく新しい、過去のいずれにも似ても似つかない」時代の扉が開いたが、それはただちに黄金に目のくらんだキリスト教徒たちによる、先住民のインディオの殺戮へと到った。スペイン領植民地におけるエンコミエンダ制(先住民を労働力として使役する権利を征服者に認めた制度)を神への違反として厳しく批判した他のドミニコ会士とともに、ラス・カサスは「人間の破壊」という激越な言葉を使って、スペインの植民地政策の非合法性を訴えた。彼が批判したのは、インディオを「絶滅」させることも厭わない残酷さであり、それを促した数々の社会的不正である[1]。
ラス・カサスは新大陸で受けた精神的な衝撃を、神学的かつ法学的な枠組みのなかで厳密に思考し直した。二〇世紀ペルーの神学者グスタボ・グティエレスによれば、ラス・カサスの企ては「掠奪と不正の上に築かれた社会で福音を宣べ伝えること」にあった。彼は聖書の教えに従い、断固として貧しきものたち、つまり先住民(インディオ)の側に立った。本来、キリストの教えでは、神と富に同時に仕えることはできない。キリスト教徒たちはインディオを、異教の神々をあがめる偶像崇拝者として蔑んだが、ラス・カサスに言わせれば、富(マモン)を行動の基準とし、富にすべてを捧げた自称キリスト教徒たちこそが、本物の神をフェイクの神に取り替えた最悪の偶像崇拝者にほかならない[2]。
黄金という「偶像」に惑溺したキリスト教徒が、おぞましいジェノサイドに駆り立てられる――この植民地でのトラウマ的な「人間の破壊」は、悪の新たな形態の出現、つまり悪の発明と呼ぶにふさわしい。ラス・カサスは大部の『インディアス史』において、この数々の邪悪な行為を歴史家として緻密に再現する一方、『インディアス文明誌』では非ヨーロッパ人のインディオがいかに理性的な人間であるかを、主にアリストテレスの哲学に拠りながら論証しようとした。そこには、人類社会のさまざまな差異とその深層の同一性をスキャン(走査)する文化人類学的な要素がある[3]。
アリストテレスの考えでは、あらゆる人間は政治的動物である。ラス・カサスが論証したのは、それはインディオも例外ではないということである。ラス・カサスに続いて、ホセ・アコスタの驚異的な著作『新大陸自然文化史』(一五九〇年)になると、アリストテレス哲学の限界が厳しく指摘され、あわせてアメリカ大陸の自然誌(気象、動植物、鉱物等)およびインディオの多様な文化についての詳細な分析が記された。それは、ヨーロッパ人に根強くあった新世界=怪物の住む土地という迷信を解体し、理性的な人間の住む範囲をヨーロッパ以外にも広げる企てであった[4]。《世界》に直面したスペイン人は、人間を破壊する暴力と、人間を発見する体系的な知を、ともに進行させたのである。
2、リハビリテーションの技法としての小説
ところで、新世界が「まったく新しい時代」を開いたと言われるのは、それが「旧世界」にも無数の変化をもたらしたからである。スペイン史の泰斗ジョン・エリオットによれば「アメリカを発見したことによって、ヨーロッパは自らを発見した」。アメリカは大量の新しい事実を、ヨーロッパの人間に示した。アメリカはたんに「新しい」世界であるばかりか、自然や文化に関してもヨーロッパとは「違った」世界であった[5]。ゆえに、ヨーロッパ人は新世界の人間や風土を理解するのに、自らの認識の土台――聖書やアリストテレスの哲学も含めて――に遡り、理性や信仰の問題を根本的に再検討するように強いられたのである。
新世界との出会いは、旧世界=ヨーロッパの自己認識に少なからぬ影響を及ぼした。そして、このヨーロッパにおける自己の再発見は、小説の認識の基盤にも重大な作用を及ぼしたように思える。繰り返せば、新しい「世界」の成立は、新しい「悪」の発明でもあった。それは人間――というより人間以下とされた存在――を組織的に破壊するという悪であり、富の増進のために貧者を資源として酷使するという悪である。
このようなジェノサイドの光景は、ヨーロッパの近代小説において変奏された。デフォーの『ペスト』やスウィフトの『ガリヴァー旅行記』、そしてサドの一連のリベルタン小説から、ドストエフスキーの『死の家の記録』、コンラッドの『闇の奥』、ソ連の強制収容所(ラーゲリ)を告発したソルジェニーツィンの『収容所群島』等に到る小説は、人間のシステマティックな「破壊」というラス・カサス的問題を執拗に反復してきた(第十章参照)。ここからは、近代ヨーロッパの発明した「世界」および「世界文学」が、人間の脆弱さや傷つきやすさへのオブセッションを抱いてきたことがうかがえる。
その反面、近代小説はラス・カサスの言説と同じく、富の発明した悪への批判、つまり富の有害さの暴露という一面をもった。われわれはここで、小説が悪からのリハビリテーションという仕事を自ら背負い込んだことに、注意を払っておこう。
現に、ラス・カサスの告発からほどなくして、フェリペ二世の統治時代(一六世紀半ば)のスペインではピカレスクロマンが流行し、無一物の「貧しきもの」の視点から、社会の富める主人たちの欺瞞があばかれた(第十一章参照)。スペインは新大陸から膨大な富が流入していたのに、財政的には赤字が膨らみ、苦境にあった。この繁栄のなかの危機を背景として、当時のスペイン社会では上から下まで、貧しきピカロの精神が浸透し、スペイン人の「人生哲学」を形成するまでになった[6]。財貨を軽蔑し、名誉を求める遍歴の騎士ドン・キホーテは、まさにこの哲学の延長線上に位置している。新世界に最初に進出したスペインが、小説の原初的なプログラムとして富=偶像への批判を明確化したことは、その後の小説の進化を方向づけるものであった。
さらに、『ロビンソン・クルーソー』や『ブーガンヴィル航海記補遺』で新世界と旧世界の対話的なつながりを創出した一八世紀のデフォーやディドロの言説は、アメリカ大陸におけるスペインの暴虐、いわゆる「黒い伝説」への厳しい批判を含んでいた。異文化の人間との友好的な対話を描いたデフォーやディドロは、スペインの悪魔的な「進出」と自らを差異化しようとする――そのとき彼らの小説は、ヨーロッパ人の発明したトラウマ的な悪からのリハビリテーションの場になった。
ここから先は
¥ 500
この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?
