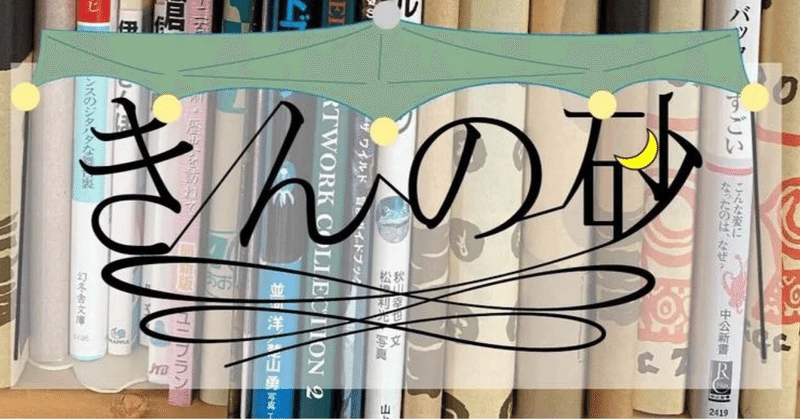
きんの砂〜4.刻の雪(3)
春も遅い長野の空気は、まだ冷んやりとしていた。
塚本という人物に本を確認してもらった亞伽砂たちは、彼から追加の依頼を受けた。それは、本を本当の持ち主に届けてほしいというものだった。だが生憎と塚本は、本当の持ち主の現住所を知らなかった。
「私が知っているのは、彼が高校卒業までいた実家の住所だけなんです。年賀状を書くときに使っていたので。残念ながら電話は覚えていませんね」
手帳を出し見せてくれた住所録には長野県の住所が記されていた。
「大きな百姓屋なので、まだ実家はあると思いますよ」
新幹線を使えばまだ帰ることの出来る場所という理由で、亞伽砂は塚本の依頼を受けた。幸いにも交通費は塚本が出してくれる。児童書を置いてくるだけの簡単な仕事だ。
「何だか面白くなってきたね」
新幹線の中で昼食を取り昼寝までしてきた公宣はすっかり遠足気分だ。
「毎回こんなだったらどうするの」
ロータリーで会話をする2人の前に、得馬が借りてきたレンタカーが滑り込んだ。
「この住所、意外と近いみたいだよ」
2人が乗り込むなり声をかける。
「帰りは俺に運転させてよ」
「あんたはよしなさい。知らない土地の運転なんて」
最近自分の車を購入したばかりの公宣を、またしても姉として嗜める。
「方向音痴の亞伽砂には言われたくないね」
この頃やたら姉貴風を吹かす亞伽砂に頬を膨らませて仕返しをする。
「え、亞伽砂は方向音痴なの」
逆に亞伽砂は得馬の反応ぶりに驚いた。これは方向音痴である部分に対してか、それとも得馬に知られたことに対してか。どちらでも構わないが一つだけ確かなことがある。
「私のことはどうでしょいいでしょ」
叫ぶなり後部座席に勢いよく寄りかかった。
以来、彼女は目的地に着くまで口を聞かないことにした。
絶対に。
果たして辿り着いた場所は、四方を広い田畑に囲まれた聞いた通りの百姓屋だった。
片側1車線の主要道路と見られる道の脇に立つバス停の横から入り、庭先に辿り着く前の畑の中で住人を見つけた。
自分の母親よりも少し上だろうか。姉の後ろから公宣は女性を見ていた。
「確かに、飛騨康徳は私の息子ですが」
見覚えのないレンタカーが敷地に入ってくるなり、仕事の手を止め彼女は近づいてきた。
亞伽砂はいきなり訪ねた非礼を詫び土産を渡すと、手帳のページを使って書いた塚本の手紙を渡した。
最初女性は怪訝な顔をしていたが、塚本の名前に覚えがあったらしい。正確には名前なのか筆跡なのか手紙の内容なのかはわからないが、表情がみるみるうちに変わった。そして亞伽砂が手にする本を受け取り、懐かしそうに頷く。
どうやら、無事追加のミッションも完遂したらしい。
亞伽砂も、彼女の後ろに立つ公宣と得馬もそう思った。
だがしかし、女性は手にしていた本を亞伽砂に押し返した。
「これは、息子に渡してあげてください」
「え、む、息子さんですか」
「どこにいますか? 近くの畑とか」
亞伽砂の横から身を乗り出して公宣が聞いた。
「康徳は神奈川のマンションに暮らしています」
嘘だろ。
得馬だけでなく、本を手にした亞伽砂と公宣も唸ったのはいうまでもない。
東京駅まで新幹線で帰り、聞いた住所のマンションにいけばもう夜だ。
「でも、それでやっと終わるから」
まさに蜻蛉返りとなった帰りの新幹線の中で、亞伽砂は自分に言い聞かせるように2人を慰めた。
紙袋から包み箱を出し、康徳の母親は仏壇の前に置いた。横には、嫁の映美が昨日持ってきた土産の菓子が置いてある。
少し前に息子が急に帰ってきて蔵で何やら探し物をして行ってから、彼女の周りでは何かが流れ始めた。結局息子は探し物が見つからなかったようだが、代わりにこれまで一度も1人で来たことのない嫁が息子の後片付けをしに来たかと思えば、見も知らぬ若い3人組が引っ越して久しい息子の恩師の手紙と本を持ってきた。
息子が何を探していたのか検討もつかなかったが、嫁の話では“心の拠り所“のようなお守りだといっていたらしい。それが、夕方奇妙な3人組が持ってきたあの本だと、母親はすぐに気がついた。
山に囲まれた海無し県で育った康徳が海の仕事をしたいと言い出したのは、小学校の高学年になってからだ。何を見てそう思ったのか不思議に思っていたのだが、あの本を見た納得した。それと塚本の存在だ。康徳のクラスの担任になった彼は息子と気が合ったのか、進路以外にも相談をしていたようだ。今でも年賀状が実家に届くということは、息子は実家を出て以来一度も恩師に連絡を入れていないのか。
「馬鹿息子が」
思わずおりんを叩く力加減が狂い、「ああ、ごめんなさい」と大きな音になってしまったことを誰にともなく謝る。それでも、あんな無口で無愛想でも面倒を見てくれる嫁がいるのだから、息子は感謝しなければ。
本を持ったなんとかという本屋の話は既に電話で映美に伝えてある。
マンションについたらすぐにわかるだろう。
妙な1日だったと思いながら、母親は夕飯の支度に取り掛かった。
奥の部屋から柱時計の音が聞こえてきた。
ノートパソコンに目を落としていた映美は時計の音で顔を上げた。
「もうこんな時間」
予定では、夕方に義母から連絡のあった本屋がマンションを訪ねてくるはずだ。
勉強用のメガネを外したその時、インターホンが鳴った。
「はーい」相手がまだ遠くにいるのについ癖で答えてしまう。リビングの壁にあるインターホンのモニターには、義母の話の通り3人の男女がいた。
「古書店キンノコ堂です。飛騨康徳さんはご在宅でしょうか」
「いま伺います」
いそいそと廊下を小走りで歩き、玄関を出ていく。
夫の康徳が初めて自分に手をあげた時は、全力で走り抜けた。
逃げたくて。
ただし夫からではない。
逃げたかったのは、物分かりのいい妻である自分からだった。いつも黙って彼の顔色を見ながら、自分の方を振り向いてくれるのを待っているだけの女。
けれどもう違う。映美が夫に内緒で取得していたボートは無線のライセンスを見られてしまった。いつか必要になることを夢見て大学にも入り直したことを話すと彼は驚いて笑って、「ありがとう」と言ってくれた。
エレベーターから降りてロビーに出て、客人を迎え入れる。
挨拶もそこそこに、キンノコ堂の店主と名乗る女性が一冊の本を差し出した。
「お届け物です」
ビニール袋に入った一冊の本。
ジュール・ヴェルヌの『海底2万里』だ。厚紙の装丁は角が取れて丸くなり、本体の紙も茶色に近いくらい黄ばんでいる。かなりの年代物だ。
「これをどこで」
1869年に発表されたこの小説は現在でも少年少女向けのSF小説として人気がある。映美も小学生のときに読んだ記憶があった。物語は、当時頻発していた海難事故の原因を探ろうと海洋に出た海洋学者が遭難し、ネモ船長率いるノーチラス号に拾われて旅をするという冒険物だ。
「飛騨康徳様の小学生の担任だった、塚本様から保管を依頼されていました」
尋ねたものの、映美は店主の話を聞いていなかった。
実家の蔵で夫が探していたものは、間違いなくこの本だ。
海と研究室しか知らない彼が、いまさら海に出ることを恐れたりはしない。だが身近な存在であったジャックの潜水艇での事故が、彼に果てなき深海の恐怖を突きつけたのだ。
「お願いがあります」
両手で持った本を、映美は中山と名乗る若い女性の店主に向かって突き出した。
「この本を、夫に届けてほしいんです」
“心の拠り所“のようなお守りなんだ。
家を飛び出したあの日、海辺の公園で佇む映美に追いついて自分の行為に頭を下げて謝った後、康徳はそういった。
海無し県の山奥で育ち日本海で海水浴をした彼にとって、海は黒い水溜まりだった。だがこの本を読んでからは、その水の下の世界への想像が止まらなかった。しかし長男で一人っ子の自分が広い田畑を持つ百姓屋である家を飛び出すわけにはいかない。
悩み続けながらも彼は夢を諦めなかった。山に残る道も海に向かう道も選択できるよう勉強に励み、広い田畑の手伝いをしながらもトップの成績を取り続けた。ひとえに恩師である塚本が親身になって悩みを聞き、この本が夢を諦めない心の支えとなったおかげだと、初めて海洋学者を目指した話をしてくれた。
初めて本当に、夫婦として心が通った気がしたのだ。
「あの、ご主人はいまどこに」
義母からの電話では、既に彼らは東京、長野、神奈川と本を運び歩いている。最後のお願いとして到着点まで運んでもらうことは可能だろうか。
「福島から宮城沖で、海洋資源調査を行なっています」
私が夫なら、この本を一刻でも早く手元に置きたい。
映美の依頼を聞いた女性は絶句していた。後ろの男性2人も唖然とした顔をしている。またか、と思われたのは当然だ。最後は陸ではなく海の上なのだ。極め付けと言ってもいい。
「少しお待ちください」
その証拠に彼女は仲間と相談すべく後ろを向いてしまった。だが男性2人のうち少し背が低い男性が一歩あゆみ出た。店主の女性にどこと来なく似ているが、3人の中で一番若い顔をしている。映美の通う大学の学生と同じ、青年と言ってもいい青さがある。
「持っていきます」
店主が二度目の唖然とした顔で青年を眺めているその反対側では、もう1人の一番背が高い男性がスマートフォンを取り出して電話を始めた。
「公宣あんた、なに勝手なこと」
「姉ちゃん言ったじゃないか、本を全部返すって」
やはりこの2人は姉弟だったのだ。
姉の手から取り上げた本を胸に、公宣と呼ばれた彼は映美の目を見つめて請け負った。
「その依頼、確かにお受けしました」
その言葉に、彼らの誠意への感謝で胸が溢れそうになる。
「私はどうしても行くことができません。よろしくお願いします」
深々と彼女は頭を下げた。
「ただし、交通費等諸経費は請求させてもらいます」
まだ何か言いたげだが、諦めたように店主が付け加える。
「もちろんです」
顔を上げた映美の目からは、大粒の涙が溢れていた。
こんな顔をされてしまって断れるはずがない。
亞伽砂は公宣の手から本を引ったくるように受け取り、元のようにバッグに入れてマンションを後にした。
外に出て左右を見れば、電話口で頭を掻いたり下げたりしている得馬が気づいて歩いてきた。かなり込み入った話をしているようだが、公宣の暴走に付き合ったのだ。住所のない海上に本を届ける上手い策でもあるのだろう。
「すぐになんて、絶対に無理だからね」
得馬の電話が終わりそうもないので、亞伽砂は公宣を睨み付けた。
「期限はないじゃないか。それにいざとなったら俺が仕事を休んで」
「駄目」
「駄目だ」
電話中でも2人の会話は聞こえていたのか、亞伽砂の台詞に得馬の声が重なった。
「公宣はまだ新人研修中だろ」
続けてからまた電話に戻る。
「得馬さんだって大きなプロジェクトの最中じゃん」
「俺には優秀な仲間がいるの」
「とにかく」
2人の間に入り、亞伽砂は得馬に電話に集中させた。通りすぎる人々の寄越す怪訝な視線から逃れるように背をむける。
「届けるのは私ひとりでも出来るから」
高春の襲撃以降、公宣はなるべく姉をひとりにしないようと努力していた。その感じが得馬にも伝わっているのか、襲撃事件を知らない彼もまた常に2人以上で行動するよう注意している。だが亞伽砂としてはそれでは駄目なのだ。
店主としていつまでも2人に守られているわけにはいかない。
「取れたよ」
ようやく長い電話を切り、晴々とした表情で得馬が振り向いた。
「なにが取れたの」
聞くのが怖くて彼女ではとても出せない台詞を、わくわくした声で公宣が口にした。
「船」
してやったりとした顔で、得馬はニヤリと答える。
「だって海の上だよ? 範囲聞いた? てか誰に電話してたの?」
「スーパー営業マン、笠置に決まってるでしょ」
いつもニヤけた顔をして店に出す彼は、忘れていたが大手IT企業の伝説の営業マンなのだ。コンピュータープログラムの開発だけでなく、日本全国の大企業に資材やハードウェアも卸している。もちろん中小企業や公官庁も例外ではない。スーパーなだけあって、さぞやいろんな所に顔が聞くに違いない。
「だから大企業って嫌われるんだよ」
地方の中企業の総務課事務員である亞伽砂は嘆くしかなった。
「それでいつなの? どこに行けばいいのかな」
かたや新入社員の公宣は能天気に訊ねる。
「明後日。茨城県の霞ヶ浦漁港に集合だから、公宣は留守番だな」
それまでの浮かれ気分から公宣のテンションがだだ下がったのはいうまでもない。
いい気味だ。
※※※※※
月曜日、亞伽砂は早春の荒れ狂う東北の海上にいた。
得馬がどれほどの仕事量を笠置の専属エンジニアとして請け負うことになるかは知らないが、1日の間に海洋資源調査船と連絡を取り、2人を連れて行ってくれる漁船をチャーターしたのだ。スーパー営業マンの呼び名は伊達ではないらしい。
「お客さん、見えてきましたよ」
操舵席の下の船室で待機して2人を、船長の片腕である若い漁師が呼びにきた。
「ありがとうございます」
手にしていたペットボトルをしまい、作りつけの椅子から立ち上がる。横の得馬は、出航した直後からの船酔いでビニール袋の中に顔を突っ込んでいた。
「私だけ行こうか」
「いや、大丈夫だから」
すでに吐くものがないために込み上げてくる酸っぱい液体を押し戻し、得馬は首に掛けたタオルで口元を拭いた。
「どうりで方向音痴なはずだよ」
背中の呟きに亞伽砂が足を止める。
「何か言った?」
「別に」
クラクラする頭を軽く振って、彼女の後から外に出た。
強い海風が、結んだ髪を解こうとする。
ライフジャケットを身につけた亞伽砂は、漁師の指差す方に白くて大きい変わった船を見つけた。海洋資源調査船は普通の漁船や旅客船と違う。マストや見栄えのいい船室の代わりに艦橋にはアンテナをたくさん付け、デッキにはクレーンやその他の設備が山のように乗っていた。笠置は、沖に出ると何日も戻れない調査船に荷物を運ぶ予定の漁船を探してくれた。
池に落ちた水に揺れる木の葉のように、漁船がゆっくりと調査船に近づいて行った。
デッキの上から見ていた船員がタイミングを見計らって荷物を受け取るコンテナを下ろす。一様に同じ作業服を着た船員の中に、違う服装の男が見えた。こんな荒れ狂う海に似つかわしくない女性の亞伽砂と、海に顔を突き出してなおも吐き気と闘っている得馬に気づいて手を振る。
彼がこの長い旅の終着点、飛騨康徳だ。
得馬の首根っこを引っ張って体を起こすと康徳の存在を教え、共に手を振りかえす。向こうの船に乗り込むことはできないので、コンテナの中の他の荷物と一緒にあげてもらのだ。
漁船の船長たちが荷物をコンテナにのせ、慎重にクレーンが上に運んでいく。
デッキの上に上げられた荷物に人が集まり、しばらしくして康徳が顔を出した。その手には防水のために2重ビニール袋に入れられた本がある。
今度こそ本当に、本が正当な持ち主の手に戻ったのだ。
遠ざかっていく小さな漁船を見送った康徳は、懐かしい思いで溢れた本を手に狭い船室に戻った。この本は小学校を卒業するときに、担任だった塚本から借りたものだ。初めて読んだ海洋小説。SF-サイエンス・フィクションと分かっていても、文章から滲み出る深海のおどろおどろしさに震えた。そして同時に海の持つ豊穣と神秘に惹かれた。
いつか自分もノーチラス号のような潜水艦に乗って深海の暗闇の謎を解きたい。
純粋な憧れから始まった夢は両親への想いと板挟みになりながらも失うことなく、こうして叶えることができた。
本を両手に挟み目を閉じる。
イメージするのは、暗闇だ。去年の夏に潜った実地訓練。比較的浅いといわれる四国沖の南海トラフだが、沿岸域を少し出たあたりの中部漸深底帯と呼ばれる1000メートルの場所を潜った。
まだジャックが事故死する前だ。
大丈夫だ。
その時の暗闇を頭の中で描く。
艇内は狭く暗く息苦しい。
広い海に憧れたはずなのに、人間は小さな泡の中でしか生きられないとは滑稽な話だ。
だめだ。
余分なことを考えたおかげで、また深海への恐怖が頭を持ち上げてきた。
本を挟んだ手を降ろし深呼吸する。
前を向くと、船室の壁に貼られた絵が目に飛び込んできた。
出発前に妻の映美が持たせてくれたものだ。
本を読んでから絵を描く授業の度に描いていた、夢にまで見た深海世界。
そこに怖いも恐ろしさもない。純粋な憧れがあるのみ。
そうだ。
ようやくだ。ようやくここまで来れたのだ。
ノーチラス号の世界へ。
この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?
