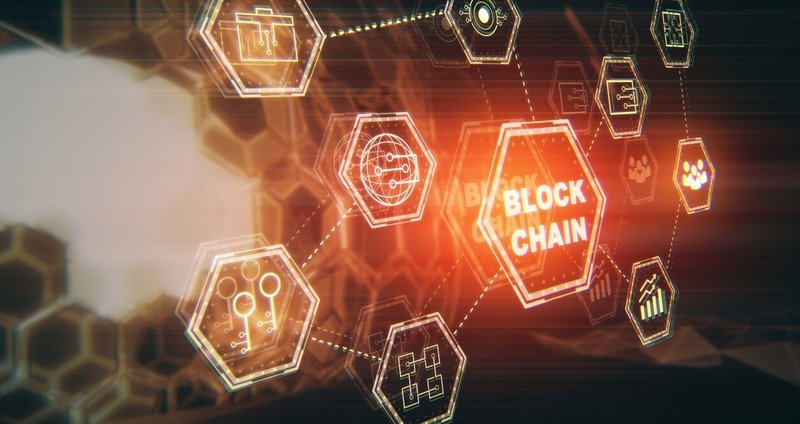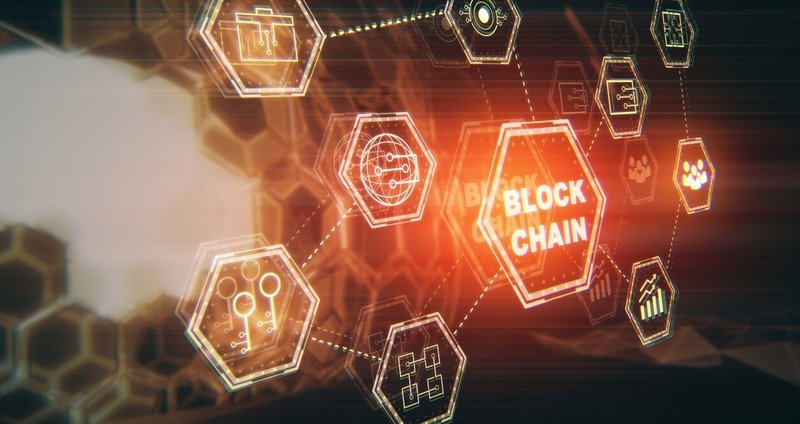ブロックチェーン入門_ #コラム:マイニングを個人がするには?暗号資産を得るよりも大切なこと
Bitcoin(ビットコイン)に代表される、ブロックチェーン上の取引データを承認し新しいブロックを生成する時に、膨大な量の反復計算以外では解けない計算式の解を求め、ブロックチェーンの連続性の正しさの担保に利用する仕組みを、プルーフ・オブ・ワーク(PoW)やマイニングと言います。ブロックチェーン戦略政策研究所の樋田桂一代表は「マイニングは仕組みやプレーヤーを変えながらもずっと続いていくものです。暗号資産(仮想通貨)を報酬としてもらえることに注目されがちですが、ブロックチェーンエ