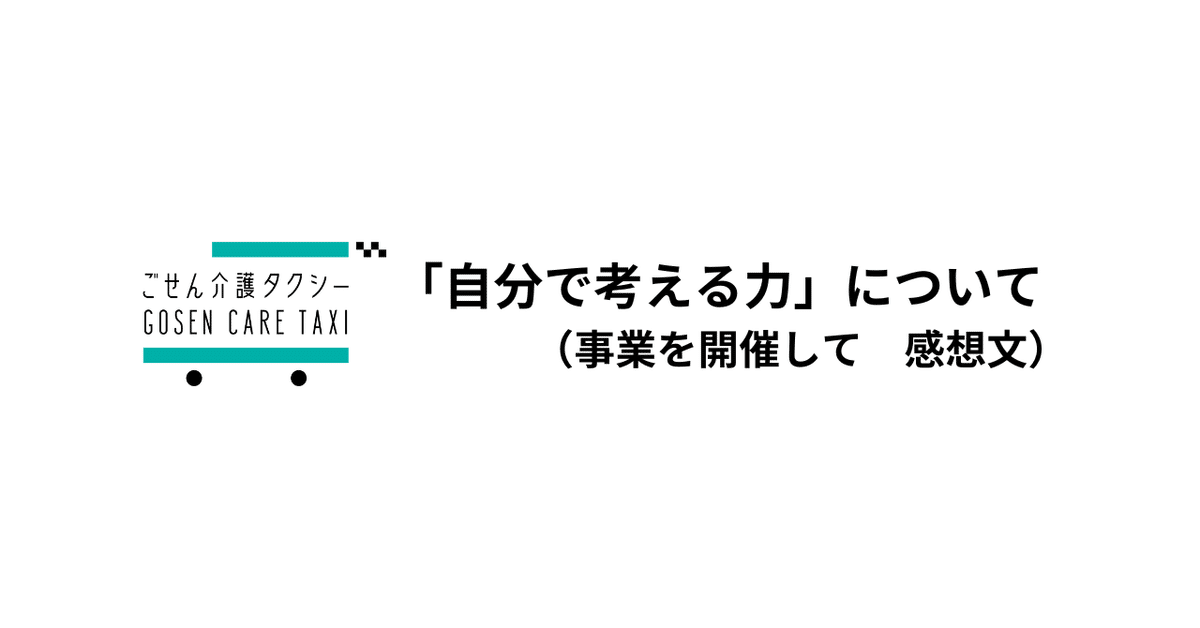
「自分で考える力」について(事業を開催して 感想文)
先日11/25㈯に五泉阿賀青年会議所(以下JCIと記載)の記念事業として、池上正さん講演会「自分で考える子どもに育てるヒント」と「山王中クエスト&逃走中ごっこ」を同時に開催しました。
私は実行委員長として、この1年間を、福祉タクシー業の傍らJCIのメンバーと共に準備に費やして来ました。いまは事業が無事に終わったことに安堵しております。

私がこの事業を開催したいと考えたのは、現代の便利すぎる環境に危うさを感じたからです。
今の時代は、スマートフォンで何でも簡単に答えが手に入ってしまい、個人が試行錯誤しながら得られる経験が抜け落ちています。子どもたちの遊び相手はもっぱらゲームかネット動画に成り代わり、人間関係の中で育まれるコミュニケーション能力が低下しています。また、大人も多忙を極め、子どもの話を聞いてあげる余裕がありません。つい自分の正解を子供に押し付けて、いつでもショートカットをさせてしまいがちです。
そこで、子どもたちには「自分で考える力」を育む環境が必要であると考えました。誰かの指示に従うだけでなく、大衆の流れに身を委ねるのでもなく、「自分で考え、決断し、行動する、力」です。
初めは、教育者や指導者、保護者など、子どもたちに関わる大人を対象にした事業にしようと思っていました。しかし、それでは「あなたたちは考えを改めなければなりません」と誰かを否定する事業になってしまいそうだったので、親が子どもたちと一緒に楽しめて学びになる事業に修正しました。
結果、100組の定員家族数は満員になり、総勢260人以上にご参加いただきました。
終了後の大人が記入するアンケート結果からも、
「とても勉強になった」「様々なことを再認識できるいい機会になった」「考えることは大切だと感じた」など、概ね皆さんに楽しんでいただけたと実感しています。
目的に沿った事業を計画しても、参加してもらえなければ想いは届きません。柔軟に対応して良かったと思っています。
「子どもたちに考える力を」とゼロから計画を始めたこの事業ですが、私自身が本当に考えさせられる1年になりました。背景・目的・方法に沿って、この事業を貫く一本の芯を整理する作業が本当に大変でした。
「そもそもそんな課題は本当にあるのか(背景)、何でそれをやりたいのか(目的)、他に有効な方法はあるのではないか(手法)」
私が出したアイデアに対して、毎月、JCIのメンバーからは激しく質問が投げられます。どんな質問が上がるか分からない中で、それに答えられるだけの準備が必要となりました。それは苦しいほどの自問自答の日々でした。
その自問自答の1年間で私が掴んだのは、「自分」という個の輪郭です。
・色々な人から意見をもらい、客観的に考え判断し、自分で決める
・関わって欲しい人に声をかけ、自分の想いを伝え、協力してもらう
・他者と自分の間で「自分」を見つめ直し、出た答えをまた他者に発信する
人と関わって生きていく上では、どうしても人とのやりとりが必要になってきます。そこに自分の想いをのせる場合、なおさらパワーが求められるのだと思います。(先日にいがた産業創造機構(NICO)の経営者向けの講習でも、リーダーに求められる資質について同じようなことが言われていました。)
私たち大人も、目まぐるしく変わって行く現代社会の中で、つい誰かの言葉に流されそうになるときがあります。しかし、そんな時でも自分でしっかりと判断できる力と、話を聞くだけでなく自分の気持ちをちゃんと表現できる力を備える必要があります。
子どもたちへの事業でありながら、計画した私たちや参加した大人たちが、何かを変えるきっかけに出来たように思います。それこそがこの事業の目的であったのです。
自分の本業を傍らに置いて(他のスタッフに任せて)、こんなにも地域活動に時間を割く年は今後やって来ないでしょう(というより、もうこりごり)。
ただ、そこまでして心血を注いだこの年を決して忘れることはありません。この経験を糧に、今後もごせん介護タクシーに関わっていただける方々の為に、努力して参ります。
この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?
