
一太郎スマイルの開発者に20年越しでお礼を伝えることができた日
「小学生のとき、一太郎スマイルを使っていた」という話が、会社のSlackで突如始まった。
「巻き戻し」の意味も伝わらなくなってきたこの令和でも、平成生まれはまだギリギリ、保存ボタンの「フロッピーマーク」を識別できる。
ただ、インターネット老人会には入れる世代ではないことを、僕は自覚している。
それでも僕らにも自分の生きてきた世代がある。
僕は少なくとも、一太郎スマイルは世代だった。
小学校の教育ソフトとして活躍していることを当時知る由もなかったが「気づいたらそこにあった」のが一太郎スマイルだった。
楽しい思い出はいつかその人の背中を押す
僕の職業はITエンジニアである。
一般的に見れば、勤務中ずっとパソコンと向き合い続ける仕事である。
現在26歳、僕がパソコンを初めて触ったのはおそらく小学校に上がった頃だった。
20年も前のことを、しかも小学一年生だった自分を思い出すのはそろそろ困難になってきている。
そういう中で、僕は「自分がいつパソコンを触り始め、タイピングを好きになり、友達とリレー小説までするに至ったか」を覚えている。
けれども、学生時代の僕は一切、IT業界に入るとは思っていなかった。
ITエンジニアの人に話を聞くと「中学生のときホームページを作ってた」「HTML, CSSはやってた」などなど、小さい頃から作り手に回っているケースがゴロゴロある。
僕はホームページがどうできてるかに関心はなかった。ゲームがなぜ動くかに関心はなかった。
僕の根底にあったのは「タイピングは面白い。文字打つの好き。パソコン楽しい」というシンプルな記憶だけだった。
"一太郎スマイル"がなければエンジニアになっていなかったかもしれない
家にも学校にもパソコンがあった。
ただ、小学校低学年では学校のパソコンは触れない。
僕は家にあるWindows98を触っていた記憶が、ほのかに残っている(おそらく2000年代中盤くらいまで家にあっただろうか)。
独特の起動音を出すそのOSを怖がりながら、僕はワープロソフト「一太郎スマイル」を立ち上げていたと思う。
どんな文章を書いてたのか、具体的なことは覚えていない。
けれども、画面キャプチャを見れば「あーそうそうこれ。これ使ってたよ」と声が出る。

引用: http://www.ita.ed.jp/edu/media/jyugyou/watanabe-taka4/smile.html
この画面は、小学校中学年になっても見ていた気がする。
学校でパソコンの授業があると、決まってこれを起動する。
キーボードの練習は僕にとって練習ではなかったとおもう。僕はきっと、その時誰よりも一太郎スマイルを楽しんだ。
僕はこの時に「パソコンは楽しいなあ」と思ったのか、小学校高学年から始まった「ナンチャッテ部活」で「パソコン部」を選んでいる。
内容はデジカメとの連携や、インターネットだったりで、実は一切プログラミングのようなことはしていない。
それでも楽しかったのを覚えている。
僕は潜在的に「パソコンが身近にある」ことが好きだったのかもしれない。
一太郎スマイルを卒業。Wordへ
6年生になると一太郎スマイルはいつの間にか卒業していたと思う。記憶はもう定かではない。
記憶の引き出しを片っ端から開ける。
この頃はWordでワープロしていた記憶が残っている。
このWordで、僕は友達とリレー小説を書いた。
好きなタイピングをたくさんするにも、もはや練習ソフトでは物足りず、物語を書き連ねる方法をとったのだろう。
その本人は知らないだろうけれど、僕はそのときの楽しい思い出が今の僕を作っている。
技術書典にサークル参加するのも、元を辿ればそこだった。
結局のところ、僕はいつ一太郎スマイルから卒業したのかわかってはいないが、教育ソフトとして最高の終わり方ではないだろうかと、今なら思う。
一太郎スマイルは僕のパソコン教育にコミットし、僕の今を作り、自らは鮮やかにフェードアウトした。
美しいなと素直に思った。
「エンジニア冥利に尽きます」
2019年、一太郎スマイル開発者に僕のエピソードが伝えられた
会社のSlackでの僕の発言。
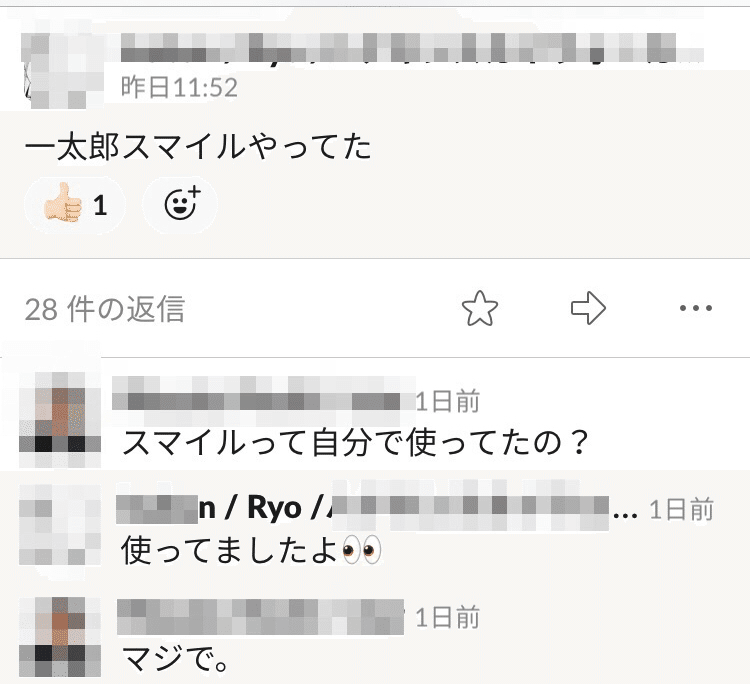
Windows98であったことなど、自分の記憶と少しずつ照合されていく。
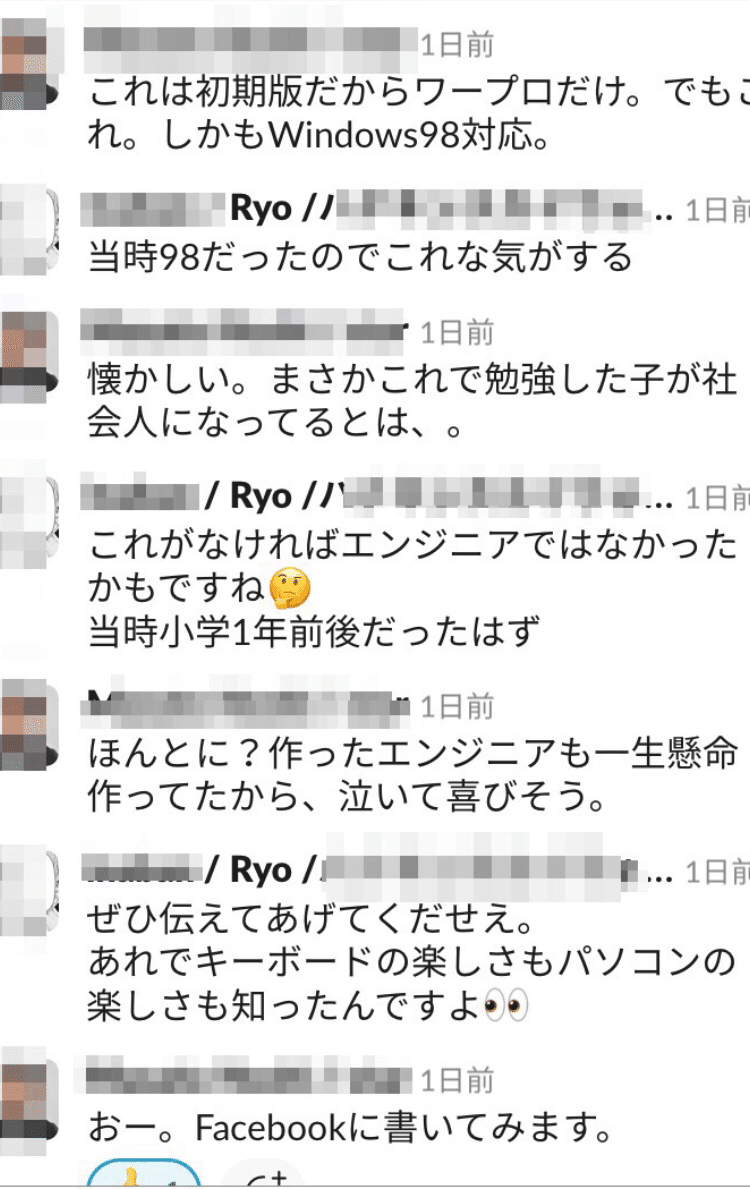
そして、ついに伝えられた瞬間だった。
開発者からの全返信内容はここでは伏せますが「エンジニア冥利に尽きます」という言葉を、確かに受け取った。
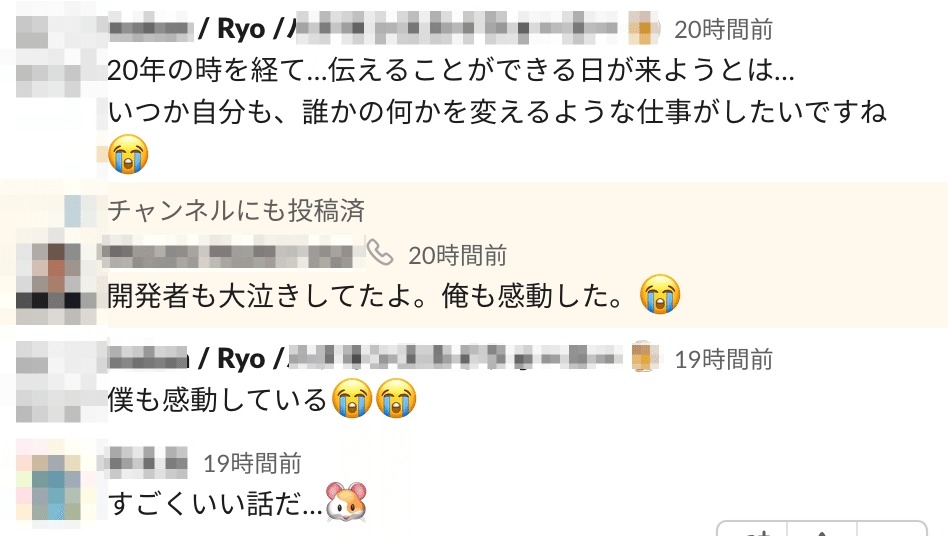
20年の巡り合わせ
彼らが一生懸命に作ったプロダクトを幼い僕が遊んで、巡り巡って自分もエンジニアになり、そのおかげかこの話を当人に伝えることができたと思うと胸が熱くなった。
もしもそれを言われたのが自分だったら?どれだけそれが嬉しいことか、想像に難くない。
たった一言の「エンジニア冥利につきます」というその返信に、彼ら開発者のこれまでの思いがぎゅっと詰まっているように感じた。
いつか自分も「エンジニア冥利に尽きます」と言えるような仕事をしたいと思える日になった。
「小学1年前後、一太郎スマイルで初めてパソコンとかタイピングの楽しさを知っていなければ今エンジニアではなかったかも」という話を社でしたら、一太郎スマイルの開発者と知り合いの人がいて、20年の時を経て僕の話が伝わった。
— VTRyo技術書典7@お29C:エモist出版 (@3s_hv) September 4, 2019
「エンジニア冥利につきます」
という言葉、いつか自分も言ってみたい
この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?
