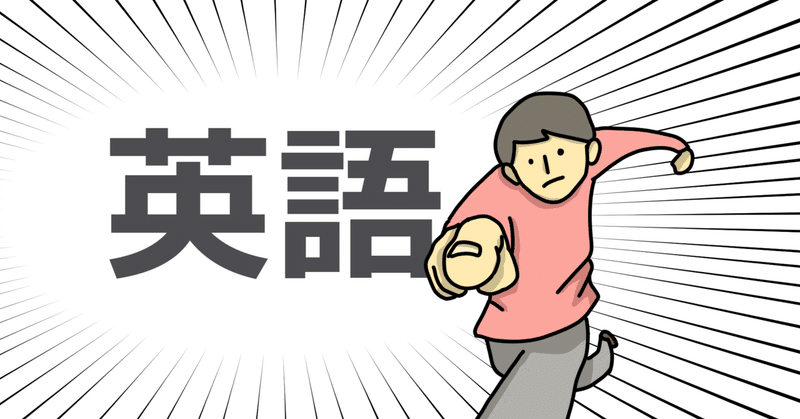
【研究日記】語彙を教えるとはどのようなこと?(多義語の「have」を例に考える)
こんにちは。飯島尚憲です。
現在、岩見沢駅にいます。
訳もなく、電車に乗ることがボクの仕事です。
そんな今日の出来事を報告します。
今日、話していくのは、ボクの研究している語彙指導に関するエトセトラの前提の前提知識になります。すなわちどういうことかというとなんで語彙指導をすることが大事なのかということです。これについては、Victoria university of WellingtonのPaul Nation教授が昨年の終わりに「語彙指導をすることは大事か」という趣旨の論文を出しています。それについて、書いていきます。
語彙指導という言葉は聞き慣れないですよね。よって、それがどのようなことを意味して、どのような効果があるのか、そもそも語彙を教えるというのはどういうことなのか、解説をしていくことにしましょう。それでは、始めます。
① 語彙指導をすること
語彙指導をすることは、少なからず大事なことであるということは、
これまでの論文などで、述べてきた通りです。
では、それを踏まえて、語彙指導をすることで何が生徒に得られるのでしょう。
僕らはそのための議論をしていなかったと思います。
よって、そのことについて、考えて行きたいと思います。
語彙指導というのは大事です。
では、どうしてなのかということを聞かれたら、
誰も答えられないというのが本音ではないでしょうか。
まず、先ほど、語彙指導というのは誰もが語れることではないということを話しました。語彙指導をすることはどのようなことなのか、ということです。
まず、語彙を指導するというのは、語彙の形と意味を教えることであります。
例えば、英単語のhaveについて。このhaveについてスペリングを教えること。
次に「持つ」などのさまざまな意味について教えることが大事だということ。
ここではhaveについて考えるということは多義語について考えるということですが、意味のフィールドについても考えていかなければいけません。
そして、そのためにはhaveという言葉の言語学的な知識を知っている必要があるのです。それでは、次のチャプターでは、haveについて知っているとは?というタイトルで話して行きます。
② 英単語haveについて「知っている」とは
英単語のhaveについて知っているということんはどのようなことなのか、
ということを考えて行かないといけません。
例えば、haveが「持つ」という意味であることを知っているというのは、
このhaveの持つ、一面としての意味を知っていることになりますよね。
このhaveがhasになるということを知っているというのは、
haveの文法的な側面を知っているということになります。
そしてhaveがどのように日常会話で使用するのか知っているということは、
haveの語用論的な側面を知っているということになります。
語用論のような側面を知っているというのは、会話において、とても大事なことだと思います。だって、実際に「英語を使える知識を知っている」から。
ボクが今、こうして書いたように「知っている」と言っても、
さまざまなバラエティーがあります。
まず、教えることは選択と集中を含みます。
教えるというのは、それらのhaveにおいての知識のどれを教えるのかということです。それはもちろん、教えるレベルなどによって、異なってくるでしょう。
しかし、意味を教えるならば、その背後には英米の思考があるので、それらについて教えることも大事です。では、教えることに関しての話に戻りますね。
では、どのようにして「仮に意味を教えるならば」教えれば良いのかということです。それについて、考えなければいけません。次のチャプターに移ります。
③ Semantic Fieldを教える
意味的な動機づけという言葉があります。
ちょうど、英語に直すと、Semantic Motivationになります。
認知言語学かつ、今の応用認知言語学(つまりは認知言語学の教育などへの応用を研究する学問)にめちゃくちゃ大事な概念です。言葉は意味が生成されて、それが色々な場面で使われていくことによって、意味が拡張されているといいます。
すなわち、haveのような多義語というのは色々な、たくさんの場面で使われるようになったので、多義語になったのだということです。
しかし、どのような場面でどのように使うのか1つ1つ解説していては、時間がとてもかかってしまい、非現実的な選択となってしまうでしょう。
そのためまず、生成の元となった中心義を教えることがとても大事なように思います。
よく、多義語の指導では、英語の参考書で書かれている「コア・ミーニング」を教えるということになります。
しかし、このコア・ミーニングというのは、ボクの主観になってしまいますが、その言葉のイメージを焼き付けるにはとても良い気がしますが、そのまま意味を覚えられるかということになるとそうはいかず、あくまでも「意味を覚えるための補助」のような役割をすることになると考えます。
では、コア・ミーニングを使って、英語を教えるというのは、上に書いたような意味の暗記の補助をする他に、何があるのでしょうか。次のテーマにしましょう。
まとめ
今日は以上です。
コア・ミーニングの指導に関しては、田中(1987b,1990)で盛んに議論されています。田中(1990)は学術書で「認知意味論―英語動詞の多義の構造」という本になります
ですが、コア・ミーニングを使った指導が実際に使われ出したのは2000年代になってからです。コア・ミーニングの元になっているのはBolinger(1977)のこの言葉です
「one form, one meaning」
1つの形には1つの共通した意味があるということです。コア・ミーニングを使って指導していくことはどのようなメリットがあり、どのようなデメリットがあるのでしょうか。コア・ミーニングをめぐる問題について、明日は考えて行きたいと思います。
2022/03/08(火)飯島尚憲
この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?
