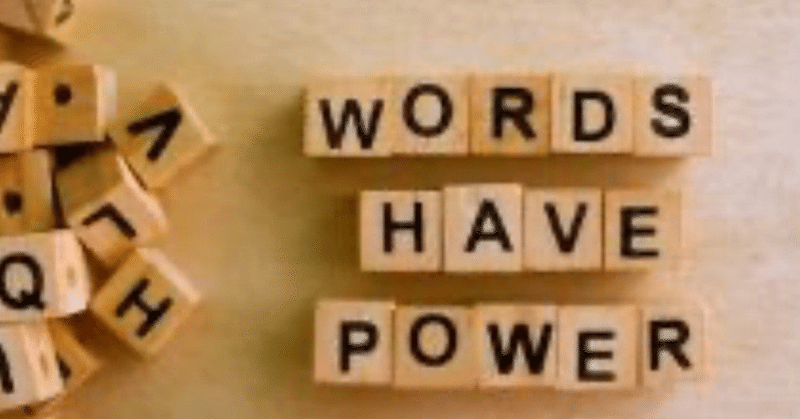
【多義語研究】多義語の研究で最近考えていること(Vol.2)
はじめに
もう何ヶ月も前、自分の研究課題である「多義語のパラドックス」について解説しました。そして、それから時間が経って書いて、さらに進展があったので、ここに書くことにしました。今の時点で、多義語の研究に関して思うところを書いてみることにしましょう。それでは、スタートです!
①過去に書いた記事
過去に書いたのは「多義語のパラドックス」に関しての記事。いわゆる多義語の定義に関して、あれやこれやと書いた記事です。記事のリンクは下に。
そこから時間が経過して、思うところがあるので、半ば殴り書きのような形で書いて見たのが下の記事。
両方とも、多義語の研究について、現在進行形で考えていることを書いた記事です。ちなみに、これらの記事、いいね!の割には閲覧数が多く、ネットで「多義語 論文」と検索するとこんな感じです。読んでくださった皆様本当にありがとうございます!

②多義語の研究をするのはなぜか?
研究に対するスタンスと言っても、さまざまなものがあります。おそらくは自分の「好き!」をもっと調べたい、追求したい!という思いがその根底にはあると思います。ボクの場合は、ベストな単語集を作りたい!というのが根底にあります。その設計ができればと思うのですが(果たしてできるか?
その時に、多義語は切っても切り離せない問題なんですよ。だって、辞書を見てみれば、大半の言葉は多義語です。さて、ボクが考えたいのは、その多義語を包括する理論です。多義語の理論を再発明すると言っても良いです。
なんでこんなことを書くのか。やはり、自分のしていることが、他人に貢献できないと、ボクは途端にやる気を失ってしまうからです。学部生の頃、塾講師とか予備校講師をやっていて、プリント作りと授業設計は誰よりもやってきたという自負があります。他人のために頑張るのは気持ちいいですね。
そして、はい!文字通り、多義語の理論を再発明しました!と言っても、理論を再発明しただけでは、学習者に貢献したことにはならないですよね。だって、学習者が多義語を実際の英会話の場面で使用、運用できなければ意味がないのでね。
つまり、どんなに素晴らしい理論を発明しても、それを使って訓練しないと学習している意味がないよ、ということです。ちょうど、数学で、三平方の公式を覚えても、それが問題で使用できないのと同じことが英語に対しても言えるということです。
ボクは、単なる自己満足ではなくて、他人が読んでくれるようなーできれば英語の先生や学習者にリーチできるようなー論文を書きたいと思います。
そして、社会にリーチするという目的で、ブログも続けていきたいですね。
他人のためなら、いくらでも頑張れます。
③分布意味論と哲学的な理論の融合
BERTとか、WordSmithとか、言語を定量的に分析できるツールが最近、言語の研究でも用いられるようになっています。おそらく、今後、理論寄りの言語学を研究している人は、言語を定量的に分析できるツールを使えないと研究をやっていけないのではないか、と思います。
従来のいわゆる「言語哲学」的な、どこまでも、深堀りしていくことには意味があると思います。特に、多義語の研究において言語哲学の果たしてきた役割はとても大きいです。定量的なこと、そして、言語哲学のようなある意味で定性的なこと。それらがブレンドしていくのではないでしょうか。
先ほど、ボクは「多義語の理論の再発明がしたい」と書きました。もちろんそれは学習者の腑に落ちるようなものです。例えば、オスロ大学のある研究者は「多義語は会話で徐々に使用されていく」といういわば語用論的な示唆をしました。研究の知見としてはとても素晴らしいと思います。
しかし「では、教育に応用するなら、どうする?」となったときにどうにもならないと思っています。最近は、教育文法、教育言語学という概念も出てきているので(もうだいぶ前から出ているけれど、最近になって論文や書籍が増え出した傾向にある)そういう実践もかんで含めて理論化したいと思っています(今、書いてみて、自分のしていることが思いのほか、壮大であーことに気づきました笑)。
④最後に
今日は、何で多義語の研究をするのかという根本的なことと、定性的なことと定量的なことの融合ができないと難しいということを書きました。これが研究者のみならず、研究の魅力を伝えられる何かになってくれればいいのですが…。とりあえず、メモしておきます。
この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?
