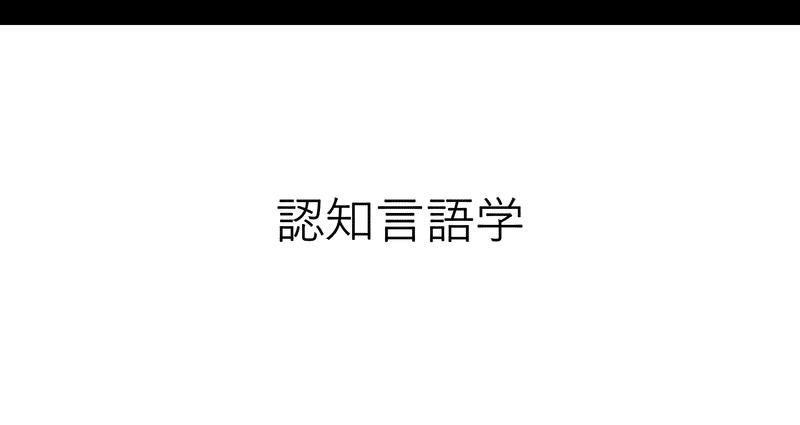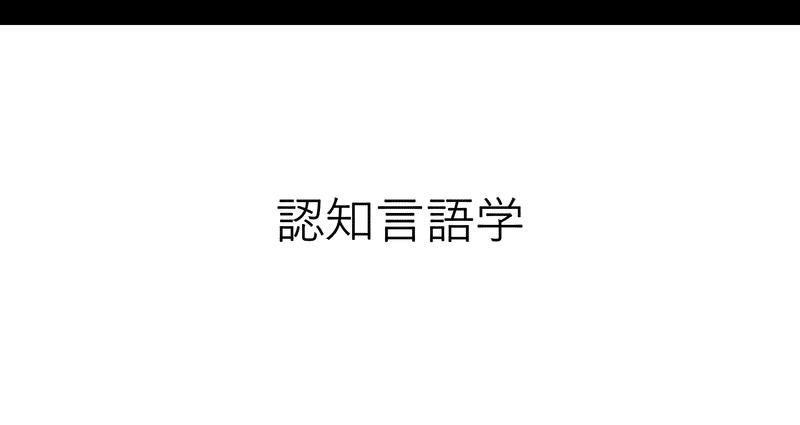認知言語学は言語学史全体にどのような貢献をしているのか?
概要認知言語学は、言語が人間の認知に組み込まれていることを強調することにより、言語理解に革命をもたらしました。文字通りの「革命」と言っても良いでしょう。この記事では、認知言語学の理論的革新、方法論、関連分野への影響に焦点を当てながら、認知言語学の言語史への貢献について考察します。
認知言語学の登場によって認知言語学の登場は、生成文法などの形式主義的な言語モデルから、人間の認知能力に不可欠な部分としての言語の理解へと、言語理論のパラダイムシフトをもたらしました。この転換は、言