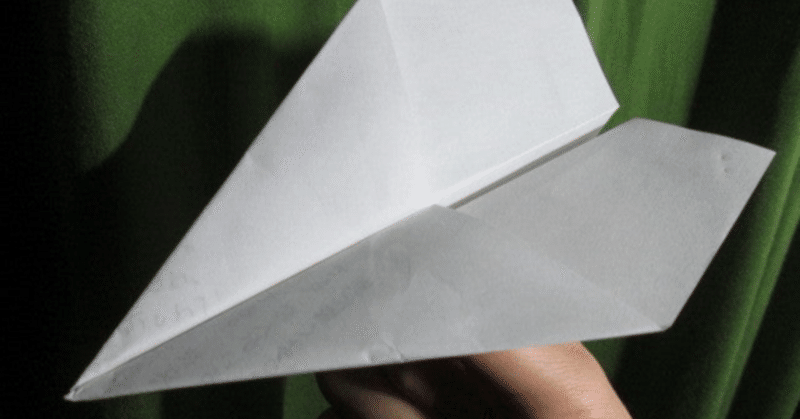
2023/6/15 スペースメモ
①Twitterの功罪
とにかく、自分の言いたいことを相手にぶつけず、Twitter内で吐き出すことには意味がありますね。傷ついているときに、自分を回復する手段として、とても有効。
でも、Twitterの構造上、同じ考えの人が集まりがちになって、考えも偏りがち。偏っているかも?という気持ちで上手に使って欲しいですね。
②支援で気をつけていること
長い間子どもと接していない別居親さんは、子どもの発達過程を知らないまま接していることが多いです。
久しぶりに会った→子どもがよそよそしいというのは、通常の反応。ここで、同居親が悪口を言っているのだと短絡的に結論付けると、面会の継続が難しくなることも。 同居親側も同様に、別居親と会うことを楽しんでないから必要ないのだと短絡的に結論づけるのは危険。
子どもには子どもの感情も、意思もあり、葛藤もあります。子どもに気持ちの整理をする時間をあげて欲しいです。 4~5回やると、子どもは「面会すること」に慣れてきて、そこからやっと別居親さんとの関係構築に入る、ぐらいに考えて欲しい。
③親の離婚を経験した立場の人とのお話
学校の中でも、親が離婚した子どもサークルのようなものができるけど、やっぱり親に会えているほうが、子どもも気持ちの整理がつけられるように見える。 全く会えていない、どこにいるかわからない場合、まわりもどのように接するのが正解かわからない。
親には親の人生もあり、いろいろあることはわかるが、やっぱりそこはがんばって欲しいかな、というご意見。 子ども同士で「会えないの?」「その話すると、同居親側がちょっと嫌な顔するからな~」のような会話があります。
両親が離婚しようと、一方の親と仮に全く会えていなくっても、子どもは親との縁が切れたなんて、考えもしていない。 親が離婚のことを気にしているのか、変に気遣ってくることもあるが、子ども自身は、離婚前と離婚後で、なんら変わるところはないし、同一人物。
変に心配し過ぎず、親にはただ、子どもを信じて欲しい。 面会ができていない友達もいたけど、それで同居親を責めるというようなこともなかった。 親同士が悪口を言い合うようなことを聞くのは、本当につらい。親の思いはわかるが、それは子どもには言わないで欲しい。ほかで発散して欲しい。
今回お話くださった方は、面会ができていた方でしたが、そこの親の努力というのは、自分が大人になり、親になってから、やっとわかるものかもしれない。 でも、絶対に通じる。 自分のために両親が努力してくれたことは、必ず通じる。
この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?
