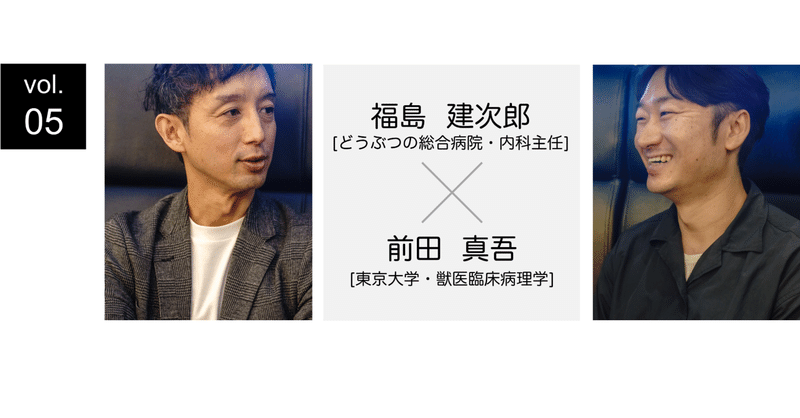
X Talk 5.2- 理想的な環境で幅広い学びが得られるアメリカ
獣医学研究者による対談シリーズ、“VET X Talks” (ベット・クロストークス)。5人目のゲストとして、「どうぶつの総合病院 専門医療&救急センター」(https://vsec.jp/)の福島建次郎先生をお迎えしています。
前回は、アメリカの獣医学教育の仕組みについてご紹介しました。専門医に認定されるには、大学入学から少なくとも12年かかるというのは驚きました。それだけに、トレーニングの内容と評価の仕組みが整っているようです。学生にとっても教員にとっても、理想的な環境でしょう。
今回は、アメリカの専門医について、福島先生の実体験に基づいたお話をうかがいます。
対等な獣医師として若手にも敬意を払う

--:前回、アメリカでは日本よりも臨床研究が評価され予算も確保しやすいとうかがいました。向こうに行かれた最大の理由は、臨床研究ですか?
福島先生(以下、敬称略):日本での診察や臨床研究に閉塞感を感じていたのは事実です。でも、一番の決め手はアメリカの専門医と会ってお話しする機会があったことです。知識の広さと深さが桁違いなのが衝撃でした。「このまま日本にいたら、こうはなれない」と思ったんです。
--:アメリカの環境は、福島先生の期待どおりでしたか?
福島:本当にありがたい環境でした。僕が行ったコロラド州立大学には、専門医が内科だけで7人いました。週に1回の“レジデント・ラウンド”というセッションがあるのですが、困っている患者さん(= 動物)についてディスカッションするんです。1つの症例について、なんと7人の専門医が議論してくれるんです。見落としていたことを教えてもらったり、提案をしていただいたり。「こんなに贅沢な環境があるんだ」という感じでした。
前田先生(以下、敬称略):専門医の先生たちは、やっぱり指導も上手なんですか?
福島:彼らは教育者としても優れていて、僕たちを完全に対等な獣医師として見てくれます。常に「君はどう思う?」と意見を聞いてくれますし、日本での経験も尊重してくれます。もちろん専門医として、言うべきことはキチンと言ってくれます。
--:若手の意見にも耳を傾けてくれるのですね。
福島:すごくオープンです。僕が「日本ではこうしていました」と言うと、彼らが良いと思ったコトは受け入れてくれます。「エビデンスが足りないな」と思えば、「そこは、少し検討が必要だね」という感じで、対等に意見交換できる関係でした。
--:"対等"ということは、インターンやレジデントに対する指導は厳しそうですね。
福島:それが、そうではないんです。アメリカの先生たちは優しいですし、自由にのびのびとやらせてくれます。教員1人にレジデントが3~4人ついて、レジデントは学生とペアで診療します。大きな部屋で、レジデントと学生が「あーでもない、こーでもない」と治療についてディスカッションすることがよくあります。

この日は、重度の免疫介在性溶血性貧血だった患者さんの再診。
「寛解して、まるまると太った様子に二人で喜んでいたところです」とのこと。
福島:指導教員は、それを聞いているんです。で、「介入しなきゃ」と思うと入ってきますし、「大丈夫だな」と思えばまったく介入してきません。よっぽど道を外れると「おいおい」って直されますが、そうでなければやりたいようにやらせてくれます。で、何かあっても、ちゃんとお尻は拭いてくれます。
前田:それは本当に素晴らしい先生たちですね。僕も大学教員になって10年くらいになるのですが、最初はいろいろ介入してしまっていました。最近ようやく、「信じて、任せて、待つ。そして『必要があればサポートするから教えてね』と声かけをする」という自分の中でのポリシーが固まってきた気がします。
専門領域における知識と経験の幅広さと奥深さ

--:アメリカでも、すべての動物病院がそういう体制ではないですよね?
福島:いわゆる町の獣医さんと専門病院は役割分担がはっきりしています。日本は町の獣医さんがCTのような高度医療機器を持っていたりしますが、向こうではCTが必要な場合は専門医のいる二次病院に行くのが普通です。日本には、MRIまで備えた(一次診療の)動物病院もありますよね。それはとてもすごいことなのですが、私は撮影も読影もやはり専門医が行った方が安心だと思います。
--:アメリカの方が獣医療のレベルが高いのでしょうか?
福島:アメリカの専門医がすごく高度な医療をやっているかというと、必ずしもそうではありません。世界標準、つまり「これがあたりまえの診断法と治療」ということを広く深く理解しているのが専門医です。
専門医の診察は基本にとても忠実です。したがって、専門医が関わることで診断の正確さが担保されます。日本の場合、そのクオリティを担保する専門医の資格が存在しないので、だいぶ“バラつき”があると思います。
--:なるほど。バラつきがあるというのが正確なんですね。
福島:そうですね。レベルというよりも、専門領域全体を確実にカバーできる知見とその深さでしょう。僕が東大で臨床をやっていた時は、消化管や肝臓、すい臓の病気を主に診ていました。そこの知識には自信がありました。
でも、内分泌が関係したり腎臓の話になったりすると、僕の知識レベルは極めて低くて…。他のことに話が及ぶと分からないんです。標準治療はどんなことがされていて、どういうことが正しくて、何が間違いなのか。
--:一点集中型というか?
福島:そういう先生が日本にはすごく多くて、「腎臓はメッチャ得意です!」って言っても、ほかの部分の知識が不足していたりします。レーダーチャートにしてみると、どこかが飛び出している先生はいるんですが、バランスよく五角形や六角形が描ける先生はほとんどいないんじゃないかな。
--:でも、臓器は全部つながっていますよね。
福島:その通りです。アメリカで学び直して改めて認識したのは、身体のシステムって全部がつながっているということです。どこかの知識が欠けていると、動物を“有機体”としてしっかり診れないんです。想定と違う何かが起こった時、対処できなくなります。アメリカに行って、特に最初の頃は自分の力不足を痛切に感じました。
--:経験値というか、症例数の差もありますか?
福島:カリフォルニア大学のDavis校に、スタンリー・マークスという消化器ですごく有名な先生がいます。講演を聞きに行ったことがありますが、犬の嚥下障害の症例を400頭分くらい集めて解析した研究についてでした。
その頃、僕は日本獣医内科アカデミーで実行委員をしていました。次の学会で嚥下障害を扱うことになり、講演を誰に依頼するかという話になりました。「あの先生が、犬の嚥下障害に関するケースレポートを1本書いていたはず。その先生に頼もう」なんて…。1症例 vs 400症例です。それぐらい、アメリカの専門医との間には症例数の開きもありますね。
--:専門医というシステムがあるから、マークス博士はそれだけたくさんの症例数をもっているということですね。
福島:そうですね。あと、大切なのは、彼は他の知識もあるわけです。レーダーチャートで言うと大きな正六角形があって、さらに消化器のところが飛び出しているんです。また彼は内科だけでなく獣医栄養学の専門医資格も取得しています。大学側も、彼が臨床研究をやることに価値を見出して、潤沢な資金を投入する体制ができています。
前田:アメリカの先生たちは、多施設で共同して臨床研究を進めるのも上手ですよね。システムを作る文化があるというか…。日本の獣医学研究者も見習わないといけないと思っています。
「人の役に立たなくても、目の前の犬や猫が助けたい」

--:日本の大学では、そうはいかないのですね。
福島:たとえば、犬のごはんの飲み込み方は、ヒト(= 医療)にまったく役立ちません。でも、アメリカには、とにかく犬の飲み込み方を調べている人たちがいます。そこに資金も投入され、何百例というデータを集めています。実際に嚥下障害の犬たちが助かる成果が出ています。こういうことが僕のやりたいことなんですが、日本の大学ではたぶん無理だろうな…(笑)
--:日本では、分かりやすいメリットが必要なのですか?
前田:日本の場合、ヒトにつなげないと基本的に大きな予算はおりないんです。
福島:「ヒトの役に立つ」というのがポイントです。トランスレーショナルリサーチ(*)が注目されているのも、そういった背景からです。前田先生のように犬の病気からヒトの病気につなげていくというアイデアで勝負していくのは素晴らしいと思います。でも、僕自身はどこまでいっても臨床獣医師なんです。「ヒトの役に立たなくても、医学に直接的には貢献しなくても、目の前の犬や猫が助かればいいじゃん」って、そんな研究がやりたいんです。
*「橋渡し研究」とも呼ばれる概念。基礎研究で新しい医療の種(シーズ)を見つけ出すところから始まり、実際の医療技術や医薬品として実用化するまでの幅広い研究活動のこと。獣医学研究では、イヌやネコの病気とヒトの病気を結びつけて獣医学・医学の双方が発展することを目指した研究を指すこともある。(VETS × TalksのVol. 4で詳しく紹介)
--:前回、製薬やフードなど動物関連企業が臨床研究をサポートするという話がありました。アメリカでそれができるのは、産業構造の差なのでしょうか?
福島:それもあるとは思います。あとは、動物福祉に対する考え方も違うような気がします。
--:ヒトにつながらなくても、動物福祉の向上につながれば評価するという考え方ですか?
福島:はい、評価されます。それから、獣医師とヒトのお医者さんの社会的地位が近いのも要因だと思います。マークス博士も、食道の病気を外科的にどう治療するかという時に、ヒトの外科医を呼んで共同研究したりしています。
--:アメリカに行かれたことは、本当に得るものが多かったんですね。
福島:そうですね、見聞も広がりました。日本にいたら得られなかった考え方や、向こうで築いた人脈も、大きな財産ですね。
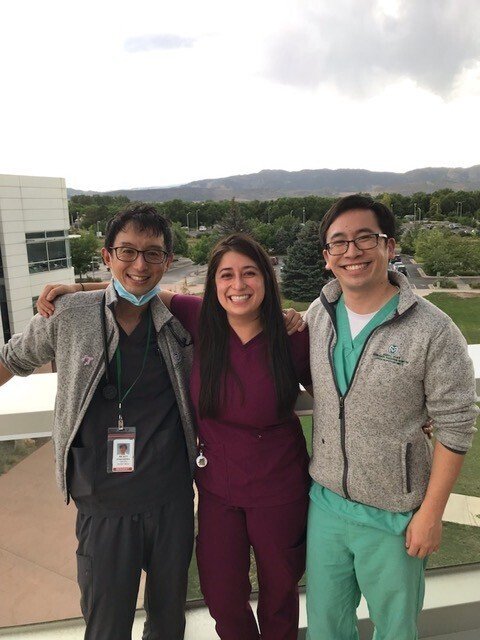
レジデント時代の同期Kennyさん(右)とCindyさん(中央)。
--:帰国後すぐに今の病院に入られたのですか?
福島:はい、今の病院にはアメリカの専門医が大勢います。お互いの守備範囲が分かっているので、働きやすいと思いました。あとは、担保ですね。
画像診断部門が画像の水準は担保してくれて、検査のレベルは臨床病理部門が担保してくれます。内科の診断は、画像診断や検査結果の上に成り立つので、ここが不確かだと内科医の仕事ができません。
前田:アメリカ獣医専門医が、それぞれの分野で一つの施設にいるのは福島先生が勤務されている「どうぶつの総合病院」しかないですよね。日本では、ここだけです。腫瘍とか、特定の分野だけ専門医がいる病院は他にもありますが。
犬の嚥下障害だけでも、400以上の症例を集めて研究する専門医がいるアメリカ。そのほかにも、様々な分野・病気を深く突き詰める臨床研究が行われているようです。それ自体がもちろん"すごい"ことですが、そんな獣医師が育って活躍できる環境があるというのも素晴らしいですね。
個人的な感想ですが、今回の対談では福島先生のこのコメントが心に残りました:「ヒトの役に立たなくても、医学に直接的には貢献しなくても、目の前の犬や猫が助かればいいじゃん」。次回は、日本の獣医療がもっと良くなるためにアメリカから学びたい点を中心にお話を聞きます。

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?
