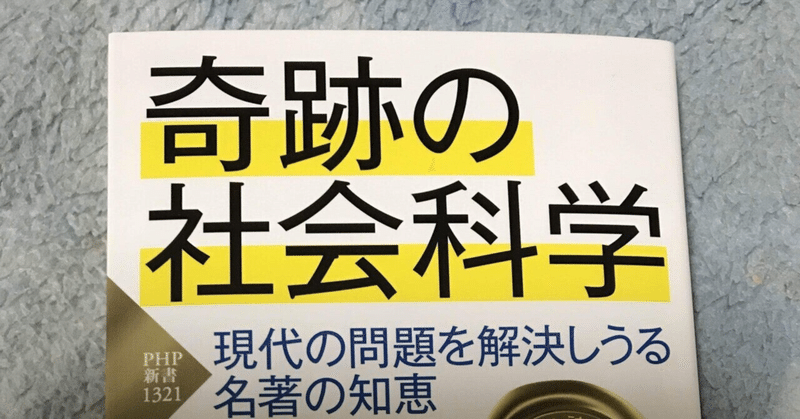
「奇跡の社会科学」(中野剛志著、PHP新書)トクヴィル①
たまーの2連休をお布団の中で過ごしております🍊
ぽんニャンです🐱
さてさて、今回からフランスが生んだ天才政治家トクヴィル編に入ります。
絶対著書を買って読みたくなりました😃
では、どーぞー😃
フランスの政治家、アレクシス・ド・トクヴィルは、独立して50年しか経っていないアメリカを視察し、民主政治の恐るべき本質を見抜き、「アメリカの民主政治」を出版した。
この本は、社会科学を学ぶ上で、重要な書である。
トクヴィルはアメリカの民主政治を視察して、専制政治を発見した。
トクヴィルは、民主政治の意思決定が、基本的に多数決であるところから、専制政治であることに気付いた。
民主政治で多数の意見が正しいということには、人々の能力に優劣が無く、平等だからという暗黙の了解がある。
トクヴィルはそれを「知性に適用された平等」と呼んだ。
トクヴィルは「多数派の支配が絶対的であるということが、民主的政治の本質なのである。なぜかというと、民主政治では多数者の他には、反抗するものは何もないからである」と言い、「多数者の専制」と呼んだ。
多数者とは「世論」のことで、世論に左右されるのが、多数者の専制。
間違いを指摘する少数派ひ排除されるのみ。
これは20世紀に入り、「全体主義」として知られるようになった。
実際、民主的なワイマール共和国からナチズムが生まれた。
少数派の言論の自由を侵害しているのは民主政治。
「数の政治」は民主政治だが、自由には反している。
ヨーロッパ君主の専制政治は、物理的な暴力で国民の自由を侵害したが、精神的なことには及ばなかった。
しかし、アメリカの民主政治による「多数者の専制」は、物理的な暴力ではなく、少数派を精神的に追い込み、黙らせる。
トクヴィルはここに戦慄した。
日本でも、小泉純一郎元首相が郵政民営化を断行した時、反対派の勢力を「抵抗勢力」と呼んで世論を煽ったことがあった。
結果、落選した議員達は沈黙してしまった。
また、近年のコロナ禍での「自粛警察」は記憶に新しいところだろう。
トクヴィルはさらに踏み込んで現している。
それは多数派の者達が、少数派の者達の権利を奪い、声をあげづらくさせる光景。
さながらそれは、少数者にとっては生き地獄と呼べるものではなかろうか。
トクヴィルは「アメリカでは、人々の精神はすべて同じモデルで作られており、また、そうであればこそ、それらの精神は正確に同じ道を辿っていると言えよう」と書いている。
アメリカは多様性の国家のように見えて、強烈な同調圧力があることを指摘している。
ウェーバー編②で紹介した社会学者ジョージ・リッツアが提唱した「マクドナルド化」のように、アメリカ人は、製品やサービスを徹底的に標準化・画一化するのを得意としている。
トクヴィルはそれを民主政治によるとしている。
日本においても、アメリカの民主政治を見習うほど、同調圧力が高まっていくということ。
次回に続くわけですが、今日本でも多様性をうたわれ、小さき声の人達が少しずつうねりを作り出しています。
では、その人達が多数者になり、なかなか認めづらい人達が少数者になったとしたら?
その時は、それも多様性の一つとして、受け入れられる社会であればいいなぁと思います。
コロナワクチンについて、厚労省は接種するしないは本人の判断としていました。しかし、医療福祉の業界ではどうだったでしょうか?
「利用者、患者を守るなら、接種して当然」
そんな空気が流れて、公言していた専門職も見られました。
有名なインフルエンサーが提唱することには疑いなく従う空気があるなど、この業界は同調圧力がおきやすい業界であると感じます。
もちろん、多様性も感受する業界でもありますが。
では、次はトクヴィル編②をまとめます😊
この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?
