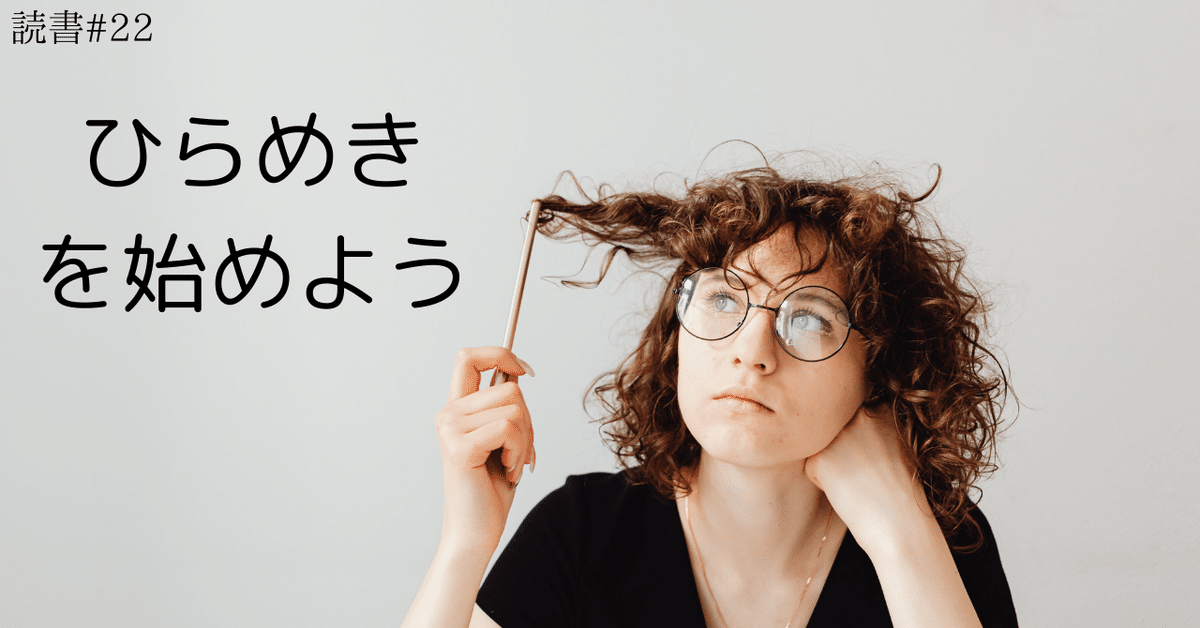
読書#22「超ロジカル思考」著:高野研一
どんな本?
我々がそうしたロジックを越えた直観力を習得するにはどうすればいいのか。
ミスリーディングというか、この本を手に取る方の中には、ロジカルシンキングに関する内容を思い浮かべる方もいるのではないだろうか。
なので、まずそうではないと断っておく。
”超”とは、超えるという意味なので、ロジカル思考を飛び越える、つまり、アンチという意味で用いられており、ロジカル思考ではないという意味である。
直観力。それがロジカル思考ではないものの答えらしい。この本では、直観力を得るためにはどうすればいいかを、エクササイズを含めて紹介されている。
とりあえず、名前を変えた方がいい。内容に合わせて”ひらめき力”とかにさ。
気づきは?
インプットしよう
行ったことのないところへ行き、会ったことのない人と会う
とにかく新しいものを頭の中にインプットしよう。
ロジカル思考とは既にある知識や法則の整理に本質がある。とすると、その知識が不足していてはロジカル思考では対応できない。ならば、知識を増やせばいいという考え。
この考えは、「脱・失敗学宣言」、また「直線は最短か?」でも行われている。とくに弁証法の考え方に近く、新しい知識を組み合わせることで、今までにない発想をしようというもの。
この新型コロナでパンデミックしている世の中で実行するのはなかなかハードルが高いけれども。
ロジカルシンキングの限界
自分の器を超える問題を解くためには、分析力やロジカルシンキングだけでは限界があるということだ。イマジネーションを広げる力、目に見えないものを見る力こそ必要になることがわかる。
言っていることは弁証法と似ている。ロジカルシンキングは、そもそもそういった未知の問題を解決するために使うものではないのだけど。
ただ、イマジネーションを広げる力はまだいいとしても、目に見えないものを見る力はいささかまやかしが過ぎる。
私の理解では、既にある知識を整理して解くのが論理的思考で、新しい知識を組み合わせて新しいものを生み出すのが弁証法。いずれにしても、新しい知識を増やすのはいいことだ。
ただし、比べるものではないということを注意しておきたい。
常識は本能と不可分である
「常識」がやっかいなのは、それが本能と一体不可分であることだ。常識を疑うということは、本能を疑うことに等しい。(中略)情報革命によってこれまでの常識や前提条件が崩れ去る時代においては、本能を疑える人が勝ち残るのである。
特に論拠はどこにも示されていないけれども、常識と本能とが不可分であるという考え方はおもしろい。
本能とは直感のことである。そういう意味では、この本はここに大きな矛盾がある気がするのだけど、好意的に解釈すると、本能を超える直感があるということだと思われる。
基本的に、常識を疑うことはできない。なぜならば常識は本能だからだ。普通に考えると本能に従って結論が出る。ここまではわかる。
では、本能を疑うとはどうするのか。論理的に考えれば、直感の逆をする。ぱっと思いついたことは本能に基づいているので、その逆を試してみる、思考してみる。
一方で、新しい知識をインプットして、本能をアップデートさせるという方法もある。この本は、どちらも書かれている気がするけれども、明確に分類はされていない。
本能に逆らうのはつらい作業なので、私はどちらかというと本能のアップデートの方がいいのではないかと思う。
この記事が参加している募集
この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?
