
オープンな採用を自社が体現したい ~HERP Culture Deckを公開しました~
調達・ミッションのアップデートの発表について
先日HERPのシリーズB調達・ミッションのアップデートを発表した。
「採用を変え、日本を強く。」
新ミッションはこれまでよりシンプルにHERPが目指したいことを表現できていると感じる。PARK田村さん、飯田さんにご協力をいただけて感謝。
ミッションのアップデートについての代表 @fabichiroxの記事はこちら。
ではHERPはどのような採用を目指すのか。
目指したい採用の仮説として、「オープンな採用を支え、事業成長を加速させる。」というプロダクトビジョンを新たに置いた。
そもそもプロダクトビジョンって何?という方は下記記事を読んでほしい。
本記事ではHERPが目指したい採用と自社での実践について書きたい。
以下あたりの方にぜひ読んでほしい。
・HERP/HERPが目指したい採用に興味がある方
・採用広報・自社の発信を強めていきたい、Culture Deckをこれからつくっていきたい採用担当・人事の方
・SaaSビジネスでプロダクトビジョンの設定などに携わっている,興味のある方
飾る採用から、さらけ出す採用へ
▼ 「オープンな採用を支え、事業成長を加速させる。」
オープンな採用は一言で言うと、飾る採用ではなく、さらけ出す採用だ。
表面的な会社の情報だけではなく、自社のやりたいことや課題・組織文化・どのような人間がいるかなど企業の内情を入社前から伝えていく。
これは言うは易く行うは難しで、やりたいと思っていたり、やると言っていたりしてもできていない会社が大半だと思っている。
▼ 内情を伝えると何が嬉しいか?
1. 相互に期待と実態のギャップを減らせるため、長く継続的に働きやすい関係につながる
2. 相互にやりたいことの両立に近づけられる
(企業のミッション達成や組織文化に共感した人が集まりやすくなる)
3. オープンな採用の実践自体が採用の競争力になる
特に1の期待値ギャップが生まれないことは従業員体験の鍵となる。
従業員は会社での体験に対して何かしらの期待を抱いており、その期待と実態のギャップがエンゲージメントに影響が出るよという話。
UX周りで使われる予期的UX(利用前のUX)、一時的UX(利用中のUX)などの概念はEmploee Experienceでも同じように当てはまる。
EXについての詳細は下記記事。
さて、その候補者にとって入社後の最良な状態とは、どのようなものだろうか?ずばり、蓄積された期待値と、入社後に触れ合うすべてに全くギャップが無い状態だ。さらに言えば、その期待を良い意味で超えた体験があればその従業員のエンゲージメントが高まることは容易に想像がつく
Amazonはハードワークな環境であるが、ハードワークな環境と初めから伝えているから期待値ギャップが生まれず、エンゲージメントが高いという話は興味深いし納得感はある。
ハードな環境のため、離職率も高い。しかし、Amazonが明確なのは「ワークライフバランス」のスコアも、「離職率」のスコアも、Amazonにとっては重要ではないということだ。そしてそれを明示し、そこに期待する人はAmazonは合わないと最初から言い切っている。つまり、彼らが大切にする価値観が彼らが発信するメッセージから大変クリアで白黒ハッキリしているため、変な期待値はそもそも生まれないのだ。
なぜ企業は内情をさらけ出す必要があるか?
できるだけ平易に書く。
▼ 理由1:企業が選ばれる時代になったから
労働人口は不足し、求人倍率は右肩上がりの売り手市場に。企業は選ぶ側ではなく選ばれる側になった。
選ぶ時代には大量に来る応募からどう自社に合う候補者を見極めるかが大事だったが、選ばれる時代には企業は、自社の候補者への能動的なアプローチが求められる。要は以下のようなシフトが起きていると理解している。
選ぶ時代の採用:どう見極めるか(ジャッジ)が大事
⬇️
選ばれる時代の採用は:どう口説くか(アトラクト)が大事
候補者に対して能動的にアプローチをしていくに際して、企業はより一層の自己開示が求められている。
▼ 理由2:飾っていてもバレる時代になったから
Twitter,Facebook,InstagramなどSNSや口コミサイトが発達し、求職者は求人サイトだけではなくSNSなどでの個人の発信する情報をキャッチするようになった。
隠していても会社の実態が今まで以上に外に出ていくようになったということだ。
---
HERPは上記のような文脈で今の時代に必要とされるオープンな採用をプロダクトを通じて支えていきたい。
HERP Hireは人事と現場のプロフェッショナルのスクラム採用を前提とした選考コミュニケーション基盤。
HERP Nurtureは企業から社外への積極的な働きかけやオープンな情報発信を通じ、候補者との中長期的な関係性構築を担う基盤
といったように候補者コミュニケーションの基盤を複数プロダクトを通じて構築していく。
より詳細は下記を読んでほしい。
自社が一番オープンな採用を体現する
新しい価値観や業務を企業に提案する主体として、自社が体現したい。
Salesforceがなぜ売れるか。彼らがSalesforceを使い込んで、それを元に成長を作っているからこそ説得力がある。
HERPもオープンな採用を体現し、HERPシリーズがそのプラットフォームとして存在しているからこそ実践できているということを伝えていきたい。
一歩目としてのCulture Deckの公開
先日のリリースに合わせてHERP Culture Deckを作成し、公開した。
社内への方針浸透をメインの目的とし、社内外への発信を可能な限り同期するというコンセプトで作っている。
▼ そもそもCulture Deckって何?
企業文化をまとめた文書、と捉えている。
下記事例を見るのが早いのでイメージがつかない人は見てほしい。
自社の企業文化を誰にでもわかりやすいように「明文化」し、それを「Culture Code」「Culture Book」といった形で公開する企業が増えてきています。
スタートアップ界隈でも採用ピッチ資料やCulture Deckや会社紹介資料や色々なネーミングで作成されている。
HERPでも会社紹介資料自体はあったが、今回新たにCulture Deckという体で作成し公開した。
▼ Culture Deckをなぜ作り、公開したの?
オープンな採用を体現していくにあたり、そもそも中に対してオープンでないとどうにもならない。HERPはオープンな文化を重んじていて、気軽に情報が手に入れられる会社ではあるが、メンバーから、何をしていきたい会社かわかっていない、中長期の方針が見えないという声は上がっていた。
情報が手に入る一方で、そもそも何をやっていきたいかという言語化があまりできていないことが原因と考えている。
あわせて、潜在的な候補者からも以下のようなフィードバックをもらっていた。
・企業として何を実現したいのか、そこに向かってどう歩んでいくのかが理解できていない
・採用管理ツールからスタートし、結果最終的にどうなっていきたいのかという絵図が知りたい
今回のCulture Deckは、上記課題に対してメインターゲットは社内メンバー向けとして、社内向けの文書を外部にも公開するという方針を取っている。

▼ こだわったこと・工夫したことは何?
ポイント1:背景にある思いを言語化する
単純にミッションやバリューの言葉だけを並べるだけではなく、背景にある思いやこれまでの歴史を紡ぐようにしている。
参考:ミッションアップデートの背景、創業からこれまでの思いの変遷

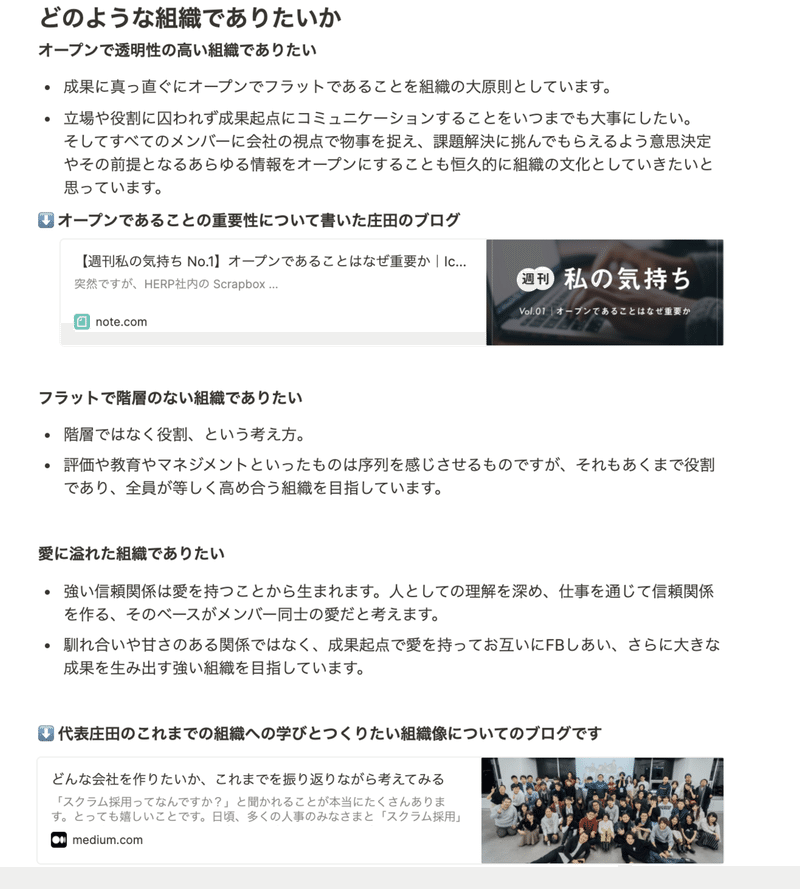
ポイント2:共有コストを可能な限り減らす
とにかくリアルタイムに内外に共有したいため以下2点を実施している。
1. 社内向けのドキュメントを社外にオープンにする
上の位置づけにある通り、メインターゲットは社内メンバーである。
社内向けに更新していくものを常に社外にも発信することで複数同期する手間を減らす。
すでに候補者の方には本ドキュメントをお送りしていて、かなり読み込んでいただけていることも多いのは好感触。
2. 更新のしやすさを踏まえてspeaker deckからNotionへ
keynoteで作成してspeaker deckで公開するという手間が更新をサボる要因となっていたため、可能な限り簡単に更新できるようにNotionに移行した。
以上がHERP Culture Deckについて。
より詳細なアジェンダは下記なので気になる人はぜひチェックしてください。

これからのHERP
HERPは、自社がオープンな採用を体現しながら、オープンな採用を支えていけるようHERP Hireに加えてHERP Nurture、新しいサービスの開発を進めていきたい。
Culture Deck自体もまだまだ作ったばかりで今後更新できるかどうかが鍵である。そもそも各所からの導線がなかったり、情報が不足している部分が多かったり、アップデートし続けていきたい。
以上。
もし本内容についてより詳しく話を聞いてみたいという方がいらっしゃったらぜひ以下から話しましょう。
調達に合わせたイベントも実施予定なので興味ある人はぜひ。
この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?
