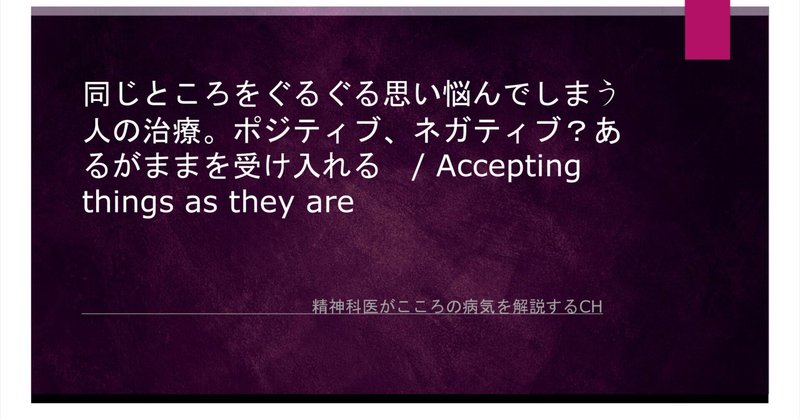
同じところをぐるぐる思い悩んでしまう人の治療。ポジティブ、ネガティブ?あるがままを受け入れる/ 精神科医がこころの病気を解説するCh
お疲れ様です。今日は、益田先生のYoutube から、1本アウトプットしたいと思います。ちゃんと字幕がついてテキストで理解できるので、インプットしやすく、アウトプットしやすいです。この字幕は絶対続けてほしいです。お願いします!益田先生!
01:35 問題を正しく認識する
05:59 ネガティブ・バイアス
07:36 認知行動療法
08:19 協働的経験主義
09:47 正しく認識することの欠点
◎本文にも書いてある通り、一時的な嫌な思いや、気分の落ち込みは、僕は9時間睡眠を強制的に取ることで、に取ることで大体程度が軽くなりますそういうお話ではなく、1つのことをずっとぐるぐる反芻思考してしまうのですね。
◎自分がネガティブで、メンタルが弱い人間なんじゃないか問思ってしまいますよね。
■問題を正しく認識する ポジティブネガティブに左右されず、正しく認識するにはどうしたらいいのでしょうか? 大野先生の認知行動療法マニュアルから、そのヒントを引っ張ってきました。 大野裕著「保健、医療、福祉、教育にいかす簡易型認知行動療法実践マニュアル」(きずな出版 2017) この本の冒頭で話されていますが、認知行動療法において大事なのは「正しく認識する」ということです。
よく例えられるのが「コップの水」問題です。 気分によって人は見え方が変わります。 気分、立場、状況によって見え方は変わるのです。「何かポジティブに見える方法はないですか」「自分の気持ちを切り替える方法はないですか」と診察室で聞く。
これは本質的な解決策にはなりません。冷静になると「これだけの量」なのです。
ですから、問題は存在します。 アドラー心理学では「トラウマは存在しない」と励ましますが、実際にはトラウマは存在します。 当然存在しますし、問題はありますし、障害も病気もあります。 なくなってはいないのです。目の前にあります。
それを「正しく認識する」ことが重要だと考えます。患者さんの訴えというのは、きちんと存在するのです。 周りの人がいくら否定しても、それは相手を騙す意味でも励ます意味でも、問題は存在します。
ですからそれを正しく認識することが大事です。 発達障害で問題があったとしても、程度はこれくらいなのだ。 一喜一憂せず、自分の特性、能力、障害、病気を正しく認識することが重要です。
その上で解決できる問題を一個一個建設的にやっていけば、結果的に治療は進んでいきますし、良い人生を送れるということです。 まやかすのではなく、正しく受ける、認識することが非常に重要です。
◎いくら、ポジティブ心理学やプラス思考の本を読んで勉強した所で、僕のメンタル疾患が消えるわけではないし、これからも一生、服薬して、メンタル疾患と付き合っていくという事実は変わらない。ということをネガティブでもポジティブでもなくただ事実として理解する。そしてよりよく生きるためにできることはなにかを自分の頭と読書、実生活の中から勉強するのだ。
■ネガティブ・バイアス 実際、人間は物を悪く見てしまう時があります。 気分の問題、精神的な疲労、そのときの状況、生い立ちの問題などがあり、ネガティブに物が歪んで見えてしまうことがあります。 僕らは正しく認識しようと思っても認識することができないのです。
人間には心というものがあり、気分、疲れ、状況、過去の記憶などがあるので、正しく認識しようとしてもできません。 生まれつきできるできないというものではなく、基本的にできません。 できないのですが、できるように努力していく、訓練していく、バイアスを認識していくことが重要です。
気分や疲れならば1日寝れば良くなりますが、生い立ちの問題や特性からくる「いつも白黒思考になってしまう」といった強固なバイアスを「スキーマ」と言います。その人の考え方の癖です。
認知行動療法の動画でも説明してるので見てください。 認知行動療法について解説(基本、ロジカル思考)
https://www.youtube.com/watch?v=kUjDlepo2So&t=0s
■認知行動療法 認知行動療法というのは、精神療法の中のスタイルの1つです。 認知行動療法はかなり主流の考え方になっていて、精神科の外来でも認知行動療法的なアプローチは浸み渡っている感じがあります。 精神分析的なタームを使いながら説明することもありますが、認知行動療法的な考え方は主流になってきて います。 この中で重要な概念を2つお話しします。
■協働的経験主義 これは何かと言うと、「治療の主体はあくまで患者さんである」ということです。 患者さんは治療者に「ポジティブな声かけをしてください」「励ましてください」「ポジティブになるようなやり方を教えてください」と言いますし、もしかしたら僕らは知っているのではないかと思うかもしれません。 ですが、僕らは(ポジティブなやり方を)知らないですし、僕らが知っていることを患者さんに伝えてもあまり意味がありません。
治療の主体はあくまで患者さんであり、皆さんが自分で考えて動いたり悩んだりしていることを、あくまで僕らはサポートしていく立場にあります。それを協働的経験主義と言います。 もちろん言葉をかけたり、考えるヒントを出したりすることはありますが、患者さんが中心になるということです。 ・短期的、中長期的目標 目先の目標を立てることも大事ですし、中長期的な目標を立てることも大事です。
治療というのは問題解決の連続ですが、問題解決の先にはどのようなビジョンがあるのか、ということを考えるのはすごく重要です。 1年後、5年後、10年後どのような自分になっていきたいのか。どういう風に生きていきたいのか。 限りある人生をどう生きたいのかを考えておきます。 もちろん訂正しても良いし変えても良いのですが、そういうことが重要だと言われています。
◎結局のところ、僕らが自分の現状を正しく認識するように努力して、精神科医の助言を得ながら問題解決をしていきながら、短期的目標を立ててクリアーしてゆく、その先の中、長期的目標、1年後、5年後、10年後、そして死ぬまでにどういう人生をいきたいか自分で決める。自分の人生だから。
■正しく認識することの欠点 しかし、正しく認識することについて話してきましたが、これには欠点があります。 「正しく認識できない人はどうしたら良いのですか」 「認知行動療法をすれば苦しくなるだけで私は楽になれませんでした。どうしたら良いのですか」 という患者さんはたくさんいらっしゃいます。 正しく認識すると苦しい、という話です。
舐達磨(なめだるま)というヒップホップグループの曲をここ2、3日聴いていたのですが、その歌詞の中で「やりたいようにやる じゃないと頭が狂う」というようなことを言っています。 貧困、暴力、虐待の問題、教育を十分に受けられなかった問題、勉強が向いてなかった、学校の問題、ドラッグの問題、周りの友人たちの問題などいろいろあり、現実が苦しすぎてわがままを言わせてくれないと俺は狂ってしまうよ、というようなことを言っているのだと思いました。 いかつい男の人が自分の弱さを語りながら、それを音楽、アートに昇華しています。
正しく認識すると言うよりは、自分の弱さを認識してそれを足し算の発想で変えていく、自分に受け入れられるように、苦しい現実を受け入れられるようにアートに変えているという作業なんだなと思いました。
自分の弱さ、特性の問題、虐待の問題があったときに、先生たちは正しく認識して建設的にやれと言うけれど、自分にはできない。 ある種の苦しさ、惨めさを受け入れて、そこから少ししかステップアップできないところで甘んじろと言うのか、そういうのは苦しい、という言い方はよくされますし、なるほどなと思います。
正しく認識することはすごく重要ですし建設的にやれる治療法ですが、限界はあり、それをやった時の苦しさ、惨めさはあるなと思います。 ですから、すべての人には認知行動療法を勧めにくかったりします。 ここら辺は難しいです。
◎ここらへんの話は、イメージがなかなか沸かないので僕は割愛させていただきます。貧困、暴力、虐待、勉強が向いてない、発達特性、依存の問題など複雑なんだろうぐらいにしか捉えられません。こういう経験を経て生きてきた人にとって、正しく理解するというのは、目をそらさずに現実を見ろ。と言うのはきつすぎるんでしょうね。だからそれをベースに認知行動療法をしても合理的考えが浮かばないんじゃないかと思ってしまいます。
治療者が思っている世界と患者さんが抱えている世界、患者さんたちが苦しい思いをしていること、どのように立ち向かっていくのかということはよく悩みます。 悩むのですが僕はラッパーではないので、代弁者になってラップやろうとはなりません。 あくまで精神科医としては共感しつつも、自分たちがやる仕事を淡々とやっていくということです。 限界はあるにしても、認知行動療法は素晴らしい治療法なので、そのようなことをやっていくというのが僕らのスタンスです。それを理解してもらった上でいろいろなことをやっていく、いろいろな考え方を知ってもらうのが良いと思います。
今回は、「同じところぐるぐる悩むのはなぜか」について、精神科医目線から認知行動療法的なアプローチを紹介しました。
この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?
