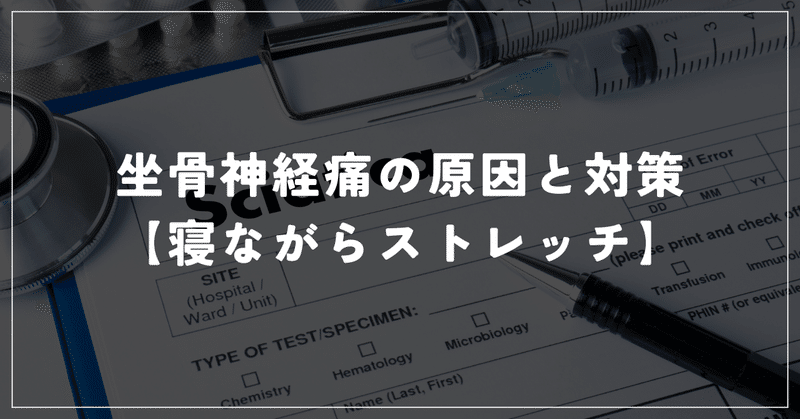
【完全版】坐骨神経痛の原因と対策【寝ながら最強ストレッチ】
「その最強ストレッチ2種目だけ習慣化していただきたいのですが、大事なポイントは3つ」
今回の内容は、坐骨神経痛と言われる「お尻や足の痛み」に関して、完全解説と言えるレベルで徹底解説しております。そして、極めつけの寝ながらできるカンタンストレッチもぜひ繰り返しご覧ください。
※このnoteでは、整形外科医:歌島大輔が医学的根拠をもとに、わかりやく、かつ実践的な医療健康情報をお届けします。
ときどき出てくる「ふんぞり男」とは、その名の通り、ふんぞり返って態度がデカい患者さんです。

ふんぞり男1「おお、坐骨神経痛か、よく聞くな。俺のケツの痛みも坐骨神経痛か?」
ふんぞり男さん、お尻も痛いのですね。
確かに「殿部の痛み=坐骨神経痛」と安直に診断されてしまうこともありますが、意外と奥が深く、未解明領域も多いです。
その難しさに悩んでいる方のコメントをご紹介します。
C&T さんからです。
私の場合は、左側の腰から臀部にかけて坐骨神経痛の突き刺すような痛みです。
梨状筋症候群・変形性腰椎症で、MRIではL5/S1の椎間関節に変性と1つの整形外科で診断されました。
試しにもう1つの整形外科では、特に椎間板も骨も異常はないけどねと言われました。
あと整体師や理学療法士さんからも、相当な反り腰になってるとの事です。
これは前職での肉体労働で10年以上勤めて出来上がってしまったものなので、心あたりは沢山あります。
この痛みとは、上手く付き合っていくしかないのでしょうか?
本当にこういう患者さん多くて、「整形外科医がちゃんと診断しろよ」という話ですが、腰からお尻の痛みは、診断が難しいのも事実です。
坐骨神経痛は、太ももからふくらはぎまで広範囲で痛みが出るため、診断は本当に大変です。

ですから、1回のレントゲン検査だけで、確信度の高い診断は難しいと考えなくてはなりません。
この難しさを、どのようにしたら良いかを説明したうえで、整形外科医が責任をもって治療できればいいのですが‥
そうはいかないため、整体師さんのところに行く患者さんが、後を絶たないとのご意見もいただきます。
整体師さんのところに患者さんが行くことが悪いという短絡的な結論ではありません。
整形外科医としての責任を果たし、治療迷子になってしまう患者さんを減らしていきたいという気持ちを持って、コンテンツを作成しています。
今回は「完全解説」と銘打っていますから、坐骨神経というものをしっかりと理解していただき
・坐骨神経痛とは何か
・どのような原因で起こるのか
・どういう対処法があるのか
を徹底解説します。
ちまたでは「坐骨神経痛にはストレッチが良い」と短絡的な情報が溢れています。
よく見かけるのは「坐骨神経痛ってこんな感じですよ」と、説明があったりなかったりしながら、一律でいくつかのストレッチやエクササイズを紹介するという情報や動画です。
しかし、坐骨神経痛は原因診断が難しく
・そもそもストレッチが効くのかどうか
・どのストレッチをすべきなのか
が全く変わってきます。
「坐骨神経痛にはこれ!」と簡単に決まるわけがありません。
そのあたり含め、徹底して解説していきますので、自分はどういう原因で、どのような対策がよさそうかチェックしてみてください。

ふんぞり男「なんだ、お前、原因っぽいとか、対策がよさそうとか、曖昧だな」
そうです。
どこまでいっても、セルフ診断には限界があります。
そうでないと、医師の診察や検査の意味がないのです。
・どのような検査をするか
・どのような治療を病院ではするのか
2つの詳しい内容に加え、タイトルにもあります「寝たままストレッチ」として簡単にできる2つのストレッチを医学的根拠込みでご紹介します。
ぜひ最後までご覧ください。
「坐骨神経って何なの?」説明できますか?

坐骨神経痛は、特殊な医学用語の割には日常会話でも出てくるくらい、一般的な言葉にもなってきています。
(そうでもないかな‥)
ところで坐骨神経を見たことはありますか?

ふんぞり男「あるわけねぇだろ。整形外科医だからってマウントとるな!」
すみません。
神経は多くの人がイメージしているものよりも何倍も太いです。
人体の中で、最も太く長い末梢神経が坐骨神経です。
そのため、とても重要な神経で、坐骨神経痛といっても様々な部位に症状がでます。
では、坐骨神経がどのような神経なのか見ていきましょう。
神経を理解するときに大切なのは
・どこから始まり
・どこを通って
・どこに届いているか
ということです。
このことを「神経の走行」と言います。
この神経の走行を知れば、たいていのことは想像がつきます。

坐骨神経はどこから始まるかというと「腰」です。
背骨は積み木のように積み上がっている骨ですが、その1つ1つの骨の間から「神経根」という末梢神経の大元のような部分が出ます。
坐骨神経はそのなかでも下の方の腰椎、さらに下の仙骨から出る神経根が最後に集まって、坐骨神経になります。

そのため、坐骨神経痛の原因としてまず考えるのは「腰」の病気です。
まずはこれが基本です。
しかし、坐骨神経は「人体で最も長い末梢神経」のため、ここから長い旅が始まります。

まず、腰の複数の神経根から出た神経が合流して坐骨神経という最も太い神経になり、お尻の深いところの筋肉の中を通って、太ももの裏をおりていきます。そして、膝の裏で大きな分岐をします。
ここまでの旅でも小さな枝をたくさん出して、いろいろな皮膚や筋肉との信号のやりとりをしているわけですが、太い神経の枝分かれは膝裏です。

膝裏では「総腓骨神経」と「脛骨神経」に分かれます。
総腓骨の「腓骨」とは、スネの外側の細い方の骨で「脛骨」は内側の太い骨です。
弁慶の泣き所の骨ですね。
枝分かれした結果、最終的に足まで届きますから、坐骨神経痛はお尻から太もも、ふくらはぎまでどこでも痛くなるのです。

ふんぞり男「なんだ、じゃあ、下半身が痛けりゃ、全部、坐骨神経痛じゃねぇか!」
それは流石に言い過ぎですね。
坐骨神経痛ってドコが、どう痛い?

神経には感覚の支配領域があります。
いくら人体で最も太く長い神経といっても、下半身全部ではありません。
しかし、解剖学的な支配神経領域を覚えなさいというのは、お伝えしたいことではなく、膝までは後ろ側で、膝下は全部と覚えてください。
つまり「お尻と太もも裏、膝下は足まで全部」です。
反対に坐骨神経ではない部位としては、骨盤の前側や太ももの前側が該当します。
そう考えると、坐骨神経は幅広く支配していますね。

ふんぞり男「ほぉ、じゃあ、その膝上は後ろ、膝下は全部って範囲が痛ければ、坐骨神経痛だから坐骨神経を治療すりゃ良いんだろ。カンタンじゃねぇか」
短絡思考ですね・・
ふんぞり男さんが言っていた「坐骨神経を治療すりゃ良いんだろ」ですが、実際どうすればいいのかですよね。
坐骨神経痛は診断名じゃない
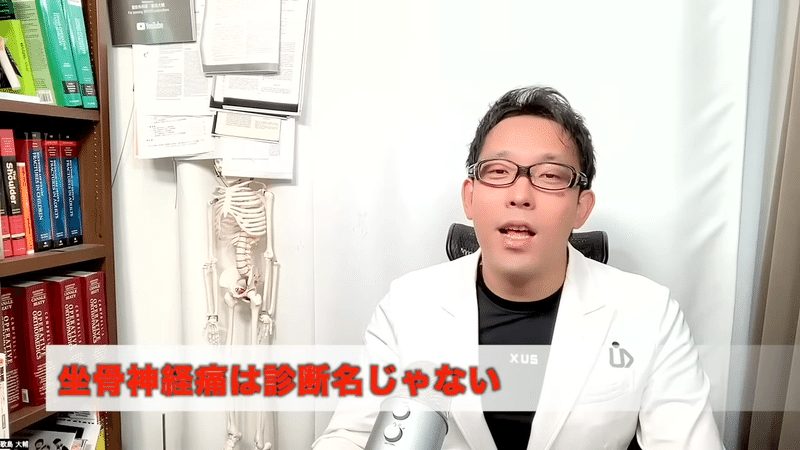
まず大前提として、坐骨神経痛は断名ではなく、症状の名前だということです。
次の言葉と同じ仲間になります。
・腰痛
・ひざ痛
・便秘
・動悸
ここで出てきた症状の治療法は、よほど軽症ではない限り1対1対応にはならないのです。
例えば動悸の治療には、軽症であれば、CMで耳にする「動悸には救心」でもいいかもしれません。
しかし実際には、手術が必要な心臓の病気が隠れているかもしれないため、動悸が起こっている原因を突き止めなければなりません。
動悸はすべて救心でいいわけがないですよね。
(一つの例で、救心が悪いわけではありません)
そう考えたときに大切になるのは「なぜ坐骨神経痛が起こっているか?」ということになります。
坐骨神経痛の原因3選

代表的な坐骨神経痛の原因は次の3つです。
1.腰椎椎間板ヘルニア
2.腰部脊柱管狭窄症
3.深部殿部筋症候群(梨状筋症候群)
一つずつ詳しく解説します。
1.腰椎椎間板ヘルニア

先ほども言いましたが、坐骨神経は「腰」から始まります。
まずは、腰の病気が原因であることを考え、大元から攻めるべきです。
その代表が「腰のヘルニア」になります。
腰のヘルニアは、腰の背骨の間にある椎間板とよばれるクッションが傷んで後ろや横に飛び出てしまうことで、神経根を圧迫してあらわれる症状です。

これはあるあるですが、レントゲンでは椎間板が写らないのに、
安易に整形外科医が「ああ、ヘルニアだろうね」と言ってしまうケースです。
稀にレントゲンで分かるヘルニアもありますが、ほとんどはレントゲンに写らず、MRIが必要です。
ですから、基本的には腰椎椎間板ヘルニアを疑ったらMRIを撮ります。
2.腰部脊柱管狭窄症

腰のヘルニアは、いくつもある椎間板の内、1つの椎間板が出っ張ってできる症状です。
しかし、脊柱管狭窄症はもっと全体的に背骨の神経の通り道が狭くなる病気です。
典型的な症状として、神経根が圧迫された坐骨神経痛というよりは、長く歩くと痛みやしびれが増えてくる「間欠跛行」という症状が多いです。
しかし、脊柱管の狭くなり方もそれぞれなので、突き刺すような坐骨神経痛に襲われるケースもあります。
一般的にはヘルニアの方が若い人に多く、脊柱管狭窄症はご年齢と共に増えていく病気です。
3.深部殿部筋症候群(梨状筋症候群)

1つめと2つめが腰の病気だったのに対して、3つめは、お尻の筋肉の問題です。
深部殿部筋症候群(梨状筋症候群)といって、深いお尻の筋肉の症候群という名前の病名です。
先ほど言いましたが、腰から始まった坐骨神経の旅はお尻の筋肉を通って、太ももの裏をおりていきます。
お尻の筋肉は、下半身のコア(根本)であり非常に重要な部分です。
さらに、肩関節の次に可動範囲が大きい股関節を動かすのにかかせない筋肉でもあるため、お尻の筋肉はかなり複雑に絡み合っています。
そのなかを最も太い坐骨神経が通るため問題が起こります。
この問題が「深部殿部筋症候群」です。
より有名な病名として「梨状筋症候群」というものがあります。

梨状筋は、お尻の筋肉の1つです。
しかし、梨状筋以外にも原因となる筋肉があるため、広い概念として深部殿部筋症候群という病名が出てきています。
実際には、お尻の筋肉が異常に大きくなってしまったり、異常にカタくなってしまった結果、そこを通る坐骨神経が圧迫されます。

例えば、こちらの2005年の研究(*1)では、坐骨神経痛があるが、その原因診断がついていない239人の患者さんをMRIで再評価しています。
結果は次のとおりです。
梨状筋症候群:67.8%
近位ハムストリングス症候群:4.7%
末梢神経巻き込み:3.0%
坐骨腫瘍:1.7%
骨折を伴う仙腸関節炎:1.2%
この結果で大事なのは、広い意味で深部臀部筋症候群といっても、昔から言われている梨状筋症候群が圧倒的に多いということです。
坐骨神経痛に見えて違う状態

僕の経験的に大事だと思う視点として、坐骨神経痛に見えてしまう状態について解説します。
坐骨神経痛は、お尻から太もも裏・膝下など、どこでも起こりうる痛みです。
そのため「本当にこの痛みは坐骨神経痛なのか?」と疑うべきです。
極論ですが、もも裏を誰かに叩かれて痛いのは坐骨神経痛ではないですね。

ふんぞり男「当たり前だろ、バカにするな!」
ごめんなさい・・
坐骨神経痛の最も有名なテストとして「SLRテスト」があります。
これは仰向けに寝て、評価する医師などが患者さんの膝を伸ばした状態で上げていきます。
角度は報告によりバラツキがありますが、一般的に70°くらい脚が上がった状態で坐骨神経痛のような痛みが走った場合「SRLテスト陽性」と判定し、坐骨神経痛がありそうだとなります。

こちらの2012年の研究(*2)は、SLRテストの診断精度などを複数の論文で総合的に調べたものですが、結論として「テストの判定基準そのものにバラツキがあった」としています。
そして、このSLRテストはハムストリングスの張りに伴う痛みなど「腰椎神経根症などの坐骨神経痛に特異的でない痛みもSLRテストの偽陽性につながる可能性がある」と述べられています。
要は、坐骨神経痛の有名なSLRテストで陽性だったとしても、他の原因かもしれないということです。
そして、この膝を伸ばして脚を上げていく「股関節を屈曲する」という動作は、ハムストリングスが緊張します。
ですから、ハムストリングスがカタい患者さんは、脚の上げる角度:70°くらいで痛みが走っても全くおかしくないのです。

ふんぞり男「お前、それじゃ、振り出しに戻るじゃねぇか。どうやって判定するんだ」
次の章で詳しく解説しますね。
坐骨神経痛とハムストリングスの筋緊張を見分けるには?

両者を見分けるには、意外と難しいです。
もちろん一番わかりやすいのは、原因である異常が検査で発見できることです。
神経の症状の場合は、椎間板ヘルニアがMRIの検査で見つかることが一番多いですね。
さらに診断的治療と呼ばれますが「神経ブロック注射」をして効果があれば、神経が原因と考えられます。
このように、精密検査や侵襲性のある治療的な検査をすれば見分ける可能性が高まります。しかし、そこまではやりたくない方もいると思います。
そこで1つの仮説としてお伝えしたいのは、先ほどの有名なSLRテストです。

こちらは2008年の論文(*3)ですが、いろいろな文献でSLRテストの定義について調べています。
ここまで定義がバラバラなテストも珍しいですが・・
例えば、SLRテストで坐骨神経痛が発生した場合を陽性とする基準があります。
しかし、そもそもその症状が本当に坐骨神経痛かどうかを確認しているのです。
この研究でも、陽性の基準には「腰痛を含むかどうか」という違いがありますし、
さらに「お尻の痛み、太ももの裏の痛み、膝下の痛みなど、どの部位の痛みを陽性とするか」についても文献によってばらつきが見られました。

ふんぞり男「お前ら、適当な検査やってんじゃねぇよ!」
そう思いますよね。
だからこそ、このような研究をして、テストの結果がバラバラだと問題提起してくれていると思います。
私もできることを頑張っていきますが、ここではSLRテストの曖昧さを逆手に取って、1つの見分け方を提案したいと思います。
これだけで見分けられる万能テストではないですが、1つの仮説を紹介します。

それは「膝下の痛みにフォーカスする」という方法です。
坐骨神経はお伝えした通り、腰から始まり足まで到達します。
一方で、ハムストリングスはもも裏の筋肉ですから、単なる筋肉の緊張の痛みなら、症状はもも裏までですね。
SLRテストで足首をダランと力を抜いて、つま先が下に落ちた状態にします。
そうなると、ふくらはぎの筋肉が緩みます。
この状態で、それでも膝下に痛みが走るとしたら、これは神経の痛みだと考えるべきです。
反対に、膝下は全く痛みがなく太もも裏の痛みのみでしたら、筋肉の緊張ではないかと考えられます。
ただ、坐骨神経痛は様々なバリエーションがあり、膝下の痛みが走らないこともあるので、これだけで見分けるのは難しく、万能ではないといった理由はここにあります。
坐骨神経痛の新分類

ここまで代表的な坐骨神経痛として、次の4タイプを代表的な疾患としてお伝えしました。
腰椎椎間板ヘルニア
腰部脊柱管狭窄症
深部殿部筋症候群
坐骨神経痛のようにみえる筋肉の緊張
しかし、疾患で分類すると少し複雑になるため、次の3タイプに分類します。
1.神経の問題
2.筋肉が原因の神経の問題
3.筋肉の問題です。
1番の「神経の問題」は、筋肉は関係なく、ヘルニアや脊柱管狭窄によって神経が圧迫されていることが原因です。
稀ですが、骨盤にできた腫瘍が神経を圧迫している場合や手術などで坐骨神経が刺激された場合なども含みます。
2番の問題は、深部殿部筋症候群です。
筋肉が過剰に肥大したり、緊張しているがゆえに神経を圧迫してしまっています。
3番目は、神経関係なしです。
筋肉が緊張するだけでも痛みがでることはあります。
この3つを大元の原因でわけた場合、
1番は筋肉以外が原因
2・3番は筋肉が原因
このように分類するとシンプルになってきますよね。
筋肉以外の問題:やるべきはストレッチではない
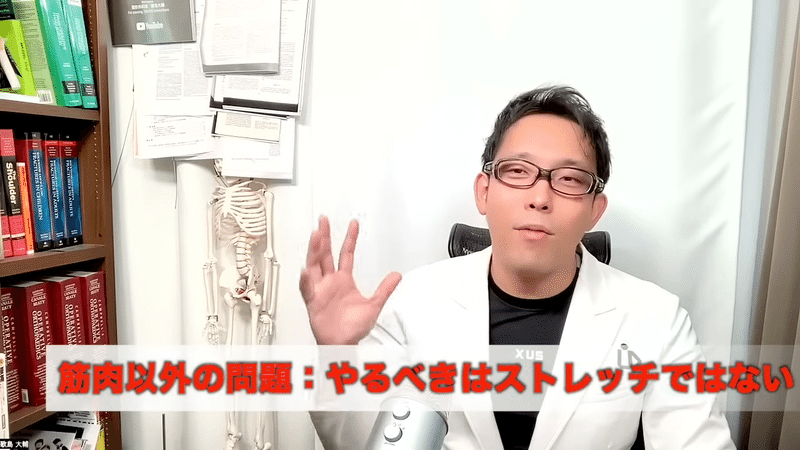
筋肉以外の問題となったときに、ストレッチをして改善しましょうというのは原因に対するアプローチではありません。
「ストレッチで痩せましょう」
「軟骨のすり減りの痛みはストレッチで治しましょう」
など、何でもストレッチで改善しそうな説明がなされることがありますが、意味不明です。
なぜかというと「ストレッチは筋肉を伸ばすこと」だからです。
少し解釈を拡大して、五十肩のときに関係する関節包を伸ばすことも含めてもいいのですが、ストレッチは伸ばすことです。
これはカロリーも効率的に消費するわけではないですから、ダイエットにストレッチは意味不明ですし、軟骨のすり減りに対しても、すり減った軟骨に対して何をどうストレッチして改善させようとしているのか、やはり意味不明です。
これらと同じで、腰椎椎間板ヘルニアで椎間板という軟骨が神経を押している状況でストレッチしてどうなるのか、脊柱管狭窄症でもストレッチが何の効果を生むのか理解できません。

ふんぞり男10「じゃあ、どうしようもないってか!?」
いやいや、ストレッチは選択肢がなかなかとりにくいだけで、筋肉以外の問題の場合は別のアプローチが必要なだけです。
例えば、東京大学の松平浩(まつだいらこう)先生は「腰痛これだけ体操」という、立った状態で骨盤に手をおいて腰を反らす運動を提唱されていますね。

昔から、腰が疲れたら何となくやっていた動きですが、これの意味・メカニズムとして「椎間板の調整」と言われています。
通常、特にデスクワークなど前屈みになったり、腰が丸まっている状態だと、背骨の積み木は前が狭く、後ろが広くなります。

模型で言うと、こういう感じですね。
この状態では椎間板は徐々に後ろに押されていきます。
これがヒドくなると椎間板ヘルニアになります。
これに対して、腰を反らせば反対の状態になるので、椎間板の位置も元に戻る方向にいく体操だということです。
これでどれだけ椎間板の状態が改善するかの研究は私が知る限り進んでいないようですが、メカニズム的には納得ですね。
さらに松平先生は痛みの性質として、脚の下まで拡がっていた坐骨神経痛がだんだん腰に近づいてきたら良い徴候だとお話しされています。
これを「セントラリゼーション」と呼んでいます。
反対に、脚の下の方に痛みが拡がってしまうと、この体操も含め今の対策は良くないことになるので、整形外科医への相談とともに体操は控えるべきとおっしゃっています。
参考にしてみてください。

もう一つ、ドローインという姿勢を保ちながらお腹をしぼませる状態を維持する、ハンドニーと呼ばれる体幹エクササイズ(*4)は、腹横筋への刺激が効率的に加わるエクササイズとして有名です。

この腹横筋がしっかり使えると「筋肉コルセット」と呼ばれるだけあって、お腹の中の圧力である腹圧が上がります。
腹圧が高まると椎間板にかかる圧が下がることが示されています。
すると、椎間板ヘルニアにはメカニズム上、良い効果が期待できると考えられます。
以上より、少なくともストレッチをやるよりは、
腰痛これだけ体操
ハンドニーと呼ばれるタイプの体操・エクササイズ
の方が効果的といえますね。
それでもストレッチをやってもいいと思えるのは、ハムストリングと呼ばれる「もも裏」がカタい場合です。
それだけで腰が丸まりやすく姿勢が悪くなりやすいので、のちほど紹介するストレッチを習慣化しても良いと思います。
筋肉の問題:寝たままストレッチ2種目だけ

筋肉が原因で神経を圧迫していたり、筋肉の緊張自体が痛みの原因の場合はストレッチしましょうというシンプルな話です。
今回は「最強ストレッチ」とあえて呼ばせていただきます。
その最強ストレッチを2種目だけ習慣化してください。
大事なポイントは次の3つです。
1.ストレッチ中やストレッチ後に坐骨神経痛が強まる場合はやめる
(もしくは、痛みが強まる前くらいの伸ばし具合にとどめる)
2.習慣化する
寝た状態で寝る前にやってもいいですし、朝起きたてで筋肉が固まっている状態でほぐす意味でやってもいいと思います。
3.「相反神経支配」と呼ばれる神経の働きを利用する
腕を使って脚の位置を誘導して伸ばしますが、それにプラスして自分でも力を入れることをしてもらいます。
肘の動きで説明するとわかりやすいですが、肘を曲げる筋肉に力を入れたときには、肘を伸ばす筋肉は緩まないといけません。
両方に力が入ったら、ぎこちない動きになってしまいます。
つまり、逆の働きをする筋肉は緩むという神経の働きを相反神経支配と言いますが、これを利用してストレッチしたい逆の筋肉には力を入れることをやります。
この3つのポイントを押さえた2種目をご紹介します。
最強ストレッチ1:寝たままジャックナイフストレッチ

坐骨神経痛の領域とほぼ被る、ハムストリングスや大臀筋などの筋肉のストレッチとして有名な「ジャックナイフストレッチ」です。
これを寝たままやりましょう。

まず仰向けに寝ます。

両膝を曲げて両手で太ももを抱えて、太ももをお腹に密着させます。
このときに腹筋を使って構いません。

密着させたまま膝を伸ばそうと力を入れます。
大腿四頭筋に力が入り、逆にハムストリングスや大臀筋が緩むという魂胆です。

「5秒膝を伸ばす力を入れて休むを10回」これで1分くらいですね。
これにより、お尻からもも裏の筋肉の柔軟性を高めます。
坐骨神経痛っぽいけれど筋緊張が原因だった状態からの改善を狙えますし、稀ですがハムストリングスが原因の神経圧迫もあるので、大切なストレッチです。
最強ストレッチ2:寝たまま梨状筋ストレッチ

深部殿部筋症候群の割合、頻度でお話しした通り、圧倒的に多いのは昔から知られている梨状筋症候群です。
梨状筋という筋肉が緊張・肥大した結果、坐骨神経が圧迫されてしまうことです。

こちらの2014年の研究結果(*5)が役に立ちます。
これは、どの状態で梨状筋が最もストレッチされるのかをCTスキャンを使って研究しています。

次の股関節の状態がもっともストレッチされたとされています。
120°くらいの屈曲
40°-50°くらいの外旋
25-30°くらいの内転
そのためストレッチでは、この状態に持っていくことが良いわけです。
梨状筋は、股関節を外旋させる筋肉の1つとして有名なため、外旋はストレッチにはならないのでは?と、感じてしまうかもしれません。
しかし、筋肉が3次元的に構成している性質上、股関節が90°以上屈曲になると、外旋筋だった梨状筋の働きが逆になり、内旋筋として働く特徴があります。
ですから、このストレッチが成立するのです。

具体的なやり方は、まず仰向けに寝ます。
映像ではわかりやすくするために、横向きに寝たバージョンでもデモンストレーションしていますので参考にしてください。

ストレッチしたい側の太ももを両手で抱えるようにして、逆側の胸まで持っていきます。

これによって股関節の屈曲120°と内転30°くらいの状態になります。

自分の股関節の力で外旋していけばストレッチになるわけですが、実は外旋筋群の力は強くないので、少し手でサポートしてあげるといいかと思います。

これも同様5秒力を入れて休むを10回やって終了です。
この2種目をやるだけですね。
たった2分のストレッチでメカニズム上効果が期待できる、医学的根拠ありのストレッチ習慣ができると思ってください。
ぜひ、お試しいただければと思います。
まとめ|本日の一言
坐骨神経痛、奥が深いけど、まずはこの動画を繰り返しご覧いただきたいです!
🎁動画講座「寝たきりリスク TOP10セミナー」プレゼント

人生100年時代・・・寝たきりの可能性が高まってしまう「恐怖の習慣」をまとめた「寝たきりリスクTOP10セミナー」をプレゼント中です。詳細はこちらから▼
🎁治療家さん向け2大プレゼント
「しがない整形外科医の外来に全国から予約が殺到してしまった情報発信メソッド」

動画セミナー無料プレゼント▼
電子書籍「レッドフラッグ100選」

危険な兆候・症状・疾患を一気に学べる▼
参考論文
(1*)Filler AG , Haynes J , Jordan SE , et al. J Neurosurg Spine . 2005 Sciatica of nondisc origin and piriformis syndrome: diagnosis by magnetic resonance neurography and interventional magnetic resonance imaging with outcome study of resulting treatment .
(2*)Vincent Scaia , et al. J Back Musculoskelet Rehabil. 2012 The pain provocation-based straight leg raise test for diagnosis of lumbar disc herniation, lumbar radiculopathy, and/or sciatica: a systematic review of clinical utility
(3*)森本ら、日本腰痛会誌. 2008 Straight Leg Raising test(SLRテスト)の定義の文献的検討
(4*)Yu Okubo et al. J Orthop Sports Phys Ther. 2010 Electromyographic analysis of transversus abdominis and lumbar multifidus using wire electrodes during lumbar stabilization exercises
(5*)Brett M Gulledge, et al. Med Eng Phys. 2014 Comparison of two stretching methods and optimization of stretching protocol for the piriformis muscle
この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?
