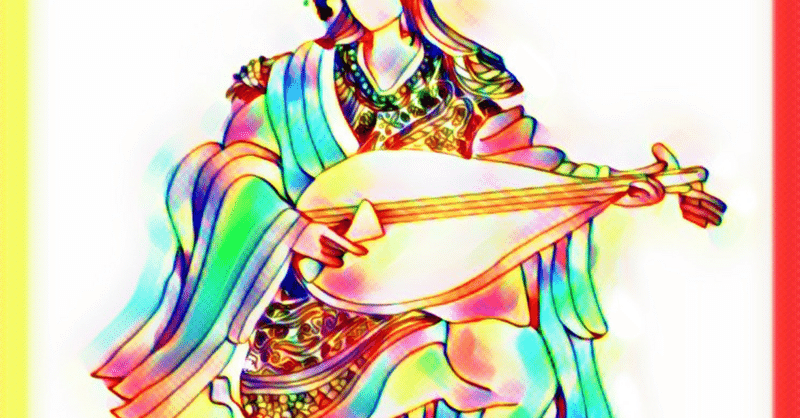
凌辱の場面について
咲夜姫の出版前、静岡新聞社の編集者の方お二人と会って打ち合わせをしたのですが、その時に編集者の方が「この小説は最後の登山が山場のはずですが、途中にある凌辱の場面の印象があまりに強い」といった旨の話をされたことがありました。
小説咲夜姫の第二章「ココロザシの章」では、
婿として認めた若者と咲代さんがその夜は離れの家屋で過ごすこととなり、
しかし不穏に感じた甚六さんが離れを訪ねると、
咲代さんが身ぐるみを剥がされて倒れていた、
という場面があります。
広がる光景を目の当たりにし、甚六は頭の中が瞬時に沸騰したように熱くなった。
そして咲代の名を叫びながら、敷かれた寝床へ駆けつけていた。
咲代は天井へ目を向けたまま、動かない。着物ははだけ、羽織一枚だけに頼りなく両袖が通してあり、その手もだらりと両側へ広がっている。脚も全てあらわにされ、捨て置かれた人形のごとくそこにへあった。この場所、他には誰の姿もない。
甚六はその身体を揺すぶりながら、名を呼びかけた。目がふと動き、こちらを捉えた。生きているとわかり、途端に甚六の目からは涙があふれた。まず、命は無事だった。次に大事なのは何か。
(小説咲夜姫/山口歌糸)
この後、甚六さんは(おそらく初めて)咲代さんの身体にふれ、事の後始末をします。確かに、この場面は刺激が強いです。
筋書きの原作としている竹取物語でもこんな場面は全くなく(家の周りに男がいつも集まってくる場面は写文にはある)、ココロザシの章の最後の展開は、原作を少し変えた創作になっています。
この場面を創作した理由は、ひとえに「人の邪心」の表現です。
咲代さんがそのような状況になった一連の出来事は、弱い者を自分の思い通りにするという、人の最も下劣で邪悪な行動を表しているのです。「人というのはどこまでも愚かで、感情や欲求に心を支配されるものなのだ」と示し、対比して「神様というのは遥かに高みにある存在なのだ」と示すのにもつながります。
しかし本文をよく見ていただくとわかるようにしてあるのですが、咲代さんが凌辱された証拠は一切ありません。あくまで状況証拠のみです。
まず、物語の視点となる甚六さんはその時にはうろたえてまともではなく、そう思い込んであのように対応しただけです。あの場面での文章全体が、錯乱状態になった甚六さんの心情と行動なのです。
そして咲代さんは、依然として何も語りません。ましてやショックを受けているのは甚六さんの方で、当人は直後からけろりとしています。
肌を合わせる記憶を思い出すことなど、咲代にあるはずはない。あるとすれば、
「お前。あの縁談のことで今も傷付いて」
甚六は記憶から追いやっていた出来事を思い出した。咲代は枕に髪を擦り付けながらかぶりを振った。
「いいえ。あのことは何とも感じておりません。私も覚悟を決めておりましたのに、悪かったのです」
悪い悪くないはさておき、やはり甚六は咲代が不憫だと思う。
「何か思い出せることが、他にあるのかい」
「寄り添って眠ってみるのは駄目でしょうか」
(小説咲夜姫/山口歌糸)
後年、甚六さんが咲代さんに対してその凌辱のことを口にしますが、咲代さんは「何とも感じていない」と明かします。それは咲代さんにとってその身体がどうせ仮の物であると同時に、彼女は人間の愚かさを初めからよく知っているのです。
けれども、人として現れたこの身が手籠めにされた後、涙を流して悲しみ、屋敷に火まで放たれた甚六様に、人の本来の姿を見ました。何よりも、深い真心に触れることができて、私はこれ以上なく幸福でありました。
そうして、世を憂い始めた甚六様に、私は心を奪われて今に至ります。俗世に下りての戯れごととも思っておりましたが、心はもう」
(小説咲夜姫/山口歌糸)
しかしながら、後年に自らの正体を明かす時「この身が手篭めにされた後」といった言葉も口にし、結果として凌辱をされていないとも言い切れません。咲代さんにとっては何をされたら「手篭め」というのかはわかりませんから。
これは読む人がどう感じるか次第としています。
人間とは、神の身に手をかけるほど愚かなのでしょうか、それとも踏み留まれるのでしょうか。
