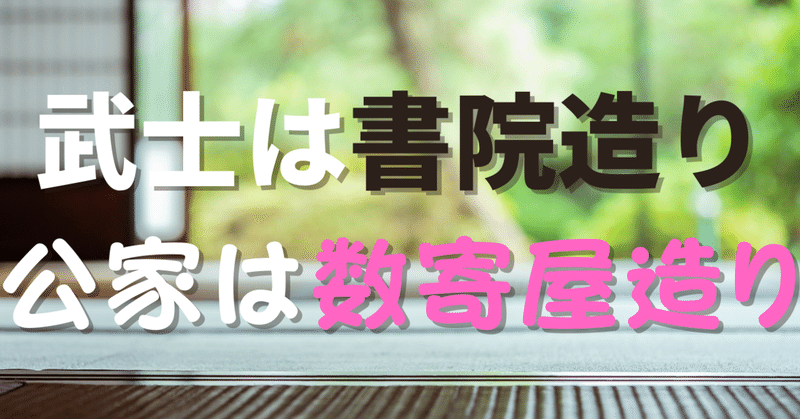
【日本建築史】武家は書院造り,公家は数寄屋風書院造り
前回からの続きです.
「光浄院客殿(こうじょういんきゃくでん)」については,令和2年の一級建築士「学科」試験問題にも出題されています.
【計画科目/問題コード02023】
光浄院客殿(安土桃山時代)は,欄間や長押をはじめ,建具や金具,釘隠や引手などに技巧を凝らし,様々な意匠が施された数寄屋風の建築物である.
【解説】
安土時代は信長の時代,桃山時代は秀吉の時代だと覚えておきましょう.書院造りは,武家社会に好まれた建築様式ですが,公家社会では格式ばった書院造りを嫌い,書院造りに茶室の要素を取り入れ,自由で軽快な数寄屋風書院造り(数寄屋造り)として進化させていき,現在の和風住宅へと至ります.その代表作は,桂離宮や西本願寺飛雲閣で,一級建築士「学科」試験においても数寄屋風書院造りについては,この2つしか出題されておりません.
問題文の記述は,数寄屋風書院造りの説明であるため誤り.光浄院客殿は,生粋の書院造り(武家好み)の具体例であり,数寄屋風の要素は取り入れられていません.
なので,この問題のフォーカス ポイントは,光浄院客殿が「数寄屋風の建築物か」という点となります.
【解答】×
続く
この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?
