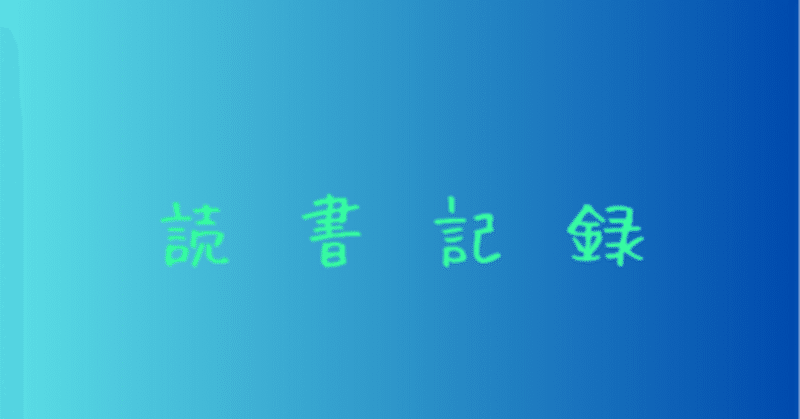
読書 人質たちの朗読会 小川洋子
人質たちの朗読会。
岸見一郎さんの著書『悩めるときの百冊百話』で紹介されていて手にしました。
が、以前読んだことがあることがわかりました。
ところどころ記憶に残ってはいましたが新鮮なきもちで再読しました。
この物語の本質は事件そのものではなく、
事件当時、同じく時を過ごしたそれぞれのひと、なのでした。
朗読で語られるのは、過去について。
極限状態のなかで自分の過去を探りたぐり寄せる。
それは正気を保つための策でもあり
途方もない時間をやり過ごすすべでもあったのでしょう。
朗読は一夜につきひとり。
その日に朗読があるというのは、今日一日を無事に生き延びた、ということ。
そのひとときだけには、安らぎがあったことが伝わります。
*
思えば
人質のための朗読会を初読したころ、
わたし自身は何かを書き記す、ということをしていませんでした。
いまひとつこの話にピントが合わなかったけれど、
noteを書いている今は、すこし違いました。
ひとが目的をもって書くことで得られるものが確実にあると知ったからです。
わたしも年を重ねたからでしょうか、それぞれの年齢や職業がとても気になりました。
年齢と職業と語られるものがたりとを照らし合わせ、そのひとなりや空白の時間に思いを馳せました。
*
文中に『過去』は、だれにもけがされたり
支配されないとありました。
たしかに過去は、そのひとだけのもので書き換えも更新もできません、
豊かな過去をもつこと。
それは今、を生きること。
誰もが持つことのできる過去。
豊かな過去は、今ここ。から始まるのでした。
