
「ラジオ倶楽部」ができるまで(魚田まさや・阿部健一対談|後半)
お待たせしました!魚田×阿部の対談、後半はいよいよ「すみだ川ラジオ倶楽部 川を流れる七不思議編」に迫っていきます。
それぞれの視点で創作過程をたどりながら、音声演劇のつくり方や風景・まちとの関係、いま考えるこれからのことを話しました。
副読本の締めくくりとして、ぜひご覧ください。
(収録:2022年12月14日 会場:北條工務店となり)
対談の前半はこちら
◆ ◆ ◆
新しい土地、新しい方法

魚田
そもそもなぜ墨田区で作品をつくろうと思ったんですか?
阿部
すみゆめの公募を知ったのは春先だったんですけど、その頃はそろそろ練馬区以外にも広げていこうということを考えていました。高松編を5年以上やっている間にメンバーは30代になって、生活も、活動範囲や規模も変わってきていて。あと、「今日のたかまつ アーカイブス ※1」に練馬区生まれの自分自身の経験を接続したことで、創作上でも一区切り感があったんですよね。でもラジオ演劇、このアイディアは別の場所でも展開していきたいねってことも相談していて。そんななかで江東区の知り合いから情報をもらったのが具体的なきっかけです。
魚田
機会とモチベーションが合致したところが墨田区だったんですね。
阿部
そうですね。あと、練馬の活動をしているなかで「東京を考えたい」というところもずっと裏テーマにあって。オリンピックもあってどんどん変わっていく東京と、生活地としての東京とを、練馬から描写するみたいなモチベーションもあったんですけど、そろそろ練馬のことも相対化しながら。視点を別のところに置いていきたいというのもありました。いわば練馬はホームなので、帰りたいときには帰れるというのもあったから。
魚田
今回、今までのuniと一番違うのが、作家を外注しているというところだと思うんです。その辺りの経緯やねらいは?
阿部
作家としての僕は、かなり時間がかかるということが高松編を通してよくわかってきていて。今回、春から動いて冬にアウトプットしていくというスケジュール感のなかで劇作まで担うのはあまりよくないだろうと思ってました。プロジェクトのディレクションの視点で見たときにも、ここで作家として阿部を入れるというのは違うなと。高松編で作品に個人史を接続した、ということをやったばかりでもあったので。今回は違う人を作家として入れたい、それはラジオ演劇に対して理解のある人の方がいい。そこで高松の流れを汲んで、魚田さんにお声がけしたという流れです。あと、僕は劇作家を名乗っていないのだけど、今回は「劇作家」に依頼したいと考えたのも理由のひとつですね。

魚田
そうですね、僕は劇作家で。ありがたいと思ったと同時に、僕もuniの企画にずっと並走するかたちでラジオ演劇に関わっていたので、今回はどうしようか、「阿部さんが劇作をやらない」ということも含めてどういうかたちが適切なのだろうかと、コンセプトから一緒に探っていくようなかたちでしたよね。
阿部
ですね。
魚田
お話をいただいたときに一番重要視したのが、ぼくの裁量の限界みたいなことでした。僕のモチベーションは、阿部さんとかなり異なっていると思っていて。やっぱり自分は、自分の作品をつくりたい。「地域の魅力を発信する」「地域に還元するために」みたいなところに主眼がないんです。かなり個人的な作家というか、個人主義的な作家としてのモチベーションがあるので。それで本当にOKか、みたいなことは最初に確認をしたという経緯がありますね。
※1 「今日のたかまつ アーカイブス」:uniが手掛けるラジオ演劇の第一弾。ちょいとそこまでプロジェクト練馬区・高松編(通称・高松編)の一環で2022年に製作。特設WEBサイトはこちら
「ラジオ倶楽部」という設定
魚田
そうして演出家と劇作家を分けた状態で進むという流れになったんですが。今回はミニFMという、あまり一般的ではない概念を中心につくっていった。
阿部
ミニFMっていうアイデアは魚田さんからの提案で。すごくいい、と思いました。
魚田
(笑)
阿部
今回のラジオ演劇の企画は、いま思うと"研究開発"のようなことが頭にあって。高松編の場合はコミュニティラジオをモチーフにああいう作品をつくって、それをコピー&ペーストするように成り立つ場所もあるかもしれないし、そうじゃないこともあるだろう、というなかで、隅田川なら違った切り口のラジオ演劇ができそうだと思って。地勢も、まるっきり練馬と違うし。練馬と同じようにコミュニティラジオをやるということではないなと感じていたので、ミニFMはなるほどと思いました。

魚田
当たり前ですけど川ってものすごく縦に長いじゃないですか。全然、一つのまちと一体じゃないんですよね。むしろたくさんのまちを貫いて流れている。そうなると、一つのまちを対象にしたコミュニティラジオは切り口としては難しくて。でも、やっぱり高松のフォーマットはすごくヒントになっています。あれはとても長い時間が分割されているんですけど、今回は流域のそれぞれの場所を、高松でいう時間に置き換えて、全く違う光景が、でも隅田川っていうひとつの流れの中にあるという作品群としてまとめられないかなと思ったんです。あと、やっぱり僕も個人に興味があって。個人の幻想とか、個人の夢みたいなことに着目したいということを、リサーチの段階で隅田川を題材にしたいろんな文学とか作品を参照していくなかで。これは現代の隅田川やまちに縛られないで、もっと川と個人みたいな関係性を詰めていった方が作品として広がりが出るんじゃないかと考えました。で、いろいろ調べてたら、ミニFMっていうすごく便利なツールが。個人でできるし、免許もいらないし、痕跡も残らないから、「ミニFMです」っていえば作品的に好き放題できる。それで「ミニFMが流域でめっちゃ流行ってる」っていう世界観を提案しました。
阿部
隅田川の、川岸ギリギリまでビルがそびえて迫りきているみたいな、断面図的というか、誰かの生活が川の向こうに見えちゃう感じとの相性がありますよね。
魚田
ある種のリアリティは感じられるかなと思って提案しました。それでお互い練っていく中で、ミニFMという文化を昔からずっと保存している同好会のような謎の組織があるということで「すみだ川ラジオ倶楽部」っていうタイトルが出来上がっていきましたね。
リサーチする人、執筆する人
魚田
阿部さんはリサーチやネットワークづくりなどされていたと思うんですけど。その辺りはどのように進めてたんですか?
阿部
これまでの活動のなかで、そういうやり方は一種前提になっているところもあるので、紹介していただきながらまちのキーパーソンに出会っていったり、まちを歩いたり、取材をしていくというプロセスはありました(こちらの記事を参考)。ただ、今回は劇作家が入っているので、聞き集めたものからどうにか作品をつくるっていう気負いがないのは大きな違いでしたね。
魚田
なるほど。
阿部
聞いたことを使うかもしれないし、使わないかもしれない。作品の一部になるかどうかより、土地に触れていく手付きとして「聞く」行為が大事かもって感じたり。今までの取材もそうではあったんですが、一層そういう面を意識したような気がします。
魚田
ぼくも逆に、自分がリサーチしない分、阿部さんから手渡されるリサーチ結果に対してドライでいられて。琴線に触れるものを忌憚なく選んでいけちゃうというか、素材扱いができちゃうっていうのは、今回の作風に影響があったなっていうのはありますね。

阿部
うんうん。自分でリサーチして自分で書いてっていうときって、取捨選択が難しくなる瞬間があるんですよね。その難しさを乗り越えるためには、僕の場合は時間がいるみたい。そう、それもあって、今回はぼくが劇作を兼ねると困るだろうなというのがありました。今回ぼくが単身で取材に行って、見聞きしたことをシェアするってかたちだったのはよかった気がします。でも一方で、魚田さんの方でも取材というか、文献調査をずっとしてましたよね?
魚田
そうですね、文献調査と、内心、引き受けたものの全然どうしていいかわからないから、すっごい回数現地に行って、ここでなんか聞いて、どうやって面白がるのがいいんだろうって。ずっと歩き回ってました。流域を。
阿部
執筆も、1スポットずつ繰り返し訪ねてっていう?
魚田
そうですね、毎回やばい、やばい、なにも思い浮かばないよ〜と思いながら歩いて。でもいただいたリサーチのテキストとかを読み返しつつ。「あ、ここでこういう音声を聞いて、こういう景色が見えたら、こういう景色に注目できたら面白いかもしれない」っていうふうに、そういうのを手がかりに書きました。でも、ひとつだけほぼリサーチせずに最初から決まってたテキストがあって、それがすみだリバーウォークの「恋するひとの放送局」。これはコンセプトを決めて、隅田川のいろんな文学をいっぱい読んでいるうちに、現代だったらこういうのがいいなって思いついたものなんですけども。
阿部
5月くらいからそのアイディアの話はしてましたね。
魚田
でしたね。聞いていただいた方はわかると思うんですが、これは橋に恋愛感情を抱いて、自分の思いを橋に対して伝えているっていう、「橋向けラジオ」をやってる女性の作品なんですが。 ちょっと倒錯的というか。隅田川っていま未来都市、ダイバーシティ、SDGsみたいな、「川と調和したまち」みたいな解釈でどんどん再開発されてきていると思うんですが、それでカミソリ堤防をスーパー堤防に変えたりとか、清潔な、パブリックな雰囲気の場所になっていっていると思うんですけど。それ自体は全然いいことだと思う一方で、やっぱり川の持ってる側面ってそこだけじゃなくて。むしろ真逆な、人に言えない私的な領域もすごく含んでいる。昔の文学とかを読んでても、真面目だった大工が川を見てたら、急になにもかも嫌になって大工道具を川に投げ捨てて盗賊になるみたいな話があったり。川自体に、なんか人間をコンバージョンさせちゃう不思議なパワーがあるし、「人間の中に流れてる川」と呼応しているような気もして。川のそういった側面こそ今回表現してみたいと思って。この作品を切り口に、他の作品をつくっていったっていう感じなんですよね。

阿部
「まち」というよりか、川のある種の魔術的な力に注目していきたいっていう。
魚田
そうですね。隅田川っていったとき「まち」っていうイメージが僕はしにくくて。本当に川っていう。流域に住んでいたり訪れたりする人、 あるいは存在っていうことから全部つくっています。
「聴く演劇」を設計する
阿部
普通の劇場で上演を想定される劇曲を書くってことと、ラジオという形式で、しかも、できれば現地で聞いてもらうっていうことってだいぶ違うじゃないですか。もちろん劇作行為なんだけれど、今回、ラジオ演劇のテキストを書くぞってときって、どういう構えでした?
魚田
僕はけっこう劇場の劇曲をメインに書いてるんですが、居間theater ※2っていう団体がいて。その人たちが野外で、音声ガイドの演劇 ※3みたいなものをつくっていたときに僕も作品提供させていただいたことがあって、そのときの経験を元手にしているっていうのはすごく自覚があります。劇場だと、例えば棒が1本立ってて、言葉の力でその棒をでっかい木とかに見立てられるというか、でっかい木として全員で扱えるっていう言葉のパワーの使い方をする。そうやって言葉を重ねていくことで、なんでもなかった空虚な空間に密な場を生成していく、人間関係とかもそれには入るんですが。僕にとっては外でやるときもそれは同じで。例えば、ぼーっと見てるといつもの街並みなんだけど、音声で「対岸の赤いビル」みたいな話をすると、そのビルが立ち上がっていく。景色から前に出てきて大きなものになっていくみたいな、言葉と、見えているものの関係を調整して使いながら作品をつくるっていうことは、劇場の戯曲を書く方法を応用して使っていると思います。
阿部
うんうん。

魚田
一方で、さっき阿部さんも話してたけど(前半を参照)、劇場って存在するものをめっちゃ調整できる。わざわざ持ってこないと現れないからいいんですけど、まちなかだと大量にある物々のなかで、赤いビルを立ち上げると途端にその手前にある青いポールがなんか変な意味を帯びちゃうみたいなこともあるので。大量に要素があって、一歩間違えるとバラけちゃうみたいなことは劇場の演劇にはあんまりないんだけど、野外だと超頻繁に起きる。それがなるべく起きない素材、見えているものの中の素材を主人公にしつつ、でもやっぱりお話として面白いものを追求する。で、結果的に、普段見ているだけでは到達できない風景の見方を、作家から提案というか、提案がきちんと伝わるように作品をつくる・・・、みたいなことを目指していますね。そう、ものがいっぱいある、あって困るっていうのが劇場の演劇との一番の違いかもしれない。
阿部
風景のなかのどこに意識を向けてもらうかとか、どのタイミングや順番で、みたいな部分の設計が、テキストの中でかなりされているなと感じてました。
魚田
そうですね、それはかなり気をつけています。一方で、お家で聞くことも想定されてる作品だったので、 ただ聞いてもお話として変で面白いものを目指すっていうところもありましたね。
阿部
でもどうやって聞いてほしいというコントロールをまちなか、というか川沿いで効かせるっていうのは難儀だと、音源をつくっていくなかで改めて感じていました。もちろん、委ねちゃうというのが基本的なスタンスなんですけど。
魚田
そうですね。劇場の中のようなコントロールは、もうほとんど最初から諦めて。静かな空間で聞いてお話を楽しめるようにもつくって、 でも一方で、現地は現地でその視線が立ち上がって、まちが違く見えるみたいなことを楽しんでいただけるようにするっていう2つのルート。うん、2つのルートは意識したかもしれない。
阿部
俳優との収録作業が終わったあとに、音源を携えて現地に行って聞いて、細かな調整をしたりしたんですけど、例えば音源だけを聞いているときは収録のままの間合いで話についていけるんだけど、船が通った、電車が通ったみたいなことに意識がいってるうちに聞き逃して、筋がわからなくなったりする。そうそう、編集作業としては、少しだけ間を増やすって作業が多かったです。
魚田
収録した音源に?

阿部
そう、手を加えて。喋り続けてるものは聞き逃しちゃうんだけど、喋らなくなると意識が戻るんですよね。現地と自宅での調整を繰り返してわかった面白いポイントでした。でもまだまだ、家で聞くと言っても、水を流してお皿を洗いながらかもしれないし。コントロールしきれないのがラジオ演劇の大きな特徴ってことに、高松以上に気付いたような気がします。
魚田
それはそうかもしれない。
阿部
比較すると「今日のたかまつ アーカイブス」は、お話として頭から追いかけるっていうより、それぞれの時代感や、一言一句を追跡するではない聞き方があったんだと思うんですよね。ただ、今回のテキストはなにを喋ってるかを追った方がいい性質のものだったんだと思う。
魚田
そうですね。お話があるというか、聞き流せるラジオの設えをとってないものがほとんどなので。このフォーマットを採用する以上、それは宿命ですよね。
阿部
そういうこともあって、そう、俳優との時間がけっこう印象的でした。個々の作品にいろいろな意図が埋め込んであるから、7つの作品がそれぞれどういう質感のものか、すり合わせや模索が必要で。俳優さんは、それぞれけっこう違う作業をしてくれたんじゃないかと思います。矢部さんの「7.安藤さんの放送局」と、トヨザワさんの「1.歩むひとの放送局」の演技はかなり、違う世界線。今回、そのあたりの未知だった領域を開拓できたのもよかったなと思います。でも、いろんな課題も同時には見えて。課題という言い方ではないのかもしれない、ここを変えたら違うものができるってことがいろいろあるというか。
魚田
例えば?
阿部
矢部さんとの収録のために、「安藤さんの放送局」は唯一現地で収録したんですけど、旧綾瀬川との合流点にレンタカーで行ってたんです、車で。その道中で、すでに録った音声をカーステレオで聞いたりしてたんです。全然違うんですよ、カーステレオで聞く「安藤さんの放送局」は。

魚田
そうなんだ。
阿部
カーステレオのスピーカーの配置とか、なんか空間全体に鳴ってる感じってのもあるし。社内で聞いてるっていう変さも。あ、案外車で聞いてると内容を聞き流さないんですよね。運転って他のことができないから、入って来ざるを得ない。
魚田
すごい。「ドライブ・マイ・カー」だ。
阿部
これはカーステレオで聞く作品です、ってラジオ演劇が存在したらまた全然違うと思うんです。
魚田
カーステレオラジオ演劇、いいですねぇ。
阿部
東名高速を100キロ移動しながら聞きます、みたいなね。
魚田
渋滞専用とか。
阿部
今回は好きな場所で聞くっていうのと、隅田川沿いで聞くっていうふたつを想定していたけど、また違うまちだったら違う環境があるし。あとあれですね、イヤホンで聞くのと、カーステレオはスピーカーだし。そうそう、「老戦士たちの放送局」も同じくカーステレオで聞いたら、猛烈にAM感があった。
魚田
(笑)。それは面白いですね。確かにつくってて、視聴する方法はイヤホンで聞くってことを想定してたので。それをポジティブに捉えて、いろんなかたちも発明できそう。
阿部
そんな気がします。あと、天気とか気温も関係すると思う。これが夏だったらきっと違うだろうとか。今回はすみゆめの期間ってことと、いろいろな年間の創作スケジュールもあってこの期間でしたけど。
※2 居間theater:東彩織・稲継美保・宮武亜季・山崎朋の4名からなるパフォーマンスプロジェクト。音楽家や美術家、建築家、空想地図作家、研究者など分野の異なる専門家との共同制作のほか、カフェ、ホテル、区役所、待合室など既存の“場”とそこにある“ふるまい”をもとに作品創作をおこなう。現実にある状況とパフォーマンスやフィクションを掛け合わせることで、現実を異化させるような独特の体験型作品をつくり上げる。(すみゆめWEBサイトより)
https://www.imatheater.com/
※3 空想型芸術祭Fiction:居間theaterが空想地図作家・地理人と組み2018年より手掛けているプロジェクト。実在の都市・東京と架空の都市・西京の2都市で開催されているという設定で、さまざまな音声作品がWEBサイトにて公開されている。
http://fiction.chirijin.com/
フィクションのレイヤー
魚田
話が戻りますが、居間theaterの「Fiction」のときは、自分の住んでるまちじゃない架空のまちがあって、そのまちでも同じ企画をやってるっていう、別の場所の存在を想像しながら聞くっていう設計で。これはちょっと複雑なように見えて、実は今いる現実をかっこに入れて「架空のまち」っていうものを経由してつくれるっていう、つくる側としてありがたい設定だったんですけど。
阿部
「Fiction」の西京市みたいな設定はラジオ倶楽部にはないけれど、強いていえばミニFMが流行っているってことと、隅田川自体に蓄積しているフィクション性。取材の話や見える風景っていう「リアル」と、ある種の虚構の領域ってものを、やっぱりまた両またにかけてやってたのかなっていう印象はありました。
魚田
僕もそう思います。
阿部
やっぱり現実だけに依拠しながらつくることはすごく難しいっていうか。分厚くリサーチしたり、扱おうと思えば思うほど、そうではないフィクション領域のもうひとつの軸というか、
魚田
レイヤーみたいな。
阿部
そういうものが創作段階であることが、きっとまちではすごく重要ですよね。
魚田
そうですね、まちは圧倒的にリアルだから、フィクションは儚すぎてすぐに飲まれちゃう。作家の中で強固な目的地を持って、そこに一瞬でもポンと飛べるような仕掛けをしておくと、僕個人としては、まちで聞いて楽しい作品だと感じられる。今回は西京市がないので、隅田川、あるいは隅田川を題材にしたたくさんのフィクションを目的地にして、そこへ飛ぶように目指してつくりました。それを自分で設定してつくれたっていうのは、作家としてちょっと成長したかなってかんじはあります。
阿部
フレームワークとしてのフィクションってところはすごく重要ですよね。あとづけ的に自家発電でフィクションをこしらえようとすると大変だし、現実で収集してきたものをもう一度、ただプレゼンテーションするだけなのも、なんだかよくわからない。でもこうやって、とある世界観を積極的に片足にしつつつくったものって、作品それ自体がまた次のフィクションの片足になれるじゃないですか。まちの申し子のような作品にはなっていないことで、確実にまちからもらったものが入っているけど、まちから距離もあって、そういうことって題材になったまちのひとにも、そうじゃない人にも開いていけるってことにつながっていくんじゃないかという予感もあります。
魚田
なるほど。
阿部
でもこれって「作品つくるぞ」という軸をしっかり持つという、シンプルな話でもある。限られた時間のなかでつくっていくときは、だから積極的になにかとの掛け算なのかもしれないなっていう。それは題材かもしれないし、人材かもしれない。そのあたりは今後の活動にとって大事なところかもって思ってます。
研究開発、そして
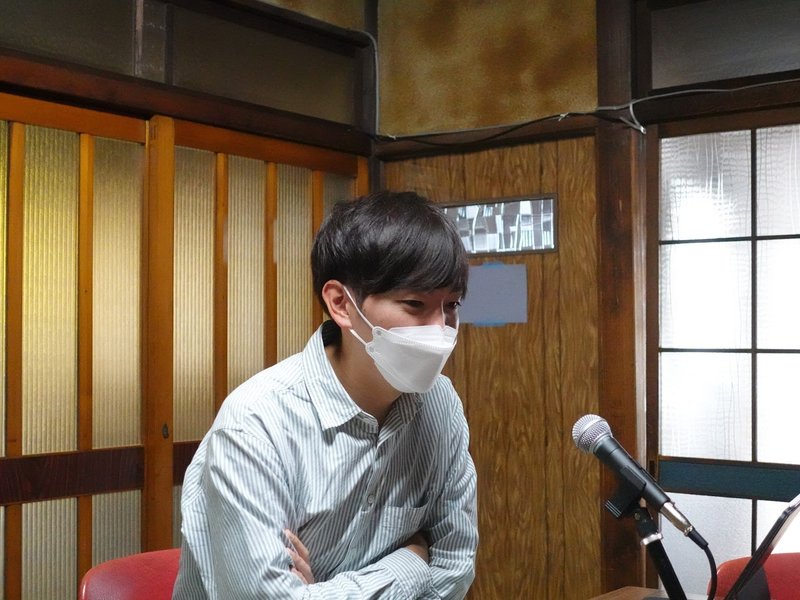
阿部
「作品をつくる」といってもいろいろあるじゃないですか。どんどん作品をつくっていくパターンもあれば、なんかもうちょっと自分たちのためっていうか、ゆっくりとしたペースもあれば、商品として割り切って売っていく人たちもいて。uniでやりたい創作はどこだろうと考えると、最近関心があるのは「研究開発」なんですよね。実験を繰り返して、知見を得ていって、ノウハウ化していく。だからラジオ演劇を別の人がやってもいいと思ってるんです。
魚田
ほうほう。
阿部
研究開発のなかでできてきたいろんなものを、次はもっと普及版みたいなかたちでやれるとか。事業的な側面も含めて。例えば、1ヶ月間の製作期間だとこれぐらいのボリュームのことができますよ、みたいな。生み出すだけじゃなく、回していくことも視野に入れたい。今後の団体としての継続性を考えていくときにそういう事業としての整理が必要になるような気がしていたりします。必要というか、そういうあり方に関心がある。
魚田
ダウンサイジングというか、ポータブル性を上げるっていう発想は今まではなかったけど、確かに大事なことかもしれないですね。
阿部
年齢的なことも相まって、徐々にひとつのまちに注げる時間が減ってきてるんですよね。それを頑張って増やそうとすると今度、生活が成り立たない面もあって。だから限られた時間に生み出されたものをどう自分のものだけにしないかってこととか。それもあって、誰と組むかとか、誰に開いていくかみたいなことがポイントになってきてる。そうそう、松竹梅みたいなことっていうか。
魚田
お試し版と、本格版と、特選版みたいな。あれですね、スケール感もかなり試行錯誤が必要な感じはしますね。
阿部
そうですね。でも、ラジオ演劇はまだまだやれることがいっぱいあると思ってて。高松、そして墨田と、全然違うあり方のプロトタイピングができた。
魚田
さらに発展、変化していく余地がたくさんあるということですね。
阿部
そうですね。変化していく余地があるし、高松編の初期ぐらいから考えると、いろいろなことが変わってきたなって感じがしますね。
魚田
必要性もあるのか、変わる。
阿部
でも、「そっか、じゃあ最近はまちづくりをやめたんですね」みたいな。いや、そういう話ではないんだけどね、と。
魚田
頑張ってなんとか生き延びていたんだよ。
(了)
この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?
