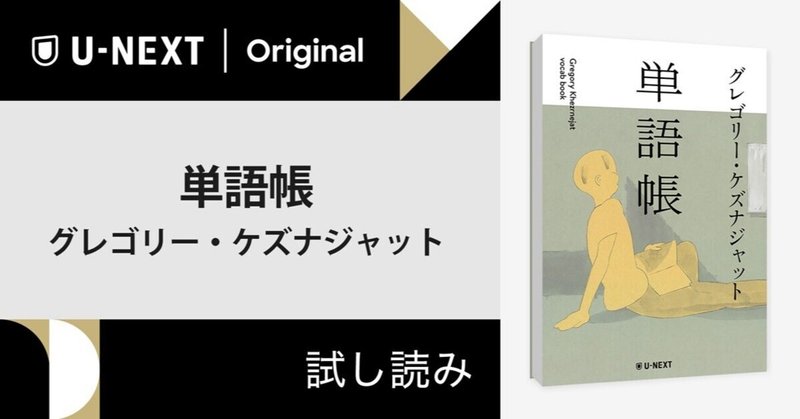
【試し読み】グレゴリー・ケズナジャットさん『単語帳』
京都文学賞受賞のデビュー作「鴨川ランナー」では、二人称を用いて日本で暮らすアメリカ人青年の心の揺らぎを描き、芥川賞の候補にもなった近作「開墾地」では、イラン生まれの父のペルシア語とそれを理解できないアメリカに生まれ育った青年の関係を小説にした、グレゴリー・ケズナジャットさんの最新作「単語帳」。本作では、同じ母語、さらに同じ方言の二人が第二言語の日本語で会話する。言語とアイデンティティをテーマにした、越境文学の新鋭による掌編。冒頭の一部を公開します。

■著者紹介
グレゴリー・ケズナジャット
1984年、アメリカ合衆国サウスカロライナ州グリーンビル市生まれ。2007年、クレムソン大学を卒業ののち、外国語指導助手として来日。2017年、同志社大学文学研究科国文学専攻博士後期課程修了。現在は法政大学グローバル教養学部にて准教授。2021年、「鴨川ランナー」にて第二回京都文学賞を満場一致で受賞し、デビュー。同年、受賞作を収録した『鴨川ランナー』を刊行。最新作『開墾地』が第168回芥川賞の候補となる。
■あらすじ
東京・神楽坂の居酒屋で僕が出会ったのは、同じ母語で、さらに同じ方言を話すマルコムだった。大学教員の僕と傷心旅行中だという翻訳者のマルコムはしかし、彼の要望から日本語で会話する。現在は仕事もプライベートもほとんど英語の僕と、モフモフの翻訳につまずいたことをきっかけに言語と自分の関係に違和を覚えるようになったマルコム。分厚い単語帳を持ち歩き、旅行する目的とは? 第二言語の習得と個をめぐる短編小説
■本文
入店してすぐに、男の姿に気がついた。
古風な家屋を改装したような居酒屋で、店内は全体的に狭かった。隅に押しやられたテーブルは空いていたが、調理場を囲む丸いカウンターに数人の客が一人、または二人組で座っていた。こちらに背を向けていた男の顔は見えなかったものの、椅子の寸法に微妙に合わない細長い体格といい、ポニーテールに束ねた黒髪の薄い髪質といい、店の中で顕著に目立つ佇まいに、親近感と、いささかの同情が自然と湧いてきた。僕もこうして後ろから見ると、おそらく同じように目立つのだろう。
若い店員に案内されるままにカウンター席につき、男の横顔を覗き見た。高い鼻の下にもじゃもじゃとした髭を生やした顔は無表情で、カウンターの一点を見ることもなげに見つめている。片方の肘をついていて、猪口をぼんやりと宙に浮かせている。アメリカ人なのかヨーロッパ人なのか、顔立ちでは判別がつかない。いや、外見だけで判断するのはよくない、日本人という可能性だってある。どこからかそんな諭しの声が一瞬頭に浮かんできたけれど、それでも僕と同じようなよそ者である確信を持った。
視線を感じたのか、男は顔をこちらに向け、さっきまでの真顔は朗らかな、やや酔っていそうな歪んだ微笑に変わった。
「Cheers」と、手に持った猪口を微かに挙げ、やはり英語で挨拶してきた。
「Cheers」僕は反射的に答える。掲げるグラスはまだなく、ただ不器用におしぼりを持ち上げた。
東京に来て半年ほど過ぎた頃、僕はよく神楽坂に出かけるようになった。
上京のきっかけは就職だった。京都の大学院で日本文学を研究してきて、ようやく博論がなんとか通りそうな段階で仕事探しに取り掛かったが、どこの大学も文系の教員を減らしている中、専門のポストの公募がなかなか上がってこない。同級生は誰しも同じ困難に遭っていたし、大した業績のない留学生だとなおさらだ。
「国際系の学部はどうだ」
そう提案してくれたのは指導教官だった。教育の「グローバル化」を進めるために、様々な新事業を打ち出しているという。英語開講科目の増加とか、英語論文の推進とか、グローバルスタンダードに適合するように、全国の大学にいろんな形で革新を催促しているらしい。「グローバルスタンダード」という言葉を、僕はそのとき初めて聞いた。
「つまりきみみたいに、日本のことをしっかり勉強した経験があって、その魅力を英語で語れるような人材は、今はむしろ重宝されているんだ。国際系の学部だと、日本と世界の架け橋を務めることができる」
半信半疑で検索すると、確かにそのような新設学部はいくつかあった。それぞれのホームページに先生が使った「グローバルスタンダード」という謎の言葉をちらほら見かけ、そのままスクロールすると採用情報のリンクが現れた。選り好みしている場合ではない。どの学部にしろ、とにかく就職先が決まればそれでよかった。
文学研究に飽きていたということもある。図書館の書庫で所狭しと並んだ書架に囲まれ、黴臭い古書と崩れかけの資料を必死に読み漁っている間に、いつの間にか重苦しい圧迫感を覚えるようになった。いくら読んでも読みきれない。どこまで研究してもその先がある。これだけ膨大な量の文章が存在するのに、なんで新しいものを書き出そうとするのか。それどころか、理解しようとすることすら愚かに思えてくる。歴史とともに絶え間なく量産されつづけて、蓄積されてきた言葉を想像すると、まるで大海原で溺れているような無力感に襲われ、息苦しくなった。
採用情報のリンクをクリックし、応募書類を確認した。
初めて就職先の教室に入って教壇に立ち、文学ではなく、母語である英語を教えたとき、あの圧迫感から解放された。新築の学舎は現代的な趣で、教育機関より高級商業施設を思わせる。壁を占める大きな窓ガラスは綺麗に磨かれていて、朝の陽射しが美しく流れ込んでくる。僕の口から発する教科書通りの言葉と、学生が続いて復唱する言葉には何の重さもない。ただの音と息としてしばらく悠然と漂っていって、静かに消えていく。
院生のだらしない生活もあっという間に改善された。博論を書いていた最後の一年間、食事も睡眠もろくに取らず、深夜まで古い資料に読み耽るのが常だったが、転居を節目に規則正しい習慣を導入した。朝八時から午後五時まで、きっちりと仕事をこなし、夕方と週末は余暇に当てた。外食を控え、栄養バランスを考えた食生活に心掛けた。毎晩、夜十時に就寝し、翌朝の五時半に近所で一時間ほどランニングする。
摩擦も障害もなく、万事順調に進んでいく。書庫で過ごした歳月も、第二言語での会話についていく努力も、すべてがこんな形で結果を実らせ、これからはやっと、ゆっくりしてもいい。今までの苦労がやっと報われた、と僕は自分に言い聞かせた。
数ヶ月が経つと就職間もない頃の気合いが少しずつ薄れ、規則的な生活が緩んできて、そのうち週に三、四回、仕事帰りに寄り道して神楽坂を彷徨するようになった。大学のキャンパスを出て、外濠に沿って十分ほど歩くと、そのこんがらがった横道や路地が迷路のように広がる。飲み屋やレストランが続く町並みを眺めながら細い坂道を登り、通り過ぎた店先の看板の字体だの、窓から漏れてくる光とさんざめきだの、ふと気づいたところに惹きつけられると、そのまま店に入っていく。
夜な夜な酒を呷らないと我慢ならないほど大変な仕事に就いたわけでもなく、一人暮らしの部屋に帰ることを忌避していたわけでもない。強いて言えば、僕の中のどこかで、この新しい生活にまだ馴染んでいなかったのかもしれない。神楽坂の飲み屋の空間に浸っていると、しばらくの間、学生時代の自分を呼び戻すことができた。
男はふいに徳利と猪口を手に、危うく立ち上がり、隣の席に移ってきた。
「Malcolm」と男は名乗り、右手を差し出した。「Good to meet ya.」
僕は笑顔で握手に応えた。
間近で見るとシャツは皺だらけで、あちこちに古い汚れのようなシミが点々としている。まだ二十代半ばだろうが、顔を覆っている無精髭が最後に手入れされたのはいつだろう。男が僕に向けていた陽気な微笑みと、目尻の張り詰めた筋肉との間に、不自然な違和が気になる。だが男が喋りだす言葉には懐かしいものがあった。
僅かな口数だけで、微かではあったが確かに南部方言特有の母音の曲がりが聞き取れた。ノースカロライナの西部か、それともテネシーの東部か、とにかくこの男はアパラチア山脈のどこかで育っただろう。たまたま同じ山脈の麓に生まれ育った僕の英語も、きっと同じような背景を語っていただろう。
「So, where ya from?」
マルコムの出身地を聞いてみた。男の訛りに釣られてか、最近使っていなかった方言が自ずと口から出た。
「Chattanooga.」
チャタヌーガか。テネシーとジョージアの州境に位置する、やはりアパラチア山脈に囲まれた都市だ。僕が生まれ育った町から数百キロ離れていて、日本の感覚でいえば遠く、アメリカでいえば近いという微妙な距離だった。高校生のとき、一度だけ修学旅行で訪れたことがあった。歴史好きの担任の先生の話をいい加減に聞きながら、南北戦争の戦場跡を見学した。詳細はとっくに忘れたが、ルックアウト山を登り切って、鬱蒼とした草木に覆われている眺めは今でも記憶に残っている。
「You?」
「South Carolina.」
そう答えると男は相好を崩した。「Now ain't that somethin'.」
日本に来てから南部出身の人と出会ったことはなかった。長い間聞いていなかった方言の聞き心地がよくて、ちょっとした発音の特徴だけで、僕はマルコムに対して思わず好意的になった。
しばらくたわいない会話を交わした。大した共通点があったわけではないが、方言が会話を弾ませた。もし神楽坂の居酒屋ではなく、たとえば故郷のバーでたまたま隣の席になっていたら、おそらく互いに口を利くこともなかっただろう。僕らが共有していたのはあくまで言葉と発音と、一連の記憶を呼び起こすなんてこともない固有名詞だけだ。しかしそれらが常に飛び交っている地方から遠く離れた店の中では、僕らの言葉は珍しくて、貴重なもののように思える。
「So ya livin' in Tokyo then?」
きみは東京に住んでいるのかと。
「Yeah, since April. You?」
ああ、四月からここに住んでいる。あなたは?
「Naw, I'm just travelin'.」
旅行者だったのか。それなら、彼の乱れた格好は納得できた。京都ほどではないものの、この街でも海外からのバックパッカーをあちこちで見かける。おそらく浅草近くのホステルにでも泊まっているのだろう。そう思うと急に観光地の情報を伝えてあげたくなる。僕も東京に来たばかりだし、誰でも知っているような名所しか分からなかったが、同胞としての親近感と、住民としての優越感が混じっているようなものを感じた。
若い店員がドリンクメニューを持ってきてくれて、僕はマルコムの前に置かれた徳利を指差して日本酒を注文した。
「同じものを、一合ください」
どこを勧めればいいかを真剣に考えた。明治神宮やスカイツリー、いかにも観光地というところは退屈だろう。バックパッカーならガイドブックに載るようなところより現地の世界にすんなり潜っていく空間のほうが楽しいだろう。見たところ酒が好きそうだし、高円寺はどうだろうか。そういえば日本橋も悪くない。
「Ya sound like a native.」
ネイティブのように聞こえると。てっきり南部方言のことを言われているかと思った。ネイティブのように聞こえるのではなくてネイティブだろ、とよく分からない自負のようなものがどこからか湧いてくる。店員に対してとっさに出てきた日本語に意識もしていなかった。
返事をする前に、マルコムはいきなり日本語に切り替え、話を続けた。
「ちょっと、日本語で喋っても構わないかな?」
すぐには理解できなかった。発音がおかしかったとか、声が小さかったとか、そういうことではない。むしろ極めて流暢な標準語で、イントネーションも僕の言葉なんかよりも聞き取りやすかった。たださっきまで話していた南部訛りの英語が急に日本語に変わり、まるで違う周波数に設定された受信機のように、僕の耳はその言葉を摑みそびれた。数秒遅れて彼が発した音に意味がついてきても、どう答えたらいいのか逡巡し、一瞬の間を置いた後、英語で返した。
「Why?」
なぜ。なぜ、僕らはここであえて日本語を使うのか。なぜ、日本語ができるのか。どちらの意味でそう尋ねたか分からない。おそらくどちらもこもっていただろう。意図せずとも挑発的なニュアンスも含んでいたが、マルコムはただ静かに笑って、さっきまでの濃い南部訛りに染まった物言いを忘れさせるほど清澄な日本語で答えた。
「まあ、別にいいんじゃない? ここは日本だし、郷に入れば的な感じで」
数秒間、マルコムの顔をただ呆然と見つめていた。だがようやく、ここ数ヵ月、店員との紋切り型のやりとりを除いてほとんど口にしなかった日本語で、仕方なく返事を絞りだした。
「ああ、わかった。じゃ、日本語で」
彼はごく自然に、申し訳ないね、と言わんばかりに短く会釈した。身体表現さえ、きっちりと「日本語」に変わっていた。
※ 続きは電子書籍版でお楽しみください。
U-NEXTオリジナルの電子書籍は、月額会員であれば読み放題でお楽しみいただけます。

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?
