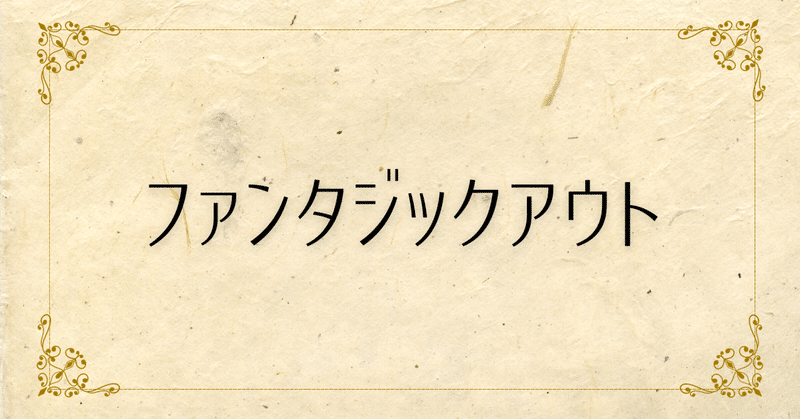
ファンタジックアウト

もう嫌だったの。こんな、特別扱いのような生活。
「これからの橋住(はしずみ)を担っていくのはお前なんだぞ?有香(ありか)」
「嫌だ!!私は普通の生活がしたい!!上辺だけの友達しかいないなんて嫌!!」
「橋住家は代々続く家柄だ。その一人娘であり、跡取りのお前が、庶民と同じ生活をしてどうする。友達など不要だろう」
「私は、お父様みたいに、他人の気持ちがわからないような冷たい人間になりたくないもの!!」
信じられない。家族ほど、信じられないものはない。
だから抜け出した。日常から。あの、異常な生活から。
「ふむふむ」
「りり、どうかした?」
教室で新聞を広げる少女に、思わず声を掛けた。
「あれ?みいがこんな早い時間に登校なんて、珍しいじゃない。また親と喧嘩?」
「まあな。で、りりは相変わらず新聞なんだな」
「もちろん!大事な情報収集ですから」
りり―苗木李梨菜(なえきりりな)は、満面の笑みを零した。
一方、みい―林条未樹(りんじょうみき)は、額に手を当てながら溜め息を零した。
「りり、みい、おはよう」
「あ、ゆう。おはよう!」
そこに現れたのは、最近転校して来たゆう―有沢結花(ありさわうゆうか)。
「で、その真剣に読んでる新聞には、良い情報でもあったか?」
みいは再び、りりに視線を向けた。
「うーん、今日はこれとか興味深いんじゃないかな?」
新聞を机の上に広げ、指を差した先を、みいとゆうは覗き込んだ。
『橋住社長の一人娘、失踪』
「橋住って……あの、不動産王の、だろ?」
「うん、そう。あの大企業の社長さんね」
「家出とか書いてあるけど……わからんね。金持ちのお嬢様が逃げるなんて」
「裕福なのが決して、幸福とは限らないってことじゃないの?」
りりの言葉に、みいは溜め息をついた。
「ってか、この顔……ゆうにそっくりじゃないか?」
「えっ!!?」
今まで黙って聞いていたゆうは、びくっと肩を揺らした。
「やだな。他人の空似じゃない?私は普通の家だってば」
「いや、でも、これは似すぎだろ」
「確かにそうね。あなた、一人暮らしだし。あまり前の学校とか、おうちのこととか言わないわよね?」
みいとりりに問い詰められ、ゆうは精一杯首を左右に振った。
ゆうは、周囲を警戒してから、さっと家に入ると、すぐさま玄関に鍵を厳重に掛けた。そのまま、扉に背を預け、盛大な溜め息を着いた。
いずれ見つかるのだろうか。橋住の家を飛び出し、何とか数か月は周りに溶け込みながら一人で生活してきた。
しかし、父のことだ。私を見つけるためなら、いくらでも金を積むだろう。そうなったら、もう逃げ場所はないだろうし、帰宅後はより家に縛られるのだろう。
そう考えただけで、とてつもなく憂鬱で、思わずその場にへたり込んでしまった。
その時、ベランダから大きな音がした。
「っ!!」
噂をすれば影、だろうか。早速、追っ手が来たのかもしれない。強盗という可能性もあるが。どちらにせよ、戦わねば!と思って、傍にあった傘を握りしめ、恐る恐るベランダへと近づいた。
ちらっと物陰に隠れながら覗けば、カーテンをのそのそとどかそうとする人影が見えた。
「うわぁぁぁぁぁっ!!!」
覚悟を決め、叫びながらカーテンを一気に開き、傘を振りかざした。
「っ!!?うわぁぁぁぁぁっ!!」
相手も負けずと叫んだが、そこでゆうの手は止まった。
想像していたものと違ったからだ。確かに人ではあるのだが、日本人かどうかが怪しい。ファンタジー小説でしか見たことがないような、不思議な服を着ており、思わず固まってしまった。
青年は、腰を抜かしかけていたものの、すぐに立ち直ったのか、若干ムッとしながら口を開いた。
「脅かすなよ、アリカ」
「え?なんで、私の名前……あなた、やっぱりお父様の追っ手ね!?」
「は?何言って……ああ、そっか。記憶ないんだっけ」
彼はそう言うと、さっと立った。
「記憶?あなた、何言って……」
「今話す……って言いたいけど、今は無理みたいだ」
彼が言い終わると同時に、チャイムが鳴り響いた。
あまりのタイミングの良さで、思わず背筋に冷たいものが走った。
隠れて過ごしているため、普段は客人など一切こないのだが、なんて珍しい日なんだろうか。そう思っていると、青年に腕を引かれた。
「なっ、何するの!?」
「……俺が出る。アリカはここで待ってて」
「いや、私の家なんだけど……」
そう言い終わる前に、彼はさっさと行ってしまった。茫然と眺めていたが、突然玄関から爆音が聞こえた。
「っ!!?」
驚くのと同時に、彼が物凄い勢いで走ってきて、ゆうの腕を掴むと、その勢いでベランダへと駆け込み……飛び降りた。
「いやぁぁぁぁっ!!!」
マンションの七階の部屋からのダイブだった。
ゆうは大きな悲鳴を上げつつ、見知らぬ男と無理心中だけは嫌だと嘆き、ふと上空を見上げると、自分達の後を追うように、やはり見知らぬ男が飛び降りてきた。太陽の光に反射した、綺麗な金髪を靡かせ、獲物を見るような瞳で射抜かれた。
ゆうの意識はそこで、暗闇へと落ちていった。
「信じられません!もしも、アリカ様に何かあったら、どうするのです!?」
「だから、謝ってるじゃん。ってか、覇族長が追って来たんだし、逃げて当たり前だと思うけど」
「それが、守族長であるあなたの台詞ですか!?」
「姫が言うような台詞でもないと思うけどな」
「ほんと、相変わらず無礼ですね!」
どこかから、男女の言い争いが聞こえる。ゆうは、そっと目を開くと、さっきの男と綺麗な女性が口喧嘩をしていた。
「ここ、どこ?あなたたちは?」
その言葉に二人は、やっとゆうが目を覚ましたことに気付いた。
「あっ、アリカ様!お目覚めになったのですね!?」
女性がパッと近づくと、ゆうの手をぎゅっと握りしめた。
「え?あの……」
戸惑っているゆうに、ハッとしたような表情で見つめ返した。
「あ……記憶が、戻ってないのですか?」
女性はそっと口に出した。
「そんな時間がなかった。覇族に追われたからな。ってか、どっちにしろ王の力じゃなきゃ、戻せないんだろう?」
「そう、でしたね。父を呼んできます」
そう言って、女性はゆうに一瞥すると、部屋を後にした。
2人だけになった部屋では、どちらからも喋ることはなく、沈黙だけが居座っていた。
やがて、彼女が戻ってきた。一人の男性を連れて。
「ああ、救世主よ。やっと目覚めたか」
「……は?」
突然の呼び掛けに、ゆうは素っ頓狂な声を上げてしまった。
「お父様。まだアリカ様の記憶が……」
「ああ、そうだったな。……では、失礼する」
そう言うと、男性はゆうの額へと手を翳すと、光り出した。
『彼女は守族の救世主として、生まれてきたんだ』
『いずれ、彼女は私たちを守って下さる』
『望まれて生まれて来た救世主、アリカ・ロジーナ』
『彼女は狙われてる。その重い運命を背負っているせいで』
『このままでは、救世主は彼らの手に渡ってしまう』
『ロジーナさん、離れるのは寂しいでしょうが……この子のためにも、下界に送りましょう』
『何故だ!何故、この子の命が狙われる!救世主である以前に、俺たちの大事な娘なんだぞ!?』
『お願い、この子守って!』
『そう、下手すれば王よりも大事な存在なのだから』
『さようなら。また会いましょう、アリカ』
「あ……こ、れは……」
思わず頭を押さえる。
今まで沈んでいた記憶が浮上する感覚。それは満たされるのと同時に、不安を仰ぐのだ。
「アリカ様!」
「大丈夫だ。心配するな。少し、辛い過去が戻っただけだ」
その言葉に、他の人間は心配そうに見つめた。
「私は……アリカ?アリカ・ロジーナ……」
ふたつの世界での記憶が交錯する中で、“本名”を呟いた。守族としての。
「アリカ様!思い出されたのですか!?」
「……あなたは?」
アリカの声に、ウェーブのかかった淡いピンク色の髪を揺らしながら、彼女は満面の笑みを浮かべた。
「私は、リサベル・アリア・リズと申します」
「これでも、姫だからな」
「もうっ!ほんとに、失礼な男ですね!」
リサベルは怒鳴り声を上げたが、アリカの驚いた声が勝った。
「えっ!?王女、なの?」
「アリカ様はそういう風に呼ばないでください。“リサ”って気軽に呼んでほしいです」
「いやいや、そういう訳には……ってか、私に『様』をつけるの?その方が間違ってない?」
「そんなことありません!」
リサベルは思わず声を張り上げたが、その後ろで青年は盛大な溜め息を吐いた。
「ったく。姫は暴走しすぎだ。さて、アリカ。自分の正体を思い出せたんだ。自分が何故、記憶を失うことになったのかも、思い出せるだろ?」
厳しく言い放つ青年の質問に、アリカは眉を顰めた。
「記憶を取り戻したばかりなのに、その言い方はないでしょう!せめて、あなた自身名乗ってからでしょう!」
思わず噛みつくように言い放つリサベルに、彼は肩を竦めながら答えた。
「思い出したんなら、わざわざ俺のこと言う必要あるか?」
その言葉に、アリカはカッと目を開いた。
幼い少女と少年。二人仲良く遊んだ草原。約束した想い。
「……ダイチ?」
その言葉に、彼は微笑んだ。
「ああ。守族長、ダイチ・ウィルだ」
そのやりとりを見ていたリサベルは、口元に手を当てて呟いた。
「……本当でしたのね。あなたとアリカ様が幼馴染だったというのは」
「嘘だと思ってたのか?」
思わずムッとしながら返すダイチだったが、それを微笑みながら見るアリカも口を開いた。
「でも、本当に族長になったなんて思わなかった」
アリカの言葉に、リサベルは腰に手を当てて返す。
「本当ですよね。そんな約束をアリカ様とした、って聞いた時、さすがに驚きましたもの」
幼い子供でも、彼女の運命の重さを感じていたダイチ。だから、子供ながらに約束したのだ。
「俺、大きくなったら強くなって、アリカを覇族から守るんだ!」
幼い子供が交わした約束。それは、彼女がいない間に果たされていたのだ。
アリカが戻ってくることを信じ、守族長の座まで上り詰めたダイチは、迎えに行くという形で再会したのだった。
「子供の約束だからな。俺も、まさか本当になるなんて思ってもなかったし」
あっさり言い放つダイチに、リサベルは冷たい視線を送った。
「あなたも夢がないですね」
「ダイチ、照れ屋だったから。ただの照れ隠しでしょう」
そう言って、アリカはぽんっと手を叩いた。
「そうだ!折角帰って来たのだし、両親に会いたいのだけど……」
その台詞を聞いて、ダイチの表情は凍りついた。そして、リサベルに振り向く。
「姫、悪いが席を外してくれないか」
「え?」
リサベルはきょとんとした表情で問うが、今まで黙って聞いていた王はリサベルの肩を叩き、一緒に出て行った。
二人だけになった部屋で、アリカは訝しげな表情でダイチを見た。
「……ダイチ?」
「お前の両親のことだが……」
その重い雰囲気に、アリカは固唾を飲み込んだ。
「お前の親父さん……亡くなったんだ」
「え?」
アリカは目を丸くした。
「……俺が守族長になったって時点で、わかっていたかもしれないけど」
アリカはそこで思い出した。父親が守族長だったことを。
言われてみればそうだ。守族長だった父。そして、今の守族長はダイチ。それが何を表しているのかに、気付いた。
「お前が居なくなった後、一度だけ覇族の猛攻撃を受けたんだ。お前を探してな。それで……守族長だってこと、救世主の父親だってこと、この二つが合わさって、親父さんの戦いぶりは凄かったんだ。今でも伝説として語り継がれてるレベルでな。ただ、その時の傷が原因で……」
そこでダイチは言葉を止めた。
「私の……救世主の父親だったから、身を挺してしまったの?」
「そういうわけじゃ……」
「でもっ!」
「いいから続きを聞け!」
アリカの叫び声を遮るほどに、ダイチは声を張り上げた。
「……親父さん、死ぬ直前までお前のこと心配してた。自分が守ってあげなきゃいけないのに、自分が先に逝くなんて、ってな。ただ、本望だったんだと思う。愛娘を少しでも守れたことが……。だから俺、親父さんと約束したんだ。俺が守族長になって、守るからって。それを聞いて、笑顔で頷いてくれたんだ。……それが、俺が親父さんと会った最期になったけど」
その言葉に、アリカはその場で崩れた。
「……お母さんは、どうしているの?」
「お袋さんは……親父さんの死が相当ショックだったんだろうな。それ以来、あまり体調が良くないんだ。今は病院にいる」
「ねぇ、ダイチ。連れてって、お母さんのところへ。そして、お父さんのところへ」
アリカのその台詞に、ダイチは大きく息を吐いたものの、すぐに頷き返してくれた。
白い壁。白いベッド。白い日用品。全て白で統一された部屋。
その白いベッドの上に横たわる女性が、真っ白な部屋の中で唯一浮かび上がる色彩。
「こんにちは。ロジーナ夫人」
呼ばれた女性はゆっくりと振り返った。生気がなさそうな虚ろな瞳で、声の方を見た。
「……ただいま、お母さん」
やや緊張に満ちた、少女の声が病室に響き渡った。
「……アリカ?」
合わなかった焦点はすぐに一人の少女へと視線を移された。
「ああ……アリカ……会いたかったわ」
掠れた声で呟き、頬には涙が伝う。母はアリカへと腕を伸ばした。
「お母さん!」
アリカは母の元へ駆け寄り、抱きしめた。
「ごめんね。辛いときに側にいてあげられなくて」
「いいのよ。あなたが生きていてくれただけで」
久しぶりに感じた温もりに、アリカも涙を流しつつも微笑んだ。
「お父さん……ただいま」
墓石の前に佇む二人。アリカは墓前に花を添え、ゆっくりと口を開いた。
「……私、絶対にこの世界を救ってみせる。もう、誰にもいなくなってほしくないから……だから、お父さん。もう少しだけ力を貸してほしいの」
その言葉を聞いて、ダイチが呟いた。
「俺は、あの時の約束通り、お前を守るつもりだ。それが、親父さんの願いだし、約束だから」
「うん。ありがとう。ダイチ、私に力を貸して。私もあなたを助けるから」
「ははっ、当たり前だろ!」
二人は笑いあう。約束を胸に誓って。
「では、やってくれるのだな?」
「はい。それが私の宿命であるのなら、出来る限りのことはしてみます」
アリカは王の前に跪いていた。
「そして、その補佐を族長自らが志願か?」
「はい」
ダイチはゆっくり頷いた。
「では……我、守王が命じる。救世主の運命を背負いし者、アリカ=ロジーナ。覇族との戦いに終止符を。我ら守族を救ってくれ。そして守族長、ダイチ=ウィル。守族長として、彼女に忠誠を誓い、彼女を守ることを」
王の声が響く。
「あの……アリカ様」
王との謁見を終え、廊下を歩いていると、リサベルに呼び止められた。
「私も一緒に行きたいのです」
ダイチは眉間に皺を寄せた。
「姫、遊びに行くんじゃないんだぞ」
「わかってます!父にも止められましたから。だから、せめて“これ”を」
リサベルは懐から手鏡を取り出し、差し出した。
「亡くなった母の形見です。これを持っている女性は、神の加護を受けるという言い伝えがありますから。せめて、アリカ様のお守りとして」
「そんな大事なもの、受け取れないよ!」
「……では、これはお貸しするので、返してくださると約束してください。一緒に行けない私の代わりに、連れて行ってほしいのです」
リサベルは、ぐっとアリカに手鏡を押し付け、目を伏せた。
「私、初めてだったんです。年の近い女の子と親しく話せたの。だからアリカ様とはいつまでも、これからもずっと友人でありたいと思うのです。だから……っ」
その言葉にアリカは笑みを零し、リサベルの手を握った。
「じゃあ、“様”は付けないでほしいな。友達なんでしょう?」
そう言うと手鏡を受け取った。
リサベルは驚いたようだったが、すぐに「ええ、もちろんです!」と嬉しそうに答えた。
「ここが……」
荒れた大地。乾いた空気。活気なんてものが全く感じられない。守族の住む土地とは全く正反対だった。
「ようこそ、覇族の地へ」
「っ!!?」
突然響いた第三者の声に、アリカとダイチはハッとして声の方へ視線を向ける。
そこには、無造作に伸ばされた金色の髪を風に靡かせる男が一人。アリカがこの世界へ帰ってくるきっかけになった、あの時の男だった。
ダイチはアリカの前へ立つと、目の前の男を見遣る。
「まさか、覇族長直々のお出ましとはな」
「それはお互い様だろう、守族長。しかし、まさか守族長までいるなんてな。用があるのは救世主だけなのだが」
そう言うと、視線をアリカに向けた。
「待っていた、救世主殿。王がお待ちだ」
「王って……覇王?」
「ああ。他に誰がいる?ここは覇族の地だぞ?」
彼はくつくつと笑い始めた。それにムッとした表情で答えるアリカ。
「どこの誰だか知らないけど、そんな態度だとあなたの話なんて聞きたくないわ」
アリカの強気な言葉に、彼は笑みを止めると真剣な表情になり、そのまま腰を折った。
「これは失礼を。俺は覇族長、キータ・サレルア。以後、お見知りおきを。救世主、アリカ・ロジーナ殿」
腰の低い挨拶をされ、アリカとダイチは気味悪さを感じたが、促されるように後をついていった。
夜のように暗い土地の中でも、自分の存在を表すように光る金の髪の後を追って歩くアリカとダイチ。
アリカは無言で目の前を行く彼を追い、その半歩後ろを気に食わないような表情で重い足取りで歩くダイチ。
「……アリカ、やっぱりいくらなんでも危険だ」
「でも、覇王に近づけるでしょ?」
「自ら蟻地獄に突っ込んでいくようなもんだろ?」
その言葉に、アリカは考える素振りを見せるが、すぐに口を開いた。
「……その時はその時かな。なるべく、ダイチには迷惑かけないようにするけど……」
「そういうこと言ってるんじゃなくて!」
「出来れば、話し合いで終わらせたいから。救世主というのなら、誰も傷つけないで終わらせたいから」
意志の強さは父親譲り。それゆえに、自らを追い詰めるのも。
「無理っ、……するなよ」
思わず否定してしまったダイチだが、すぐに訂正した。
「ようこそ、救世主殿。覇族の地へ」
男は低い声を響かせながら呟いた。アリカはすぐに緊張した表情へと変わる。
「あなたが、覇王?」
「いかにも」
「それなら話は早いわ。私は、話し合いで争いを止めたい。そっちにその意思があるかないか。イエスかノーで答えてほしい」
はっきりと述べるアリカに、覇王は楽しそうに顔を歪めた。
「ああ、随分と気の強いお嬢さんだな。好きだな、そういうところ」
そう言ってアリカに笑みを向ける。
突然の告白に、気持ち悪さを覚え、アリカはぞわりと背筋を凍らせた。しかし、覇王から帰って来た言葉は、欲しい言葉ではなかった。
「もちろん、話し合いで何とかなるのなら、とっくにそうしてるさ。……救世主殿は長い間下界にいたのだろう?我々が争う理由は聞いているのか?」
この世界には二柱の神が存在する。
全ての“始まり”を司る守護神と、全ての“終わり”を司る破壊神。
守護神は世界の繁栄を歓び、破壊神は人々の絶望を宥めた。
しかし、正反対の彼女らは戦いを始めることになる。
いずれ、自分たちの生存を維持するため、それぞれ自分の眷属となる生命体を作り上げた。守護神を守る守族。破壊神を助ける覇族。
神自身は戦いから身を引き、彼らに自分たちの命運を任せた。
彼らは神のために何度も何度も衝突を繰り返し、血を流す。
神は第一線から身を引いたと言っても、彼らに力を注いでいたため、各々力の限界を悟り始めた。
そして、守護神が動いた。救世主を作ることによって、この無意味な戦いに終止符が打たれることを。世界に平穏が訪れるように、と。
「そう、だから滅びる訳にはいかない。我々も、守族も」
覇王はゆっくりと呟いた。
アリカは何も言えずに黙ってしまったが、すぐにぐっと力を入れると静かに、だがしっかりと言葉を紡いだ。
「だったら、どちらも生き残ればいい。目的が同じなら争う必要もないじゃない。生も死も、どちらも大切なものだし、どちらも無くなることはない。手を取り合うことは難しいかもしれないけど、お互い干渉せずに生きていくことはできるでしょう?」
「簡単に言うな。我々は争うことが使命なんだ。争わなくなったら、滅びるのは我々だぞ」
「……そんなことないと思うわ。あなた、さっき言ったでしょう?戦いに終止符を打つために生まれたのが私だって。それは、神だってこの戦いが不毛だって思ってるからよ。たぶん、意味なんてないんだわ」
その言葉に、その場にいた全員が目を見開く。
「そんな……じゃあ、我々は何をすればいいのだ!?」
「それを、これから見つけるんじゃない。戦いがなくなったのだから、他のことに裂く時間が増えたんだもの」
今日も快晴で、その空の上で行われていた種族間の争いはいつしか消えており、ただただ青空が綺麗に映えている。
「アリカ、姫のところに寄ってくのか?」
「うん。今日遊びに行く約束してるし」
ダイチは鞄を肩に担ぎながら、アリカに聞くと、アリカも教科書を鞄に詰め込み、ダイチの元へ急いだ。
今、彼女らは下界で過ごしていた。
アリカの願いは一人一人の意思を変え、それぞれの王を……神を動かした。
王のみがそれぞれの地に残り、神に仕える形で、世界の均衡は保たれた。そして、王以外の者は下界に下り、神とは切り離すことによって、争いを回避した。
それぞれの種族を纏めるのは族長で、種族間の喧嘩は許されていない。下界とそれぞれの土地への行き来を許されるのは、王の継承者と族長、そして救世主のみ、という形で厳しく定められた。
アリカは、守族の救世主としてだけでなく、覇族の救世主として、唯一全ての土地を自由に行き来できる存在になった。
「で、何でお前までいるんだよ!?」
ダイチは思わず叫んだ。目の前には金髪の青年、キータが座っている。しかも、リサベルと向かい合う形で。
「うるさいぞ、守族長。俺らはお互い、王の継承者として話をしていただけだ」
鼻で笑いながら高圧的に答えるキータだったが、驚いたのはアリカだった。
「え!?キータって覇王の継承者だったの!?」
「ああ、現時点ではな。王に子供がいないどころか、結婚もしてないからな」
「マジかよ……いい歳したおっさんだろ?」
ダイチが思わずツッコんだが、キータは思い出したように口を開いた。
「……ああ、そう言えば、救世主殿を嫁にしたいって言ってたぞ?」
ぴしりと音を立て、アリカとダイチは固まってしまった。
何とか意識を取り戻したダイチは冷たい声で言い放った。
「そうか。覇王はロリコンだったのか……」
「勘弁してよ!」
「そうですよ、キータ殿。アリカはうちの族長とくっつく予定ですから」
「ちょっと待てっ!!」
キータに続き、爆弾発言をするリサベル。ダイチの盛大なツッコミが返ってきた。
「いつからそんなことになったんだ!?」
「だって、“一生”守るって約束したのでしょう?」
笑顔でさらりと述べるリサベルに、ダイチは盛大な溜め息を漏らした。
「そうか。守族長と救世主殿はそういう間柄だったのか。王に伝えておこう」
「納得しないでよ!ただの幼馴染よ!」
アリカの否定に、キータはニヤニヤと笑いながら彼女を見つめる。
「救世主殿がどう思ってるかは別として……守族長はわからないぞ?」
「違うっつってんだろ!!」
ダイチの盛大な叫び声が聞こえるが、キータは一切気にしていないようだ。
「守族長、そんなに否定しなくてもいいだろう?救世主殿が可哀想だ。あ、それとも守族長はそちらの姫君の方がお好みだったかな?」
さすがのそれには絶句して固まったダイチだが、リサベルは「最低ですね!」と言いながらダイチに平手打ちを食らわせた。哀れ、守族長。
「じゃあ、救世主殿。俺にしないか?」
キータの暴走発言に、ダイチは彼に飛び掛った。
「貴様っ、本気で殺されたいのか?」
「種族間の争いはなしだぞ?なあ、救世主殿」
ぴしっと音を立てながら、二人は火花を散らして睨み合った。
「あらあら。モテモテですね、アリカ」
その台詞に、アリカは溜め息を一つ零すが、携帯のベルが鳴った。その内容は、種族間の揉め事が勃発した、という報告だった。彼女はそれを切ると、立ち上がって身なりを整える。
「ほら、いつまで喧嘩してるのよ!仕事よ!」
そう言うとさっさと走り去る。
キータとダイチもお互いを睨むと、すごい勢いで去って行った。
「喧嘩するほど何とやら、ですわね」
残されたリサベルは笑顔でそう述べた。
神同士の争いがない世界で救世主はいらないかもしれない。
けれど、彼女は今までなくすことができながった争いを、いとも簡単に無くした人物。
神が望みを託した救世主に間違いなかった。神も人も共存出来る世界へ。
おわり。
この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?
