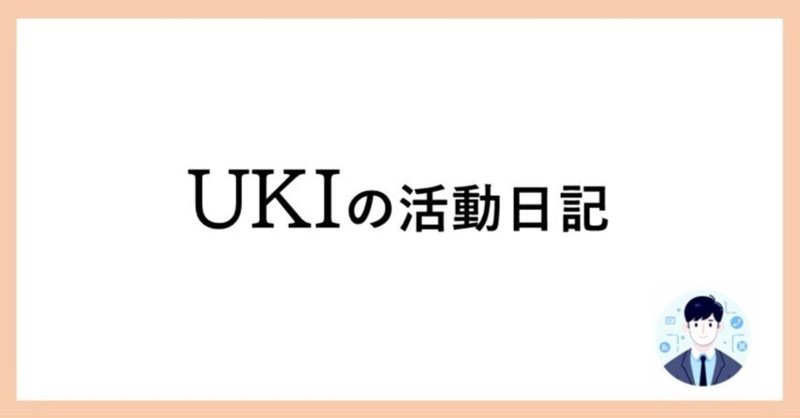
【#28】基本情報技術者「システムの移行」
おはようございます。
データサイエンスを学んでいる、大学4年生のUKIです。
今日は、『基本情報技術者「システムの移行」』というテーマでお話ししたいと思います。今日は、昨日に引き続き、基本情報技術者の模試で分からなかった問題で学んだことのアウトプットです。
模試を通じて学んだこと
問題「システムの移行」
今回紹介する問題の一つ目は、こちらです。
問題)システムの移行計画に関する記述のうち、適切なものはどれか。
A.移行計画書には、移行作業が失敗した場合に旧システムに戻す際の判断基準が必要である。
B.移行するデータ量が多いほど、切替え直前に一括してデータの移行作業を実施すべきである。
C.新旧両システムで環境の一部を共有することによって、移行の確認が容易になる。
D.新旧両システムを並行運用することによって、移行に必要な費用が低減できる。
この問題は、なんとなくAを選択して、一応正解はしたのですが、深く理解できていないので、「システムの移行計画」について深く調べてみました。
新システムの開発から導入まで
新システムを導入するには、「システム開発部門」「システム運用部門」「システム利用部門」の3部門が関わります。
新システムの開発から導入するまでの流れとそれぞれの担当部門は、次のとおりになります。
新システムの開発(開発部門)
移行計画・作業(開発部門)
受入れ支援・テスト(開発部門)
導入サポート(開発部門)
保守(開発部門)
サービス設計(運用部門)
移行・受入れ作業(運用部門)
運用の引継ぎ(運用部門)
システムの移行計画書と移行方式
今回深く掘り下げるのは、太字で書いた「移行・受入れ作業」の部分です。
移行作業は、事前に作成された計画書(移行計画書)に従って行われます。
移行計画書には、「移行の日時」「移行手順」「移行が失敗した時にもとに戻す場合の判断基準」「元に戻す手続き」などの内容が記載されています。
次に、移行方式の種類についてです。
移行する方法は一つではなく、主に4つあります。
一斉移行方式
これは、休日などを利用することで、一気に新システムに切り替える方法のことです。
この方法のメリットは、「移行期間が短い」「移行にかかるコストが安い」ことです。一気に移行するので、移行期間は短く、元のシステムと同時並行でやるわけでもないので、コストが抑えられるというわけですね。
これに対してデメリットは、「障害が業務に与える影響が大きい」ことです。もし移行時点で障害が発生した場合、元のシステムに戻すにしても、大規模な作業になってしまって、業務に与える影響が大きいということですね。
つまり、一斉移行方式は、システム移行の費用や時間・手間を抑えたい場合に適しています。
パイロット移行方式
これは、一部の拠点や部門に限定して新システムを導入し、動作を観察した後で全体を移行する方法のことです。
少し脱線しますが、先ほどの「一斉移行方式」は、「一斉」という用語が入っていたので分かりやすかったのですが、「パイロット」では名前が分かりづらくて、覚えられない気がしました。そこで、名前の由来についてChatGPTに聞いてみました。
得られた回答はこちらです。
「パイロット移行方式」は、コンピューターシステムのアップグレードや変更などの際に、新しいシステムを段階的に導入する手法です。この手法の名前の由来は、航空機の操縦手法に由来しています。航空機のパイロットが、新しい機種やシステムを学ぶ際には、まずはシミュレーターや訓練機で基本的な操作を練習し、徐々に実機での飛行に移行していくのが一般的です。同様に、パイロット移行方式では、新しいシステムを段階的に導入することで、従来のシステムと新しいシステムの間でスムーズな移行を実現します。
つまり、パイロットがいきなり実機で飛行せずに、訓練機である程度練習してから実機に移るという流れから、パイロットのように段階的に移行していくシステムのことを「パイロット移行方式」というらしいですね。
※これが真実かどうかは確認していませんが、一つの覚え方として、これを頭に入れておきます。
話を戻します。
この方法のメリットは、「移行時の問題による影響範囲を局所化でき、リスクが少ない」ことです。先ほどの一斉移行方式と比較すると、リスクの少なさが一目瞭然ですね。
次にこの方法のデメリットは、「全社的なやり取りが生じる部分については、運用が複雑になる」ことです。
つまり、パイロット移行方式は、初めてのシステム移行で慎重に移行を行いたい場合に適しています。
順次移行方式
これは、業務や機能ごとにシステムを分割し、段階的に新システムへ切り替える方法のことです。
この方法のメリットは、「障害を一部に限定できる」「運用部門の負荷が少ない」ことです。業務や機能ごとにシステムを分割することで、障害が発生する範囲を抑えることができます。そのおかげで、運用部門にかかる負荷も抑えることができるというわけですね。
それに対してこの方法のデメリットは、「移行の手順が複雑である」「移行期間が長い」ことです。元のシステムと同時に稼働するため、新旧のシステム間で連携が必要になり、多くのコストや時間がかかります。
つまり、順次移行方式は、移行するデータの量や種類が多く、一斉移行を避けたい場合に適しています。
並行移行方式
これは、新旧システムを同時稼働させ、新システムの安全が確認するまで運用したうえで、切り替える方法のことです。
この方法のメリットは、「移行方式の中で最も安全である」ことです。新旧システムを同時に稼働させることで、もし新システムに障害が生じても、元のシステムで業務が続けられるので、安全というわけですね。
それに対してこの方法のデメリットは、「移行期間が長い」「運用部門の負荷が大きい」ことです。新旧システムを同時に稼働させている間に、「新システムに問題がないか」を検証するため、移行期間が長くなります。また、データを2回入力したり、システム同士を同期させたりといった手間が発生するというわけですね。
つまり、並行移行方式は、リスクを最小限に抑えたい場合に適しています。
参考資料:
・令和03-04年 基本情報技術者の新よくわかる教科書 情報処理技術者試験 | イエローテールコンピュータ | コンピュータ・情報処理 | Kindleストア | Amazon
・システム移行は侮れない|5つの注意点と手順をくわしく解説 (wakka-inc.com)
長くなってしまったので、今日はこのあたりで終わりにしようと思います。
まとめ
最後まで読んでいただき、ありがとうございました。
今日は、『基本情報技術者「システムの移行」』というテーマでお話しさせていただきました。
今後も日々の活動や学び、考えていることなどを発信していくので、よろしくお願い致します。
また、X(旧:Twitter)でも発信しているので、フォローお願いします。
Xでnoteの更新を投稿しているので、DMや引用リポストで感想などを呟いていただけると、大変うれしいです。
この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?
