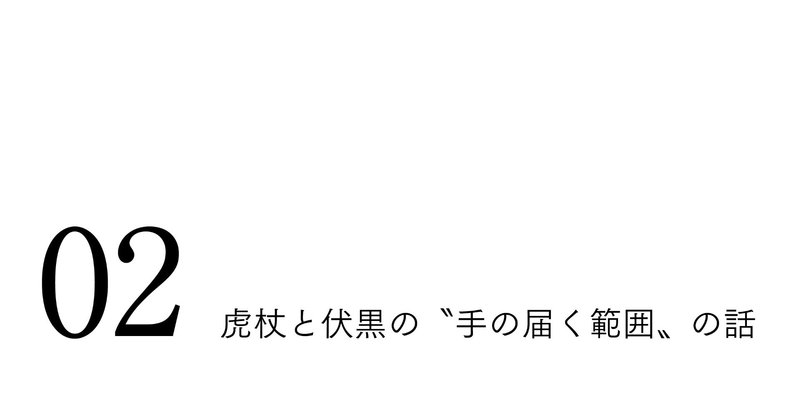
02. 虎杖と伏黒の〝手の届く範囲〟の話
同人誌『瞼の裏で覚えてる』より再録。
この記事の大幅加筆修正版です。
前章で「夏油は人に順位をつけることを嫌っている」と書いたが、このテーマは虎杖と伏黒にも顕著に表れている。虎杖と伏黒(そして釘崎も)は夏油と違い、非術師全員を救おうだなどと大それたことは考えない。虎杖も伏黒も、すべての人を救えるわけではないことをわきまえている。言い換えれば、虎杖と伏黒は人に順位をつけることを忌避しない。
ただ、二人はその区切り方が違う。虎杖は自分の手の届く範囲で命を選別しないで救おうとするのに対し、伏黒は更に命の価値に順位をつけて上位(自分が〝善人〟と定義した人)を救おうとする。
虎杖の〝手の届く範囲〟
「誰もかもを救うことはできない」のを最初から理解している主人公はとても珍しい気がする。もちろんこれはごく当たり前のことで、人間関係には序列(親密さの差)がある。知り合いが死ぬのは怖い。寂しい。助けたい。家族や友達ならなおさら。だが、赤の他人の死は、ただの数字だ。
例えば、医療職や教職といった、ある種の〝聖職者〟と見られがちな人であっても「結局は人間なのだから、私生活をなげうってまで自分の身を捧げるのはどうなのか?」という問題提起と似ている。そのような職に就いていても、身も知らぬ他人のために、親しい人と同じ温度で自分の命を賭けることができるだろうか? 自分の能力の限界まで、あるいは限界を超えて献身を求められたらどうするのか?
人の命を助けるという医療職と似たような性質を持つ呪術師であっても(現実の医療職以上に労基署に通報されたら即アウトなのは間違いない)、特段、崇高な職業ではなくて、ただ人を助ける特別な〝力〟があったから、その力を生かしているに過ぎない――この考え方が作品の根底にあるように感じる。そして、その考え方は主人公三人組にとてもよく表れている。
虎杖の動機は序盤に示されている。
「宿儺を喰う」それは俺にしかできないんだって。死刑から逃げられたとして、この使命からも逃げたらさ、飯食って風呂入って漫画読んで、ふと気持ちが途切れた時、「ああ今宿儺のせいで人が死んでるかもな」って凹んで、「俺には関係ねえ」「俺のせいじゃねえ」って自分に言い聞かせるのか? そんなのゴメンだね。自分が死ぬ時のことは分からんけど、生き様で後悔はしたくない。
これには祖父の遺言が影響している。
オマエは強いから人を助けろ。手の届く範囲でいい。救える奴は救っとけ。迷っても感謝されなくても、とにかく助けてやれ。オマエは大勢に囲まれて死ね。俺みたいにはなるなよ。
虎杖は遺言を呪いと呼ぶけれど、その呪いを自ら望んで受け入れる。彼は「寂しがり屋だから、大勢に囲まれて死にたい。そのために人を助ける」とも言うし、きっかけが祖父でも、きちんと自分で選び取った道だ。
己の力の及ぶ範囲で人を「正しい死」に導くこと――「正しくない死」を回避すること。自分が強者で、誰かを救う力を持っているから、何もしないではいられない。呪術師になる理由としては重すぎないくらいで、とても身近に感じる動機付けだ。世界を救うとか、呪霊によって苦しむ人間すべてを助けるだとか、大それた望みを虎杖は持たない。
元来、このような「救える人には限りがある」みたいなドライなことを言うのは、伏黒のような(主人公たりえない)クール系ポジションが担ってきたように思う。だが、お人好し主人公であるはずの虎杖も、現実の無情さを知っている。自分には限界があると知っている。ジャンプの作品をすべて見てきたわけではないけれど、虎杖はジャンプの主人公の中ではかなり毛色の違いを感じる。
知ってた? 人ってマジで死ぬんだよ。だったら、せめて自分が知ってる人くらいは正しく死んでほしいって思うんだ。
だいたいにして、誰かを助ける理由として「生かすため」ではなくて、まっさきに「正しい死」を提示してくる主人公は初めて見た。
この考え方は序盤での祖父の死によるものだが、「死」が――終わりが必ず来ることを虎杖は強く意識している。何をどうしても自分自身の死刑が確定しているからだ。だから、自分の「生き様」、すなわち「死ぬまでどう生きるか」に焦点を当てる。それがとても新鮮に感じる(処刑されそうになる主人公が死刑を回避するために人を救うというパターンは比較的よく見るが、何をしても死刑が覆らない虎杖はけっこう珍しいように思う)。
「正しい死」を与えようとするのは、時に傲慢な行いとなる。何が正しいのかを定義しなければならないからだ。価値観の多様化した今、正しさはひとつではなく、絶対的な正義は独善と化した。それを背負おうとするのはとても難しい。
「正しい死って何?」
「そんなこと私にだって分かりませんよ。善人が安らかに、悪人が罰を受け死ぬことが正しいとしても、世の中の多くの人は善人でも悪人でもない。死は万人の終着ですが、同じ死は存在しない。それらを全て正しく導くというのはきっと苦しい。私はおすすめしません。などと言っても君はやるのでしょうね」
「……」
「死なない程度にして下さいよ。今日君がいなければ私が死んでいたように、君を必要とする人がこれから大勢現れる。虎杖君はもう、呪術師なんですから」
七海が言うように、この世は善人でも悪人でもない人が大半を占めている。時に善を為し、時に悪を為す。善行のみを積める人はめったにおらず、悪行とも呼べない小さな悪を為すのは珍しいことではない。虎杖も世間知らずの幼い子どもではないから、知らなかったわけではないだろう。だが、それを眼前に突きつけられる衝撃はあった。
正しい死に様なんて分かりゃしない。ならせめて、分かるまで、あいつを殺すまで。もう俺は負けない。
虎杖は少年院で己の上を行く強者がいることを思い知らされ、順平の一件で「正しい死」への信念を揺るがされる。それでも、「正しい死」へ人を導くのは止めない。手の届く範囲しか助けられないことを知りながら、助けられなかったことを悔やみ、歩みを止めない。そういうところはジャンプ的主人公らしさとも言える。
先輩であり、一度逃げ出したはずの七海が虎杖を止めないのは、呪術師にとって〝呪術師で在り続けるための意味〟が必要だからなのだと思う。延々と消耗戦を繰り返すばかりの理不尽さへ立ち向かうためには、強い信念が必要になる。たとえ独り善がりになる恐れがあったとしても。そういう傲慢さにも似た強い意志を持ち合わせていることこそが、過酷な環境で己の職務を全うしなければならない〝強者〟たる呪術師なのかもしれない。
この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?

