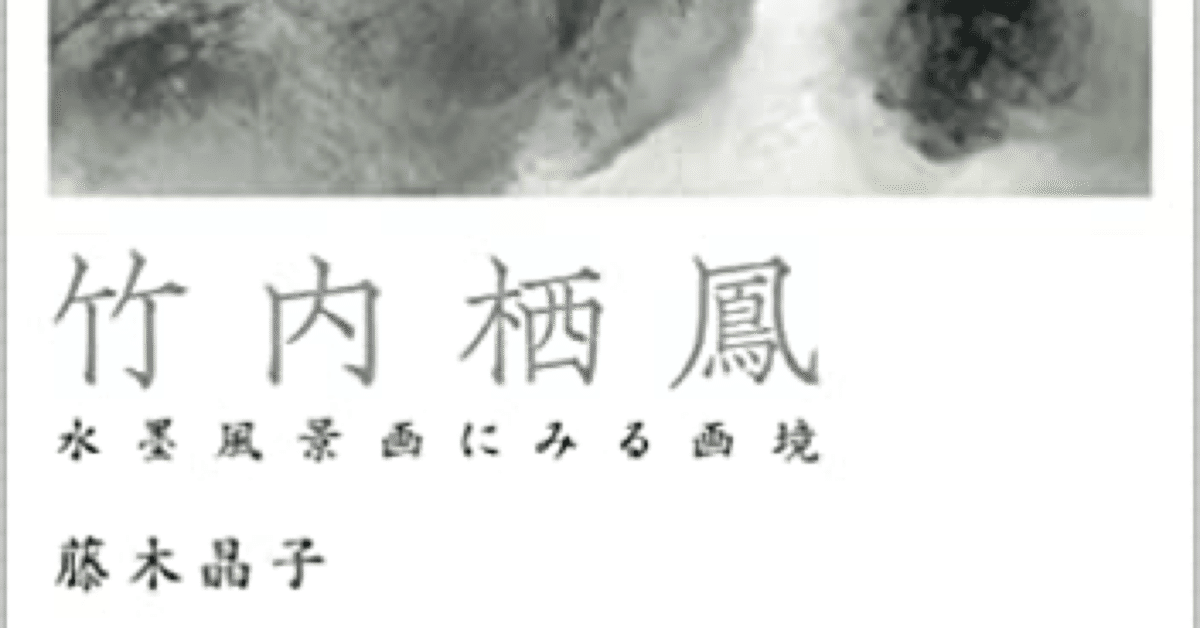
論文マラソン27 藤木晶子『竹内栖鳳 水墨風景画にみる画境』
今日は頑張って書籍1冊のご紹介です。
藤木晶子さんのご著書『竹内栖鳳 水墨風景画にみる画境』(思文閣出版、2023年)です。
論文マラソン24で紹介した論文は、この本をまとめたもののようです。
【目次】
第一章 栖鳳晩年の水墨風景画の全貌
溌墨・破墨の画法と栖鳳作品
大正末期頃~昭和七年頃
昭和八年頃~昭和九年頃
昭和一〇年頃~昭和一六年
水墨風景画制作の変遷
第二章 「淡交会展」における挑戦
淡交会の特徴と意義
第三回淡交会展
第七回淡交会展
淡交会における出品画家の動向
第三章 潮来風景の写生取材の実態
写生帖の素描分析
藤岡鑛二郎の著述
竹内栖鳳の著述
写生取材から絵画化への推移
第四章 中国と潮来の風景表現の連繋
中国訪問と同地の風景画
中国風景画に辿る表現の契機
潮来風景画における表現の変遷
水墨風景画に至る絵画創作の展開
第五章 「栖鳳紙」開発と作画意図
日本画の基底材に関する動向
栖鳳紙の開発着手から完成まで
栖鳳紙に対する試験分析
紙本と絹本を巡る栖鳳の思索
第六章 近代水墨画と栖鳳の画境
近代の水墨表現の推移
東京画壇の水墨画
京都画壇の水墨画
南画系の水墨画
洋画出身者の水墨画
栖鳳の水墨画の位置付け
博論を書籍化されたものです。作品分析が多いせいか、読みやすいです。
第2章の淡交会の分析、これは販売を前提としている会ですよね。官展出品作との違いはそういう点もあるのかな、と思ったのですが、どうなんでしょう。
第3章・第4章、潮来が中国・揚州の風景と重ねられたっていうのは、栖鳳以外の画家もなんでしょうね。近代の潮来がどういう風に画家とか観光客とかに認識されていたのか、もっと知りたくなりました。
第5章の紙の話が、私は面白かったです。近代日本画って、絹に描いていたのが大正頃からみんな紙に描くように変わっていきますよね。その変化に越前和紙の職人さんが関わっていたのですね。
第6章、近代の水墨画の流れをまとめるのは大変だろうな、と思いました。栖鳳の晩年の水墨画、魅力的ながらも今まであまり注目されずにきたので、いろいろ面白く拝読。
2時間半ほど
この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?
