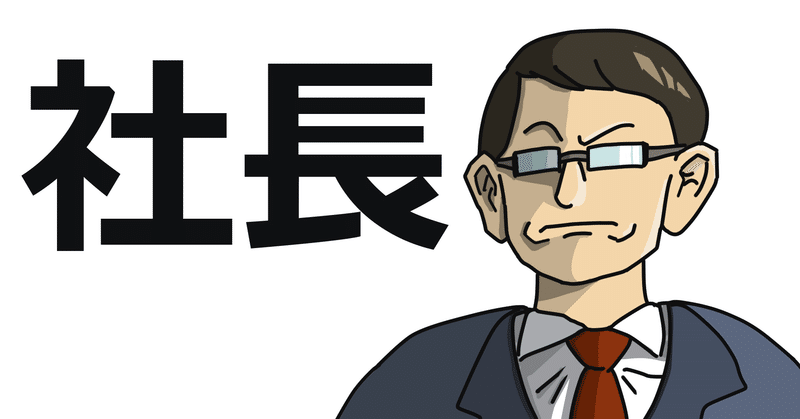
経営者の立場から退職金を考える
これまでは退職金をもらう方、つまり従業員の立場から退職金について考えてきました。
では、視点を変えて経営者の立場から退職金の問題を考えていきましょう。
1.なぜ経営者の立場を理解する必要があるのか?
労使の交渉を行う上で、経営者の立場、考え方を理解しておく、ということがとても大事だからです。
なぜか、それは前回触れたことに関係しています。
前回のnoteで確認した様に、日本の退職金(企業年金含む)は労使関係で変わってくるからに他なりません。
この記事では、確定拠出年金への移行が進んでいる、ということが書かれています。
ただ、まだ多くの企業が確定拠出への切り替えを行っているわけではありません。
でも取り上げたように、
○退職給付(一時金・年金)制度がある企業は若干の増加。退職年金制度がある企業は引き続き減少しているが、それを上回って退職一時金制度のみの企業が増加。
というのが現状です。

こちらでも確認できるように、1,000人以上の企業で50.5%の企業が確定拠出年金を採用している訳で、残りの49.5%では採用していない訳です。
さらにいえば、300~999人 31.5%、100~299人 16.4% 30~99人 6.9%と規模が小さくなるに従い、採用企業は少なくなります(確定給付企業年金についても同様)。
企業年金を採用していない企業は、退職金制度、すなわち自分の会社の中で退職金の原資を積み立てているだけ、の状況です。
繰り返しになりますが、倒産しても資産の保全がされていなければ退職金は満額払われない可能性があります。勤め先が法律上の倒産手続きに入った場合の記述部分を抜き出しましょう。
賃金を含む勤め先が負うすべての債務の弁済は、それぞれの法律に定められたそれぞれの債権の優先順位や手続に従って行われます。
・法律上の倒産手続においては、賃金等の労働債権については、一定の範囲について優先権が与えられていますが、会社等に残された財産の状況によっては、賃金の支払が遅れたり、カットされたりする可能性もあります。
・一方、倒産手続に拘束されない債権は、勤め先の会社等に請求すれば足りますが、それぞれの法律に基づいて財産を管理・処分する管財人等が選任されている場合には、管財人等に対して賃金債権の弁済を請求することになります。(法律上の倒産手続のうち、破産及び会社更生においては、必ず管財人が選出されることになっていますが、民事再生においては、必ずしも管財人が選出されるとは限りません。)
え、倒産したらやばいじゃん・・・
と思われると思います。
安心材料にはなりませんが、退職金が保全されていなからといって、劣後債券(優先度低い債券)として取り扱われるわけではありません。
以前の分―つまり破産手続開始前3か月よりも前の分については、支払期限が来ている賃金請求権は、財団債権ではなく「優先的破産債権」という債権として扱われます。「優先的破産債権」は、財団債権とは違って、配当手続きによって支払いを受けることになります。ただし、他の一般の破産債権よりも優先して配当を受けることができます。
さらに未払賃金立て替え制度もあります。
本来、賃金の支払は個別の事業主の責任の範囲に属するものですが、会社等が倒産した場合には、残された財産が乏しい場合も多く、実際に労働債権を回収できるとは限りません。
そこで、労働者の救済を図るために、法律上の倒産又は中小企業の事実上の倒産の場合に、賃金を支払ってもらえなまま退職した方を対象に、国が「未払賃金の立替払制度」を実施しています。
いいねぇ!と思われる方、すいません。
・ 立替払の対象となる未払賃金は、定期的な賃金及び退職金に限ります。
※賃金の支払期日について条件がありますので、ご注意ください。
・ 立替払される額は、未払賃金の額の8割です。
ただし、退職時の年齢に応じて88~296万円の範囲で上限があります。
涙・・・・・。
最大296万円という。無いよりはいいですが・・・。
2. 勤め先の退職金制度の確認方法
ご自分の勤めている退職金制度ってどうなってるんだっけ?
と思った方は、労働組合関係の資料や自社の総務室にお願いすれば出してもらえると思いますが、上場企業であればこちらから確認できます。
有価証券報告書についてはこちらで詳しく取り上げていますので、ぜひご参照ください。
有価証券報告書には投資の判断に必要な情報があります。「金融商品等の公正な価格形成等」(金融商品取引法 1 条)を実現するための基礎資料と位置付けられています。なので、偽りの情報を記載すると法律違反になります(有価証券報告書虚偽記載)。
上場企業であれば、社内で手に入れられる情報の他にこちらの情報も合わせて参照してください。
有価証券報告書をデータで入手したら、キーワード検索で「退職給付」と打ってみてください。そうすると自社の退職給付制度(退職金制度)がどういった形で運営されているかが出てきます。
ソフトバンク・グループのケースでは以下のように標記されています(有価証券報告書(106頁)。
(12) 退職給付
確定拠出制度は、雇用主が一定額の掛金を他の独立した基金に拠出し、その拠出額以上の支払について、法的債務または推定的債務を負わない退職給付制度であり、確定給付制度はそれ以外の退職給付制度をいいます。当社グループは、主として確定拠出型年金制度を採用しています。
a.確定拠出制度
確定拠出制度への拠出は、従業員がサービスを提供した期間に費用として認識し、未払拠出額を債務として認識しています。
b.確定給付制度
確定給付制度債務は、独立した年金数理人が予測単位積増方式を用いて算定し、その現在価値は、給付が見込まれる期間に近似した優良社債の市場利回りに基づく割引率を用いて算定しています。制度資産の公正価値を控除したものです。確定給付費用は、勤務費用、確定給付負債(資産)の純額に係る利息純額および確定給付負債(資産)の純額確定給付制度債務は、独立した年金数理人が予測単位積増方式を用いて算定し、その現在価値は、給付がに係る再測定から構成されます。勤務費用および利息純額については、純損益で認識し、利息純額の算定には前述の割引率を使用しています。
当社グループでは、再測定は数理計算上の差異から構成され、その他の包括利益で認識し、直ちにその他の包括利益累計額から利益剰余金に振り替えています。
なお、当社は、2007年3月以降は全ての確定給付型退職一時金制度を凍結しています。凍結した確定給付型退職一時金制度の債務は、凍結時に確定した退職給付額に基づき算定し、従業員の将来の退職時に一時金として支払われるまで、確定給付負債として認識しています。したがって、これらの確定給付制度については勤務費用の発生はありません。は前述の割引率を使用しています。は勤務費用の発生はありません。当社グループでは、再測定は数理計算上の差異から構成され、その他の包括利益で認識し、直ちにその他なお、当社は、2007年3月以降は全ての確定給付型退職一時金制度を凍結しています。凍結した確定給付型退職一時金制度の債務は、凍結時に確定した退職給付額に基づき算定し、従業員の将来の退職時に一時金として支払われるまで、確定給付負債として認識しています。したがって、これらの確定給付制度については勤務費用の発生はありません。
ここで読み取る情報は二つで大丈夫です(他の情報は今の段階では読み取れなくてよいです)。
・ソフトバンクグループは、確定拠出年金制度を全面的に採用している。
・ソフトバンクグループは、現在(2007年3月)以降、全ての確定給付型退職一時金制度を凍結しています(つまり廃止している)。
ということです。
確定給付というのは受け取る給付が保証されている(確定している)企業年金制度のことです(ソフトバンクは全て一時金で給付していたので、確定給付型一時金制度と呼んでいるようです)。
一方で、確定拠出は受け取る給付は保証されておらず、運用次第で変化します。
えー、確定拠出って不利じゃん。
と思われる方もいるかもしれません。
ただ、前に申し上げた通り、退職事由で減額されない。企業経営者が後出しジャンケンでやっぱ満額払えないからゴメン!減らしてください!
ということが出来ないのである意味とっても安心です。
かつて破たんした日本航空では確定給付、すなわち退職金の減額が実施されました。この点、確定拠出はすでに個人の勘定で計算される仕組みなので、後で減額することが不可能な制度です。
ただし、老後保障の観点からいうと確定拠出はとても不安です。なぜならば、老後に受け取る給付が確定していない、からです。
すいません。経営者の話をするつもりが、ついつい従業員目線で話してしまいました。
ソフトバンクは確定拠出に完全に切り替えましたが、大企業でも併用しているケースが結構多いです。例えば、こちら。
企業年金(トヨタ紡織の年金)
●企業年金制度(3階)は、確定給付企業年金(DB)と企業型確定拠出年金(企業型DC)で構成され、従業員の皆さん及びその遺族の将来にわたる生活の安定を図ることを目的として運営されています。
退職金制度も含めて、様々な制度を併用しているケースが大企業では結構多くあります。
3. 経営者にとっての退職金制度は?
経営者の本音でいえば、退職金はあってもなくてもいいものかもしれません。ただし、離職者のコントロールをしたい、長く務めて欲しいという場合、退職金制度をその意図で設計している場合が多くあります。
逆に辞めてもらって大丈夫です。という場合、退職金制度そのものがない、ことが多くあります。確定拠出年金すらない、というケースもしばしば起こりえます。
ベンチャー企業などは退職金制度はないケースがほとんどでしょう。
だって、みんな辞めていきますから。
逆に、ある程度熟練したノウハウを持つ従業員が欲しい企業においては、退職金制度を設け、かつ途中退職した人に不利な制度を設けていることが多いでしょう。
あと何も考えていない、他社を模倣しているだけ、という企業もあると思います。結構多いかもしれません。つまり、ライバル社がこうしているからとか、業界団体としてこうした傾向があるから、ということで受け身で判断しているケースですね。給与体系なども他社の模倣だったりします。
退職金の原資を企業年金(確定拠出・確定給付)に振り替えるかどうか、ですが、
企業経営者の本音でいえば、
あまり積極的にしたくない、
というのが本音でしょう。
なぜならば、現金を拠出する必要があるからです。
税金のメリット、拠出金を損金算入できるとはいえ、そもそも利益を多く出していない企業にとってはこのメリットはありません。と考えれば、退職金の原資を外に拠出するよりは、現金として企業経営の資金にした方がよいと考えるのは自然なことです。
大手の企業(上場企業)で利益を上げているところは、税法上のメリット、つまり、拠出金の分だけ税金を減らすことが出来る、ということを享受しやすいので、別です。
この辺りもう少し触れていきたいと思いますが、企業のカラーが退職金制度に表れる、といっても過言ではないでしょう。
この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?
