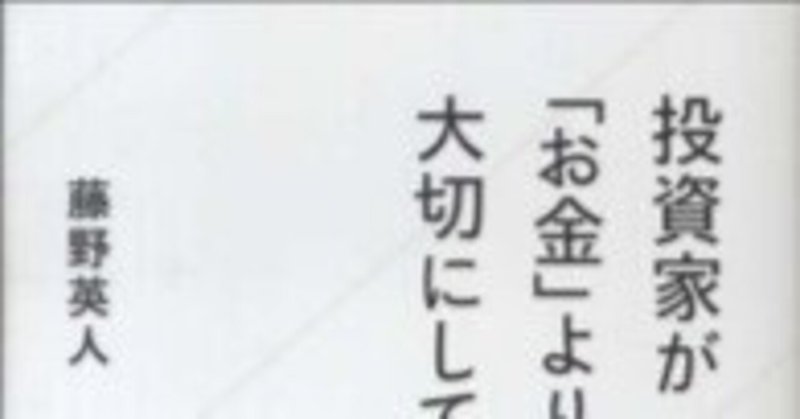
投資家が「お金」よりも大切にしていること(藤野英人)【書評#160】
「ひふみ投信」を運用するレオス・キャピタルワークスの社長が書いた本。
お金に対する著者自身の考えが述べられており、お金の理解が深まる本である。ただ、タイトルにもあるとおり、お金の話が一番大事なのではない。より大事なことがこの本では書かれている。
投資家といえば、一般的にお金に執着している印象がある。確かに、まとまったお金がないと投資では儲けが出ないので、お金は重要だ。しかし、明らかに著者は私たち一般人より、お金に執着はない。
逆に、私のような一般的な日本人の方がお金に執着している。
あえて断言しますが、日本人ほどケチな民族はいません。 困っている人のために寄附もしないし、社会にお金を回すための投資もしない。じゃあ、他の先進国の人たちと比べて、公共のためのお金である税金を多く払っているのかといえば、そんなこともない。日本の税率は、むしろ低いくらいです。 じゃあ、いったい何をしているのか? 日本人は自分のこと、すなわち、自分のお金のことしか考えていないのです。 自分のお金を現金や預金として守ることしか考えていないのです。 p.36
日本人がお金に良いイメージを持たないのは、「清貧の思想」の間違った理解にも由来する。
残念なことに、(...)「清貧の思想」は、本来の思想とはかけ離れた解釈で日本人に根づいてしまいました。「理念に生きるために、あえて豊かな生活を拒否する」という思想が、「豊かになるためには、理念を捨てて汚れなければいけない」という考え方に変わってしまったのです。(...) 清いことはとてもすばらしい。でも、そのために貧しくある必要はないし、ましてや貧しいことそのものは、正義でもなんでもないんですね。 私は、そういった「(間違って解釈された)清貧の思想」ではなく、清らかで豊かになることを目指す「清豊の思想」こそ、私たちは考えていかなくてはならない、と思っています。 pp.57-58
このような日本人マインドがある中、私たちは清豊を目指すべきだと述べる。
私は長年、投資家として生きてきたからこそ断言できることがあります。それは、 「清く豊かに生きることは可能であり、また”清豊”を目指すことが、結果的に長期間にわたって会社を成長させることがにつながる」 ということです。 けっして、あるべき姿だから、という理由だけではなく、ビジネス的・お金的な面からも、清豊を目指すべきなのです。 p.62
お金稼ぎをやらしいものとは考えない。お金稼ぎを通していかにして社会に貢献するべきかが大事なのだ。
日本人のマインドの問題は他にもある。
社会的な善とお金持ちになることがまったく両立していないのが、日本の社会になります。 パブリックなことは、とにかくぜんぶ国に任せておけばいい。そういう意識が根強くあります。ビジネスの成功がパブリックな社会貢献につながるという意識も弱い。(...)民間の機関がパブリックなことをしていることに大きな違和感があるわけです。パブリックなことは国がやる、すなわち官がやるべきだと思っている人が、圧倒的に大多数なのです。 pp.71-72
実際、政治家が子ども食堂の見学に行ったニュースに、「政治家は子ども食堂のような活動をしなくても済むような社会にするべきだ」という批判を見たことがある。たしかに、国の政策に不備があることは否めない。この国には国のセーフネットでは救うことのできない人が多く存在し、そのような人たちを救うために国が動くべきという考えは同意だ。しかし、だからといって、子ども食堂の活動を否定するべきではないし、政治家が子ども食堂を視察することを批判するのはまた別問題である。民間の活動だからこそできる政策というものもあるし、国の税収が少なくなる中、国ができることにも限界がある。
国にだけ、パブリックな政策を任せるのではなく、民間と国が二人三脚で取り組んだ方がより問題解決に近づくだろう。
社会貢献とは、新しい何かをつくりだすことだけでなく、消費することによっても成し遂げられるものです。ですから、私たちが働くことにも大きな価値があるし、私たちが消費するすることにも同じくらい大きな価値があります。 そういう意味で、「人は、ただ生きているだけで価値がある」のです。 p.84
すべてはつながっている——このことを、経済用語で「互恵関係」と言います。(..) まわりとの関係で私たちは生かし生かされているのだと認識することが、経済を理解する上でもっとも重要なことです。 p.94
統計を取ったわけではないので、詳しいことや因果関係まではわかりませんが、やはり感謝を伝える人というのは、お金や労働の価値をわかっている人、経済とはどういうものかを実感している人なのではないでしょうか。私はそう考えています。 お金持ちだからお礼を言うわけではなく、お礼を言う人だからこそお金持ちになったのではないか、と。 p.104
本来あるべき金融教育とは、働くことに価値があり、その価値ある労働の延長に企業の利益があり、その利益の将来期待が会社の価値を形成していると理解することです。 p.151
この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?
