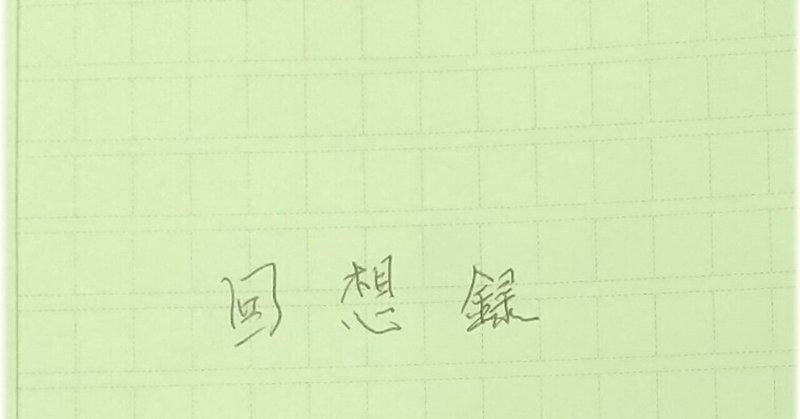
回想録 四、中学から高校へ・大学受験(父が戦場から帰って来た)
三、(その3)隣の松崎さん からつづく
父が帰ってくると冬だったので、田畑の仕事はなくて、店にも何もなく、専売品も配給だった。
庫治さん(父の兄)と植木屋の仲間と静岡へ行って、塩を焼いて内山へ持ってくる仕事をしていた。塩も配給だったので、貴重品だ。カマスに入れて囲炉裏の天井に吊るして置いてニガリを採っていた。父は軍人の特別給付の列車の無料パスの券を持っていたので、塩を運んでいた。
夜になると戦場の話をした。近所の人もお茶飲みに来ていた。満州から南へ進み、四川省の重慶を狙って夜中に更新(行進)していたようだ。
昭和19年~20年まで、その頃は米軍が東京など、軍関係のある都市を狙って爆弾を落としていた頃で、時々戦闘機に狙われるので夜の行軍になったという。灯りの代わりに行く先の家に火をつけて歩いたり、金持ちの家に入って略奪や牛を盗み、しがみつくおばあさんを殺したりしながら進んで行ったと話していた。
それが8月7日(広島に原爆が落とされた翌日、急に引き上げるように命令されたと手帳に書いてあった。本土では誰も知られていなかったが、軍の幹部は敗戦を知っていたらしい。
敗戦の知らせがあって、中国人に逆襲される恐れがあったが、途中まで武器を持っていいと言われ、安全地まで八路軍(毛沢東の共産軍)に守られた。と話していた。
戦地でのいろいろな話をしてくたれ。暇な時に歌った歌もノートを見て歌っていた。
やがて、父は軍隊的な命令が多くなった。
朝起きたら「親には『おはようございます』と言いなさい」と言い、そういう習慣はないので嫌だった。少し経つと言わなくなった。
春になると子牛を買った。それの世話を任された。散歩や餌やり、毛の手入れなどだ。
やがて、百姓の仕事を手伝いながら家族労働の一人として、仕事を覚えていった。
種蒔きから収穫まで、田や畑の仕事、山での薪採り。牛車の扱い方。と。
中学生になると、手伝いではなくて、百姓の一人として扱われるようになった。その頃は近所では、働き者の息子として褒められた。田植え、稲刈りも仕事が早いと褒められた。
中学でも、宿題は無く毎日学校から帰ると牛の草刈りがあった。
休日は畑の仕事や田んぼの仕事をした。家でも近所でも学校の成績の話は誰もしていない。周りの同じような家の子どもは学校の話はしなかった。
中学校では、一年の担任は国語の先生、二年で組替えがあり担任は理科と数学の先生。二人とも新制中学になって高校と給料が同じようになったので、中学校へ移った先生だった。
当時一年生には英語があったが、二年生になったら、英語か職業科に分けられた。
農家の長男と高校進学予定の無い者は職業科に分かれ、農業やアメづくりなど教わっていた。自分も職業科を選んでいた。(のちに大学まで英語の試験はなかった。公平を保つためだった?)
高校進学の話が出てきてのは三年生の12月だった。自分では行くなら農業高校だと思っていた。担任は家庭訪問で来て「北高(現在の野沢北高校)へどうか」と話していた。
先生たちの点数稼ぎで何年度は何人普通校に入れたかがあって、確実に合格しそうな自分に勧めていた。
そんな時、畑を借りていた岩井さんの奥さんが年貢を取りに来てお茶を飲みながら高校について話していた。
「兄が農業高校で、夏休みや休日は当番や実習で家の手伝いができない。それに比べて弟は北高で休みは家にいるので手伝いができる」
と言っていた。
その話を聞いて、普通高校への受験を認めた。自分もそう言うことならいいかと考えた。
これが分かれ目になった。家の仕事をさせるために普通校を選んだ父はその通りにした。
北高では農家の後継ぎは誰も居なかった。
部活も出来ず、ただ高校に入れただけ。
父は中学の時より更に農家の人間としていろいろ教え、やらせていた。すべて命令的で自分の考えなどは無視して聞く耳を持たない。
仕事をしながら、農家のこれからを考えていた。
今は家族労働で何とかやっているが、一人が働くだけで生活している勤め人や、商業の人、職人に比べ先が見えない。
父の命令的な所を嫌って、一度は東京のおじさんに手紙を書いて、「東京で働きたい」と。
すぐにおじさんが家に来て、「何事か」と聞きに内山まで汽車で来てくれた。
その日は友達と牧場へ遊びに行っていたのでおじさんと父がどんな話をしたかわからない。家から離れる望みは消えた。
「何とか家の事を考えたら、信大へ行って教員になるしかない」と思った。
父には何のためのテストか言わず、進学適正検査(公立大はこの成績で足切りをする)を上田まで行って受けた。父とはこの頃から何も話はしなくなった。
高校の担任に内申書を書いてもらい受験した。少し高望みをして中学校の国語科を受けたが落ちてしまった。
浪人中は、続きで家の仕事をして、青年団に同級生みんなで入った。自分たちは皆高卒だったが、上の人は中卒だった。
公会堂を自由に使えた(掃除をしていたので)
夜は青年団の者が集まって話をしたりしていた。
学校はもう一度受けようと思ったが、当時は進学塾は東京にしかなかったので、前年と同じ参考書をたまに見ていた。
農閑期には石山の手伝いをしたり、土方のようなこともした。
受かっても不合格でもしょうがないと思ったが、小学校の方を選んだ。
浪人生活が終わり、信大生になった。
この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?
