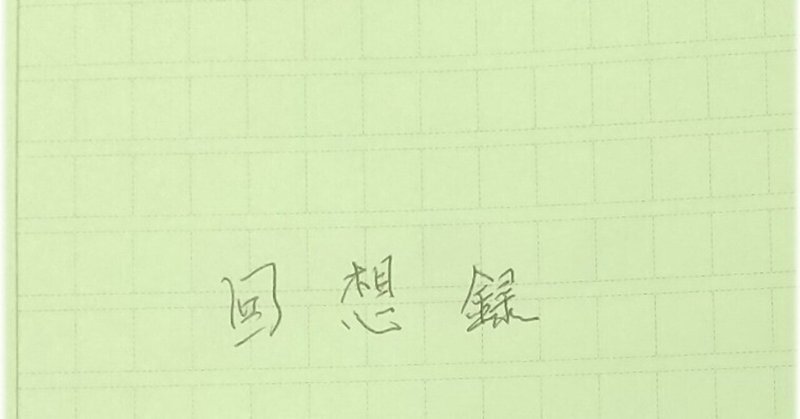
回想録 五 大学生活
回想録 四、中学から高校へ・大学受験(父が戦場から帰って来た)
からの続き
1、宿
初め学生寮に入れなかったので、小諸の竹内健二さんの家に下宿させてもらった。長野までは汽車で通った。大事にしてもらった。
少しして、長野の本郷の家に下宿した。大きな家で、桜井兄妹も下宿(自炊)していた。少し出ると田畑が広がっていた。
思い切り息を吸って、『自由だ』と思った。
田の畔や道端に草が伸びているのを見て、「牛の餌にしたら」と思った。
次の年、学校の近くにあった寮(あけぼの寮)に入った。
県下全方面から来ていて、訛りや方言がひどかった。
2、生活費
寮は三食付きで2500円/月で、繭一貫目(4kg)が3000円くらいの時だったので、家から送ってもらった。
授業料は下宿の学生も免除。それに奨学金が200円で、何とかやっていけた。
家庭教師も3年になってしたが、夏休みは内山の家の手伝いで休んだので、中学の受験生はやめた。小学四年は一年くらい、週に二日、二時間くらいでやった。
食費以外は喫茶店でコーヒー1杯40円くらいで、学生同士で話したり、クラッシックの音楽の好きな学生のリクエストしたのを聴いた。有名な曲はそこで覚えた。
教科の所属は国語で、主任は江戸文学の先生で、映画の解説などもしている先生で、雑談が面白かった。
サークルは松本部校から続いている人たちが中心の「中国文学研究会」で、主として現近代の作家、魯迅の作品で「阿Q正伝」を読んで話し合う会だった。
そんな事で、中国現代史(中文研)も学んだ。4年になったら、サークルの長になっていた。
卒論も中国文学の作品で書いた。東京の神田、内山書店まで行って参考書を買って、それを例文等に入れて書いた。中国語は分からなくても、論文の意味は分かった。
原文をあちこちにいれたので、中国文学の卒論の教授に褒められた。
中文研は左翼的だということで、学生運動の教育学部の会の役員もやらされた。ちょうど、県の財政再建中で教員の採用が厳しくなった。それやこれやで東京へ行ったり、金沢へ行ったりしたがよくわからなかった。東京では富三さんの家(父の弟)に泊めてもらった。
やがて、就職の時が来た。郡単位の採用だったので、組合の先生とも交流があったので、佐久では採用されなかった。
校長職を勇退する代わりに息子が就職したりの時代だったので、一年間浪人生活で、農業をして就職を待った。家の者には迷惑をかけた。当時は就職試験もなく、地域の校長の代表との面接だけで教師に採用された。どういう調査を元にしたのかはわからずだった。
青年団に入り、いろいろ学んだ。一年後の四月の下旬、更級郡の大岡小学校から声がかかって、就職できた。
分校が5つもあるアルプスの見える村だった。大学の同期の者が7割ぐらいで、後は村の出身者や年取った分校主任なので、青年部が中心だった。
その後も佐久へ帰ろうとするごとに、教育会から拒否されたが、中学の時の先生や佐久の同級生の口添えで転任できた。
この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?
