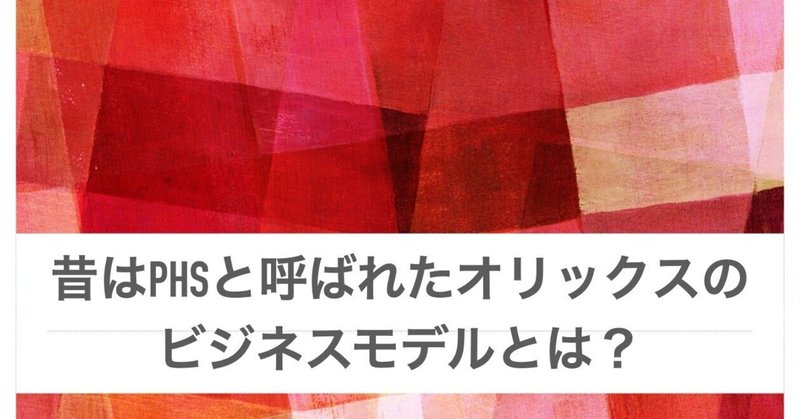
昔はPHSと呼ばれたオリックスのビジネスモデルとは?
こんにちは。ようた@英語コーチ&フィンテック(Fintech)アドバイザー& FP (Financial Planner)です。
私はプロ野球、オリックスバファローズ(バッファローズではない)のファンなのですが、親会社のオリックス株式会社の株主でもあります。
2022年5月11日、オリックスは2022年3月期の決算を発表しました。直近1年間の当期純利益は3121億円と国内企業の中でも大手の一角になっています。(急成長というより安定して成長しているというイメージでしょうか)

この記事では昔PHSとよばれたオリックスのビジネスを紹介しつつ、「結局オリックスってなんの会社なの?」という質問への答えを掘り下げて解説したいと思います。
昔はPHSと呼ばれたビジネスモデル
オリックスは今から60年ほど前の1964年にオリエントリースとして設立されています。商社の日綿(現双日)や三和銀行(現三菱UFJ銀行)など、3商社、5銀行が株主になって設立されたノンバンクです。
ノンバンクとは従来の銀行融資などではない金融サービスを手掛ける金融サービス会社のことです。社名の通り当初は、リースサービスを手掛けていました。通常の融資は、金融機関が借り手にお金を貸して、借り手はそのお金を設備投資などに使うのですが、リースは設備を金融機関が購入して、借り手に貸し、その利用料(リース料)を毎月返済していくことになります。設備には、店舗設備、パソコンやサーバなどのIT設備などが一般的でしたが、(後述しますが)その後オリックスは、不動産、船舶や航空機などにもビジネスモデルを拡大していきます。
ちょっと難しく書きましたが、簡単にいうと「金貸し」です。ただ、お金だけではなく、「もの」の管理のノウハウも必要な「金貸し」でした。特に当時の金融機関があまり取り扱わなかったPHSと呼ばれる業種へのサービスにおいて市場拡大をしていきます。
P=パチンコ
昨今は規制の影響などで市場は縮小していますが、パチンコ市場はそれでも20兆円前後の市場規模を誇る大市場です。パチンコは今でもギャンブルの一形態と考えられていますが、なかなか当時の金融機関では与信(返してくれるかどうかの判断)が難しいものでした。

オリックスは企業の最終的な数字だけではなく、日々のキャッシュフローを徹底的に分析しました。毎日何人のお客さまが来るのか、一人当たりいくらくらい使ってくれるのか、一日の運営で出ていくお金はいくらかなど。今ではAmazonなどのアメリカ企業も含めて、会計上の数字よりもキャッシュフローを重視した経営が大切というのは浸透していますがまさに国内でこれを実践した先駆者がオリックスだったと言えるかもしれません。パチンコはまさに「キャッシュ」が動くビジネスでしたので、入ってくるお金の方が出ていくお金よりも多ければ、お金を貸しても返してもらえると考えることができたのです。またこの店舗の集客はうまくいっている、他の店舗はうまくいっていないなどのノウハウも溜まっていきます。この辺りは、現在のオリックスのホテルや水族館運営、球団(球場運営)、不動産ビジネスなどの目利き力につながっています。
H=ヘルス(ラブホテル)
パチンコと同じくこの業種も従来の金融機関が扱いづらいものでしたが、これもキャッシュフロー重視の考え方が適用できました。1日に何組の客がはいるのか、一組あたりの料金はいくらか、1日にどのくらい回転するのか、これらが分かれば1日あたり手元に残るキャッシュが計算できます。手元に残るお金がわかればいくらなら返すことができるのかなどがある程度計算できるわけです。当時の営業マンなどは、ホテルの受付のおばさんの横に座って、1日の客数、単価などを正確にメモしたというような逸話もあるほどです。こちらも後に不動産オフィスビルの賃貸ビジネス、施設運営ビジネス、不動産売買ビジネスなどにつながっていきます。
S=サラ金
サラリーマン金融とか消費者金融とか言われる業種です。最近はほぼ全ての会社が銀行カードローンに名前を変えて運営されていますが、1980年代、90年代などはプロミス、武富士などをはじめとする百花繚乱のプレーヤーが乱立する市場でした。サラ金などのノンバンクはある意味、「安い金利でお金を仕入れ」、「高い金利で貸す」ビジネスモデルです。オリックスはリースなどで主に企業向けのビジネスをおこなっていましたし、(当時はすでに独立路線をとっていましたが)母体が銀行や商社でしたので高い信用力がありました。一方、サラ金業者は、一般消費者に高く貸すことはできたとしても貸倒れリスク(返してもらえないリスク)も高く、「安定して安くお金を仕入れる」ことが難しい業者もいたそうです。オリックスはここに目をつけ、一部のサラ金業者に対して、「安くはないけど高くもない金利」でお金を貸したのです。
収益還元法による考え方
オリックスの堅実なキャッシュフローの考え方はバブル期においても発揮され、大火傷をせずに済みました。日本のバブル崩壊は不動産市場の急落(および関連する信用収縮)をきっかけに起こったのですが、当時は不動産や株は買えば上がるという状況でした。今日100億円のものが1ヶ月後に150億になっている、だから今日買わなければ損だと。しかしなぜ1ヶ月後に150億になるのでしょうか?もちろん美人投票的な要素などはあるにしろ、不動産、株、会社などが1ヶ月後に50億円増えるには合理的な理由が必要というのが現在のファイナンスの考え方です。現在このファイナンスの考え方の基本になっているのが収益還元法やディスカウントキャッシュフロー(DCF)の考え方です。
収益還元法とは、不動産から将来的に生み出される収益を、現在の価値に割り引いて不動産価格を計算する方法です。不動産価格を算出する方法は複数ありますが、その中でも不動産の収益性に着目した方法といえます。
「不動産から将来的に生み出される収益」というのは将来に渡っての日々の賃料などです。簡単にいうと、ある不動産をみて、まあ悪くても毎月100万円の家賃を貰うことができるよね、管理するための費用は10万円あれば足りるかな、であれば毎月90万円は手元に残るよね、この不動産はあと30年は持つよねと計算します。30年間のキャッシュフローを特定の金利で割り戻した価値がその不動産の現在の価格と考えるのですが、この現在の金額がオリックスが投資できる(融資できる)金額の基準になります。なんかバブルで1ヶ月後に絶対50億増えているからというのは、そうなるかもしれませんが、そうならない可能性もある(そうなると合理的に説明できない)と考えいち早くバブル期の不動産投資から手をひいたそうです。
バブル期の不動産は、ある意味安易なビジネスでした。大きな金額の取引ができて利潤も得やすかった。日本中の金融業がそこに群がっていたと言っていいでしょう。しかしその方の言葉で、物価が上がらないのに株式や不動産などの資産価格だけが上がりつづけるのはおかしいな、という不安が頭をもたげてきたわけです。
バブル崩壊を事前に察知できた「皮膚感覚」
得意な分野から横へ横へ
この収益還元法の説明、上述したパチンコやラブホテルのキャッシュフローの考え方と同じだと思いませんか?オリックスのビジネスモデルは現在は多岐にわたっていてわかりづらい企業の代表になっていますが実は得意な分野からその横へ横へ展開していてきているのです。

オリックスの多くの事業説明の資料でこの1ページがオリックスの事業展開の経緯を最もわかりやすく示しているかと思います。
リースは、ものの価値を理解した上で、借り手の信用を測ります。仮に借り手の返済が滞った場合、オリックスはその「もの」の所有者として売却先や次の借り手を探さなければいけません。上の図の下半分はそのような流れで事業展開してきたと考えられます。店舗設備やパチンコ台に関するノウハウを積み、それが自動車、船舶、航空機と横展開されます。これらは「動産」と呼ばれるものですが、「不動産」と呼ばれる土地や建物にもこられのノウハウは生かされます。オリックスは今では、マンション分譲、不動産開発、オフィスビル開発、オフィスビル賃貸、ホテル旅館運営、球場運営、水族館(すみだ水族館、京都水族館)運営までしているのです。
環境エネルギーというのは、再生可能エネルギー系のビジネスです。これもどの土地で行うのか、どのように行うのか、どのような設備(もの)を導入するのかのノウハウが必要になります。
コンセッション事業は運営事業の延長ですが、主に自治体などからの委託を受けて行う運営事業です。自治体の水道事業や関西国際空港を含む近畿圏の空港運営などがこちらに当てはまります。
海外ビジネス割合も32%

直近の決算では海外からの収益貢献は32%もあります。決算説明会では、最近の円安の影響により、海外資産における含み益も積み上がっているとのコメントもありました。こちらでも安定した事業ポートフォリオを構築していることが見て取れます。(ただ、10個もセグメントがあること、それも国内、海外で網の目のように入り組んでいるので、やはり一般の投資家にはわかりづらいビジネスモデルともいえます)
株主優待を廃止
オリックスの個人株主数は75万人を超え、東証の中でも3番目に個人株主が多い銘柄のようです。株主優待や配当も充実しており、およそ4000円相当の贈答品が贈られるふるさと優待をはじめ野球、ホテル、レンタカーなどの各種優待が受けられました。2022年5月、オリックスは2024年3月末でこれらの優待を廃止すると発表しました。

一方で、2025年3月期の目標として、純利益4400億円と継続した配当と自己株買い(2022年は500億円)を示唆しています。

まとめ
オリックスのビジネスモデルの過去からの変遷とその強さの背景をまとめて見ました。現在のオリックスの株価はPBR1倍以下で取引されています。この背景には、事業が多角化し過ぎていてわかりづらい(一般的にいう)コングロマリットディスカウントや成長しているものの市場環境の影響を受けやすいという点、成長スピードがIT系などの会社に比べると小さいという点などがあるかと思います。とはいうものの、オリックスという企業は国内では珍しく継続して付加価値を生み出している企業だと思いますし、引き続き注目していきたいと思います。バファローズもがんばれ!全員でWおう!
よろしければこちらの記事もご覧ください。
よろしければお気持ちだけでもサポートいただけると記事作成の励みになります。 You can support me and my articles by tipping from here. I really appreciate your support.
