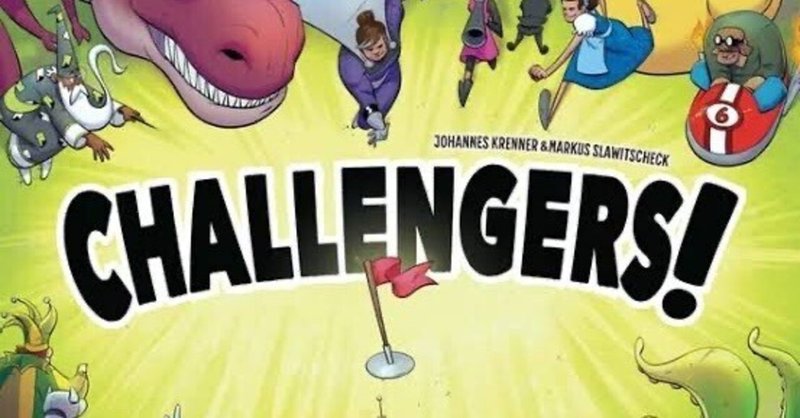
いざ、デッキ構築の新時代へ! Challengers!ショートレビュー 10点/10点
https://twitter.com/uchibacoya/status/1631180743740362752?s=46&t=o9J7embS_8uaaHZhiN8gag
チャレンジャーズ!、3人以上で遊ぶなら8人までダウンタイム変わらず何人でも遊べるゲーム。めちゃめちゃ良かった〜!
— uchibacoya (@uchibacoya) March 2, 2023
デッキに数枚カードを加え、好きなだけ圧縮してから坊主めくりで対戦。勝ったら名声点がもらえる。
デッキの枚数は増やしたいけどデッキの構成種類数は減らしたいという pic.twitter.com/3GZWK1vvXq
3月に、ケンビルさんの丸田さんとぬんさんに誘われて、Challengers!というゲームをプレイした。
アートが好きじゃないなあと思いながらプレイしたが、これが非常に素晴らしいゲームだった。
それ以降もBGAで複数回に渡って、様々な人数でプレイした。
アートを理由に避けたり、埋もれて欲しくないと強く思ったため、記事化することにした。
この記事では、ゲームデベロッパーとしての視点からこのゲームを構造的に読み解いていく。
読者として、ある程度の経験や知識のあるボードゲームデザイナー、ユーロゲーム文脈のファンを想定している。
尚、筆者はTCGは一通り触れてはいるものの、嗜む程度しかプレイしないボードゲーム畑の人間であり、TCGに関する記述には誤りがある可能性がある。
また、特にゲームの文脈に関する記述は独自解釈している部分が多々あり、実際の流れと多少異なる場合がある。当記事は、筆者の独断と偏見によって書かれていることはあらかじめご了承願いたい。
1.明確なコンセプトとその徹底

複数人が参加する物作りの現場では、コンセプトと呼ばれるものの設計が非常に大切だ。
コンセプトとは、耳慣れた言葉だが理解しづらいかもしれない。簡単に言えば「制作チームを導く北極星」だ。
何か判断に迷った時に、常にコンセプトに従って判断が下される。
任天堂さんのWiiというゲーム機があるが、この例がコンセプトの理解を最も助けてくれる。
まず背景から話すと、任天堂はゲーム人口の拡大を目指してハード開発を行っていた。
それでリリースされたハードがNintendo DSだ。
Nintendo DSが普及していく中で、最も障壁となったのは、親からのゲームに対する拒否反応だった。
「ゲームばっかりせずに勉強しなさい!」と言われたことがある方も多いのではないだろうか。
今でこそマシになったものの、当時、親世代のゲームに対する拒否感は相当なものだった。
そこで登場したハードがWiiだ。
Wiiは、ゲーム人口を拡大するために、親世代を攻略することにした。
Wiiのコンセプトは「母親が嫌じゃないゲーム機」だ。
Wiiは、そのコンセプトに従って他の家電と同じように白を基調したデザインになった。これならば、リビングに置いてあっても目立たない。
また、実際に体を動かすWii Fitなど、「ゲームは不健康なもの」というバイアスを破壊するためのゲームがリリースされた。
色を決める時、リリースするゲームを決める時、毎回コンセプトに立ち戻って判断が下されている。このようにすることで、最初に設定した目標(=親世代を攻略し、ゲーム人口を拡大する)を達成しやすくなる。
これがコンセプトだ。

チャレンジャーズは「TCGの大会をメタ的に再現する」という明確なコンセプトを持って、頑なにそれを守っている。
例えば、このゲームの対戦はほぼ自動で坊主めくりを行っていく。
人によってはここが味気ないと感じることもあるだろう。
しかし、このゲームのコンセプトはTCGを再現することではなく、TCGの大会を再現することだ。
このコンセプト下において、個々の勝負の展開は重要ではなく、
・誰が勝ったか
・決勝戦は誰と誰が戦うか
・先手をコイントスで決める
・戦う前に挨拶して、終わったら対ありを言う
・お互いのデッキについて感想戦をする
・サイドボードでカードを入れ替える
・現環境のカードプールを把握する
といったゲーム大会全体の体験自体が重要だ。
だから、このゲームではわざと対戦を簡略化している。
断言するが、チャレンジャーズほどのゲームを作れる開発チームならば、もっと面白く戦略的な対戦のルールを作ることができるはずだ。
だが、対戦のウェイトが重くなるとこのゲームは凡百なゲームとして埋もれていただろう。
戦略的な対戦ゲームは世界にいくらでもあり、このゲームが面白く戦略的な対戦を備えている必要はない。多数のゲームが存在する市場において、プレイヤーは自分に合ったゲームを選択できる。「あらゆるものに迎合する」ことは、多くの場合正しくない。
目標達成のために的確な判断を下せる、非常に良いチームがこのゲームを作っていることが伺い知れ、1ゲーマーとして本当に嬉しく感じる。
2023.9.24追記:公式からリリースされたデザイナーズダイアリー( https://boardgamegeek.com/blogpost/152306/designer-diary-challengers )を読みましたが、コンセプトや「カードゲーム大会を再現する」という記述はなく、当記事末尾にある通り、Dota:Autochessなどの自動対戦ゲームを構造的に再現しているのがメインコンセプトであるようです。上杉カレーさんの指摘に感謝します。
よって、上記記事内容は一部正確ではありません。
不正確な文章を書いたことをお詫びいたします。
ただ、この文章には制作上強い意義があると考えているため、削除せず残すこととします。
2.デッキ構築の文脈上の立ち位置

Magic the Gatheringには、リミテッド戦と呼ばれる遊び方がある。
一般的なTCGは、構築されたデッキを使って対戦を行う。
リミテッド戦はこれと異なり、デッキ構築フェイズと対戦フェイズで構成されるゲームをプレイする。
デッキ構築フェイズでは、ドラフトやシールドといった方法で不自由な中カードを獲得し、集めたカードでデッキを作る。
その後対戦フェイズでは、作ったデッキで対戦を行う。
この文脈上で、もっと構築をメタ的に捉え、ボードゲームに落とし込んだ傑作が「ドミニオン」だ。
ドミニオンは、リミテッド戦の対戦フェイズをデッキ構築フェイズに統合して、デッキ構築というジャンルを作り出した。(7wondersなどもリミテッド戦派生だが、これについて話すと無限に記事が伸びてしまうので記載を避ける。)
デッキ構築は、入力と出力が内包されているという強固すぎる構造により、フォロー作を作ることが容易で、多数のフォロー作品が出版された。
あまりに美しいこのシステムは、誰が作ってもそれなりの出来になる。

こうして一大ジャンルとなったデッキ構築だが、強固すぎる構造は、当然似たプレイ感を生み出してしまう。
似たプレイ感は独自性を薄めてしまうので、色々なゲームで様々な対策が取られてきた。
ハートオブクラウン(国産の傑作デッキ構築)など、UIの革命やルールのバリエーション化を行ったり、Dune InperiumやLost ruins of Arnak、クランク!シリーズ、Slay the Spireなど、別の出力メカニクスと組み合わせて独自性を持たせる方向に進化が進んでいる。
しかし「同じデッキを何度もシャッフルしながら使い回す」という性質により、あらゆるデッキ構築ゲームでは圧縮する(=デッキのカードを取り除き、強いカードの使用回数を増やす)というプレイが基本的に強い。
強いから、どのゲームでも行われて、大体同じプレイ感を味わうことになる。
圧縮、ほとんど全部のゲームで結局やるじゃん?問題に対しては「クアックサルバー」「リビングフォレスト」「テイフェンタールの酒場」などが面白い解決を図っている。

プッシュユアラックのバーストゲームにすることで、弱いカードを引くことが邪魔にならず、弱いカードがデッキに入っている事のデメリット自体を無くしてしまったのだ。
これは一定成功していると思うが、長時間ゲームとバーストゲームは相性が悪く、色々なゲームで使える進化系統ではない。
バーストのデメリットを重くしすぎると、バーストしたプレイヤーは長時間勝負に絡めずつまらない時間を過ごすことになるし、軽くしすぎるとバーストを恐れなくなってしまう。
何より運要素が強く「最終ラウンドに最初に引いた3枚でバーストした」みたいな状況が起こったらゲーム体験は最悪になってしまう。
いずれも本当に優れたゲームではあるものの、この性質により傑作には至らなかった。
そこに彗星の如く登場したのが「Challengers!」だ。
チャレンジャーズは、
「デッキ枚数はHPなので多い方が良い。」
「デッキ内のカード種類数は少ない方がいい。」
という絶妙に背反する二つのルールにより、圧縮にメリットデメリットの両者を持たせた。
その上で、プレイヤーは特に何の制限も支払いもなく、自由に圧縮していいというルールを採用している。
個人的な感覚でしかないが、この絶妙に背反するルールによりプレイヤーの創意工夫を生み出すシステムは、テラミスティカにおける
「建物は繋がっていた方が良い」
「建物は細切れでブロックを作ると良い」
というロンゲストと都市化の関係に似ている。

デッキ構築の文脈上に現れた、新しい素晴らしい発明だと考える。
3.キューブドラフト的カードプール
先ほど対戦は坊主めくりで進む、味気ないと書いたが、このゲームはその制限下で最大限面白くなるようにカード自体もデザインされている。
対戦自体はシンプルではあるものの、しっかりと楽しめる。
テラフォーミングマーズ、エバーデール、ウィングスパンなど、大量のカードプールを持つボードゲームは、MTGのリミテッド戦におけるキューブドラフトというフォーマットに少し似ている。
MTGのキューブはキューブ作成者がアーキタイプやシナジーについて理解しているが、ボードゲームの場合、キューブ作成者はゲームデザイナーだ。
プレイヤーは複数回同じキューブ(カードを積み重ねて立方体のようにしたもの)で遊ぶことで、同卓者全員で何が強いのかを読み解いていく。
チャレンジャーズは、エバーデール系統のハイランダー(デッキ内に同じカードが含まれない)でないキューブを持っている。
また、各カードにアイコンを付けることで、シナジーをわかりやすく提示している。
「初めてのプレイヤーは、大体同じ色だけあつめておけばOK。同じカードもデメリットないので取り得。(分かりやすい当たりカードの提示)」
「慣れてきたらカードプール内で組み合わせた方が強いよ」
というゲーム構造だ。
モンスターハンターにおける一式装備とキメラ装備の関係を思わせる、初心者にも熟練者にも優しい実装だ。
そういったキューブの読み解きと奥深さ、初プレイヤーへの優しさ、みんなで読み解く一体感を全て備えており、見事な設計と言わざるを得ない。
また、チャレンジャーズのキューブはいくつかのデッキの集合体でできている。
コンテンツの拡張性というプロダクト面でみても素晴らしい。
今度出版されるChallengers2とも混ぜて遊べるのではないだろうか。
キューブが変われば、今までの正解は正解ではなくなっていく。
ゲーム内のカードを全て把握して、今回出てくるカードはあれとあれだから…とコンボを考える。
そういった楽しさも内包している。
4.論理的勝利と感情的勝利を分ける
このゲームの優れた点として、ゲームの終了時までワンチャン勝てるんじゃないかと思える点がある。
7ラウンドプレイした後、獲得した勝利点を比較し、上位2名で決勝戦を行い勝った方がゲームに勝利するという構造だ。
実質的に、獲得した勝利点を比較した際に勝者を決めても何の問題もない。僕はこれを論理的勝利と呼んでいる。
対して、2位を獲得したプレイヤーは、もしかしたら決勝戦で勝てるかもしれない。これで勝ったら一発逆転、優勝だ。
僕はこれを感情的勝利と呼んでいる。
論理的勝者が決まった時点で、ゲームの上手さは確定している。
感情的勝利は、勝利点を持っているプレイヤーが確率的に優位であり、もし逆転したとしても確率的に上振れを引いただけ。本質的には何の意味もない勝利である。
チャレンジャーズは、意図的に感情的勝利を設けている。これがあれば、一位のプレイヤーが確定しても、二位を目指してプレイすることが勝利につながるようになる。
誰かが圧倒的に走ってしまっても、全員の集中力が途切れづらい。

当たりを持っているか確認する。
これはゴールデンチケットなど別のゲームでも「集めたチョコレートを開封し、当たりが入っていたら勝ち」というルールで採用されている。
チョコレート(勝利点)を集めた数で勝者を決めても良いが「当たりを引いたら勝ち」とすることで、最後までチョコレートを集める意味がある。
最後の一つが当たりかもしれないのだから。
重量級ゲームではこの実装は好まれないと思うが、論理的勝利と感情的勝利を分けた点も、ラフに遊ぶゲームとして優れた点であると評価する。
終わりに
チャレンジャーズ、褒めちぎりまくってしまったが、いくつか悪い点も挙げておこう。
まず、あまりアートが好きではない。
ただ、この気の抜けたコミカルなアート以外であれば、対戦の坊主めくりのラフなコミカル感とアートでアンマッチになってしまうと思う。
アートを良くするのが正解かは微妙なところだ。
また、運要素が大きいため、麻雀やポーカーに近い「複数回やって勝率が何%か?」で上手さを測るタイプのゲームだ。
勝利というものに対しての考え方がモダンなユーロゲームの文脈と離れているので、苦手な人はいるかもしれない。
また、TCGの大会というもの自体がハイコンテクストなので、TCGに馴染みがない人が感じられる楽しさは一段落ちるかもしれない。
悪い点はそれくらいだ。
3人くらいで遊んでも楽しいし、8人くらいで遊んでも楽しく遊べる。
オープン会/クローズ会問わず、あらゆる場面で活躍できる極めて優秀なゲームであると評価する。
BGAでプレイできるので、3-4回繰り返してプレイしてみることをオススメする。
(追記)
当記事を書くにあたって、上杉カレーさん、ナオプーナさん、実兄など、TCGやデジタルゲームに詳しい知り合いにも内容を確認していただいた。
また、Takewatchさん、戸塚中央さんに記事内容を確認していただいた。協力に心より感謝する。
その中で、ハースストーンのバトルグラウンドや、オートチェスの自動戦闘にルーツがあるのではないかとの指摘を受けた。
筆者はデジタルゲームをあまり遊ばないため、その可能性には思い至らなかったが、実際に動画等でみてみるとこの指摘は正しいのではないかと感じた。
今後は、デジタルゲームなど、近接する他ジャンルも積極的に学習に取り入れながら、多面的にゲームというものを紐解けるようにしたい。
※筆者はChallengers!に対して一切の利害関係がない。
この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?
