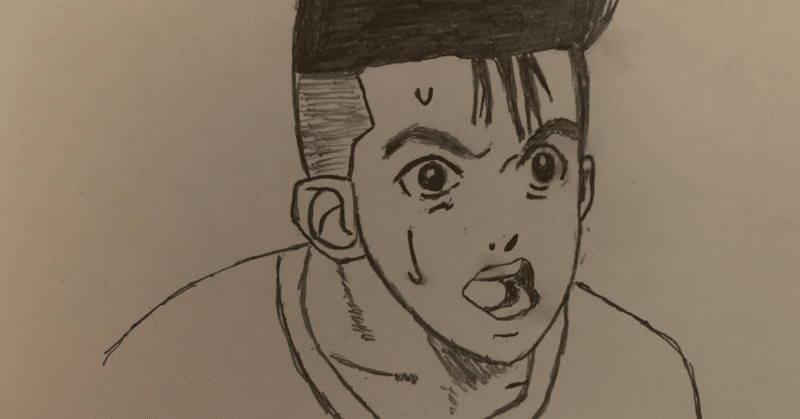
2022年3月24日:好きなバスケットのこと
画像は、とても魅力的な彦一の絵です。どうもありがとう。
バスケットの勉強がしたい
もっとバスケットの勉強がしたい。
コーチとしての勉強がしたい。
勉強をするだけではなくて、結果を出せるようになりたい。
好きなバスケット
どんなバスケットが好きなんだろう。
バスケットの100点を目指したい。
完成形などないのは知っているけれど、限りなく100点に近づきたい。
普遍的なものだけを極めた、そういうバスケットをやりたい。
真理に近づきたい。
原理と、そこからわかること
真理、普遍的なもの、原理。
私がバスケットにおいて考えているそれらはなんだろうか。
「そうなっているもの」
「変わらないもの(ルール変更等が無い限り)」
リングの大きさ、高さ。
コートの広さ、ペイントエリア、3Pライン、1.5倍の得点。得点期待値。1人が守れる範囲。
トラベリングのルール。時間制約系のルール(24秒、3秒、8秒、5秒)
リングの大きさと高さから、シュートの3原則が導かれる。
トラベリングから、ドリブルか。まあでもこれは、そこまで重要じゃないよな。
得点期待値から、シュートの優先順位と、ペイントアタックの重要さが導かれる。
1人が守れる範囲から、スペースは可能な限り広く使った方がいい、と分かる。
可能な限り広く使うには、シュートレンジとパスレンジが重要になる。それら2つが、使えるスペースの広さをに対する制約条件となる。
個人戦術:OF,DFの2人だけで考える
個人戦術は、シュートorドライブの読み合い。
シュートラインが空いているのか、ドライブライン(=インライン)が空いているのか。
シュートラインの定義
シュートラインの定義は、リングと目線を結んだ線。これにDFの手があったら、シュートラインは空いていない。手が無いなら、シュートラインは空いている。
ドライブラインの定義
ドライブライン、いや、インラインと呼ぼう。いや、どっちでもいいや。
インラインは、ボールとリングを結んだ線。ここにDFの胸があれば、インラインは空いていない。胸がないなら、インラインは空いている。
どっちも空いてるなら
インラインもシュートラインも空いている状況=シュートもドライブもできる状況なら、ドライブを優先する。
ゴールへアタックすることの方が、周囲のDF、や次のチャンスの発生など、波及効果が大きいと考えるからだ。
個人戦術の目標
個人戦術においては、シュートラインを空けること+ドライブラインを空けること、を目標に置いてプレーする。
もちろんこの先には、得点を取ること+味方の得点を演出すること、がもっと大事な目標になるが、それはまあ、自明ということでいったん考えないでおく。
シュートラインを空けるためには、相手の手を下げさせる必要がある。
ドライブを狙う姿勢が、DFの手を下げさせる。
だから、最初にシュートラインの状況を見て、シュートをしないと判断したら、まずはドライブを考えればいい。
ドライブは、ドライブラインを作って、攻める。
ボールの移動+自分の移動によって、ドライブラインを作る。
だから、スキルとして扱うのは、この2つのどちらか、あるいは両方を達成できるものにする。
DFの重心移動や、タイミングのズレなどを狙ったスキルも確かにあるけど、ボールが相手の真正面(インライン上にDFの胸)にある状態では抜けない。
重心移動やタイミングのズレを作るスキルは、別途取り上げてみようかと思うけど、これも一旦保留。
いったんまとめ①
ここまでをまとめると、
個人戦術の攻防は、「シュートライン」と「インライン」の攻防。
OFが自分でこれを作れないのなら、パスをするしかない。
DFは、パスは一旦置いておいて、これを止められるようにプレーする。
個人の戦いで、OFが勝ったら
個人戦術の戦いで、OFが勝ったとする。
シュートで勝ったら、リバウンドの局面に行くので、一旦保留。
ドライブで勝ったとする。
ドライブでシュートまでいく前に、インラインをおさえられたら、エリア2の攻防になる。
ストップスキルや、切り返しが必要になる。あるいは反転してポストアップという流れにもなる。
DF側は、一度インラインが空いて、攻められても、それを取り返せるようなDFスキル(フットワーク、ボディコンタクト)を磨く必要がある。ラングライドとか呼ばれるやつはそれにあたる。ここも一旦保留。
インラインを完全に抑えきれずに、ペイントエリアへの侵入を許したら、すごく単純化すると、レイアップに行かれる。そこを止めるには、DFの集団戦術が必要になる。一旦保留。
DFは可能な限りヘルプDFを必要とせずに、DFの個人技術の向上によって、OFを守れるようにしたい。
個人戦術の戦いで、OFが勝てない=DFが勝ったら、味方の助けを借りる必要がある。OFの集団戦術が必要だ。
最初はパス。パスして、他の人の個人戦術の攻防に託す。
他には、自分自身の個人戦術を、他の人に助けてもらうプレーもある。スクリーンの活用だ。
個人戦術の戦いを、戦う前に助けてもらうのがオフボールスクリーンで、戦いの最中に助けてもらうのがオンボールスクリーンだ。
これもOFの集団戦術になる。
閑話休題:グループ戦術、チーム戦術、集団戦術
集団戦術を、グループ戦術とチーム戦術に分けて考える人もいるけど、
私の中で定義が曖昧だから、ひとまず集団戦術とする。書いていく中で、グループ戦術とチーム戦術に分けられるかもしれない。これも一旦保留。
またここまでの整理をする。
保留事項
シュートを打たれた後の、リバウンド局面の攻防
DFの重心移動、タイミングのズレを狙ったOFの個人スキル
インラインへの復帰のために必要なDFの個人スキル
インラインへの復帰が出来ず、味方の助けを借りる、DFの集団戦術
OFが個人戦術の攻防で勝てないときに、味方に助けを借りる、OFの集団戦術(パスして他の個人戦術攻防へ移行、オンボールスクリーンで個人戦術を助けてもらう。貰う前の個人戦術の補助であるオフボールスクリーン)
シュートの邪魔をする:ヘルプDFの発生
シュートラインorインラインの攻防
↓
OFはインラインをアタック。DFが止められずに、レイアップの危険が生まれた。
↓
DF側は、レイアップを止めないといけない。
ヘルプDFが必要になる。
シュートの邪魔をする。侵入の邪魔をする。
DFの目標は、シュートが外れて、リバウンドを確保することだとする。
TOも勿論いいし、シャットアウトするような激しDFも良いけど、ひとまずそれらをOFが打ち破るという前提で考えていく。
シュートの邪魔をする
シュートの邪魔をするためには、心理的なプレッシャーをかける。
シュートに集中させないようにする。
ボールとゴールの間に障害を作り、シュートの軌道を難しいものにする。
ハンドワークによるプレッシャー。
(下ならスティール、上ならブロック、上下関係なく触れたらディフレクション)
バーティカルジャンプ(名称は不明。ビラノバ大がよくやるやつ)によるプレッシャー。
ヘルプに来るのか来ないのかの駆け引きによって、迷いを生じさせることもできる。まあこれは、OFのレベルが上がるほど、あんまり意味なくなってくるので、ヘルプに行った方がいいな。
OFは何を考えるか
OF側は、ここでも同じことを考える。
ボールとゴールの間にDFの胸があるか。このときのDFはヘルプDFとする。
あるなら、パスだ。ヘルプDFが本来マッチアップしている味方への、アシストパス。ないなら、シュート。中途半端なら、フェイクで様子を見る。
パスフェイクからのシュート、パス。
シュートフェイクからのパス、シュート。
インラインの読み合いで、プレーが決まる。
シュートはシュートで、リバウンドの攻防に行くので、後ほど。
パスが出されたら
パスをしたときの展開を考えていく。パスをした場合、DFが取りうる行為は2つ。
ヘルプDFが自分のマークマンに戻ってくる。クローズアウト状況。
他の選手がローテーションを起こし、守りに来る、ローテーション状況。
ローテーションにも、少なくとも2種類あって
3人以上が絡むローテーションと、2人で完結するローテーションがある。
パスした選手のマークマンが、パス先の選手にローテーションするパターンが、「2人完結」のローテーション。
そうじゃない3人目の選手が絡むのが、「3人以上絡む」ローテーション。
ローテーション無し=ヘルプDF自身がクローズアウト
2人完結のローテーション
の2パターンの場合は、カウンター1on1を狙う。クローズアウトに対して、1on1をする。
3人以上のローテーションの場合は、エクストラパスを選択肢に入れる。
よりオープンな選手がいるはずだからだ。
ただもちろん、時間にもよる。OF側は24秒ルールの制約があるからだ。
DF側は、クローズアウトやローテーションを駆使して、OFにシュートラインorドライブラインの選択を難しくさせる。選ばせない。取れなくても、時間が味方になってくれる。
そのためOFは、短い時間で、DFが妨害してくるシュートラインorドライブラインの邪魔を突破し、得点に結び付けたい。
大切なのは、当たり前だけど個人戦術での突破と、ヘルプDFへの対処という意味での、OFの集団戦術だ。
OF側のヘルプDFへの対処
盤面的対処:スペーシング
ヘルプDFへの対処をするには、いくつか重要なことがある。
1つは、盤面的な対処。スペーシングだ。
まずは距離感。1人で2人を守れない距離で、OFを配置する必要がある。
クローズアウトをより長く=1人で対応しきれないようにするための、ゴールとの距離も大切だ。
3Pをラインを一つの基準とすることが多い。そのくらいは距離を取って、DFの回復を妨害する。
判断負荷を強いる対処:ポジションチェンジ他
次に、複数の判断を要求することで、良い判断をさせないという対処。判断面での対処。
これは、ポジションへのステイに対して、DFが予測し、ローテーションやクローズアウト、パスへの妨害を行えるレベルになると、OF側は次の一手として必要になる対処だ。
よくあるのは、オフボールマンでスクリーンを掛け合う(ダウン、フレア)、スクリーンを使わずとも行うポジションチェンジ。
私はここで、ポジションチェンジを基本としたい。
ヘルプDFは、ボールサイドに寄っているという前提に立つと、スクリーンをしにOFがDFに近づく行為は、ゴール周辺のスペースを潰してしまう。
また、スクリーナーがボールから視線を一瞬でも失うことによって、2つあるアシストパスの出先が、1つ失われてしまうことも考えられる。
だから、基本はポジションチェンジ。2人ともパスをもらえるように。
スクリーンは、特定の選手にチャンスを作りたいときに使う。
シューターに対してフレア( ハンマー)みたいな感じ。
ドライブへの合わせで、ダウンスクリーンは、私はあまりないかな~と考えるけど、そこまで深く考えていないから、保留。
まとめ②
ここまでをまとめると
個人戦術での攻防(シュートライン、ドライブラインの攻防)
↓
ヘルプDFを使って、ボールマンのシュートorドライブを邪魔する
↓
vsヘルプDFに対する、パスorシュートの攻防
↓
パスに対する、DF側の対応(クローズアウト、ローテーション)
↓
ヘルプDFを難しくさせるOFの攻防(ポジションチェンジ、オフボールスクリーンなど)
基本的にはこの流れになる。
止められた後も、次なる個人戦術での攻防をOFは開始するだけだ。時間の制約も考慮に入れながら。
あとは、アドバンテージゲームへ突入する。
これについてはまたいつか…。
ドライブの合わせ(ドライブリアクション)についての原則と、パスした後のドライバーの原則。まあ、サークルルールとリロケイトなんだけども。
これやっとけば、スペーシングは整い続けて、ドライブ&キックの連続になる。
設けるべきチーム原則を違う切り口で
これについて違う切り口で考えてみる。
ボールが動くアクションは、パスorドリブルorシュートしかない。
シュートが起きたらリバウンドだ。
パスが起きたら...?
ドリブルが起きたら...?
この2つに対して、チームとしては、どんな狙いを持って、何を方針とするのか。
この2つについて、チーム原則を定めておく必要がある。
パスした後のチーム原則
よくあるのは、パス&カット。カットしたら逆サイドの行きましょう。
リロケイトも、これに則るよね。パスしたら、逆サイドに行きましょう。
ただ、サグDFに対しては、パスしたらブラースクリーンをしながらカットしましょうでもいいかもしれないし
ポストアップしたいチームなら、カットの後に、インサイドでシールしてもいいかもしれない。
オフボールスクリーンを好むチームなら、パスした後はオフボールのスクリーン(アウェイスクリーン)をしてもいいだろう。
まあそんな感じで、パスした後の動きについて、チーム原則は狙いによって、幅を持たせられると思う。
ドリブルが起きた後のチーム原則
ドリブルが起きたら、基本的にはサークルルールだ重要になるのは間違いない。
1人で2人を守れない距離を、OF側は作り続ける必要があるからだ。
ただ、サグDFに対しては、違う考え方があってもいいのでは、と最近感じるようになった。ユーロカットだ。
ただ、ユーロカットも、ドリブルに対してアウェイ(離れる動き)が出来ないときに、使う方が良い気がするな。
すでにコーナーにいる状況でのユーロカット
コーナー・ウイングに人がいる状況での、ウイングの選手のユーロカット。
この辺はDDMのドライブリアクションが参考になるが、まあこれもいつかまた。
疲れたので終わりの一言
書きすぎて疲れたので終わり。
私のバスケットは100点に近づいているのだろうか。
マッチアップを見極めて攻める、みたいなところは、私はまだ苦手にしているので、それはこれから考えていこう。
この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?
