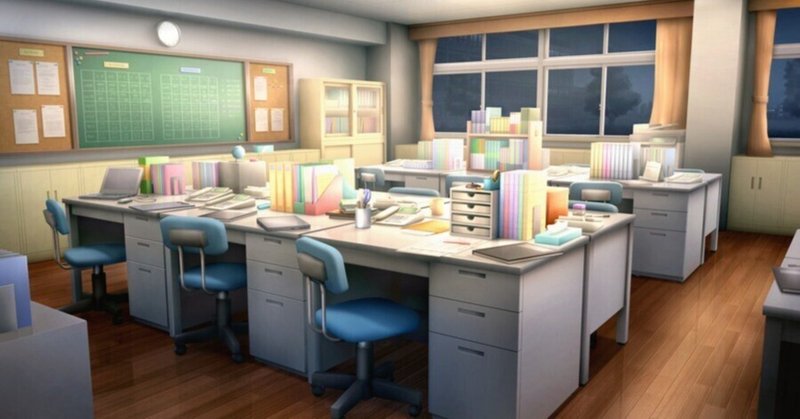
今の校務支援システムやめて新しいのができるの?
もう以前の記事書いてから10か月ぐらい経ってしまっています…。
去年9月からデジタル庁に勤めるようになり、その立ち位置もあって投稿を控えるようになっていました。
そんな中、昨晩以下のような報道が。
この報道を受けて
「国が新しい校務支援システムをつくるのか」「導入したばっかなのに変更するのなら早く言ってよ」「また設定が大変だ」「民業圧迫じゃないのか」
などなどのコメントが。
どうも報道に対する受け取りに誤解がありそう(というより誤解を生む報道内容になっていそう)なので、自分理解の解説をしたほうが良さそうかな、と思ったので久々に書いてみることにしました。
ちなみにデジタル庁の勤務について、NTT Comからの出向(NTT Comから派遣されている)と思っている方が多っかたのです。が、実態はダブルワークでして、NTT Comに雇用されつつ、デジタル庁にも雇用されています。なので、2つの仕事(厳密には起業している会社もあるので3つ)をやらないといけず、時間の制約が辛いことになっています。
なので、今回の記事は1時間一本勝負で書きます!子どもの頃からゲームも縛りプレイで長く楽しむタイプなので、この方が効率あがるはず!(エビデンスなし)
報道内容の要約
今回の報道内容を要約すると、
職員室からしか利用できず不便。なので、どこからでも安全に利用できるようにしよう。
教育委員会ごとに仕様がバラバラで転校や進学で引継ぎができない。なので、仕様を統一して引き継げるようにしよう。
GIGAで学習データが蓄積されつつあるが連携できない。なので、連携できるようにしよう。
上記を「新たな校務支援システム」と定義し、2023年度はモデル事業を行い、2030年までに全国で導入を目指そう。
とのこと。
問題は「全国で導入」の主語が誰か、です。
新しいシステムを国が統一的につくる、は誤解(のはず)
この報道で誤解を産んでいそうな箇所は
文科省はクラウドで情報を管理する新たな校務支援システムを全国で構築することを目指す。
の部分でしょうか。
この文章だと「新たな校務支援システム」を構築するのは文科省、という風に読めます。
確かに国が校務支援システムを開発し、自治体に提供するのであれば大転換です。その割には「来年度モデル事業を行う」とあります。モデル事業って「モデルケースを作って横に広める」のパターンなので、国主体ではなく自治体(学校設置者)主体のパターンのときです。
校務支援システムの導入は地方財政措置の一部にもなっています。あくまで整備主体は自治体(学校設置者)のままのはずです。
なので、この部分をミスリードしないように書くのであれば
文科省はクラウドで情報を管理する新たな校務支援システムの開発を促進し、
を全国で各自治体によって構築するされることを目指す。
って感じなのだと思います。
開発するのは民間、導入するのは各自治体、ということかと。
今回の報道は専門家会議の要約(のはず)
報道を読んでみると、GIGAスクール構想の下での校務の情報化の在り方に関する専門家会議における議論内容の要約であり、その議論内容を踏まえた令和5年度概算要求を踏まえた内容となっていることが分かります。
直近では8月26日に会議が行われておりおり、審議の経過と中間まとめが共有されています。
中間まとめを見ていただくと、今後の方向性が分かります。

具体的な課題と改善の方向性として書かれている10項目は以下です。
汎用クラウドツールと統合型校務支援システムの一部機能との整理
自宅や出張先での校務処理ができず、ワークライフバランスの改善が困難
教育委員会ごとにシステムが大きく異なり、人事異動の際の負担が大きい
校務支援システムの導入コストが高く小規模な自治体の教育委員会で導入が進んでいない
学習系データと校務系データとの連携が困難
教育行政系・福祉系データ等との連携が前提となっていない
帳票類の標準化が道半ば
校務支援システムが災害対策が不十分な自前サーバーに設置されており、大規模災害により業務の継続性が損なわれる危険性が高い
ほとんどの自治体で学校データを教育行政向けに可視化するインターフェイスがない
上記を踏まえた方向性
アクセス制御による対策を講じた上での、校務系・学習系ネットワークの統合
汎用クラウドツールで対応できない、真に必要な機能に絞った上での校務支援システムのクラウド化
校務の県域レベル・全国レベルでの標準化を進めること
読んでいただけると分かると思いますが、私の方で記載した報道の箇条書きとほぼ同じ内容であることが分かります(上記に令和5年度のモデル事業のことが付け加わっただけ)。
校務支援システムはゼロトラスト化と連携仕様統一の流れ
基本的に国の政策は、外部環境の急激な変化に伴う政治決定(ex. コロナ禍の対策など)を除くと、上記のような有識者会議によって決まっていきます。
そのなかで「校務支援システムは国が担うべき」のような議論はなされていません。
なので、校務支援システムの開発・構築の主語が国になることはまず無く、報道の伝え方で一部ミスリードを産んだのでは、と考えることができます。
※国の見解ではなくあくまで私個人の解説であることはご容赦を
一方で「新たな校務支援システム」を2030年までに導入する、という方針にはそのままです。
新たな校務支援システムとは、要約すると
ゼロトラスト化(アクセス制御による対策を講じた上での、校務系・学習系ネットワークの統合)
連携仕様の標準化(校務の県域レベル・全国レベルでの標準化を進めること)
の2つが主になると考えられます。
校務支援システムを提供する事業者は上記に対応していくこと、自治体はそれらを校務支援システムの更新・新規導入時に上記をサポートした製品を選択・導入していくこと、が求められる訳です。
なので、自治体の皆さんは「折角導入したのに」と焦る必要はなく、導入している校務支援システムに上記への対応を要求していけば良いのだと思います。または、これを機会に、校務支援システムそのものの在り方から見直していくこともアリですし、むしろそうしていくことが重要なのだと思います。
そのうえで、特に自治体の方々にとっては、校務系・学習系ネットワークの統合というのが教育ネットワークシステム全体の再設計となるので、それなりに大事なのだと思います。
それは校務支援システムの導入だけでなく、学習系システムの導入時にも、ネットワーク統合を見据えた設計・構築が必要になることを指します。
この辺り、手前味噌ですが以下で記事なんかも書いていますが、参考にしていただけたらと思います(この時はデジタル庁勤務でもないので好き書いてんなー)。
終わりに。また書く機会をつくらねば。
いつもより少し短めですが(と言っても長い…。)、報道の解説・補足ですのでこのぐらいで。
久しぶりに書いたせいか、この長さでもぴったり1時間かかってしまいました。うーむ、鈍っていますね…。
デジタル庁勤務もある意味で縛りプレイの一環だと捉え、これからはまたギリギリを攻めて何か書く機会をつくれればと。
ではまた!
この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?
