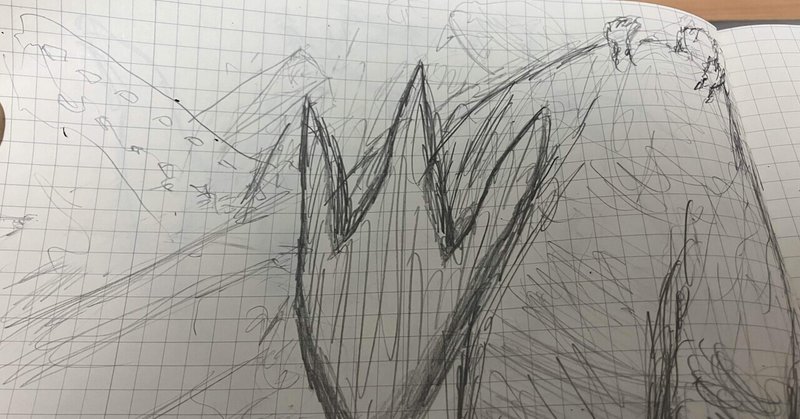
嘘か真か大雨か
■今日は天気が悪い。とても眠い。首もなぜか凝っている。左肩も痛む。さっきはものすごい勢いで雨が降っていた。特に書くことはない、気がしている。でも実際はあるんだと思う。それを今から聞き出す。産婆術的な意味で。
僕は大学で哲学を専攻した。僕が通った哲学科では最初の一年で、哲学入門と古代哲学史、2年目で中世哲学史と近世哲学史を取る。そして3、4年で自分の専門分野を思想・倫理・美学のうちから一つ選択し、4年生の終わりに卒業論文を提出するという形だ。
自分自身は卒業論文を「なるようになるということについて」というテーマで書いたが、これはシェリングという近世の哲学者のいわゆる『人間的自由の本質』と呼ばれているものを参考文献にしつつ、一体どのようにして「なる」と「ならない」とが世界を構築していくのかというようなことを書いたものだ。『人間的に自由の本質』における光と闇の対立を「なる」と「ならない」とに置き換えてみた時何が起こるかを実験的に書いてみた形である。
とりあえず卒論の評価としてはAをもらったものの、僕は自分の書いたものに満足できたわけではなかった。というかそもそも、この「なるようになる」問題自体が自分自身の人生に食い込み過ぎていて、これをほったらかしにしたままで他の何事かに真剣に取り組むなどあり得ない感じであったし、むしろこの「なるようになる」問題を解決した暁には、他のあらゆる具体的問題の解決も必然的に約束されるというような、問題が存在するということそのものを問題にしたテーマだと、僕はそう考えていた。ざっくり言えば「なるようになる」問題とは、「なるようになるとはいうし、論理的にはA=Aで何も間違っちゃいないはずなのに、僕らの人生は結構なるようにならないと感じることばかりじゃないですか。それ、どうなってるんです?」というようなことだ。また、この「なるようになる」という言葉は僕の中でロックンロール的なものと結びついて、創造の扉を開け放つための鍵概念として一刻も早く解明されるべきものになっていた。だから当時の僕には就職などしている場合ではなく、未だ見えていないものを見にいくべく暗闇の中に身を投じるのは至極自然なことだった。暗闇の中に身を投じれば目指すべき光が最もよく見えるだろうと、僕はそう考えた。
おかげさまでかなり時間はかかったが「なるようになる」問題の基礎構造は解明し終わっているしその中で自分自身が取るべき立場をどのように表現すべきなのかというのも日々研ぎ澄まされてきているので、当時の僕が今の僕を見たらあまりの眩しさに失明するのではないかというくらい今の僕はギンギンに輝いている。振り返ってみるとそんなに複雑な話ではなく正直中学生でも理解できるような論理だけで世界は成り立っているんだなと今なら思えるが、木の葉が隠された森に迷い込んだような状態だったので、そもそもその森の中でサバイブしながら探している木の葉はどれなのかをその根拠からして見抜くというような暮らしは僕の精神をかなり異常な状態にさせていた。今なら、目の前に落ちているその木の葉がお前が探しているそれだよ、と言える。しかし当時の僕にはそれがそうであると信じることができなかった。それがそれであると信じられない状態は、まさしくなるようにならない今生の迷いの表れそのものだったのである。
精神の無限の泉にたどり着くことができたのは、この先行き不透明な時代を生き抜くためには必要なことだったし、絶対に沈まない船に乗り込むことができたようなものなので、ラッキーだったし自分の直感を信じてよかったと思っている。正直、これ以外の問題は僕にとっては瑣末なものなので、もう以前のように本当の意味で不安に飲まれるということがない。というか、絶対に浮上できるということがわかっているからこそ、飲み込まれることに対する恐怖がなくなったということだ。不安の波に乗る感覚がわかったということだ。
現代史は人間の不安を煽ることで成立してきた。その一つの到達点が、今現在中東で起きていることだ。人間を人間と非人間とに分け、非人間の烙印を押されたくなければ人間の言うことを聞け、ほら、これが非人間の受ける扱いだよ、という、一つの見せしめが今、人類史における人間性の大きな源泉の一つであったはずの場所で行われている。ここで言われる人間性とは一体なんのことなのか?人間的自由の本質とは一体なんなのかということを、僕らは今こそ、自分自身の存在を賭けて問い、そして、問い続けるという仕方で表現していかなければならない。「お前は一体何者なのか、人間とは何者か」と。
この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?
