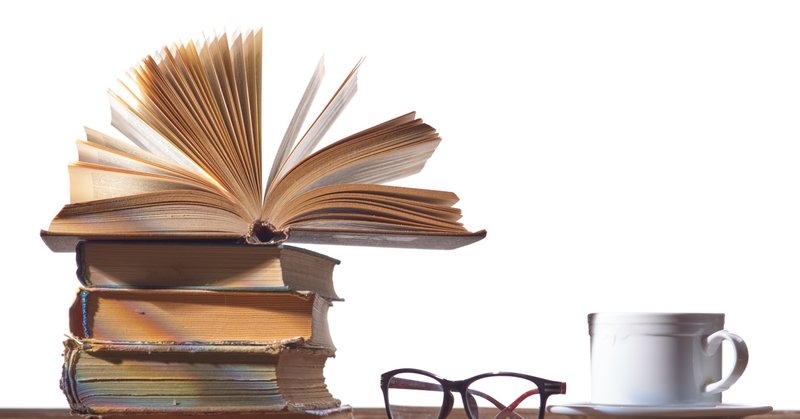
フリーライターはビジネス書を読まない(9)
単行本の執筆は難行苦行
締め切りまでちょうど1カ月。編プロから、まだ何の連絡もない。項目案が通ったかどうか、それだけでも知りたいのだが……。
仕方がない。こっちから編プロの社長にメールを出してみた。
「お送りした項目案で書き始めていいですか?」
なんと、すぐに返事がきた。
「版元との調整に手間取っています。あの項目で書き始めてください。手直しがあったら、そのときに知らせますから」
書き始めないと締め切りに間に合わないのだけど、項目案が変更になるかもしれないとは――。
書いてしまってから「この項目、やっぱり要らない」なんていわれたら、時間を大きくロスしてしまう。
そうなったら、なったときに考えたらいいか。
とにかく始めよう。
前回5本だけ手伝ったときに気づいたのだけど、ビジネス書というものは、経済アナリストとか経済学者と呼ばれる、いわゆる「識者」が著者になって自分で執筆している場合ももちろんあるけれど、多くはライターが下請けで原稿を書いている。
著者はライターが書いた原稿を確認して、自分の著書として出版できるかどうかをチェックするだけ。いってしまえば、ゴーストライターが主に稼ぐ市場のひとつなのだ。
原稿の書き方にしても、誰かにインタビューしたりどこかへ取材に出かけたりするわけじゃなく、同じような内容の本(=類書)を数冊~十数冊買ってきて、おいしいところを継ぎはぎしてリライトするのだ。しっかりと一次情報に基づいて書かれたビジネス書はあるけれど、そういう本は値段が高いのだった。
編プロの社長曰く、
「情報には著作権がないのです」
当時はそんなビジネス書が多かったが、当たり前のことだけど内容にウソがあってはいけない。参考に使う類書はできるだけ新刊を入手しなければならなかった。
類書の購入費はあとから精算して、必要経費として原稿料と一緒に支払われるが、購入費を一時立て替えるのは結構な負担だった。
いまだったらネットでサクッと手に入るような情報も、書店で類書を選んで買ってこないといけない。チョイスを間違えて内容の薄い類書だったら、ほとんど参考にならなかった。
そんな失敗もしながら、まるごと1冊の本を書くのは、人生初めての経験だった。
ライターデビューが単行本だったことは後々、私のライター稼業で大きくプラスにはたらくことになる。だが、このときは、まさに難行苦行。金融の勉強なんかやったことがないから、類書に書いてあることが情報のすべてである。引き写しにならないように、意味を変えずに文体だけ変えるリライトは、思いのほか難しい作業だった。
推敲とプリントアウト、郵送の日数もあわせて考えたら、1項目あたり1200字の原稿を1日に4本は書かないと締め切りに間に合わない。
1項目目から順に書いていたのでは、かえって遅くなる。項目によっては書きやすかったり、身近な内容だったりして、わりあいスラスラと書けることもある。そういう項目から先に書いて行き、その勢いを維持しつつ難しい項目をやっつける作戦に切り替えた。
金融機関の種類や金融市場の仕組みは、自分の頭でもなんとか理解できたからスピードがあがった。
参ったのは国際化時代の金融について、10項目ほど書かないといけない。自分で捻りだした項目案とはいえ、類書に横文字が多くて閉口してしまった。
この10項目だけで、1週間近くもかかってしまったのだった。
(つづく)
この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?
