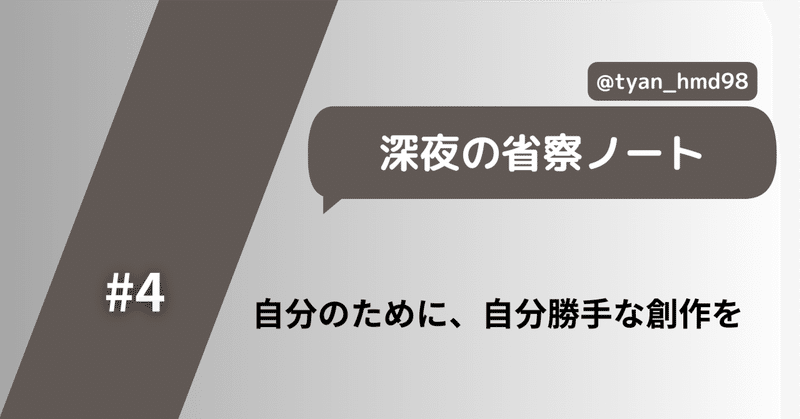
#4 自分のために、自分勝手な創作を
ジブリ映画「耳をすませば」では、主人公・雫が人生で初めて書き上げた小説を、地球屋店主の西老人に読んでもらうシーンが印象的である。
街灯り煌めくベランダで、ありがとう、とてもよかった。と評する西老人に、雫は泣きそうになりながら、自らの不出来な作品に対する否定の言葉を重ねていく。
「そう、荒々しくて率直で、未完成で。聖司のバイオリンのようだ。」
「よくがんばりましたね。あなたはステキです。」
「慌てることはない。時間をかけてしっかり磨いて下さい。」
西老人はそのように言って笑ったのであった。
職業とするにはあまりに拙筆で、それでも人並み以上には嗜む程度と言える文筆活動(はたして10字のツイートでも文筆活動足り得るのだろうか?)は、今でも私にとって最も恥ずかしい創作活動である。
齢90を超えた祖母と数か月前に会った際に、祖母は新聞の投書に掲載された自書のコピーを嬉しそうに見せてくれた。何かにつけて文章を書く癖はそんな祖母の血筋ではないかと今では確信している。そして中高時代の日記(当時は文庫サイズで1日1ページ、日付だけが入った新潮文庫の「マイブック」を日記帳として使っていた。)は、明確に恥ずかしさを覚えた最初の創作物であった。
◆
手元に残る日記の創作物としての恥ずかしさは、もはや特級呪物級である。
(心の内を無策にテキスト化することが、いとも簡単に文章を呪物化させるということを、10年前の私はまだよく分かっていない。)そもそも誰かに見せるために書いたものでない以上、過去の自分の独白にケチをつけるのはお門違いというものだが、それでも未来の自分が見て恥ずかしくなるというところは、大概問題ではなかったようだ。
インターネットで誰もが見られるような場所にテキストを投げるようになってからは、なるべくそうした呪物を生成しないよう努めているものの、最近になって、大学以後に作成した過去の記事のいくつかを非公開にした経緯もある。物の分別がついているようでついていない、学生時代の最後の青臭さであったかもしれない。
さてこれら何か物を書くという行為自体は、自分にとっては心の整理整頓だ。書くことによって自分の中でとっちらかり、ただでさえ狭くて息苦しい部屋から溢れそうになっている声たちを、紙やあるいは画面上に整列させていくのである。
ただそのようにして整列された考えは、本当の意味で「見えやすく」なってしまう。思考の整理は生理的に必要な運動であると同時に、ただ曖昧に、ぼんやりと隠していた私の秘密を、最も分かりやすい形で外界へ晒すことでもある。
これでは体の内側から私を見透かされているのと変わりない。相手の受け取り方一つで、ガラスの内張りで支えていた私と、取り巻く世界の境界線が脅かされる端緒となりうる。ともするとこの場合、創作の恥ずかしさとはすなわち、自他の境界線を脅かされることへの恐怖心であるのかもしれない。
◆
そんな創作の恐怖心を取り除く、あるいは軽減するために私が心に留め置いていること、それは、あらゆる創作活動は、たとえそれらの生産物が誰に評価されるようになった(あるいは「別にならない」)としても、その第一義的受益者は他ならぬ自分自身であるという確信だ。
常にどこか恥ずかしさを抱えながらも、私は私自身の言葉を、文字で綴ることですくい取り、そして救ってあげたいと思っている。浮かんでは消える取るに足りない言葉、気の迷いから来る言葉、誰に何ら影響を及ぼさない言葉でも、それらは私自身が積み上げてきた時間と経験によって裏打ちされた言葉たちであり、生の証左そのものと言える。
形として残さなければ、風前の灯にすらなり得ないものをすくい取りたいと願う思いは、理屈というよりは衝動に近いものだ。もとより、創作活動は根本的に、衝動に駆られた自分の勝手が過ぎた先なのだから、何を今さら顧みることがあろうかと笑ってやればいい。
まずはとにかく、創り出すことが自分のためになっているという前提を持つことが、創作の恥ずかしさ、恐怖心とうまく付き合っていくための第一歩となる。出過ぎた期待を添えるならば、いずれ創り出したものたちが自分にとっての需要を十分に満たしたときに、余剰となった利するところ、生み出した功利が、身の周りを心地よく巡っていてくれればと願う。
この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?
