
第7回 予兆
[編集部からの連載ご案内]
『うろん紀行』でも知られるわかしょ文庫さんによる、不気味さや歪みや奇妙なものの先に見える「美しきもの」へと迫る随筆。今回は「目にうつる全てのことは〜」な話。(月1回更新予定)
騒々しい駅前のビルの中にある図書館に行きたかったのに、間違えて別のビルに入ってしまった。そのビルには書店があり、わたしは読みたかった書評のことを思い出して中に入り掲載誌を探した。
「ご覧のスポンサーの提供で、お送りします。
ご覧のスポンサーの提供で、お送りします。
ご覧のスポンサーの提供で、お送りします。
ご覧のスポンサーの提供で、お送りします。
ご覧のスポンサーの提供で、お送りします。
ご覧のスポンサーの提供で、お送りします。
ご覧のスポンサーの提供で――」
声のするほうを見ると、落ち着いた色のチェック柄のシャツとベージュのパンツといういでたちの骨太の男性が、こちらに向かって歩いていた。白髪交じりの頭を短く刈り揃え、片方の口の端に笑みを浮かべながら何度もそのフレーズを繰り返している。音量、速度、イントネーションのすべてが的確だった。おそらく話すことを生業とする人物の模倣なのだろう。だが男性の発声は、もはやオリジナルといって差し支えなさそうだった。男性はその優れて音楽的な響きを口にしたまま、悠然とした足取りで書店の奥へと消えていった。
どうしてわたしは強く心を動かされたのだろうか。周囲の全てがスポンサーであり、ひとはみな誰かに生かされている、という普遍的な教訓を感じ取ったからだろうか。んなわけあるかい。男性が発していたのはきっと大いなるメッセージ。わたしはこの予兆から何かを読み取らなければならないのだ。
書店の向かいに保険の代理店があって、店頭にシリコンのおっぱいが置かれていた。ご丁寧に乳首まであるそのおっぱいは、ラップが巻かれており誰でも自由にさわってよかった。乳がんの早期発見を促すための展示で、中に隠れているしこりを探して触診の感覚を知る。わたしはさきほどの響きが何を予兆するのか考えながら、三本の指でおっぱいを押した。しこりは全部で六箇所あるらしいが、ひとつも見つけることができない。
「なかなか、わからないですよね」
制服を着た女性の販売員がやってきた。わたしは無遠慮におっぱいをさわった非礼を詫びた。販売員は、このおっぱいは新品なのでしこりがわかりづらく、みなさん苦労されます、と口にしながら、このへんだとわかりやすいかな、と渾身の力でおっぱいを強く押し込んだ。おっぱいは痛々しいほど変形した。わたしも負けじと指を押し込んだ。これか、という違和感を指先にわずかに感じ取ったが、気のせいだとも思った。
実はこの世には予兆が溢れていて、読み取ることで未来に備えることができる。ちょっとした異変や出来事が、これから起こる身の破滅や類い稀な法悦を表していることがある。
駅のホームドアにゲボがかかってひからびていた。〆に雑炊を食べたことがわかった。最寄り駅のホームドアは安価なタイプで、ドアというより柵だが、柵全体にゲボがかかっている。甘酸っぱく匂い立つようなゲボを見ながら、そこで吐いたら電車に頭を持っていかれますよね、と心のなかで語りかけた。血だまりはなかったから二次被害には至らなかったようだ。なぜかいいものを見たという気になり上機嫌になった。それから数日と経たないうちに、ひとりで赤ワインを飲みすぎて家のトイレで吐いた。なんてことだ。ここ何年も失敗していなかったのに。あのゲボはこのゲボの予兆だったのだろうか。いや、予兆はスロットのリーチ目のようにさりげなく表れるはずだ。わかりやすく直接的なものではない。予兆は読み取りにセンスや技術を必要とする。
レンタカーで夜の高速道路を走っていた。東北道を北上する道すがら、走行車線に合流した白い軽自動車が目の前に現れた。軽自動車は70キロ台の速度で蛇行していた。特段風が強いというわけではなかったし路面は滑らかだったが、車体が左右に揺れていた。わたしは速度を上げて追い越し、佐野に到着するなり佐野ラーメンを注文した。箸をいれてスープからすくいあげると、麺が波打つように縮れていた。あの軽自動車の蛇行は、この縮れ麺の予兆だったのだろうか。
わたしはかつて、とある占いをひどく憎んでいた。占うものも占われるものも、全てを嫌悪していた。その占いは占星術の一種なのだが、星の動きから予兆を読み取ることよりも、ひとの心の隙間に忍び込むことに重きを置いていた。たった12の分類のもとに、あなたはこんなひとで、こんな意外な一面があると、誰にでも当てはまるようなことを言い聞かせて信用させ、自尊心をなでまわして自我をぐらつかせる。その占いが公開されるたびにインターネットは沸き立ち、涙したと言うものが大勢いた。ファンの多くは若い女性だ。彼女たちは自分に自信がなさすぎるのではないかとわたしは思う。自尊心の隙間を埋めたくてたまらないのだが、自分自身に肯定的な言葉をかけられるほど、自分を信じ愛することができない。だからその占いを使う。当たってる、と口にして、自ら予兆を読み解く努力を怠り、目を背けている間に、生き抜く力も魂も奪われてしまう。いかにも「女」が、「迷信深さ」や「愚かさ」の予兆みたいじゃないか。逆らえよ、とひとりひとりに言いたかった。だが、彼女たちが占いに流す涙よりも、わたしの外見のほうが愚かさを予兆させることもわかっていた。わたしはよく初対面のひとにうすのろの馬鹿だと思われる。そのひとたちは腫れぼったい目や下ぶくれの輪郭に、浅薄が引き起こす失態や退屈な時間の予兆を見出だす。
実家で16歳の頃の吹奏楽部の定期演奏会のパンフレットが出てきた。送られてきた画像を見ると、一定の距離を保ちながらトランペットを持ち、仏頂面で正面を向く三人の男と一人の女のいる写真の隣に、それぞれの紹介文が載っていた。先輩が考えたわたしの紹介文はこうだった。
「いつもまったりしてます」
どこがだ。わたしは「まったり」というよりは「ぐったり」としていた。あの頃のわたしは憎悪に駆られながら四六時中嵐の中を叫び、走りまわっているようなものだった。どうしてあのとき誰も、あの嵐を何かしらの予兆から読み取ってくれなかったのだろう。わたし自身でさえもだ。いや、もしかしたら誰かは気づいていたのに、パンフレットにはふさわしくないと判断されて削られたのかもしれない。
もしかすると。この「いつもまったりしてます」も、予兆なのかもしれない。16年後にこのパンフレットが、実家から発掘されることを表していたのかもしれない。だとすれば、「まったり」とはそれまでにかかる年月のことだったのだろうか。わたしが自分のなかの嵐を理解するまで時間がかかることを、密かに予兆していたのだろうか。
「実はわたしは占いができるんです」
最近仲良くなったひとが教えてくれた。え、そうなんですか、と口走りながらも、同時にしっくりきていた。わたしは何がしかの予兆を読み取ることができていたのかもしれない。
「今度わかしょ文庫さんのことも占ってあげますね」
全身を鳥の羽でなでられるようなむず痒さと心地よさが走った。何を読み取ってくれるというのだろう。彼女が予兆する能力に長けていることがわたしにはわかっていた。占われるわたしの運命が破滅的で悲劇的であると想像すればするほど、恍惚とした。めちゃくちゃに言われたい。めちゃくちゃになりたい。わたしは彼女が、何人にも救い難いわたしの未来を告げるであろうことを感じ取った。予兆の予兆を予兆して、わたしは口の中にたまった唾液を、喉を鳴らして飲み込んだ。甘かった。
わかしょ文庫
作家。1991年北海道生まれ。著書に『うろん紀行』(代わりに読む人)がある。『試行錯誤1 別冊代わりに読む人』に「大相撲観戦記」、『代わりに読む人1 創刊号』(代わりに読む人)に「よみがえらせる和歌の響き 実朝試論」、『文學界 2023年9月号』(文藝春秋)に「二つのあとがき」をそれぞれ寄稿。Twitter: @wakasho_bunko
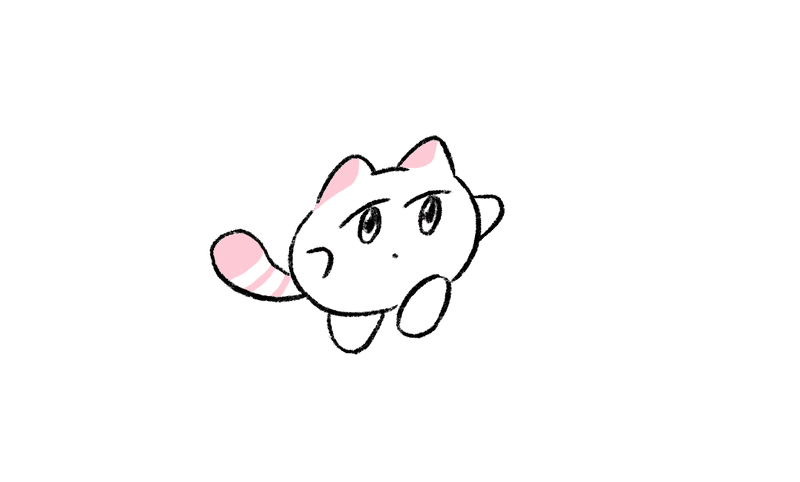
/ ぜひ、ご感想をお寄せください! \
⭐️↑クリック↑⭐️
▼この連載のほかの記事▼
この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?
