
第4回 太陽の宮殿
[編集部からの連載ご案内]
『うろん紀行』でも知られるわかしょ文庫さんによる、不気味さや歪みや奇妙なものの先に見える「美しきもの」へと迫る随筆。今回は夏休みスペシャルのような。(月1回更新予定)
いつも地引網をするみたいにして原稿を書いている。「悲しい」「苦しい」「腹が立つ」といった負の感情を手繰り寄せていけば、きまって言葉がついてくるものだ。だが、人間はいつまでも負の地引網をし続けるようにはできていないだろう。ネタ切れになって悲劇や不幸を探し求めるようになったら本当にまずい。怪人のようだし、やがて自分で辻斬りでもし始めるようになったら最悪だ。
では、「嬉しい」「楽しい」といった感情をもとにハッピーの地引網をすればいいのになぜしないかというと、そもそもわたし自身があまり幸せな人間でないというのもあるが、わたしの場合はハッピーについてくる言葉は「イェーイ」とか「わーい」とか、「やべー」とか「すげー」とかばかりで、とてもではないが原稿に使えないからだ。幸せなときは頭のなかで非常に限られた語彙しか使っていないから、幸せの詳細はあまり覚えていない。思い出そうとするとやってくるのは、「いまがピークだ。この瞬間も徐々に尻すぼみになって終わってしまう。そうしていつか、みんな死ぬんだ」というアレばかり。絶叫マシーンが最も高いところから落ちるときの、内臓がふわふわとした軽いものに変えられたような心もとなさばかりをすぐ思い出してしまう。
悲劇的なもの、失われてしまったものはたやすく胸をうつ。平家も義経も滅びる姿はどちらも魅力的だ。わたしが『平家物語』で好きな死は、馬がぬかるみにはまってもたらされる木曽義仲の死だがそれはそれとして、でもそれでいいのか? 悲劇とともにでなくても、美しい瞬間はあるんじゃないか? スプーンですくったアイスクリームを舐めとるみたいに、残らず味わいつくしたほうがいいんじゃないか?
思い出すんだ。たとえば、絶叫マシーン。そう、あれは、三井グリーンランド!(現在は北海道グリーンランドに改称) 家から遊園地に行くならばほぼ二択、ルスツリゾートか三井グリーンランドだ。かつてピカピカしていたはずの遊具は、ホームページで見るかぎり、退色して何とも言えない淡い色になってしまっている。多くのアトラクションが整備中のようだが、しかし閉園はしていない!
遠くからでも見える名物の観覧車は、風が吹くと狭い箱のなかがその音でいっぱいになって、いたずらに不安をかき立てた。三回転ジェットコースターでは頭を側面にしたたかに打ちつけた。巨大遊具に乗れば、縦に回転した拍子にポケモンのシールがポケットから落ちてどこかへ行ってしまった。乗り放題の権利を有していることを表すマゼンタ色のビニールの腕輪には、切り取るためのミシン目がついていた。全体をすこしずつ伸ばしてから石鹸で手をぬるぬるにしてゆっくりひっぱったら切り取らなくてもきれいに外れたけど、どう見てもずるだとわかるから、結局、次行くときには使わないで捨てた。
どうしてこんな思い出しか出てこないのだろう。いまのところ、これをハッピーの地引網と呼ぶのは無理がある。でも、夏休みは楽しいことがたくさんあった気がする。居間で昼寝をしている背後でついていたテレビのタモリ。しけっていると思い込んでごみの山に投げ込んだら音を立てて爆発した花火。白いスクーターにまたがって仕事から帰ってきた叔母の、腰まである黒くて長い髪。涼しげな風に吹かれながらヘルメットを外した叔母が、夕暮れに染まった顔を輝かせて、駅前に生きた化石であるメタセコイアという木が植えられたことを話す。わたしは、その木自体が何百万年も生きているのだと、ずっと勘違いしていた。
夏になると子どもを海で遊ばせねばならないという義務感でもあったのか、よく海に連れていかれた。手段はいつも車だった。祖父が荒っぽく運転するワゴン車か、叔母の深緑色のスタイリッシュな普通車か。父親の紺のカローラはずんぐりとしていた。車はどれも持ち主たちによく似ていた。
海岸に数十ものクラゲが打ち上げられていた。たとえ死んでいても針が刺さると面倒だから、裸足のまま避けて歩いた。わざわざ海中でクラゲを捕まえて砂浜に並べている大人がいた。無防備な子どもたちが刺されないようにと、ボランティアのつもりだったのだろうか? クラゲは半透明できれいと言えないこともなかったが、まばらに砂がついていて汚いと言えないこともなかった。それでもまだ浅瀬のそこかしこにクラゲがいたから、海に入るのはやめて砂浜に妹を埋めて遊んだ。よだれでべろべろになるまで息を吹き入れてもなかなか膨らまない浮き輪が、大人の手にかかるとあっという間に膨らむのはいつだって魔法みたいだった。海の家は高いからって一度も連れていってもらったことはない。でもツブ貝の屋台にはよく並んで、炭火で焼かれて醤油を垂らしたのを買って食べた。つまようじをなるべく奥まで差し込んで手首のスナップを効かせると、弾力のある肉から螺旋状の内臓まで一気に引きずり出すことができた。内臓に毒があることは知っていたがみんな気にせず食べていた。全員が毒にあたって酩酊状態で帰った日があった。
海にまつわる記憶は曖昧に溶け合い、隣にいるのは両親だったり妹だったり祖父母だったり叔母だったりする。晴れ、あるいは曇り、あるいは小雨が降っている砂浜のそこかしこで、わたしの顔を誰かがのぞきこむ場面がいくつもあった。リラックスした表情を浮かべる彼ら、彼女らの瞳のなかに、水着も身体の大きさも異なるいくつものわたしが映っている。
なあんだ、ハッピーの地引網もできたじゃないか。言葉は自分の奥底にいくつも転がっていて、あとは慎重に引き寄せるだけでよかったのだ。幸せは儚いものだと定型文のように信じていた。しかし幸せが儚かろうと美しい瞬間は確かにあった。ただそこにある一瞬がそれだけで美しく、わたしはそのことを覚えていた。記憶している、という事実だけでその一瞬を美しくかけがえがないと感じるのかもしれない。悲劇でなくともいいのだ。
「波の下にも都のさぶらふぞ」と、およそ八百年前に二位尼が壇ノ浦で言った。荒々しく恐ろしい源氏の武者たちに囲まれ、もう助からないと全員が覚悟したそのとき、もしかしたら安徳天皇だけは、涙を流しながらも祖母である二位尼の言葉を信じたのかもしれない。二位尼たちが自分をすげー都に連れていってくれて、やべーくらいにわーいって思えると、そう信じたのかもしれない。なぜならば安徳天皇はそれまで、いろんな大人たちに大切にされ、愛されていたに違いないからだ。まだまだみんなでイェーイってできるって、信じられたのならば安徳天皇はその瞬間も幸せだったはずで、だとすればこのお話が悲劇だと簡単に言いきることはできないだろう。
海から帰ってテレビをつけると、いつだって同じコマーシャルが流れていた。大浴場と波の発生する巨大なプールを併せ持つ宿泊施設の宣伝には、きまってこんな歌が使われていた。
ここはお風呂の遊園地 なんてったって宇宙一
行ってみたいなサンパレス サンパレス
巨大なプールは無くなったらしいが、いまでもこのコマーシャルソングをそらで歌える。耳にするたびに、「行ってみたいな」と心のなかで唱えていた。実は以前に家族四人で行ったことがあり、「宇宙一」がどの程度なのか知っていた。それでもサンパレス、すなわち「太陽の宮殿」に、大好きなひとたちみんなで訪れることができたらきっと楽しいに違いないと、子どものわたしは恋い焦がれ続けていたのだった。
わかしょ文庫
作家。1991年北海道生まれ。著書に『うろん紀行』(代わりに読む人)がある。『代わりに読む人1 創刊号』(代わりに読む人)に「よみがえらせる和歌の響き 実朝試論」、『文學界 2023年9月号』(文藝春秋)に「二つのあとがき」をそれぞれ寄稿。Twitter: @wakasho_bunko
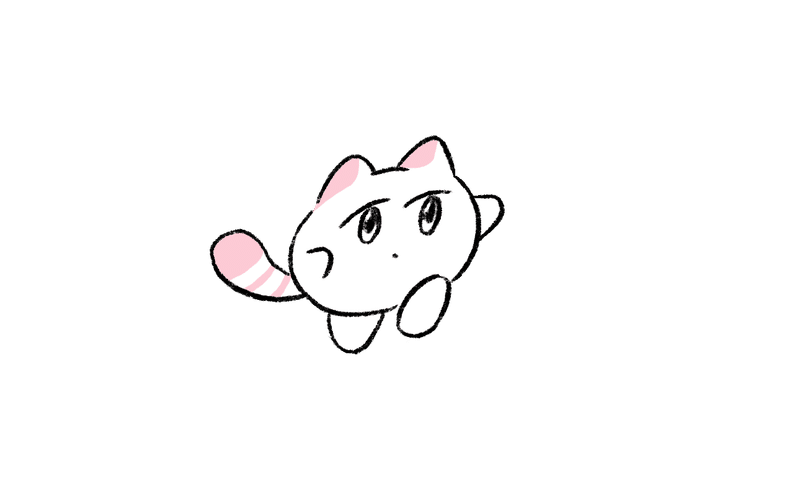
/ ぜひ、ご感想をお寄せください! \
⭐️↑クリック↑⭐️
▼この連載のほかの記事▼
この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?
