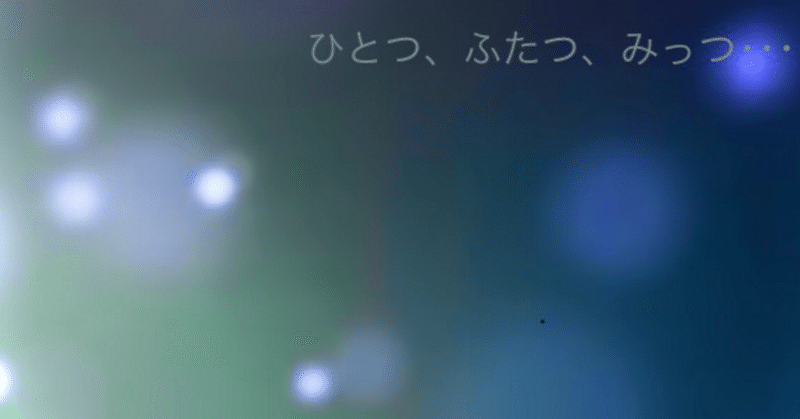
空談①
僕は賢い子どもだった。
たくさんの本を読んで、言葉を覚え知識を増やした。
年齢よりもませた子どもだった気がする。
母は、僕を賢い子だと頭を撫でる。
父は『もっと好きな事して我儘を言ってもいいよ』と言って頭を撫でる。
僕は好きな事してる。
だから父の気遣いに納得できないでいた。
そんな僕に『零と混ぜて中和したらいいかもね』なんて笑う。
零も途中まで賢い子だと、母から頭を撫でてもらっていた。
いつからか、少し我儘になっていった気がする。
それでも父は、優しく頭を撫でていた。
母はよく父に『甘やかすからだ』と苦言を呈していた。
僕は母と同じ様な気持ちを心に隠して、口にはしなかった。
でも、気がついてしまった。
零はバランスの悪い子なだけで、決して賢くないわけではない。
いや、むしろ“賢い”その事がバランスの悪さの元凶だと思った、
零は記憶力がもの凄くよかった。
母はよく何処に何を置いたか忘れるが、そんな時は零が「あっ」と声を上げ、そして僕に教えてくれるので、それを母に伝える。
最初のうちは偶然だと思っていたが、何度も重なれば何故こんなに知っているのだろうと疑問に思う。
それ以外にも、僕がパズルをしていると横で必ず見ている。
それも僕より先にピースをはめ込むことができるようだった。
小さな頃は僕が少し悩んでいると、そのピースを僕の側に寄せてくる事もあった。
平仮名やアルファベットも一度見せると直ぐに覚えた。
でも、それだけだった。
覚えるのは早いが、それらを上手く使う事には繋がっていない様に感じた。
だから僕は賢くて、零は賢く無いと母は決めていた様だった。
零は伝える事がうまくできなくて、癇癪を起こしていたのだと、後になって気づいた。
だから僕に伝える様にしたのだと思う。
それを僕は大人たちに伝える役割をしていただが、あえて零からのものだと言わなかった。
だから僕は賢い子で、零は困った子にされてしまったのだ。
意図したものではなかったが、罪悪感はいつまでも消えない。
この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?
