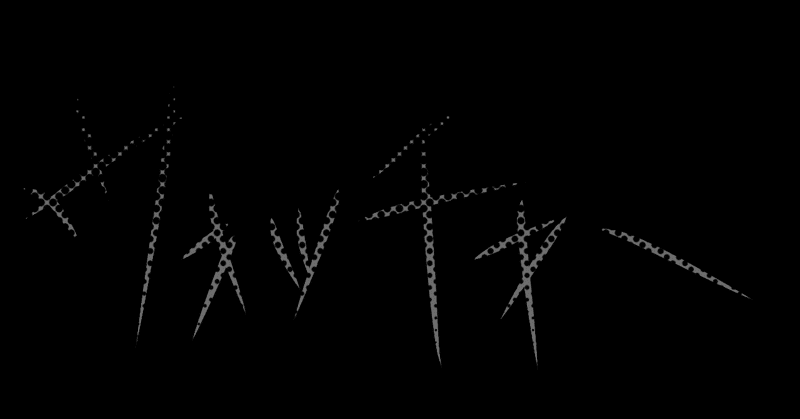
Watcher #11
友人から久しぶりに連絡があった。
連絡を取ることをひかえていた友人だ。
嫌っているわけではない。
友人が物書きとして売れて以来、忙しいだろうと、連絡するのを遠慮していたのだ。
友人からきたのは、おれの心配からはじまるLINEだった。
SNSでのおれの投稿を見てのことだった。
おれの、脳の検査を受けたという、旨のつぶやきを。
久しぶりに会おうとなった。
昔はよく友人やおれの家で宅飲みをした。
たまに外で友人にごちそうもしたが、申し訳なさそうに何度も礼を言ってきた。
当時の友人は貧乏だったので、金の価値を大きく感じていたからかもしれない。
おれも金持ちでもないし、そんなおれに、おごられると思って声をかけるのをためらわれたら困る。
気軽に誘ってほしかった。
なので、外食はせず、互いの家での宅飲みになっていたのだ。
そんな友人が「ごちそうするよ」と言ってくれた。
待ち合わせは、友人の今の住まいの近くだ。
貧乏時代からは、考えられないような場所に住んでいた。
近所に、よく行く美味しい焼肉屋とフレンチがあると、選択肢を提示してくれた。
おれは、冗談で寿司がいいなーと笑いながら言った。
そしたら、友人も笑いながらいいよと言ってくれた。
近所で済ますわけではないならせっかくと、かなりの高級店へつれていってくれた。
あまりの高級店におれは面を食らった。
高級店の空気に飲み込まれ萎縮しかけた。
しかし、縮こまって大人しくしていたんじゃ、友人もおごり甲斐がないのではと思った。
おれは、少し無理して興奮ぎみに、うまいうまいと食べたのだ。
無理した反動でやりすぎて、高級店にふさわしくなく、逆に友人に恥をかかせたかもと思った。
だけど、そんなおれを友人は、子供に好物を与えて、嬉しそうにしている親のように見ていた。
もしかしたら、昔おれがごちそうした恩を返せるのがうれしかったのかもしれない。
ここの会計は、おれが友人におごった総額なんか、くらべ物にならないだろう。
テレビで名前を聞いたことがあるし、たしかあの星がついている。
店を出てごちそうさまと言ったあと、飲みたりないからと、友人の部屋で飲もうと誘われた。
最初からそうするつもりだったから、友人宅の近所での待ち合わせだったんだろう。
友人の部屋で飲みはじめてすぐに告白された。
友人はこの話がしたかったんだ。
だから、脳の検査をしたおれに声をかけたんだ。
腫瘍があるのだと言われた。
友人の脳に。
しかも悪性の···
余命も宣告されたとのこと。
やっと売れたと思ったらこれだよ、と。
おれはそれを聞いて、なにか言わなきゃと焦りつつ、何も言えずに黙ってしまっていた。
そんなおれに、友人は売れなかった時期の話をはじめた。
売れていないとき、友人は一度コンテストで賞を取ったことがある。
そのとき、周りが一瞬友人をちやほやした。
友人が好きだった娘も好意的な反応で、つき合ってほしいと言ったら、つき合うことができたそうだ。
おれも知っている娘だった。
顔がよくてモテる娘だ。
美人というよりは、かわいい顔をしていた。
当時、おれと友人はまだよく飲んでいのだ。
なのに、なんでつき合ってることをおれが知らなかったのか。
彼女が、周りには内緒でつき合おうというノリだったらしい。
それを律儀にまもっていたのだ。
おれなら、あんなかわいい娘とつき合えたら、そんなノリは無視してすぐに人に言う。
そして、彼女は売れる気配のない友人から離れていった。
別れるときに「私とつき合っていたこと誰にも言わないでね」と言われたそうだ。
さらに、あとから二股だったことがわかたっそうだ。
二股のもう一方は、バンドマンだと。
おれは、競争率の高いバンドマンの保険だったと、友人は言った。
よくあるパターンだよ、とも。
だけど、売れたあと全く音沙汰のなかった彼女から連絡がきた、というよくあるパターンはなかった、と。
そして、そのバンドマンは結局売れずに、彼女はおれの青田買いに失敗したんだと···
様見ろと思ったけれど、おれは死ぬんだって···
彼女の見る目は正しかったよ、と。
友人はそれを笑いながら言った。
友人のしぼり出した自虐ネタに、泣きそうなのをこらえながらおれは笑った。
おれの友人とのつきあいに、全く打算がないとは言いきれない。
友人は小難しい文章を書く。
こいつと話が合う自分は、頭がいいんじゃないかと錯覚してしまう。
そういう気持ちよさがあった。
そんな自分の打算を棚上げしつつ、おれはその女を罵った。
結局その日、おれは友人に気のきいた言葉をかけれずに、そんなことしかできなかった。
友人は、帰りのタクシー代を出すと言ってくれた。
だけど、まだ終電はあったし、タクシーで帰る気分じゃなかった。
自分が死ぬとわかっているのは、どんな気分なんだろう。
いつか自分が死ぬことはわかっているけれど、リアリティーがない。
友人は別れぎわに、おれの検査結果が問題なくてよかったと言ってくれた。
脳検査も異常がなく、結局“あれ”は正体不明のままだ。
だけど、おれにとって自分の死より正体不明の“あれ”ほうがよっぽどリアルだ。
そう、目の前のこの“あれ”のほうが···
“あれ”が帰り道をふさいでいた。
道幅を測ったかのように、ぴったりの大きさだ。
“あれ”には、機動性を無視したものが少なくない。
今日のもそうだ。
全く動くことなんて考えていない。
その“あれ”は巨大な水槽のようだった。
立っているやつと、這いつくばっているやつが、互いに背を向けて足の方でつながっていてL字になっている。
そのL字にビニールを張って、そこに液体を流し込んで、そんで、そんなかにもう一匹いる。
なかのそいつは、上半身がビニールなのか、膜なのか、肉体がグラデーション的にそうなっていってる。

おれは、動きそうもないその“あれ”の佇まいに、友人の死後のモニュメントを連想してしまった。
普段ならこんな大きな“あれ”には、少なからず恐怖を覚える。
それで、道を変えて帰るだろう。
だけど、おれにそんな連想をさせた“あれ”が癪にさわった。
だから、おれは道を変えなかった。
さっきの連想を否定するように、その“あれ”をまたいだのだ。
酔っていたのも、手伝っていた。
這いつくばるほうの頭を、侮蔑もこめて、またいだ。
そうして、おれは変えなかった帰り道をすすんだ。
背中で“あれ”の気配が遠のくのを感じながら。
そしたら、襲われたんだ。
ある感情に。
むなしい、
と。
この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?
