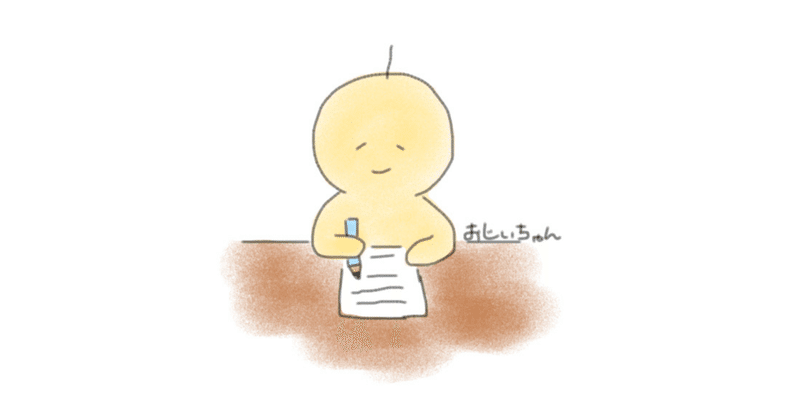
たとえば一首『歩む』(1589字)
人生を歩めば歩みぬ歩まむと歩まざるもの歩まば歩め
(じんせいを
あゆめばあゆみぬ
あゆまんと
あゆまざるもの
あゆまばあゆめ)
☆
こんにちは。^^
うただ荘管理人の つる です。
以前から、
文語文法を分かり易く説明することは
できないかと、考えつつ、
本を読んだりしています。
今回の拙歌は、
そのヒントにでもなりましたなら、と
思いながら詠んでみました。☆
一首、自分なりに
解説してみます。m(_ _)m
☆
まず、『歩めば』。
現代でも通用する言葉です。
意味も、文語として使う場合でも
同じ意味として使えるかも。
また、「歩むので」、と、
理由を表す際にも使われるかとも
思われます。
ここでは、言葉通り、
『歩めば』という意味で詠んでいるつもりです。
☆
お次に、『歩みぬ』。
『ぬ』は、完了を表すのだったかな。
意味は、「歩んだのだった」
くらい。
過去を表すために使うのですが、
単純な過去ではなく、
昔のことがなお余韻として
残っているニュアンスを表すときなどに
使ったりしています。
他の用例を挙げますと、
少し取り扱い易いでしょうか。
歩みぬ(あゆんだ)
遊びぬ(あそんだ)
転びぬ(ころんだ)
誘ひぬ(さそいぬ、と読んで、さそった)
など、
イの段で動詞が活用する例が多いです。
完了は他に「つ」が
あります。
微妙に「ぬ」とは意味、
ニュアンスが変わってきます。
「ぬ」は、ニュアンスが
間延びする感じ。
「つ」は、過去の事柄を
ちょっと言い切る感じでしょうか。
「歩みつ」
「転びつ」
完全に過去の事と言い切る場合は、
過去形「き」を使うかな。
歩みき
遊びき
飛びき
☆
そして次を読みます。
『歩まむ』
音読しますと、「あゆまん」
「む」は旧かな遣いです。
使わない場合は、
『歩まん』と表記します。
新かな、旧かなは、
一首の内で統一しておくのが
通例のようです。
そして意味ですけれども、
「歩もう」、と
意思を表す言葉です。
他の用例としては、
頼まむ(たのもう)
学ばむ(まなぼう)
申さむ(もうさん、と読んで、もうそう)
など。「ア」の段で動詞活用する場合が
多いみたい。
拙歌では、これに「と」
を付けて、
「歩もうとして」くらいの
意味として詠んでいるつもりです。
☆
『歩まざるもの』
否定、打ち消しなどの意味で
使います。
「ざる」は、連体形と言って、
そのあとに名詞、あるいは
名詞形をつなげる用法の
ようです。
終止形(基本形)は、
なんだったかな。。
「ざり」、でしょうか。
でも普通使われないようです。
通例として、「ざる」は
よく見かける形として
覚えておく程度でいいかと
思われます。
用例
歩まざるもの
動かざること
「ま」、「か」、など
「ア」段で動詞活用するようです。
☆
歩まば
これも「ア」の段で
動詞活用しますけれども、
「ば」を語尾に付けることで、
仮定を表すことになるでしょうか。
意味は、「歩むならば」。
理屈より、用例を挙げます。
歩まば(あゆむならば)
急がば(いそぐならば)
向かはば(むかわば、と読んで、むかうならば)
などなど。
ここまで用例も挙げて
説明申し上げていますけれども、
全ての言葉に当てはまるかと
いいますと、
そうでもないようです。
古来の和歌など、
使う頻度の多い言葉は
意外と限られていて、
文法的には合っていても、
あまり読みの馴染まないことに
なったりもします。
要は、昔の歌の言葉を
真似るのが先決かもしれません。
つづけます。
☆
歩め
あゆめ、と読んで、命令形です。
これは割と理解しやすいでしょうか。
飛べ
遊べ
読め
などです。
☆☆☆
おつかれさまでした。💦
お読み下さる方、
ありがとうございます。
最後に、この一首の意味ですけれども、
どう読もうかな。
人生を歩めば歩みぬ歩まむと歩まざるもの歩まば歩め
人生を歩めば歩んだ、と。
歩もうとする歩まない者よ、
もし歩むならば、歩め。
ちょっと苦しい解釈、詠みかも
しれませんけれども、
以上で、
つる の、ちょっと文法の話を
してみました。
また、考えてみます。
悪しからずです。☆m(_ _)m
つる かく🍂
お着物を買うための、 資金とさせていただきます。
