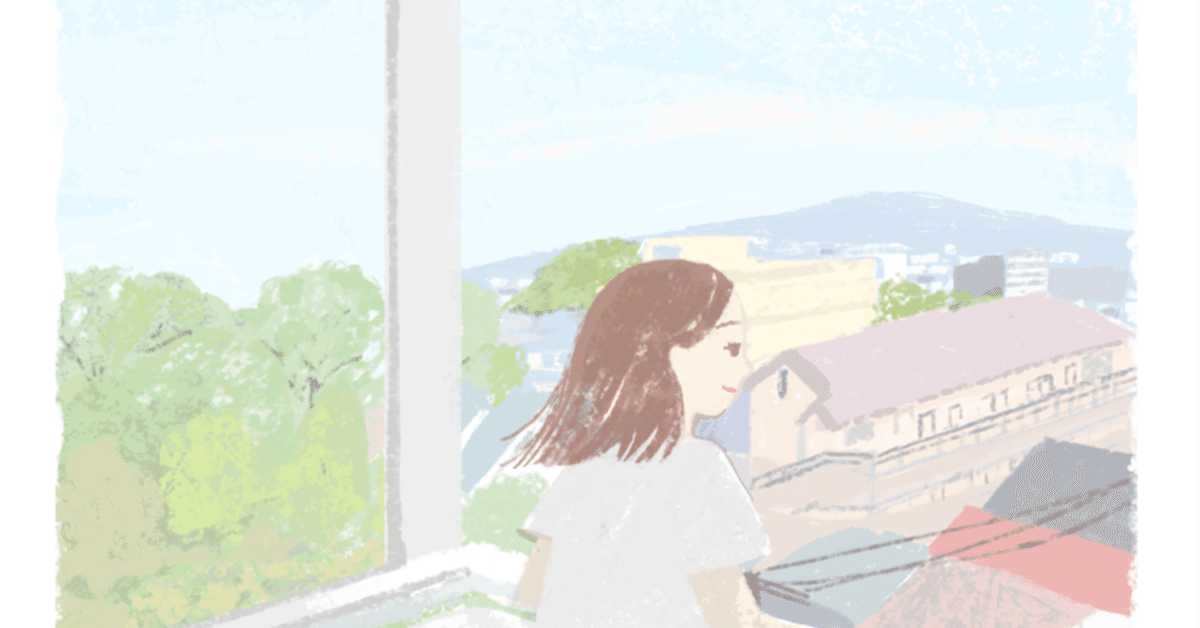
「住めば都」という言葉があるけれど
どこでも住めるとしたら、住んでみたい場所はありますか?
今の住んでいる場所が大好きで、ここから離れるなんて考えられないという人もいるでしょうし、憧れの場所があるという人もいるかもしれませんね。
私は、「この場所にいつか住みたい」もしくは「ずっとここに住みたい」という明確な理想はありません。
学生時代にフランスへ留学したことや様々な国へ旅行をした経験もあるので、日本だけでなく、海外で暮らすことの素晴らしさ、楽しさ、開放感も少しだけ知っているつもりなのですが、それでも「ここが良い」という理想を持っていないのです。
「住む場所」よりも「どう捉えて住むか」
昨年11月に千葉県から岡山県に転勤で引越しをしました。
転勤族なので、いつ引越しを言い渡されても不思議ではなく、心づもりはしていたものの、実際に引越しが決まった時は、初めて住む地域への不安に襲われました。
その時、私の気持ちを占めていたのは「岡山ってどんな場所?」「すごい田舎だったらどうしよう」「子育てはどんな感じでできるんだろう」「保育園すぐ見つかるかな」といった、「住む環境」に対しての不安でした。
私自身は社会人になってからはほとんど、関東地域(東京、千葉)でしか暮らしたことがなく、岡山は足を踏み入れたことが全くなかった地域だったので、そういった不安が非常に大きかったのだと思います。
実際に住み始めて約3ヶ月。
その不安は今では全くなく、むしろとっても快適。
岡山から離れたくないとすら感じることもあります。
実際、住む環境としては想像以上に良かったということはありますが、
それでも千葉にいた時のように、気軽に友達や家族に会うことはできません。
実家に帰るには、新幹線と飛行機を乗り継いで行かなければならない。
そして、子供たちは千葉にいた友人と離れ、新しい環境で新しい友人関係を構築しなければなりませんでした。
決してここが「最も理想的な環境」ではないとも思っています。
それでも、今このように感じているのは何故なのか。
それを深掘りしてみてわかったことがあります。
それは、重要なことは「住む環境」そのものではなく「住む環境への捉え方」なのだと。
天候事情、交通事情、子育て事情、県民性、生活全般における利便性などなど、理想の環境を挙げるとキリが無い。
どんな環境にいても、隣の芝生は青く見えるもので「もっとこんな施設があれば」「こんな制度があれば」と感じるものだと思うのです。
それよりも、与えられた環境、もしくは自分自身が選び取った環境へ自分の気持ちを適応させて、納得感を持って住むということが、まさに「理想な暮らし」につながるのだと思います。
私が今回、住む場所への納得感を持つきっかけになった思考はこんなことです。
「岡山の穏やかな県民性が子供たちにとっても良い影響を与えてくれるかもしれないな」
「住む環境が変わったという、この経験が家族にとってプラスの経験になるはず」
「家族と今まで築いてきた友人と距離的に離れることで、再開できた時の喜びは今までよりも大きくなるはず」
「引越しという大きなイベントを乗り越えて、家族4人の絆はもっと深まったかも」
私たちは、今回引越しに関連した、住む場所に対しての捉え方でしたが、色々な状況で適用できると感じています。
ずっと、この場所で住むと決めたけど、なんとなくしっくりこないなら、「なぜそう思うのか」「どうしたらその感情を払拭できそうか」など自分の感情と向き合い、深掘りしていくと答えが見つかるのではと思います。
その先に、「住む場所を変える」という選択肢があっても良いのです。
今の住む環境に対して、どんな感情、意味づけをできるかが本当に大切だと思うのです。
それができた時に、本当の意味での「住めば都」になるのではないでしょうか。
転勤族という立場上、どんな環境でも、家族みんながそんな気持ちを持って、様々な地域、環境を楽しんでいけたらと思っています。
そして、全ての場所で柔軟性を持って「理想の場所」にすることができたら、こんな素敵なことはないよなぁと感じるのです。
スタンドFMでラジオ配信しています!
よろしければ聴きに来てください☺️
この記事が参加している募集
この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?
