(54)「邪馬台国はなかった」説
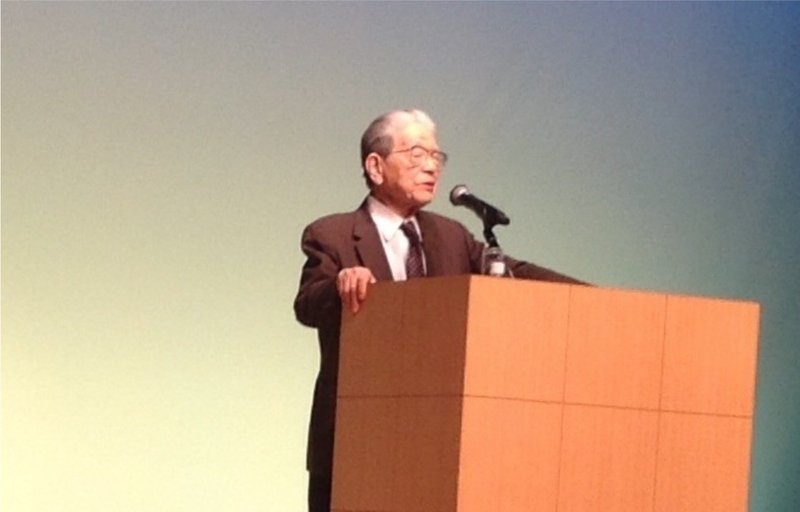
「倭人伝」は伊都國が倭人の王都で、だからこそ「郡使往来常所駐」(帯方郡の使者が往来するに常に駐まるところ)だと言っています。そうすると、「女王之所都」(女王の都するところ)の「邪馬壹国」は宙に浮いてしまいます。
「原文の表記は邪馬台じゃなくて邪馬壹だ、邪馬台国はなかった」という古田武彦氏の説(九州王朝説)では、「邪馬壹國」は博多平野にあった、としています。ヤマトと読んで類似の地名から探ろうとする従来の手法とは一線を画しています。
Wikipedia「九州王朝説」による解説を紹介しておきます。
●紀元前から7世紀末まで日本を代表した政権は一貫して九州にあり、倭(ゐ)、大倭(たゐ)、俀(たゐ)と呼ばれていた。(注1)
●1世紀には倭奴国(倭国)が北部九州を中心とした地域に成立し、倭奴国王(倭王)は博多湾近くに首都をおいて漢に朝貢し「漢委奴國王」の金印を授与されていた。
●倭王卑彌呼(ひみか)は伊都国に都し、倭国は福岡平野の奴国(当時としては大都市の2万戸)を中心としていた(注2)。漢が滅亡し魏が興ったことにより、「漢委奴国王」の金印に代わり魏より「親魏倭王」の金印が授与された。
●卑弥呼は、筑紫君の祖、甕依姫(みかよりひめ)のことである。また、壹與(ゐよ)は、漢風の名(倭與)を名乗った最初の倭王である。
●倭の五王(讃、珍、済、興、武)も九州倭国の王であり、それぞれ倭讃、倭珍、倭済、倭興、倭武と名乗っていた。
注1は次のようです。
「委」は、上古音(周・秦・漢の音)では「uar、わ」。中古音(隋・唐音)では「ui、ゐ」(両唇音のwはなかった)。「法華義疏」に「大委国上宮王私集非海彼本」とある。倭を委としており、上古音で委の発音は倭(わ)と同じであった証拠の一つである。万葉仮名では「委」は「わ、ゐ」。藤原京出土の木簡に、「伊委之」(=鰯、いわし)。藤堂明保著『漢字語源辞典』(学燈社、1965、ISBN 4312000018)によると、魏代の「倭(委)」は「(I)uar 」という読みである。
また注2は次のようになっています。
「魏志倭人伝」に見える3世紀の「邪馬壹国」(邪馬台国)を記録どおり「邪馬壹国」とする(邪馬壹国説)。古田は、魏志倭人伝など古い記録は、邪馬壹国であり邪馬壹(邪馬壹)国の表記は誤り、邪馬壹国(やまいちこく)であるとしているが、後漢書倭伝に「邪摩惟(やまたい)」、隋書俀伝に「邪靡堆(やまたい)」等とあることから、南朝滅亡後の倭(ゐ)→大倭・俀(たゐ)への変化に伴い邪馬壹国→邪馬壹(邪馬壹)国になったと考えられる。
「学会」という牙城に1人で立ち向かっただけでなく、上代から7世紀まで一貫する通史を構築したという意味で、古田氏の論説・著作活動は尊敬に値します。
甕依姫は「筑後国風土記逸文」に登場する巫女だそうで、「甕」の文字が使われているのは弥生の甕棺、肥前の大甕とのつながりを想起させます。卑彌呼を「ヒミカ」と読んでいるのも、ミカ(甕)を踏まえているのかもしれません。
口絵:古田武彦氏
この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?
