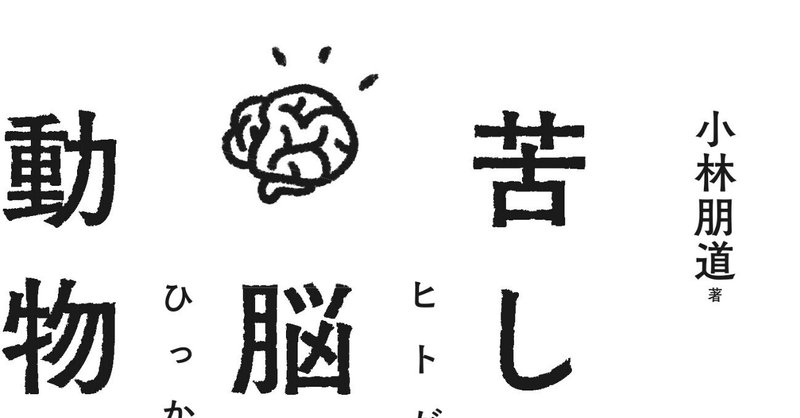
苦しいとき脳に効く動物行動学―はじめに
今、私はハンバーガーショップにいる。店内には私を入れてわずか3人。それでもすべてのテーブルの上にはプラスチックの衝立が置かれている。
そんな中で、ハンバーガーとコーヒーを頼んで、これを書きはじめた。夜の7時過ぎだ。
車でここへ来る途中、橋の上を通るとき、前方上空にたくさんのツバメが群れて飛んでいた。子育てが終わった個体や、巣立ちをし一人前(一鳥前)に飛べるようになった若鳥たちが集まっていたのだろう。糞が車のフロントガラスに落ちてはこないかと、少々心配しながら通り過ぎた。
なぜ群れていたツバメたちのことが気になったのか、なぜ今、思い出したのか、理由は2つある(意識にのぼらない理由もあるのかもしれないが)。
1つは、卒業研究で「親ツバメの〝夜間労働〟」を研究している学生がいるからだ。
夜の10時近くまで、確かに、餌を捕り、ヒナたちに食べさせている親ツバメがいることに、つまり「親ツバメの〝夜間労働〟」の現象に数年前から気がついていたのだが、その現象や実態をしっかりと調査し報告した論文がないことにも気がついていた。
そんなおり、今年ゼミに入ってきた学生の一人が、なんとしても鳥を調べたいという。テーマをいろいろ考えたが、私がなかなか一緒に調査できない中でも可能だと思われ、興味深いテーマだったので、その学生に勧めたのだ。学生は一生懸命、頑張っている。機会があればその成果もいずれどこかでお話ししたい。
もう1つの理由は、「橋の上を通るとき、前方上空にたくさんのツバメが群れて飛んでいた」という光景、そしてその光景と結びつく「親ツバメの〝夜間労働〟」と、「ヒトがつくり出す夜の明るさに合わせて行動するようになった」という出来事が、「はじめに」の内容とつながってくるからである。
読み進めていただければわかっていただけると思う。
私は、しゃべるのは苦手(若いころはそうでもなかったのに)だが、文章を書くのは好きだ。
仕事が終わった一日の、寝る前の少しの時間に書くことが多いのだが、スラスラと自然に手が動き(嘘である。そんなことがあるわけはない。もしそんなことがあったとしたらそれは重い病気だ)、(ここからは本当だ)楽しさを味わいながら書くこともある。次から次へと文章が浮かんで、筆が進むのだ。
でももちろん、そうではないときもある。七転八倒、とまでは言わないが、考えて、考えて、考えて、それでもなかなか文章が出てこなくて頭を抱えて、とにかく苦労しながら書くこともある。
前者のような状態になるか、後者のような状態になるかは、必ずしも書いている内容にはよらない。
よく聞く話ではないか。漫才師は苦労して苦労して、お客さんが笑って楽しんでくれる面白いセリフを考える………みたいな(たとえがかなりマズかったりして)。
ヒトの行動に関する、多少とも、専門的な内容の本を書いているときも、スラスラ、楽しみながら書けることがある。一方、私が大好きな動物のことを書くときも、なかなかぴったりの言葉が見つからず筆が進まず、苦労して文章をひねり出すこともある(今はどちらか? ここまでは、まー、前者かな)。
さて、私が本書の執筆にとりかかった最初の気持ちは、こんな感じだった(以下のような明確な思いがあった)。
科学が、目を見張る速度で進展し、例えば、物理学の分野では一般相対性理論と量子力学(それぞれの成果は、すでに生活の中に取り入れられている)の統合が模索され、物体や空間、時間の、直感的にわれわれが感じる存在形態が否定されつつある現在(そしてこれから)であっても、動物行動学が示してきた次の知見は変わらないだろう。
生物の形態や行動、心理といった特性は、その生物が進化的に誕生した生活環境の中で、生存や繁殖がうまくいくように適応している。
もちろん、ヒトもそうである。
ヒトにとっての「進化的に誕生した生活環境」というのは、「自然の中で(森の中ではなく開けた草原で)100人程度の集団をつくり、互いに協力し、狩猟採集によって食を得て生きていくような生活環境」である。
したがって、太陽光にあたる体表面の面積が小さくなる二足歩行や動植物の習性に対する強い関心、他人の心を読み取ろうとし読み取った内容にしたがって自分の行動を決める性質などが、遺伝子に、骨格の構造や脳内神経系の配線の設計図として書きこまれている(設計図としての遺伝子の実態もわかっている)。
そのような特性を、大まかに、「本能」と呼ぼう。
その本能の中には、「因果関係」という軸に沿って、対象を科学的に(〝科学〟とは、仮説を立て、検証テストによって仮説をより再現性が高い内容に高めていく行為)理解していく、一般的に「理性」と呼ばれる特性も含まれる。
理性は、ヒトが進化的に誕生した生活環境の中で起こる新しい事象などに対処する働きを担って進化したと考えられる。
こうした本能には、例えば、血液の中の水分量が減りすぎると喉の渇きを感じたり、愛するヒトが死んだら悲しんだりするような、強固な本能もあれば、因果関係の理解に影響を受けて抑制できるような柔軟な本能もある。例えば、われわれは、ヒトが進化的に誕生した生活環境では遭遇する機会が多く、一歩間違えば命を落とす可能性もあったと推察される(毒)ヘビに対し怖さを感じる本能を、今なおもっており、その写真や映像を見ただけでも反応する。しかし、(少なくとも現代の先進国での生活環境においては)毒ヘビと出合う機会はほとんどないといった状況や、怖さを感じてしまう理由などを理解することを通して、徐々にヘビに対する恐怖本能を低下させることも可能である。
このような状況を俯瞰(ふかん)したとき、私は(いや、もちろん私だけではなく、少なくとも多くの動物行動学者は)次のような、われわれの未来にとって重要なテーマをずっと感じてきた。一つひとつの事例への対処とは別に、全体を貫く普遍的な問題に対する方針のようなものを用意しておくべきだ。
われわれは、おもに科学の力によって、自然環境や居住環境などを含む生活環境を大きく変化させ、その変化は、ヒトの成長やヒト同士の関係に大きな影響を及ぼす物理的な環境にも及んでいる。
AIを含むITの進展による地球全体に張りめぐらされた高速のコミュニケーション環境、際限のない情報取得可能環境などもそうである。
ヒトが「進化的に誕生した生活環境」に適応した特性、その設計図である遺伝子(タンパク質の暗号になる遺伝子だけで約四万個)が歩調を合わせて現代社会の新しい環境に適応する状態に変化するには、時間が短すぎるのだ。
その特性が、現代社会の環境と合わなくなり、またわれわれが備えている本能では対処できない状態が、いくつもいくつも生まれていることは、否定しようがない事実だ。
もちろん、今から1万年前、1000年前、100年前の社会と比べると、一人ひとりのヒトの苦しみのもとになる、飢餓による死、病気による死(特に乳幼児の死)、戦争や暴力による死などは、現代社会では格段に減少し、だれも100年前にもどりたいとは思わないだろう。
その点は、事実としてしっかりと理解したうえで、でも、各人がもつ本能と社会環境とのズレによって生み出されている深い苦しみ、生きにくさをどう改善していくのか、それは今後、ますます重大なテーマとして認識されるべきだと思うのだ。この問題は、これからも、その大きさを増しながら確実に続いていくだろう。
少々長くなったが、以上のようなことが、私が、本書を書きはじめた動機のようなものだ。
でも、だ。
それがまたヒトの特性(私だけの特性?)なのだと思うのだが、書き進めるうちに、最初の動機とけっして無関係ではないのだが、ちょっとズレたような内容も書きたくなってきた。
例えば、私が、現在、科学の中で、重大な問題だと考えているテーマのいくつかであったり、そして、書いている間には、いろんなことがあり、とても苦しいときに、ハタと、次のようなことも思ったのだ。
私がこれまで一生懸命取り組み、こよなく愛してもきた動物行動学は、まさに、苦しんでいる私について、私を支えてくれる、どんな知見を提示するのだろうか。そういった、まさに自分の生に直接関係する事象もテーマにすべきではないか、と。
これは半分、助けてくれーー、という叫びであり、半分は、動物行動学という学問の手ごたえがほしかったと言えばよいのか。
ハンバーガーショップで、粘って粘って、以上の文章を書きあげた。
よく書いた、と自分を褒めてあげたい気持ちになったが、私には十分にわかっていた。
私が深く感謝しているのは、築地書館の編集部の方たちだ。
軸には、最初の動機がしっかり(?)あるとはいえ、ズレた内容の章もあり、それらを束ねて一つの本として出版にまでこぎつけてくださった編集部の方たちには心から感謝している。
でも結構、いい本だと思う自分もいる。
最近、「終活」という言葉を聞くようになった。
「自分が死んだあとの、家族などのことも考えていろいろな準備をしている人もいるんだ。へーっ、しっかりされているねー。立派な覚悟ができてるね」と思っていた。もちろん私も、自分が早く死んだときに残される家族などのことを考えているが、それはそれとして、自分が歩んできた道に残したい足跡の一つとして、死ぬまでに書いておきたかった内容の本である。
最後になったが、冒頭に書いた以下の文章の意味、わかっていただけただろうか。
………その光景と結びつく「親ツバメの〝夜間労働〟」と、「ヒトがつくり出す夜の明るさに合わせて行動するようになった」という出来事が、「はじめに」の内容とつながってくるからである。
ツバメは、人間がつくり出した「明るい夜」という環境に、本来彼らがもっている本能を調整して、行動するようになりつつあるのだ。
さて、では「はじめに」を終える。終えるが、次の1点を、ツバメの糞のように皆さんの頭上に落としていきたい。
科学は、仮説を立てて現物で実験し(哲学でしばしば行われる思考による実験=思考実験の場合もあるが)、仮説を真実により近づけることを繰り返す、永遠に続く作業である。本書の中でも、ところどころに書いたが(例えば「乳児期の大半を、十分、特定の個体とスキンシップをとることもなく、言葉をかけられることもなく育った個体に、何らかの、特に、脳という臓器の発達にネガティブナな器質的影響がなかったと考えるほうが科学的には分が悪い。以上が私の仮説だ」)、脳のクセ(バイアス、偏り)の内容なども含め、まだまだこれから永遠に改善されていく仮説である。仮説によっては、「私は違うな」と思われるものもあるだろう。仮説が未熟な場合もあるし、そもそも生物現象は、すべての個体で常に同じように起こることはあり得ないからだ。
一方、現段階の仮説にしたがって、世の中で見られる事物事象や自分自身に起こったことをより深く理解しようとし、よりよい方向を提案しようとするのが啓蒙書なのだと思う。 仮説を絶対視することなく、しかし仮説にしたがった分析に耳を傾け、新しい見方、真実により近づいた見方を知っていただきたい。
そんな本になれば望外の喜びである。
この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?
