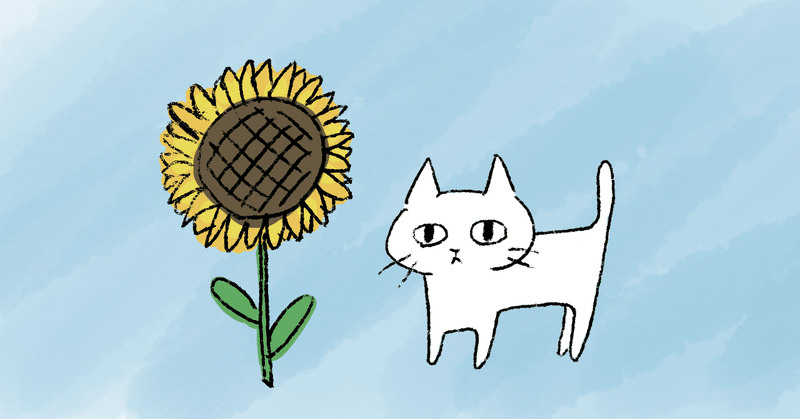
死に語りな猫(上)
死にたがりの猫が向日葵に登っていた。
「このままその太陽で押しつぶしてくれないか」
枯れかけた向日葵はいいました。
「君の体をこの陽射しで押しつぶしたとしても、それは腐敗するだけだ。君を焼きつくすことはできないし、ましてや消し去ることなど到底無理だ」と。
死にたがりの猫は悔しそうに舌打ちをしながら、それでも向日葵にすがりつき、がりがりと葉に歯を立てました。口の中に溢れる苦い香り。
「この苦さを知れば、死ぬことが出来るだろうか」
向日葵はいいました。
「その苦さが逆に生きることを君に教えてくれるだろう」
苦い汁を舌に感じながら、死にたがりの猫は、もっと苦い表情を浮かべて苦しげに咳をこほんとひとつ。
くたびれた向日葵は首をうなだれながら死にたがりの猫に問いかけます。
「ねえ、君。なぜそんなに君は死にたいの」
猫はまだ苦い表情のまま応えます。
「そこに理由なんているのかな。生きたいと思うことが本能なら、死にたいと思うこともまた本能じゃないのかしら」
向日葵は、ほぅと納得したように呼吸をし、それからまた話し始めました。
「ねえ、君はさっき、僕のこの花を太陽と言ったね。けれど、太陽は夜には眠るし、いつかは消えてしまう。君を焼きつくすことも、おそらくは押しつぶして腐敗させることもできないこの花は、それでも太陽に見えるのかい?」
「ああ、見えるよ。僕には君の顔が太陽に見える。だから、僕は君に焼かれたいし、押しつぶされたかったんだ。つまりは死にたいってことさ」
「なぜ僕を選んだの?ただ死にたいだけなら、水にでも飛び込めばいいのではないかしら」
猫は何故そんなこともわからないのかという顔で言います。
「君にはわからないかもしれないけれど、僕の中には水があふれている。そして、僕は水に囲まれた場所からここにやってきたんだ。だから、多分僕が水の中に入っても、またここに戻ってきてしまいそうな気がするんだよ。だからさ、君に、君に僕は焼かれたかったんだ」
そんなものかと向日葵は首を傾げました。すると、傾げたその角度から、種がほろりと落ちます。その種は死にたがりの猫の額にこつりと落ちました。
「あいたっ」
「ああ、そろそろ、お別れの時間が近いようだね。枯れた僕は、君の頭に落ちた僕の欠片から、また此処に、いや此処ではないとしてもどこかに芽を出すだろう。残念だけど、君の望みを叶えてあげる事はできないみたいだ」
「なんてことだ。せっかく君に焼かれたいと思ったのに、それも断られるし、僕よりも先に君がいなくなってしまうだって?なんてことだ。なんてことだ」
向日葵の根本で死にたがりの猫は脱力しきってもたれかかり、がっかりしました。
「ああ、そうだ。せっかくだから、君はまた僕が帰って来るまでここにいるといい。また僕がここに戻ってきた時、それでも君が死にたいままなら、僕が太陽に、僕ではなく僕に似ていると君が言ってくれた本物の太陽に君を焼いてくれるようにお願いしてあげよう」
死にたがりの猫は、嬉しそうに「本当かい?」「本当なのかい?」と踊り出しそうに言います。
「ああ、本当さ。だけれど、それまで君はここで僕が枯れて、また戻ってここに芽を出すまで、僕を見守ってくれなければいけない。さもないと、君は生きることも死ぬこともできなくなるよ。君の中の水にそうするように、僕は水にお願いしてしまうからね」と言いました。
ぶるぶると震えながら、死にたがりの猫は何度か首を縦に振った。了承の合図と、何かとんでもないことを選んでしまったような気分を感じながら、同時に得体のしれない、ぞくぞくした気持ちになっていた。
「じゃあ、悪いけれど頼んだよ」
そういうと、向日葵はゆっくりと体の力を抜いて目を閉じた。
死にたがりの猫は何かを言おうと思ったが、最後に掛けるべき言葉も、問うべきことも、ふさわしいものを見つけることができなかった。何かを言わなければ、言わなければという気持ちだけで発する言葉は何かを意味するとは思わなかったからだ。
言葉の代わりに、死にたがりの猫はそこで始めて泣いた。
にゃあ。
そして、向日葵は枯れた。それを死にたがりの猫はずっと観ていた。
この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?
