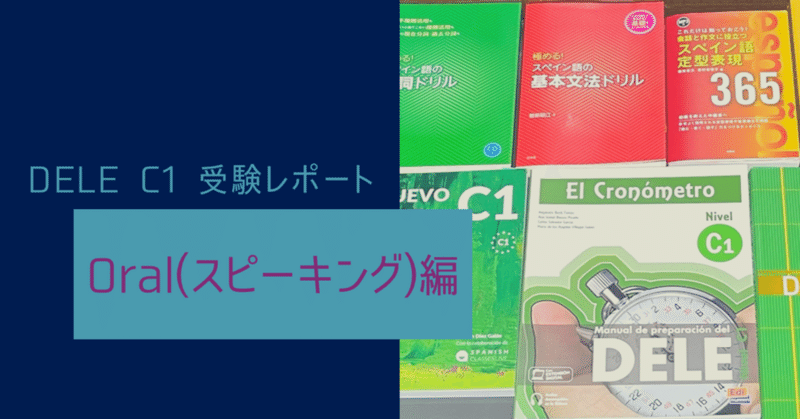
【DELE C1】受験レポート<スピーキング編>
2022年3月31日(木)から4月1日(金)にまたがり、初のDELE C1を受験してきました。
ネット上にDELE C1の試験概要や対策のポイントを網羅的に理解できる記事が少なく、私自身の試験対策期間はかなり苦労しました。
そこで上記の通り私の主観を大いに含んだ受験レポートをお送りします。
今回はOral(スピーキング試験)の試験概要をまとめます。
※学習開始から4か月でB1を獲得するまでに活用した教材については、別の記事で紹介しています。
日程
2022年3月31日(木)
Oral(スピーキング試験)のみ木曜日に実施し、それ以外の試験科目は翌日に受験。
会場
Salamanca大学/外国人向けコースのキャンパス(スペイン)。
事前準備と実際に試験を行う教室は異なります。
内容
1.事前準備:20分
2.試験:約25分(受験者によって多少の差があります)with 面接官1名+採点官1名(他nivelと同様です)
1.事前準備
●流れ
・事前準備用の部屋に入室した後、試験官から渡される2つの記事から受験者が希望するものを1つ選択します。但し「記事の見出しだけで選択してください」と指示があり、私は"教育"に関する記事を選択。もう片方の記事のテーマは環境問題でした。
・20分間で選択した記事を読み、Tarea1のモノローグに向けてメモを作成する。Tarea1で述べるべきものは「筆者の主題、副題、読み手への提言」であり、受験者の意見は聞かれていないということに注意です(Tarea2で述べます)。
●ポイントと感想
・記事を選ぶ際には、受験者が慣れているテーマや幅広い知識を持っているものを選択すると良いです。そのテーマに関する単語量や意見の有無によって、Tarea2での話しやすさが大きく変わります。私の場合は、環境問題よりも教育(具体的にはチームワーク)の方が単語の豊富さやハッキリとした意見を持っていると判断し後者のテーマを選択しました。
・17分程で記事の読み取りとメモの作成を行い、残りの3分はメモを見ながらTarea1のモノローグを(声には出さず)練習しました。このイメトレを通じて、メモ内で不足している単語やフレーズ、誤った論理構成に気が付くことが出来ました。
・Tarea1では受験者が作成したメモを見ることが出来るため(≠読み上げる)、著者の主題や副題を抑えたうえで、受験者自身がモノローグの最中に見やすい文字、構成でメモすることをおすすめします。
・メモは「段落ごとに」「接続詞と共に」「類義語で」取ることがポイントです。段落ごとの筆者の主張や根拠を拾うと共に、段落間の繋がり(意見を述べているのか、一般論を紹介しているのか、反論しているのかなど)を明確にし、それを接続詞で繋げるイメージです。
2.試験(3部構成)
●流れ
Tarea1
・事前準備で作成したメモを基に、3〜5分で記事の内容を面接官へ説明します。
・語彙の豊富さや論理の一貫性を見られている為、上記の通り類義語で記事の内容を言い換える他、ディスコースマーカー(接続詞)を適切に使用して話します。
Tarea2
・選択した記事に関連する質疑応答。主な質問としては「筆者の主張に賛成か反対か」「日本で似たような事例があるか」や面接官の意見に対する反論などです。
・意見を述べる際の表現やディスコースマーカーを的確に使った論理的な話し方が求められます。
Tarea3
・選択した記事とは全く関係無いテーマで、面接官との交渉・議論を行います。複数の条件文と画像が4枚載っている2パターンの紙が面接官から渡されます。こちらもまたタイトルを基に、受験者が希望するテーマを選択することができます。「地方公共団体の一員として、地方活性化に必要な施策を選択せよ」というテーマを私は選択しました。
・まず受験者が条件に合致すると考える選択肢(画像)とその理由を述べます。それ以降は「なぜ他の選択肢はダメなのか」「あなたの意見は条件1を満たしているが、条件2には合致しないのでは?」などといった面接官からのツッコミに答えていきます。
・論破する場ではなく「建設的に議論する場」ということを忘れることなく、面接官との会話を楽しみながらコミュニケーションしていきます。
●ポイントと感想
Tarea1
・類義語を多く用いること。固有名詞や専門的な単語などの一部の単語については記事からそのまま拝借できますが、それ以外は別の単語や言い換えた形で内容を伝えるようにします。例えば、「地球温暖化」という単語も「地球全体の気温が高くなっている現象」や「気温上昇」といった別の単語をうまく使いながら言い換えることを意識します。
・接続詞(ディスコースマーカー)をふんだんに使いながら、筆者の主張や記事の論理構成を伝える。”En primer lugar”などの順序を示す接続詞、"ya que"などの理由・根拠、"Sin embargo"などの逆説、"A pesar de"などの譲歩、"por consiguiente"などの結果を示す接続詞を効果的に使用します。
※接続詞一覧は後日掲載予定です。
Tarea2
・面接官からの質問に対しては、結論→理由の順で完結に答えます。"Sí, estoy de totalmente acuerdo en la idea del escritor, ya que..."といった流れです。
・記事に対する意見を述べる際に、"Creo que以外のフレーズも使うことをおススメします。例えば、"Me parece que"や"Supongo que"、"Desde mi punto de vista"など幅広い表現方法を使いこなす必要があります。
※こちらの表現リストも後日まとめて掲載します。
Tarea3
・Tarea2の1つ目のポイントと同じく、結論→理由の論法で完結に自分の意見を述べます。
・交渉の際には「条件付きの未来」「提案」「可能性が未確定な状況(想像)」を伝えることになる為、Condicional(直接法過去未来)を使い倒します。また「もし~だったら」という現状と異なる条件を述べる際には"Si+接続法過去"とセットの構文も有効です。
※Condicionalの文法説明はこちらのブログ記事に譲ります。
次回は読解パートの受験レポートを掲載します。
この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?
