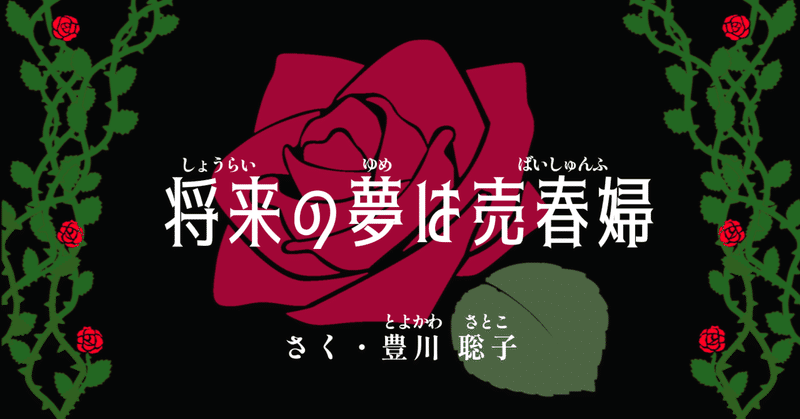
最終回「機能不全国家に生まれて」
子どもの頃、いつもここはどこなんだろうと思っていた。家族が連れてきたこの場所を私はどこなのか知らない。説明してくれたことがない。誘われたことも、許可を取られたこともない。この飛行機や電車がどこにむかうのかもわからない。
「ほら、新宿のホテルでこんなことがあったでしょう」とあとから言われて、初めてそこが東京だとかどこだとか場所が分かる。親と私がひとつの脳みそを共有しているようなふるまいで、そこに知識や感性の非対称があると仮定されたことがない。
人生を終わりのないジェットコースターか、何がどこから出てくるのか分からないお化け屋敷のように感じていた。時間や空間がいつものっぺりとして感じられ、無限のように長かった。夕餉の時間、私の何らかの無作法に激怒した母に家から追い出され中から鍵をかけられたときはとても心細かったが、その記憶は甘美な空想として繰り返し反芻された。あのとき自分自身の足で、どこまでも家から遠く遠く歩いていくことが出来ていたなら、どんな人生が待っていたのか……。
大人になった私は何よりと言っていいほど、どこまでもいつまでも歩いていくのが好きで、あるときは20キロも30キロも歩いて海を見に行った。自分の足で歩ける自由と健康があるということは、何ものにも換えがたい宝のように感じ、涙が出るほど気持ちいい。何のくったくもなく成長した人間には手にできない宝だ。
休日、本を読んで空想にひたっていたかった私が無理やり連れ出されていた森林のなかのアスレチック公園。父はとても満足そうに笑顔だった。
私のように親の機嫌をうかがって大人になった人間たちが、今度は親になり、子どもたちに嫌われないよう機嫌をうかがっている。いまどきの子どもたちはみな変に大人びていて聞き分けがよくまるでかつての私のようだ。一見してコミュニケーション能力が高く、共感や同調を表現する語彙は豊富だ。しかしそれ以外は?
どうも国会議員が汚職をしているらしい、政治家たちが私たちのお金をぬすんでいるらしいと、証拠は出そろっているのに、国が揺るぐどころか何も起こらない。わたしたちは精神的にも、経済的にも自立をしていない。税金の使い道にきびしい目を向けてはじめて経済的自立だ。でもわたしたちはヘビににらまれたカエルのように立ちつくしている。子の稼いできたお金を父が取り上げるのを止めることができない。父はわたしたちの声をとっくに聞いてくれない。
あまりにも強大な存在に生殺与奪を握られたとき、人は無力感によって心を守り、まひさせる。
国家という父はわたしたちを愛しておらず、せいぜい道具としか思っていない。好きでもなければ、邪魔だとすら思っていない無関心状態。そんな父に命がけで反抗する者などいない。昭和の時代は家庭内暴力が吹き荒れていた。金属バットで父をなぐり殺した少年が話題になった。青少年の非行は減少し、かわりに自殺がふえた。子どもたちのナイフの刃先はDV親父ではなく、自分自身に向けられている。
第二次世界大戦が終わったとき、怒り狂ったイタリア国民は独裁者ムッソリーニを惨殺した。しかし日本人は、日本を戦争にみちびき、わたしたちを戦場へ駆り立てて殺していった戦犯を神社に祀り、神とすることにした。
感情がすべてだ。感情が人間を人間たらしめている。だけど、ものごころつく前に、わたしたちは花を見て「きれい」と口に出すばかりか、そう「感じる」ことすら強いられる。
花はきれいで、葬式は悲しく、男はきたなく、女は美しいと感じることを強制させ、本来の感情は尊重されない。それだけで人の心というのはかんたんに壊せる。花は気持ちわるく、葬式はおもしろく、男はかわいく、女は美しくないと感じてしまえば、私たちは親に家から追い出され、中から鍵をかけられ、衣食住を失うとおもいこまされている。
わたしたちはそれでもなお、わたしたちを見下す父に愛してもらおうと必死になっているようだ。親の自慢になるようないい子ではない、少しでも反抗的な態度を見せた「不良」に鉄槌をくだすのは、いまの世の中、親や教師の鉄拳制裁ではない。SNSでそいつを炎上させて見せしめにすれば、罰くらい簡単にあたえられる。
捨て子のわたしたちはだれもが人目を気にして、人に嫌われないことを人生の第一義として生きている。もはや個々の家庭環境がどうという話じゃない。国そのものが、虐待親のように、わたしたちの感性を制限し、人にノーを言わないことを奨励している。日本全体が機能不全家族になっている。だれも自分のいちばん大切な人に、いちばん分かってほしい人にすらノーを言えない。フェミニストを自称する人間と話していると、彼女らが巨大な目玉だけの存在に見える。他人の顔色をうかがい、必死に相手に同調し、正しい側から踏み外れないよう足元に用心する機能だけの目玉しかわたしには印象に残らない。まるで親に捨てられかけている子どものように、彼女らはわたしに必死にすがりつく。わたしはあなたの親ではないのに……。
「グスッ、グスッ……オレな、弟が障害者で……ずっと親にほっとかれてさみしくて……」
12歳のわたしにむかって、「13歳になったらセックスしよう」とグルーミングした、ゲームショップ1983の店長今村秀樹は、別れを切り出したとたんに電話口でさめざめと泣き出した。
聞き分けのよさを強制され、子ども時代を奪われたわたしたちにとって、「権力をにぎったあとの最高のぜいたく」とは、こども相手に母性を強制し、うしなわれた幼児時代の補填をはじめることなのだろうか。
街はきょうも巨大な目玉だけが歩いている。放蕩親父の身分は安泰だろう。この修羅の棲む家を出ていくためのナイフを研ぐ音は、どこからも聞こえてくることはない。わたしたちはいまここはどこなのか、これからどこに向かうのか、なにひとつわからない。
短い期間でしたが、途中、掲載媒体変更などのハプニングがある中、本連載を最後までご愛読くださり、本当にありがとうございました。
(了)
この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?
