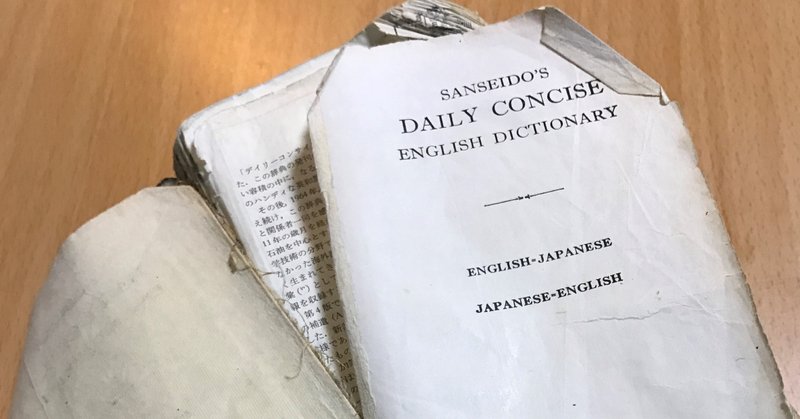
冲方塾 創作講座2 主語を学ぶ②
講義の第1回の後半戦をお送りします。
選択的注目(セレクティブ・アテンション)を利用した面白画像などは「見ても気づかない」といった検索キーワードで探せます。
ご興味のある方は、いろいろ体感してみて下さい。
重要なのは、そうしたトリック的な画像を目にしても、言葉の力によって人間はすぐさまものの見方を変えることができる、ということです。
ゴリラがいる、といったきわめて短い言葉でも、人はとっさに、視点を変えなければいけないと自分に命じる。何を認識していいかもわからない状況で、言葉が示されたものを認識しようとする。そうしながら、ちょっと笑ったり、知人にも教えようと考え、行動しようとする。
これがもっと重大なものになると、自分がそれまで抱いていた常識や自信といった、人生の価値観にかかわるものまで変えてしまう可能性がある。
次はもう少し複雑な言葉の力を体感してみましょう。
「激ムズIQテスト」というネット上で公開されているIQテストがあります。お好きな方は全問トライしていただくとして、このうちの一つを見てみましょう。

いかがですか? Aだと思う人? Bだと思う人? Cだと思う人? Dだと思う人? ややわかれていますね。これは、こうです。
「二つの図を重ねる。重複した線を消す。すると右端の図になる」
ちなみにこれは重複した線がないので消す必要がありませんね。ということは、Aだと思う人? Bだと思う人? Cだと思う人? Dだと思う人? はい、ほとんどの方が正解。
これが言葉の力を使う上で重要な、「説明」という方法です。
正しく説明することによって、人の意識を気づくべき事柄に向けさせる。
いくら大声で、これは大変だ、あれは大変だ、これは価値がある、これは自分にとってすごい発見なんだ、みんなも聞いてくれ、と言ったところで、理解できないことに人間は意識を向けられません。
歴史上さまざまな例がありまして、たとえばポリオワクチン。
これを全米で普及させようとしたところ、ワクチンというものが病原菌であって、政府は俺たちに病気を植え付けてコントロールする気だ、という恐怖心のほうが広まってしまったそうです。
そのため予防接種を子供たちに受けさせるものかと考える親がたくさん現れてしまった。最終的には、子供に予防注射を受けさせない親は罰するという法律を作らないといけなくなったとか。
これは人間の選択的注目がときにとても強固となることを示す好例です。変えるには、より巧みか強力な言葉が必要となります。このワクチンの場合、法という別の恐怖心を覚えさせるものを出して、人々の行動を変えようとしたわけです。
このように、説明するということがうまくいかないと、人間はたとえ正しいことでも、それが正しいと認識できません。
これが言葉の力を身に着ける上で重要なことです。人を動かす、人を感動させるためには、まず何より理解させなければいけない。
当然、この気づかせる、理解させるという力を伸ばせば、自分自身の理解と気づきの力を伸ばすことにもなります。
他者への説明が上手になればなるほど、誰かが発見したものを理解する力も増していく。説明する力と、説明を理解する力、この二つを身につけることが、自己批評において重要となります。
ご自分が書いたものを、説明という観点から常に意識するようにして下さい。何も知らない相手に、ちゃんと理解させようとしているか。自分がこの世の中で生きていることで気づいたことを、誰にどう説明しようとしているのか。そうした意識を持つことで、おのずと文章が明白になってゆきます。
さて、では人間が何千年もかけて発達させてきたこの言葉の力を使ううえで、最も注目しなければならないものはなんでしょうか。
主題=「何の話をしているか」
主語=「何の話をしているか」
主題とは文章全体において相手に理解させようとしているもの、主語は文章一つ一つにおいて相手に理解させようとしているもののことです。
たとえば、先ほどのポリオワクチンを例に出してお話しましたが、これはあくまで一例にすぎません。ここで僕の興が乗ってしまって、さまざまなワクチンにまつわる面白い話をどんどんしていったとすると、何の話しかわからなくなる。言葉の力について学びに来たのに、なんかウィルスや細菌の知識ばっかり増えてしまった、となる。
あるいは一例にすぎないものに注目してしまって、ポリオワクチンとはなんであるかもっと厳密に話すべきだ、となるとこれまた何の話かわからなくなる。いわゆる揚げ足を取る、というやつです。
「何の話をしているか」ということを決定づけるものが、主語です。これは主題とまったく一緒です。主語とはある一文における主題といえます。主語が綺麗に連なることで、主題というものが形成されるわけです。
主語は、価値を判断づける基準を示すものでもあります。あれが大事、これは大事ではない、という優先順位をつけるには、当然ですが、主語が明白でないといけません。
また、自分が言っているのか、誰かの言葉を伝えたいのか、という点でも主語は変化していきます。その際にも、主語をきちんと関連させ合うことで、何の話をしているかを相手に伝えやすくなります。
これも一例ですが、文章というものを要素にわけると、こんな感じになります。小説に置き換えると、こんな風にあらわせます。

論文では、主題とその背景を論じ、各論や反対意見と突き合わせ、最終的な結論を出すことが目的となるわけです。
これを小説に置き換えると、主題があり、背景となる世界があり、主体となる人物がそこで生きていて、物語においていろんな矛盾が起こったり、主題が脅かされたりしつつ、その様子は全て文章によって結論づけられてゆきます。
一方、文法の基本ですが、主語・述語・目的語というのは英語の文法で、日本語には実はそんなにぴったり当てはまりません。日本語の文法の研究は、なかなか多彩といおうか、ややこしいことになっているようです。
とはいえ人間が何かを理解する上で、主語・術語・目的語を認識することが大事であるという点は、どんな言語においても同じです。
主語は人称によって表現が変わります。
こんな感じですね。

日本語でitはモノですね。動かない物体だけでなく、ときに生き物なども英語ではモノとみなされます。「彼・彼女・あるモノ」
四人称、これはまあ、一人称二人称三人称を超えた、人類全部です。過去に存在したもの、未来に存在するであろう全てという意味で「人類は宇宙人だ」となる。
なぜこう並べたかといいますと、地球人がいるところに、宇宙人が来て、エイリアン呼ばわりされたり、地球人の自己主張があったりするものの、やはり宇宙全体からみれば「地球人も宇宙人」だよ、という主題が展開されているわけです。人称が変化しながらも一つの主題が維持され、一つの結論へ向かっていく様子がおわかりでしょうか。
では次に、こちらはいかがでしょう。

一人称だと思う人? 二人称だと思う人? 三人称だと思う人? 四人称だと思う人? さすがにいませんね。
みなさん正解です。
この文章には主語がないんですね。
私はあなたが好きだ、あなたはあなたが好きだ、彼はあなたが好きだ、彼らはあなたが好きだ。などなど。これらすべての可能性がある文章です。
未完結文体とでもいうべきもので、その一文だけだと何を言っているのかわからない。わからないにもかかわらず、前後の文脈や、常識などを用いて、推測させる。
日本語の特徴は、なんといってもこれです。
文章を作る上で最も重要な主語を省いてしまう。
述語と目的語から主語を推測させる。実際は書かれていない主題を前後の文脈で推測させる。
一時期、忖度なんて言葉が流行りました。空気や行間を読む。それができないと日本語は読んでも意味がわからない。主語を省くという重要な文化的背景を知らない限り、意味不明の文章としか思えないわけです。
では次に、この文章を見ていただきましょう。

一人称だと思う人? 二人称だと思う人? 三人称だと思う人? みなさん優秀ですね。そう、ここですここ。
「私はこう思う」
これが主語です。日本語の特徴でもう一つやっかいな点がこれです。
主語をあとからあとから付け足して文章の意味を変えてしまえる。
さっきまで彼の話をしていたかと思うと途中から私の話になり、そして最終的にあなたの話にしてしまえる。そうやって、文章の意味自体をどんどん変えてしまえるのです。
こうした特徴は、「述語主義」などと呼ばれています。前後の文脈から主語を連想させるため、一文だけだと意味がわからないんですね。
主語を知るには、前後の文章の連なりを見抜く必要があるわけです。

いつからそうだったのか? 千年前には、すでにそのような日本語が存在したことがわかっています。
なぜそうなったのか? いろんな説があります。身分の高い人物を文章上で明記すると失礼になるという社会通念のせいかもしれません。諱(いみな)は忌み名なんていって、相手の本名を記すことが敵意を示すことになったりもする。名前というのは力を持っているので名前を知られることを防がなければならないなんていう文化もありました。
また、昔は読み書きができる人が極端に少なかったため、誰が読むかわかっていた。だからわざわざ書かなくていいことは書かなかった。そのほうが高価な筆記具をいたずらに消耗せずにすむ、という考えもあったかもしれません。
平安期に日記文学が発達しましたが、誰がいつ書いたかはっきりしている。前後の文脈もはっきりしている。だから主語を省いてもわかる。そういう書き方をしているわけです。
では実際に平安期の文章を見てみましょう。
『紫式部日記、管弦の御遊び、人々加階より』
「満歳楽、太平楽、賀殿などいふ舞ども、長慶子を退出音声(まかでおんじょう)に遊びて、山のさきの道をまふほど、遠くなりゆくままに、笛のねも、鼓のおとも、松風も、木深く吹きあはせていとおもしろし」
加階というのは、いわば人事異動とかで昇任昇給した人がいるということです。そのお祝いをする会があって、管弦のお遊びをした、つまり音楽を楽しんだわけです。
以下が現代語訳です。
「満歳楽、太平楽、賀殿などの舞曲を演奏して、長慶子を退出音声(まかでおんじょう)に演奏して、築山の先の水路のあたりを漕ぎめぐってゆくとき、だんだん遠くなるにつれて、笛の音も松風も、奥深い木立の中に一つに響き合ってとても趣がある」
満歳楽、太平楽、賀殿、これは曲の名前ですね。
退出音声(まかでおんじょう)というのは最後の歌ということです。カラオケでみなさんが遊ぶときでいうトリですね。
曲名を列挙することで、どんな身分の、どんな趣味を持った人の集まりであるか表現している。ただし誰なのかは明記しない。
「暮れゆくままに、楽どもいとおもしろし」
日が暮れゆくにつれて、奏楽どもがたいそうおもしろい。
誰がそう思っているのかわからない。あたかも普遍的な事実であるかのように読めてしまう。
「上達部(かんだちめ)、御前にさぶらひたまう」
上達部というのは上級役人のことで、天皇がいる空間に脚を踏み入れることを許された人々ですね。そうした人々が、御前に伺候なさる。当然、相手は天皇です。上達部の前にいるんだから天皇に決まっている。そういう書き方です。
こうした文章は、その世界の知識がない人にはわかりません。わかる人はわかる。ネット上でも、わかっている人同士だけが理解し合える文章が散見されますよね。それと同じです。
このように、日本語は、わかる人だけを対象にした、内向きのものなのになりがちなのです。
例文に戻りましょう。築山の先の水路のあたりを漕ぎめぐってゆく。ここも推測するしかありません。山の先の路を舞うほど、とあれば、水路でしょ? みたいな。水なんだから船でしょ? みたいな。
まったく書かないんですね。で、だんだん遠くなるにつれて、笛の音も松風も、奥深い木立の中に一つに響き合ってとても趣がある。
そして、これ、一文です。一つの文章でこれだけのことを書いてしまう。
楽曲や風景は詳細に書きますし、服装などもずいぶん書き込みます。そうすることで、どんな身分の人間かわかるからです。身分がわかれば、人物が特定できます。もちろん、特定できない人々も大勢います。
「演奏して」誰が? 「漕ぎめぐって」誰が? 船は何艘あるんだ? そういうことはまったく書かない。「遠くなる」どこに行っているの? 「趣がある」誰がそう思っているのか?
このように、たった一文で複数の主体を明記せず入り乱れさせる。
我々もまた、日本語で文章を書くとき、こうした書き方を無意識にやっているのです。
なぜこうした主語の省略が一般化したかはさておき、その分、文章表現が自由になる、という利点もあります。
たとえば、主語がなくてもいいということは、何に置き換えてもいいということにもなります。事実、日本語の人称表現(代名詞)はいくらでも増やすことができます。

英語だと全て「I」ですが、こんなにも種類がある。
主語を省くことには、このような利点もあるんですね。
人称は現在も増える一方です。ちなみにどれくらいご存じですか? 我輩は聞いたことがあると思います。小官とか小職と卑下しているからにはそれは自分である、自分であるからには一人称であるという理屈で成り立っています。非才や愚か、という卑下も、一時的に身分格差を作って主語を特定させています。拙僧、愚僧、愚生みたいな。
あるいは当方、当局の者、なんていう言い方もあります。自分に矢印を向けているようなものですね。ここにいる自分、と言葉で指し示している。
このように、日本語は造語を作る能力がきわめて高い。
術語主義の最大の特徴といっていいでしょう。前後の文脈から何となく意味を察することができる、ということを最大限に利用して、それまでにない言葉の使い方をどんどんする。
かつて造語であったけれど、いつのまにか定着した言葉がこちらです。

「社会」は、福沢諭吉が作った言葉と言われていますが、そうではないという反論もあり、よくわかりません。文明、小説、誕生日というのも若い造語です。日本人は一月一日に数え年を祝っていましたし、誕生日を祝ってもらえる人というのは身分の高い人に限られていた。だから誕生日という言葉はなかったんですが、これもまたいつの間にか誰かが考えて定着した。
ちなみに、「誕」という言葉は「ごまかす」という意味でした。なぜ人が生まれる日にこの漢字をあてはめたのか、もうわかりません。年をごまかす人が多かったんでしょうかね。
釈迦(当て字)。釈も迦も仏教とは無関係です。インドからきたサンスクリット語に似たような音を発する漢字を中国であてはめられたものを日本が輸入し、より読みやすい漢字に変えてしまった。なぜこの漢字なのかさっぱりわからない。仏を仏という理由も不明です。輸入するときに、こう書けばみんなわかると判断して漢字をあててしまった。
浪漫、これは明治あたりに作られた言葉らしいのですが、完全な当て字ですね。夏目漱石が作ったと言われていますが、実際はわかりません。
電力。電気。原子力。日本語にしてみたらこうなったという一例に過ぎなかったものが、一般化した言葉です。
無意識。これは、気絶している状態のことではない、という暗黙の了解があって成り立っている言葉です。
肩こり。これも一説には夏目漱石が作ったなんて言われていますが、よくよく調べていくと一八〇〇年代にはあったとか。
ちなみに、僕は腰痛持ちなので鍼師さんにお世話になっているんですけど、腰痛という言葉を使うのは日本人だけだとか。座骨や背骨が痛むのならともかく、腰全体というのは対象が広すぎてなんだかわからないそうです。
こうした造語が生まれた背景には、主語の不在があります。
前後の文脈から推測するという主語を省く文章術は、さらに外来語においても発揮されます。
外来語・和製外国語
バイバイ ヤッホウ デマかせ(デマゴーグ)
内ゲバ(ゲバルト) カルテ
天麩羅(テンペロ ポルトガル語で調理の意味)
最近の造語
ググる インスタ映え ばえる
チルってる
ユーチューバー ツイートする
バイバイ、ヤッホウ、これはもともと日本語ではありませんね。
デマかせのデマはデマゴーグ、扇動する、人を煽る、ひじょうに暴力的な行為に走らせる。そのために本当かどうかわからないことを並べ立てる。そうしたニュアンスで、「でまかせ」という言葉にしてしまった。
内ゲバ。当時は英語よりドイツ語を使うほうが一般的だったのでしょう。ゲバルト。ドイツ語で争う、闘う、戦闘するという意味で、内輪もめという意味です。いろんな社会的な影響を及ぼしたい政治的な集団や組合がしょっちゅう内ゲバを起こしていた、なんて言われます。
カルテもドイツ語ですね。
八〇~七〇年代ぐらいはシャンな人だね、なんて使われていたとか。美人だねという意味で、ドイツ語のシェーン(美しい)から来ています。
最近の造語で定着したものもあります。ググる。何をいっているのかわからない人はいないと思いますが、わからない自分を想像してみてください。そして、なぜわかるか考えてみて下さい。
我々がググると言えば、なんのことかわかる。過去に何度も聞いたことがある。グーグルというものが存在することを知っている。自分も実際にグーグルを毎日使っている。毎日使っているから、使っているときの使いやすさ、便利さ、問題点とか、そういったことも全部知っている。知っているから、ぱっと言われたときにわかる。
これが述語主義です。大前提となる知識を膨大に必要とするのです。
インスタ映え。これもよく言われますよね。しまいには、ばえる。インスタという本来の語をとってしまう。この「ばえる」と言われたとき、おそらく思い浮かぶのが、携帯電話、アプリ、アプリでSNSというものが使える、人とつながれる、人に自慢できる、映像あるいは画像のことを意味している。ある人が本来の外貌よりもちょっとよくなった外貌を見せている。もしくは周囲にその人を「ばえさせる」ものがある。……ということまで、なんとなく、みなさんにはわかる。
もしこうしたことがらが一つでもわからなければ、何を言っているのかわからないでしょう。
他にもあります。「チルってる」みなさんご存じでしょうか? 英語でチルというとゆっくりするという意味です。クールダウンするということですね。チルドは冷蔵庫のことです。
では千年前の文章と、こうした今の文章を並べてみましょう。
満歳楽、太平楽、賀殿などいふ舞ども、長慶子を退出音声(まかでおんじょう)に遊びて、山のさきの道をまふほど、遠くなりゆくままに、笛のねも、鼓のおとも、松風も、木深く吹きあはせていとおもしろし。
友達がおもしろスタバでばえてるの見たから、ググってチルってきた。
どちらも、前提知識がなければ、まったく意味がわかりません。
日本語はこの術語主義によって、時代の変化をいち早く吸収します。
それまでにまったくない考え、まったくない道具がぱっと現れたときに、なんとなくこうでしょ、と言葉で輪郭を固めることで、それがなんであるかを特定してしまう。
世界中の文章を日本語に翻訳できる、といわれるゆえんです。英語だろうがフランス語だろうがアラビア語だろうがアフリカの特異な言葉だろうが、あるいは字を用いないアイヌ語だろうが、全てなんとなく翻訳してしまう。GPSでたくさんの衛星を飛ばして位置を特定するのと一緒です。いろんな意味合いの言葉を並べ立てることでなんとなくわかるようにする。
事実、日本は驚くほど海外の文献を翻訳している国です。世界一といっていい。それほど世界の情報を吸収している国なんですね。
そして吸収すればするほど、造語によって言葉自体が変化する。
時代に適応する力を優先するため、百年前の日本語ですら難読になってしまう。英語なら千年前の文章でもなんとか読めますが、日本語だと意味不明になる。
このように一長一短ありますが、言葉である以上、重要なことは一つです。
主語であり主題であるもの。いったい何の話をしているかを、明白にすることです。
さきほど見た紫式部日記の文章ですが、書いている紫式部は、なぜそれを書くか、なんのために書くか、そして何を書くべきで何を書くべきでないかを明白に意識しています。
文章上、省けるから考えなくてよいというのではなく、書かずとも伝わるものごとをどれほど増やせるか、文意をいかに多義的にできるか、ということが、日本語では重要となります。
大事なことなので、繰り返し申し上げますね。
文章で書くときに主題と主語を省いてしまうことが多々あるわけです。
私の? あなたの? 彼の? このように主語がすぽっとぬけてしまう。これが日本語の癖です。ただし、だからといってそれを考えなくてもいいわけではない。
書き手が、はっきりと頭の中でイメージしてこそ、書かずともそれが人に伝わるのです。伝わらないということは、つまるところ書いている人間の頭の中で、主語や主題がはっきりしていないということです。
逆に、イメージを明白にすればするほど、日本語が持つさまざまな力が発揮できるのだといえます。
では本日のまとめ。まあほとんど一つのことしか言っていないのですが。とにかく、主語を意識しましょう。主語は大事。なんで大事か。何の話をしているかが大事だから。
人称は大事。英語だとまずこれを徹底的に叩き込まれますね。
日本語の場合、また別の特徴があって、一人称二人称三人称をしょっちゅう入れ替えるんですね。私は、と言うところを、冲方は、と言ったり。これは本来三人称ですが、一人称として使うこともできる。
あるいは、御前(おんまえ)とか。御前というのは、本来一人称です。「あなたの前にいる人」だから「私」なんです。それがいつの間にか立場が逆転して、お前という二人称になった。
尊敬語や謙譲語によって相手を特定するわけですが、これもしょっちゅう入れ替わる。あるいは上下の別が変わってしまう。
たとえば貴様。なんかちょっとイラっとする言葉かもしれませんが、これは本来「尊いあなたさま」です。
たとえば身共(みども)。集団が一人称になっちゃった。
そなた、こなた。方角が人称になっちゃった。
変わってはいけないというルールがない。それが日本語の自由なところでもあり、文法面で学習しにくいところでもあります。
文法よりも、様式を重んじるといっていいでしょう。ときと場合によって言葉の意味が変わる。それが日本語です。
漢詩のルール、俳句のルール、詩吟のルール、朗詠するときの歌のルール。こういったものはひじょうに厳密です。かと思うと、すぐにそのルールを逸脱する。むしろルールがあることによって逸脱しやすくもなる。逸脱するからルールを厳密にする。そうなるとまた逸脱しやすくなる…といったことの繰り返しです。
そうした日本語のダイナミックな面白さを理解することで、文章を書くことがさらに楽しくなるはずです。
この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?
