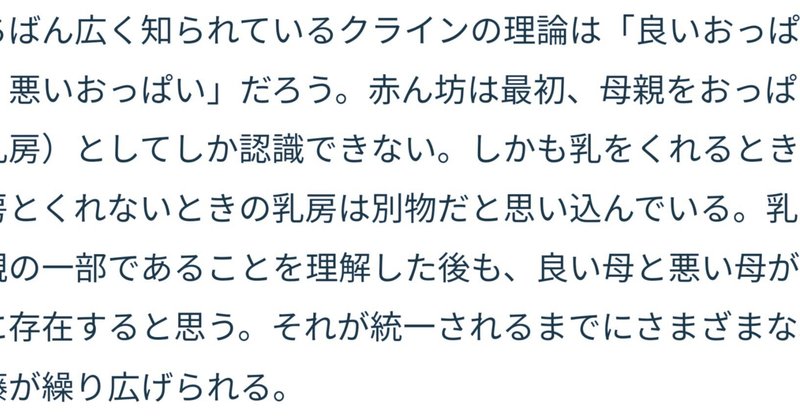
[小説・全文無料] 逃げてゆくおっぱい
一、失恋
ぼくの人生の一番のつまづきは、初めての女に手もなく振られたことでした。
それは、二十歳(はたち)の終わりを迎える秋の季節、世紀末のバブル崩壊がやってくるのはもう少しあとになる、にぎやかにも懐かしき昭和末期の話です。
当時のぼくはと言えば、理系の国立大学に入ったばかりで、どちらかと言えば暗い青春系の地味なSFファンだったのですが、友だちの中には割合い軟派なやつもいて、そんなやつの一人の元恋人と深い仲になったのです。
奥手の若い男が、同年のマセた女の気まぐれに翻弄されて、ひと夏の天国を味わったのも束の間、冬が近づく時分には無間地獄に突き落とされていた……。
まとめてしまえばその程度のお話で、どこにでも転がっているつまらない失恋譚にすぎません。
けれども、このありふれた人生の挿話がじきに笑って振り返ることのできるような小さなつまづきで終わらなかったところが、我が人生の不幸の所以であり、またそれは見方を変えれば僥倖の始まりでもあったのです。
二、泥沼
ここでぼくの子ども時代について少し説明しておきましょう。
物心がつく前のぼくは何か不幸な人生を送っていたのかというと、特筆するほどの事件があるわけではありません。
ただし、両親との関係が相当に希薄なものであったことは間違いありません。
父からも母からも放任される中で、三つ上の兄と二つ下の弟の関係を頼りに、何となく退屈を覚えながらも、自分勝手な幼年期を送っていたのです。
ここで敢えて、母親との感情的関係のことをやや強調して言うことにすれば、それは富士山山頂の大気の希薄さにも似て、酸素が十分体に回らず、心身の調子に影響が出るほどのものだったのです。
そんな母との関係性の欠落があったものですから、世間知らずで女心などさっぱり分からぬ愚かな少年であったぼくが、初めての大人の恋の対象に神の救いと見まごう過大な幸福を見てしまったのは、どうにも仕方のないことだったと思えますし、一旦与えられたその神の恩寵が、残酷にも気まぐれな女神(ミューズ)の手によっていとも簡単に取り消されてしまったときの失意・落胆・絶望・激情……。そうした風雲と嵐の悲喜劇と言いましたら、この小さな空間にいちいち書き記すのもためらわれるほどの惨状だったことは皆さんにも容易に想像がつくことでしょう。
三、変転
幸いにも、ぼくという人間の持つちっぽけな精神は、この人生の不条理劇に打ちのめされこそしたものの、自死を選ぶこともなければ、気の振れるほどの歪みをこうむることもなく、砂を噛むような日常な中にも、ささやかなの慰めを見出すことで気を紛らわして生き延びることができました。
初めての女を失ってから七年が経ち二十七になる年にようやく次の彼女が見つかり、その人とは知り合ってひと月も立たぬうちに結婚しました。
そのときは何も考えていなかったのですが、今思えば「あのような失恋はもうしたくない」という想いが、ぼくに結婚を急がせたに違いありません。
とはいえ、まだまだ青臭い若者でしかなかったぼくには、その結婚をうまく続けていくだけの適性もなく、結局四年後には二人の関係は破綻することになるのでした。
この第二のつまづきは、けれども一番目のつまづきに比べれば圧倒的に穏やかなもので、何しろ双方合意の上に婚姻関係を解消し、そのあとも数年の間は連絡を取り合っていたのですから、人生というものは不可思議なものです。
相手から縁を切られるようになっても、その縁を切られっぱなしにはしないで済むだけの柔軟性が、このときにはぼくの中で育っていたのかもしれません。
四、収斂
このように不安定な人生を送る中、仕事も人並みにできぬ無法者でしたが、幸い人間関係には恵まれたことから様々な援助をいただいて、そろそろ還暦も近い今日の日まで、ひどい苦労をすることもなく生温い人生を生きながらえてくることができたわけですから、まったく自分は果報者であると、日々折々に憂鬱に囚われながらも、考えないわけにはまいりません。
そして、この果報を賜わりながらも抑鬱と背中合わせの、人生の道行きをもう少しきちんと説明するためには、千九百年代も終わりを告げる頃に知り合った今の奥さんとの、そろそろ四半世紀が近くなる関係性を抜きにすることはできませんが、奥さんには、いくつもの厳しい峠を共に越えてくることによって、心根の極深いところから打ち直し、鍛え直してもらったのだということを記しておくにとどめましょう。
五、そして今日
母との関係性の絶対的な希薄を抱え、それを原因とする失恋地獄を経験したことで、ぼくは結果的に、この世界の冷酷さと豊穣について、人生の道行きの中、深い理解を求めざるを得ないこととなりました。
あの失恋は、この世の地獄を経験するものではありましたが、そのおかげで今の道行きがあることを考えれば、確かにぼくという存在にとってそれは僥倖だったということができるのです。
そしてそう考えるとき、ぼくの人生というものは、逃げてゆくおっぱいを追いかけ続ける珍道中だったようにも思えてきます。
よいおっぱい、悪いおっぱいという話があります。赤ん坊は初め、お母さんのおっぱいはいつも同じものなのだということが分からず、自分がしゃぶることができるおっぱいはいいおっぱい、自分がしゃぶることが許されないおっぱいは意地悪なおっぱいとして認識するというのですね。
赤ん坊は、このよいおっぱいと悪いおっぱいが元々同じものなのだということを経験を通して学ぶことによって、大人への道を歩み出すのだというのです。
とはいえそれは、標準的な多数派の話でありまして、中にはよいおっぱいと悪いおっぱいを統合することができず、自分の母の中に天使と悪魔が同居しているとしか理解できない場合もありましょうし、そもそもよいおっぱいを知らないで悪いおっぱいに悩まされながら一生を送る人もいることでしょう。
では、ぼくの場合はどうだったのかと言えば、体の近くにおっぱいはあるものの、それを求めても得られることはなく、だからそれがほしいと欲求することすら諦めて、幻のようなおっぱいが自分の周りを漂っているのを見ては、ああ、あれ、ちょっとほしいんだけどなと思ってはみても、言い出すこともできず、そのうちそのおっぱいはどこかに消え去ってしまう。あるいはちょっと気が向いてそのおっぱいを追っかけてみたとしても、おっぱいも手に取る方法が分からないものだから、結局はそのうち逃げられてしまう。
そうやって、自分でも気づかぬうちに、逃げてゆくおっぱいを追いかけてゆくだけの道行きが、ぼくの人生だったようにも思えてくるのです。
母や彼女や奥さんが、いるときでも、いないときでも、ぼくの一人遊びの世界ではいつもそんな光景が繰り広げられていたように思えてなりません。
それが今、ぼくの愚かさに辛抱強くつき合ってくれる奥さんに出会ったことで、おっぱいは近くにありて思うもの、おっぱいが象徴する母性というものは、言葉をかけ合い、思いやりの気持ちを持ち合うという人間独自の関係性の中で、女か男かということにも関係なく、相手を優しく包む気持ちとしてどこにでも存在しうるものなのだという、存在論的心理学上の結論として暖かくぼくの上に降り注ぐことになったのです。
北インド・ハリドワルの滞在しているヒンドゥー寺では犬が数匹飼われており、年のうち何回かは子犬が生まれてこの世の春を祝ってくれます。
生まれてひと月ちょっとの子犬たちが、今十匹近くも母犬を追いかけてわらわらと歩いています。
乳離れが近くなり、母犬は邪険になってきます。子犬に追われてもどんどん逃げるし、場合によってはおっぱいにまとわりつく子犬に吠えかかって追いやることさえします。
つまり、初めは子犬たちにとってよいおっぱいだったものが、いつの間にか逃げてゆく悪いおっぱいになってしまうわけです。
けれども子犬には、それを悪いおっぱいとしてとらえるだけの弁別の力もないのでしょうから、吠えかけられて噛みつかれてきゃんきゃん泣き喚くことになりながらも、自然におっぱいから卒業してゆくわけです。
で、ぼくはおっぱいからきちんと卒業できたのかというと、その点の答えはあやふやです。
とはいえ、我々凡人のほとんどには、お釈迦さまのような完璧な生き方ができるわけもなく、結局は何かと不完全なままに生きてゆくしかないはずで。
昔ほどは逃げてゆくおっぱいに振り回されることのなくなった自分を、その愚かさ共々愛おしく抱きしめることにして、今日もぼちぼち歩いていけばいいじゃないかと、陽射しの強い熱帯の冬に思うのでありました。
[2022-12-20 北インド・ハリドワル]
ここから先は
¥ 200
いつもサポートありがとうございます。みなさんの100円のサポートによって、こちらインドでは約2kgのバナナを買うことができます。これは絶滅危惧種としべえザウルス1匹を2-3日養うことができる量になります。缶コーヒーひと缶を飲んだつもりになって、ぜひともサポートをご検討ください♬
