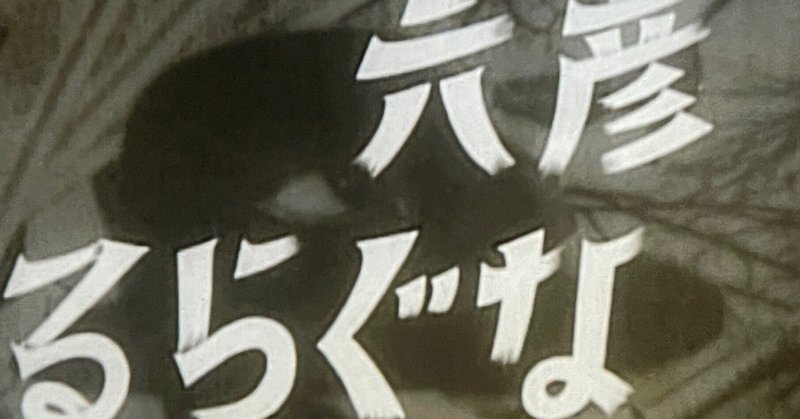
『彦六なぐらる』(1940年3月7日・南旺映画=東宝・千葉泰樹)
戦前映画研究。徳川夢声主演、三好十郎作・脚本『彦六大いに笑ふ』(1936年・P.C.L.・木村荘十二)から四年後に作られた続編『彦六なぐらる』(1940年3月7日・南旺映画=東宝・千葉泰樹)をスクリーン投影。1939(昭和14)年に設立され、東宝と配給契約を結んでいた南旺映画の製作。同社専属の千葉泰樹監督による『空想部落』(1939年12月7日)、『秀子の応援団長』(1940年1月31日)に続く第三回作品。今回の脚色は八田尚之。前作とはテイストもムードも違うが、千葉泰樹らしいハートウォーミングなホームドラマとなっている。
前作は、政宗彦六(徳川夢声)が主人の新宿のビリヤード場の立ち退きをめぐる、彦六の息子・彦一(丸山定夫)と娘・千代(堤眞佐子)たち一家と、事件屋・白木(小杉義男)との一夜の戦いを描いていた。今回はそれから数年後の物語。

彦一は出征中という設定で未出演、新宿の劇場で踊り子をしているミル=千代役は堤眞佐子→若原春江、彦六のかつての愛人・お辻役は英百合子→水町庸子、彦六の弟分だった鉄造役は小島洋々→長濱藤夫、その女房となった元女給のおあさ役は清川虹子→本間教子、そしてミルの恋人・修役は河村弘二→石黒達也とキャストが変更されている。
新興の映画会社である南旺映画製作なので、キャストには戦後活躍して、僕らにも馴染み深い新劇俳優が多数出演。鷲渕(千田是也)、松五郎(殿山泰司)、おっちょこちょい吉(多々良純)、寺本(加藤嘉)、仙公(久保松夫)などの若き日の姿が楽しめる。戦後、東映時代劇の悪役として活躍する薄田研二も、新築地劇団で活躍、病院の医師・国木田先生で出演。

武蔵野の雑木林を、孫・彦太(小高まさる)と政宗彦六(徳川夢声)が散歩している。彦太は空気銃で小鳥を捕まえようとするも失敗、ならばと彦六は「心眼」を使って、見事に小鳥に的中。その腕前に驚く彦太。得意気な彦六はすっかり好々爺となっている。そこで彦六は彦太に「心眼会得」の秘伝を授け、家の柱の黒い点をじっと見つめて、それがだんだん大きく見えてくる筈だと、特訓を開始。彦太は素直に、一日一時間、正座をして黒点をじっと見つめている。
さて、息子・彦一は府中の工事現場でならずもの、ヤクザものを束ねて現場監督をしていたが、しばらく前に応召。今は戦地にいて不在。彦六は嫁・お夏(中村美穂)と彦太の三人暮らし。彦六は最近、ウサギを飼育して近所の病院に卸す商売を始めたが、その利権を狙って、悪どい業者・蟹山金四郎(新田地作)がダンピングを初めて、卸値がどんどん安くなっている。そこは我慢の彦六。大枚三百円を借金して、飼育事業を拡大。痩せ我慢を続けている。一本気で頑固、辛くとも痩せ我慢をする性格は、前作のまま。
そのウサギの飼育を任されているのが、彦一の現場で働いていて、ダイナマイトの爆破がきっかけで、少し頭が弱くなってしまった山下椋兵。演じる本庄克二はのちの東野英治郎、築地小劇団出身で、千田是也、小沢栄太郎らと俳優座を設立、劇団運営のために『黒田誠忠禄』(1938年・松竹下加茂・衣笠貞之助)で映画にも進出。松竹下加茂専属として数々の映画に出演。本作に出演してほどなく、1940(昭和15)年8月19日、新劇弾圧で、治安維持法違反で検挙されてしまう。その時、俳優座は強制解散、1941(昭和16)年に仮釈放され、再び南旺映画製作『流旅の人々』(1941年3月5日・高木孝一)に出演後の5月に不起訴となる。この時、内務省の命令で本名・東野英治郎を名乗ることに。(ちなみに国木田先生役で出演している薄田研二も、新劇弾圧で検挙された)。

というわけで、少し呆けた山下椋兵のキャラクターは、戦後の東野英治郎のイメージそのまま。お人好しで、喧嘩早く、それでいて頑固。彦六が、息子に代わって面倒を見ているのもよくわかる。山下椋兵が、ウサギの餌の「おから」を豆腐屋から貰い受けてリアカーを曳いていると、かつての現場仲間、松五郎(殿山泰司)、おっちょこちょい吉(多々良純)たちに「白飯も食えないのか」とバカにされる。怒り心頭の椋兵は、暴れ出すも、寄ってたかっていじめられて傷だらけに。
その話を聞いた彦六、工事現場に乗り込んで、現場監督に直談判。最初は相手にされなかったが、三多摩の無頼の凄みを利かせると、監督は謝罪。彦六は椋兵の前で、全員を殴れと命じる。千葉泰樹監督らしい、のんびりとしたローカリズム溢れる演出で、こうした場面がユーモラスに展開。
前半は、こうした府中での田舎暮らしの日々を描いていく。やがて、新宿でダンサーをしているミル=千代が久々に帰ってきて、彦六に「結婚したいので、相手をみて欲しい」と頼む。そこで彦六は、新宿伊勢丹裏にある千代のアパートへ。ワンショットだけだが、伊勢丹、そしてその裏側の住宅街のロケーションがいい。前作から四年、目まぐるしく発展を遂げた新宿の姿が活写される。


千代の住む「帝都アパート」には、カフェーの女給や、劇場のスタッフといった人々が住んでいる。千代の恋人で、劇場の装置を担当している田所修(石黒達也)は、月給は五十五円と千代よりも五円安いが、おっとりとした好青年。「それでお前、つけあがっちゃダメだ」と娘に釘を刺す彦六。「あたしそんなバカじゃないわ」と千代。
修は前作では学士という設定だったが、今回はいかにも美大出のインテリ、という感じ。「じゃあ、たらふく亭にいるわ。修さん、落第しないでね」とアパートの部屋を出ていく千代。たらふく亭とは、鉄造とおあさが経営している食堂である。千代は修と、ほとんど毎日、ここで食事をしている。おあさ(本間教子)はしっかり者の女房となっていて、鉄造(長濱藤夫)は相変わらずフラフラしているようである。彦六から頼まれて、かつての愛人・お辻(水町庸子)を店の二階に住まわせているが、またまた鉄造はお辻に誘惑されて浮気していることが示唆される。
帝都アパートでは、修と二人きりになった彦六は、娘のどこが魅力的か?を率直に尋ねる。「どこが気に入って一緒に暮らそうというのですか?」。深く考えて黙りこくっている修。自分の言葉を探しているようである。
「では率直に言います。ミルちゃんほど、心の純粋な人は他にいないと思います。」
「なるほど、で、純粋というのは?」
「ちっとも混りっ気のない生一本とでも」
「生一本か? ああ、わかるわかる。何も混ぜたりしねえ奴だね」
「そうです。たとえば、山の奥の泉の水。あれみたいに澄んで綺麗なんです」
「うん」
「僕を思ってくれるミルちゃんの純粋さは怖いぐらいです(中略)あんな心の美しい人は、他に二人とないと思います。そして辛抱強くって、思う男のためには、どんなことでも尽くしてくれる人なんです」
「うん。よく見抜いたな。えらい!」
この時代、結婚というのは「家と家が結びつくもの」という観念があり、見合い結婚が日常的だった。しかし洋画や、こうした都会生活者を描いた日本映画の中では、若い世代の「理想の恋愛」が描かれていた。彦六が、娘・千代への修の素直な気持ちを聞いて「えらい!」と褒めて、二人の結婚を認める。昭和15年といえば、大政翼賛会の翼賛運動の一環として「ぜいたくは敵だ!」「パーマネントはやめませう」の7.7禁令が発布されて、さらなる戦時体制になっていく年。そうした時代のリベラルを、こうした映画で感じることができる。


彦六は、理想の恋愛を礼賛する理想の父であると同時に、人生でさまざまな失敗もしてきた。その最たるものが、府中のだるま芸者(借金で身動きできなくなっていた)だった、お辻(水町庸子)との腐れ縁。前作では、英百合子扮するお辻の腐った性根に、三行半をつけた彦六だったが、その悪縁が再び蘇る。続編とはいえ、設定や状況は微妙に異なっている。彦六は、行き場所を失ったお辻のことを、鉄造夫婦に頼んでいたのである。男好きのするお辻は、すぐに鉄造をたらし込んで、おあさの悩みのタネになっている。
千代から彦六が「たらふく亭」に顔を出すと聞いていたが、彦六はお辻に会うつもりは、毛頭なかった。それを察したおあさは、帝都アパートへ。正直に、鉄造とお辻の関係を話して、この事態を収めてくれ。亭主と別れさせてくれと、彦六に頼む。そこで彦六は、お辻と対峙することになる。

お辻役の水町庸子は、1933(昭和8)年、21歳でムーラン・ルージュ新宿座でデビュー、脇役からトップ女優となり、芸名を水町玲子から水町庸子に改名して『冬の宿』(1938年・東京発声)で映画デビュー。東宝映画で活躍。この映画の翌年、中川信夫監督『暁の進発』撮影中に、急性盲腸炎となり、宿泊先の京都の旅館で亡くなる。ちなみに娘・水町瑛子は、後年、三木のり平夫人となる。
たらふく亭の二階の座敷で、彦六とお辻の再会、壮絶な喧嘩は、本作のハイライト。鉄造と別れてどこかへ行け!と彦六に言われても「あたしが何をしようと旦那には関係ない」と開き直るだけ。辛抱できずにお膳をひっくり返して出てく彦六。お辻は、彦六への憎悪から、なんと修に手を出そうとしていた。この辺り、前作ではセリフで匂わせていただけだが、今回は、酔い潰れた修を抱き抱えてアパートへ。布団に寝かせているところに、千代が帰ってきて、千代は大ショック。千代は、おあさと鉄造にその話をする。そこで、お辻が、父の愛人だったことを聞かされ、さらにショックを受けた千代は、行方不明となってしまう。
前作の千代(堤眞佐子)は、彦六とお辻の関係を飲み込んで一緒に暮らしていたが、今回は純情派の若原春江だけに、何も知らなったという設定。千代は、激しい気性と「山の奥の泉の水」のようにピュアで一本気の性格ゆえに傷ついてしまう。映画はここから、千代と修の関係、父・彦六との関係が壊れて、修復することができるかのドラマとなっていく。

というわけで、前作が一幕ものの芝居的な構成で、木村荘十二監督のセット撮影による緊張のドラマが魅力的だったが、今回は千葉泰樹らしいハートウォーミングな人間ドラマが楽しめる。クライマックス、修が彦六を訪ね、ことの真相を聞いているところに、千代が戻ってきて、修を激しくなじり、それを諌めようとする彦六に猛烈なパンチを喰らわす。ここがタイトルの『彦六なぐらる』の所以。そのシーンが実にいい。
またしても日本刀を振りかざす。抜いた鞘をいかに収めるか、がドラマの要となる。柳家金語楼映画の娘役として清純可憐、朗らかなキャラクター・イメージのあった若原春江が激するのは、なかなかの見もの。その性格は、実は、彦六の亡き妻そっくりだったことが、父と娘の和解シーンで明らかになる。亡き母の墓前での、彦六と千代の会話のシーンがいい。
ラスト、和解をした千代と修が歩くシーン。京王線が一両編成で走ってくる。最初は距離を置いていた二人だが、やがて寄り添っていく。紆余曲折あった二人が、新しい人生に一歩踏み出す。いいショットである。
よろしければ、娯楽映画研究への支援、是非ともよろしくお願いします。これからも娯楽映画の素晴らしさを、皆さんにお伝えしていきたいと思います。
